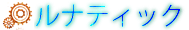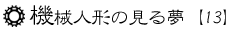チッ、と舌打ちをしてルチアーノはその部屋に鎮座する主を見遣った。くず鉄の城の王ゾーン。不動遊星をトレースしすぎて、狂ってしまったアンドロイド。 しかしそれを哀れだと言うことも、かわいそうだと言うことも、ルチアーノには出来ない。 「なんだ……いたんだ」 『私がこの城に存在することが、そんなにおかしいことなのでしょうか。ルチアーノ……アポリアよ』 「べっつに。ただ、あんたここんとこ全然いなかったからさ。びっくりしたんだよ……何、してるわけ?」 『同胞を弔っているのです』 カタコンベ、あの天蓋を硝子に覆われたパイプオルガンのある部屋の中央に浮かんで、ゾーンは白百合を手向けている。パラドックスをルチアーノが安置した棺桶に向けてだった。壊れたアンドロイド。もう、元には戻らない。 『彼は最後までその使命を全うしたのですね』 「……そうだね。最後は、正史の不動遊星に壊されてさ。アンチノミーが聞いたら発狂するんじゃねぇのォ。ま……あいつ、いないけどね?」 ルチアーノは肩を竦めてバカにしたふうな声を上げたが、それにゾーンはなにも返さなかった。 ――アンドロイド・パラドックスの末路。 名もなきファラオが盗賊王バクラに協力させて張り上げた結界のおかげで全てを見ることは叶わなかったが、それでも大まかな事の顛末は回収係として補佐で出て来ていたから、ルチアーノは知っている。英雄因子を取り除くために弱体化した英雄達にデュエルを仕掛け、そして敗北した。勝てるはずだった戦局を大きく揺るがしたのは弱体化した幸福な恵まれた青年ではなく、往年の強さを誇る、「正史の不動遊星」だった。 本来存在してはいけないはずの不動遊星が介入してきたせいで――恐らくは赤き龍の差し金だろうが、実のところルチアーノにはまだ納得出来ない点が幾らかあった――歴史の伸縮特性は補強され、結果返り討ち。あの頃はまだマザー・プラントが現存していたけれど、それに持ち込んだところで殆ど意味はなかっただろう。パラドックスはもうすっかり満ち足りた顔をしていたし(アンドロイドのくせにだ!)、恐らくは不動遊星に絆されて、もう、駄目だった。使い物にならないのだ。 だから、棺桶に花と共に埋めた。 それが英雄の腕の中で安らかな死を迎えたがった彼にルチアーノが出来た、最初で最後のはなむけだったから。 『アンチノミーは、まだ……《ブルーノ》なのですか』 「そんなの、あんたの方がよく知ってるんじゃないの。何せあんたは……」 『――偽りの造物主。そうですよ。わかっていますとも……それは私が一番よく知っている』 あなたと彼女が私のことをそう思っているということも……ゾーンは相変わらず抑揚に乏しい機械的な声音でそれを平坦に告げた。ルチアーノの表情が強張る。それを見て、ゾーンは薄く「笑う真似」をした。 そんな表情は、不動遊星の思考プールの中には存在しない。だからあの顔は自らを不動遊星という個人でオーバーライドする前の愚かな科学者のものだ。偽物だ。不動遊星の皮をかぶってその真似事をされるのが酷く不愉快に感じるのはそのせいに違いなかった。 ゾーンのしわがれた唇がゆるゆると開かれる。御伽噺の老婆が、毒リンゴを与えようと甘言を紡ぐ時のように。 『羨ましいですよ……』 ゾーンが言った。 ぞっとしない。吐き気がする。 『あなたは彼女に、AIを凌駕した心を与えられました。ええ、羨ましいのです。それが、心底……』 「……そんな、いいもんじゃないし」 『私は結局彼女から何も貰えなかった。……彼女は』 「……」 『壊れたのですね。……いいえ。――殺されたのですね、あの、男に』 あの男、と口にする時、決して感情の乗らないはずのゾーンの声音が、酷く醜悪で嫉妬に塗れたものになっていたようにルチアーノには思えた。 人工皮膚がぴりぴりと痛む。痛ましくおぞましい感情。ルチアーノは、愛という執着の感情を《マザー》に与えられたけれど、ゾーンのそれがもしルチアーノの持つものと同じであったとしても愛という名をそこに当てはめたくはない。 それはもっと怖いものだ。あの、死んでしまったルルイエの聖女が恐れたもの。彼女が歌うポピュラー・ミュージックのような。この部屋を満たすセキセイインコの剥製の鳴き声のような、そういうかわいらしいものじゃない。 ルチアーノも、きっとゾーンが抱いているようなものはどこかに持っているのだと思う。それはどうしようもなく人間らしい剥き出しの感情が根源だからだ。けれど。ルチアーノは思う。 あそこまでは。どうして、ああなってしまったのか。 それは不動遊星の資質だったのか。それとも不動遊星を身勝手にトレースした結果起こってしまったプログラム・バグなのか。或いは不動遊星の欠片ほどの感情を肥大化させた結果可視化してしまった、モンスターなのか…… 『ヨハン・アンデルセン。また、彼なのですね。おかしなものです。因果律が歪んでも、どのような形にねじ曲がっていても、あの男は『遊城十代』の元へ辿り着く。まるでかくあるべき形に還ろうとしているかのように。そうあるべきだと、腐敗した非存在の神がプログラムしたかのように……』 虚ろな人工合成物の眼球がルチアーノの、同じく造りものの眼を見据えた。贋作と贋作が見つめ合い、しかしそのどこにも救いはなく、両者が求める答えはどこにもない。 ゾーンが首を振った。くたびれた動きだった。 『私にはそれがわからないのです。ルチアーノ。心を与えられたあなたは、この、私を……どう思うのですか』 「……別に」 付き合ってやる気が失せて、ルチアーノは踵を返す。この部屋にはパラドックスの顔を見に来た。それから、プラシドがまだ破壊されていないか、ホセが眠っていないか。しかしゾーンがいてはパラドックスの遺骸を覗き見ることも出来そうにない。ならばこんな部屋には用なしだ。 「あんたは気が狂ってるって、僕はずっと、そう思ってるさ」 去り際にそれだけぴしゃりと言い放った。 背を向けてガレリヤへ抜けていく。『そうですね』というゾーンの機械合成音声がルチアーノの耳に届いた。だけどそれだけだ。ゾーンはもう、何か明確な指示を滅四星に示さない。アポリアはアポリアで独立した目的を持ち、アンチノミーは失踪、パラドックスはそれでもゾーンを補佐しようとして結局壊れてしまった。 ゾーンが、もしかしたら自分に何か言うかもしれないということを期待していたことに気が付きルチアーノはぞっとする。今更、あのろくでなしに何を望むのだ? また、絶望が欲しいのかアポリアよ。心臓を掻き抱くようにボディを両腕で抱いた。けれど、その奥にあるのは脈打つ臓器なんかじゃなく、モーメントの無機質なエンジンだけだ。 「母さん……」 聖女は死んだ。その事実が、今また大きな意味を伴ってルチアーノを苛んでいた。聖女が死んだ。ルルイエの聖女、不動遊星の劣化コピーが欲しがった造られたまがい物の英雄人形は壊れた。ゾーンが欲しがったものは、形だけの偽物でさえ、「本物の」ヨハン・アンデルセンに破壊された。 間もなくゾーンは動き始めるだろう。沈黙を破り、自らその断罪の鎌を振り下ろしに、あの恵まれた青年の住まうネオドミノへ侵攻を開始するに違いない。急がなければ。ルチアーノは歩を早める。急がなければ……ゾーンが、その地に降り立つ前に……。 《Z-ONE》がこの世界に終焉をもたらす前に、ルチアーノには願いがある。 ◇◆◇◆◇ 『よお――クソガキども。俺が目覚めたってことは、あれか。王サマがとうとう動き出した、そんな塩梅か?』 玉手箱かびっくり箱かな、というのがまずその蓋を開けた直後の十代とヨハンの感想だった。 結論から言うと、蓋は開いた。それは制約の都合上「不動遊星の手に渡ったはずの黄金の封印櫃が眠りから醒めている」ということであり、もっと言えば、名もなきファラオが眠る櫃の方の開封条件だった「まるで世界が滅んでしまいそうな時」という条件を満たしているということになる。世界は今秒刻みで滅亡へ向かって足を早めている。足早に、猛烈な勢いで、終末へ向かって走り出しているのだ。 《千年リング》に眠っていた「盗賊王バクラ」の人格が、今解き放たれ二人の正面に顕現していた。だが、さりとて驚くようなことではない。分かっていた。こうなることが……二人の前に間もなく、「メッセンジャー」が現れるだろうことは。千年リングには、歴史の歯車を正しい方向に回し直そうと願う誰かの意思が遺されていたからだ。 今一度現れた幽霊の姿をしかと見定めた。白い肌に上向きに跳ねた白い髪、人相の悪い顔。しかも不遜に腕を組んで、上から目線で「クソガキども」呼ばわりだ。久しく受けていない扱いに十代が苦笑する。 「いや、悪い。俺達もまだ遊戯さんが云々は、確証がないんだ。だけどあんたが目覚められたってことは、つまり遊戯さんも目覚めたってことなんだと思う」 『おいおい……っと、そういやそうだったな。オレ様の知ってる遊城十代とヨハン・アンデルセンは、もう死んでるのか。お前らは……確か』 「イエス、別の、並行した世界の存在だ。あなたは……こちらの世界の俺達を知っているんだな」 『そりゃあ、もうな。《ミニオン》のヨハン・アンデルセンに《天才寵児》遊城十代だ。オレ様のような人間でも嫌と言うほど名を聞いたさ。遊戯との関係で何度か顔も合わせてる。デュエルもしたぜ。あの、パラドックスとかいうイカレ野郎を相手取った時だ』 「パラドックス?!」 十代の顔色が変わる。正史の遊城十代にとってパラドックスというのはヨハンの究極宝玉神レインボー・ドラゴンを奪った男だ。そして武藤遊戯と不動遊星と三人がかりで完膚無きまでに叩き潰した相手でもある。 「パラドックス……あいつが、そういえばイリアステルの一人であるって話は俺もゾーンから聞いていた気がするな」 「なっ……そうだったのかヨハン」 「十代、君は人の話をちゃんと聞く習慣を付けた方がいい」 尤も何百年経ってもそのままなんだから、もう直らないのかもしれないけれど。その言葉をそっと仕舞い込んで「教えてくれよ」とぶうたれる十代をそっと撫で、若干話について行けなさそうになっているバクラに視線を戻した。 「ちなみに」 『あ……ああ』 「ミニオンっていうのは……なんなんだ?」 『あ? ……知らないのか? そりゃあまた……並行世界って奴ァ、随分と関係性が様変わりしてんだな。《ミニオン》――《ペガサスミニオン》っていやあ、他でもねえ。『ペガサスの寵児達』の名で知られるペガサスの養子共のことさ。奴ら、揃ってペガサス・J・クロフォードの狂信者どもだ。オレ様もあのイカレ野郎に会うまでは、ペガサスミニオンが一番に反吐の出る集団だと思ってたもんだ……』 「イカレ野郎……?」 なんだそりゃ、と首を捻る。思い当たるものがなく、二人で顔を見合わせているとバクラは『パラドックスだよ』と先も上がった名前を復唱した。 『あの魂のないアンドロイド野郎。オレ様が見た限りでは、奴は造物主に傾倒し切ってた。オレ様が一番に大嫌いな、『自らの信仰する唯一神への絶対の崇拝』ってやるつだ……。聞けばあの人形、機械人形になる前は自前の肉と魂を持っていたはずの人間だって言う。オレ様も珍しく、柄にもなくゾッとしたね。相手取ったのが生身の頃じゃないことに思わず感謝したぐらいだ』 「絶対神への盲目的崇拝か……」 『千年ロッドもなしに造り上げるんだからまったく恐れ入るな。まァ、あれはもう墓守の管理下に置かれて久しいはずだが』 バクラの口ぶりに見え隠れする微妙なニュアンスを理解して、ヨハンが呟いた。盲目と崇拝が人間を出口の見えない迷路に立たせるというのはどの時代でもままあることで、ヨハンも十代もそれでダメになった人間を何人も知っている。崇拝の対象は他者であったり、自己であったり、様々だ。それが強度の依存に繋がっていき、場合によっては、身を滅ぼす者も少なくない。 十代とヨハン自身もその危ういラインに足を踏み入れているということは重々自覚している。遊城十代は武藤遊戯を無条件に崇拝していたし、ヨハン・アンデルセンは遊城十代との間に相互の依存関係に近いものを築き上げてしまった。破滅した奴らと大差ない。ただ、その関係性に付けられた名前が違うと言うだけで。 狂気と正気の境は何ミリもあるわけじゃない。殆ど裏表のようなものだ。紙一重の危ういバランスの上で綱渡りをするようにふたりは生きているのだ。 「墓守……それじゃ、千年アイテムはこのリングと、遊戯さんのパズルだけ外に出てる、って認識でいいのか?」 『少なくともオレ様が眠った時点ではそうだな。どうしても心配ならエジプトまで行けば分かるだろうよ』 「墓守の一族に会いに行くのは、俺はちょっと遠慮したいかな……いや、向こうがそれを持ち出してこないんなら別にいいんだ。で、結局リングに眠ってたあんたの用事って何なんだ? 俺達のサポート?」 『まあ概ねそうだな。不動遊星の元に王サマ、『赤と青』……遊城十代とヨハン・アンデルセンの元にオレ様。オレ様達はそれぞれ別のルートで仕入れた情報を確実にお前らに伝達することを第一目的にこの仕事を引き受けてる。どうせ成仏出来ねえしなァ。それなりに腕は立つぜ?』 バクラの唇がにやりと歪み、自信満々に彼は両手のひらを広げる。十代は彼の話を昔遊戯に聞いた程度でしか知らないが、そのバクラの自信を十代の中で確固たる事実として裏付けるだけの「昔話」を聞かされていた。クル・エルナの亡霊と盗賊王、闇のゲームで幾度となく名も無きファラオを追い詰め――武藤遊戯とファラオとは違う形で宿主と共生、或いは宿主への寄生を行っていた闇人格。 名も無きファラオがそうであるらしいように、彼もまた、宿主に先に逝かれた幽霊なのだ。彼にそのことを尋ねてみたかったが、堪えた。踏み込んでいい領域と、その先の区別は付けねばらならない。 「第一ということは第二もあるのか」 ヨハンが話題を一度切る形で、先を促した。 「そろそろ、俺達が次に何をするべきかの目的をはっきりさせないといけないし」 『ああ……それだが、リングとオレ様を納めていた櫃をもう一度見ろ。実はイシズと遊戯からのハッピーなプレゼントがあってな。オレ様も昔ちょいと借りたが、三枚のカードで……』 バクラの指示に胸騒ぎがして二人で争うように櫃に手を伸ばす。三枚のカード、というふうにひとくくりで表現されるカードはそう多くはない。武藤遊戯の三幻神、ペガサスが作成を踏みとどまった幻のカード三邪神、それから…… 「や、やっぱ、三幻魔だ……」 幻魔。かつて影丸理事長が手にし、己の私利私欲のために用いたあの悪夢のカード達だ。 バクラが腕組みをして、『へえ』と興味深げに口笛を鳴らす。存在自体は闇のルートでうかがい知っていたバクラも、その名や効果を実際に知ったのは遊戯がアカデミアから取り寄せて手元に渡った後のことだ。おいそれと手に入る情報ではない。何しろアカデミアという所は、母体である海馬コーポレーションに輪を掛けて秘密主義な側面を持っている。 『なんだ、知ってんのか? そいつは都合がいい。説明の手間が省ける』 「知ってるも何も……俺が昔どれだけ三幻魔を倒すのに苦労したか。でも変だぞ……俺の世界じゃ、このカードはアカデミアから門外不出になってたはずなんだ」 かつて遊城十代がまだ高校一年生だった頃に対峙した三幻魔は、この世に顕現しているだけで世界中からエナジー・ドレインを行い被害を撒き散らした、実に凶悪極まりないカードだった。騒動が沈静化した後、念には念をということで元々より更に厳重にアカデミアの最深部に封じられたと影丸理事長から聞いている。その後、異世界騒ぎのどさくさでユベルが勝手に持ち出したりもしたが、それに関してはヨハンと二人で鮫島校長相手にしっかりと後始末をした。よっぽどのことがなければ、あのカードは危険すぎてもう外には出てこないはずだ。 『遊戯……っつうか、王サマの指示で一度オレ様預かりに管理が移って、以後は墓守の手を借りつつここまで面倒見てきたんだよ。ここ数百年アカデミアには一度も戻っちゃいないが、まあ危険なことも別に起こってねえ。そいつが、必ずこの時代で必要になるってのが遊戯とイシズの見立てだった。後は勝手にしてくれ』 「勝手にって、こんなの、どうやって使えばいいのか俺にはわかんないよ。この効果、アクティベートしたところで何に利用すればいいのか全然わからないし」 『そこをなんとかするのがお前らの仕事だろうがよ。なんとかしてみせろ――お前らが、真実世界をどうにかしてやりたいと思うのならな。さて……』 無茶苦茶を平然と言ってのけて、バクラがちらりと時計を見た。それから、彼はもう時間を気にして動かなければいけない宿主がそばにいないことを思い出して小さく息を吐く。漠良了はもういない。バクラの最高の宿主、人格の受け皿、ただ一人認めた存在である宿主は死んでしまったのだ。 漠良了が息を引き取ったのは、武藤遊戯が亡くなるより少し早い冬のことだった。配偶者もおらず、父親もとっくに死別していて、彼には戸籍の上で家族と呼ばれる存在はもう誰もいなかった。遺産を食いつぶそうとする自称親族ばかりが死に体の彼の周囲に集まってきた。よく覚えている。肉体に残された僅かな力を振り絞り、それらを追い払ったのはバクラだったから。 だが、了の最期は、決して孤独ではなかったと思う。バクラはそう信じている。バクラが名も無きファラオ共々後続へ力を貸そうと決めたのはその証明のようなところもあった。 漠良了が生きた世界を、無駄だったなどと言わせるつもりはない。 『オレ様が預かったもんは、それで全部だ。お前ら二人に宛てて残されたカード、それから、オレ様というこの存在そのもの。情報は……恐らく、オレ様も王サマも、お前らほどは持ち合わせていないだろうよ。現状把握が一番進んでいるのは間違いなく並行世界からやって来た存在であるお前ら二人。そいつは、例の不動遊星が殆ど全てを理解して消えていったことからも明らかだな』 「は?! 遊星が……消えた?! だってあいつ、つい数時間前まで俺と一緒にいたんだぜ。ま、まさか……その後ちょっと目を離した隙に……」 『落ち着け、お前そそっかしいのは変わってねえのかよ。消えたのはこの世界の不動遊星じゃない。バイクで、パラドックスとのデュエルに乱入してきた方だ。パラドックスはそいつに向かって、『正史の』不動遊星と、言っていた……』 気分を切り替え、「不動遊星」の話を振ってみると十代が猛烈な勢いでそれに食いついてくる。わかりやすく慌て始めた彼を宥めるように手を上げ、補足を入れた。第一、名も無きファラオから何のアクションもないのに、この世界の不動遊星が突然消えていたりなんかすることがあるはずがない。 『王サマにメッセンジャーを頼んだのも、そもそもはそいつだ。消滅の間際に、何かを言い残していた。内容は知らされてねえ。オレ様達には必要のないことなんだろうさ』 赤き龍のシグナーの痣を持ち、絆の力を誰よりも確かに信じ、あの局面を全てひっくり返してバクラ達を勝利に導いた青年の後ろ姿を、バクラは倒れて半分ほど意識を失っていたので宿主越しに朧気にしか見ていない。 ただそれでも、彼の持つオーラがその場の他の人間と違っていたのは一目瞭然のことだった。あの背中は、あまねく世界のすべてを――その両手で掴める以上のものを託され、そしてまんまと救ってみせた――英雄の背中。バクラとは相性が悪い類のそれだ。敵に回すのが嫌だな、そうでなくてよかった、とぼんやり思ったのを覚えている。その話を後でしたら、了には「バクラらしいね」と何故か笑われたのだっけか。 「俺達の知ってる遊星だ」 バクラの言葉を受けて、ヨハンが呻いた。 「俺達の世界の。なんてこった……俺の記憶じゃ、あの子は確かに寿命で……大往生だったのに」 「その後、イリアステルの手が入ったんだな。じゃ、正確には……俺達の辿ってきた歴史と分岐してるから別の歴史ってことになるのかもしれないけど」 「大元は俺達が生きてきた歴史だ。変わらないさ。武藤遊戯が名もなきファラオと別れを告げ、遊城十代はユベルと魂を分かち、不動遊星が世界を救った――あの歴史だ。《最も正しい歴史》。いつかゾーンがそう言っていた」 英雄因子が全て正しく機能し、十全にその暴力的なまでの能力をふるった結果選び残された最後の歴史。破滅を免れ、物語が一番幸福な形で完結出来るようにイリアステルが最後に調整した歴史のラスト・モデル。 武藤遊戯が礎を築き、遊城十代が守りたいと願い、不動遊星がその身を挺して掴み取ったものだ。 十代がヨハンの言葉に深く頷いた。言いたいことは、もう全部伝わってきている。 「じゃ……基本方針は、これでおおよそ決まったようなもんだな。三幻魔の使い道は追々考えるとして、今やるべきことはイリアステルの襲撃に備えて下準備をしておくことと……遊星と出来れば合流しておきたいかな。問題はどうやって今の遊星を納得させるかなんだけど。彼は俺と協調作戦をとるの、多分嫌がるだろう」 「や、でも遊戯さんが遊星んとこに行ってるんだろ? なんか上手い具合に取りなしてくれてたり、もしかしたらするんじゃないか?」 『いや、無理だろ。お前らは決闘王武藤遊戯――というより、王サマを過大評価しすぎなんだよ。あの野郎、説明能力とかマジで皆無だぜ。何の前振りもなしにとりあえずデュエルで勝っときゃ、どうにかなると信じて実際アホみたいなその考えでどうにかしてきた馬鹿だからな』 「バクラさん、本当に随分ずけずけと言い切りますね……」 『事実だからな。そのせいでオレ様と宿主がどれだけ苦労させられてきたかは、あんまり思い出したくはねえなァ。この時代に海馬がいないだけマシだ』 海馬、という名を口にした時、僅かにバクラの眉間に皺が寄ったのをヨハンは見逃さなかった。海馬瀬人と言えば、ヨハンも十代について何度か目にしたことがあるが、本当に破天荒な人だ。こちらの世界でもどうやらそれは変わりないらしい。 そして用意周到で執念深い一面も持ち合わせている人だ。明日の出社予定を確かめて、ヨハンは頼れる友の顔を思い浮かべた。KCには彼がいる。何か残されたものがないか、遊星をあてにする前に自分で探りを入れておいた方が何かと確実だろう。情報アドバンテージを持っておくに越したことはない。 ◇◆◇◆◇ 武藤遊戯からもたらされたもの。 龍亞と龍可が語って聞かせたこと。 それから、ヨハン・アンデルセンがいつか示唆していたこと。 それらが一つの線を描いて、繋がっていく。星と星を繋げると正座の形を描き出すみたいに、一見ばらばらだったものが繋がりを得て強固な事実となって浮かび上がってくる。 「十代さん」 遊城十代は普通の人間じゃない。不動遊星のそばに、いつまでもいてくれるような人じゃない。彼はヨハン・アンデルセンを選び取りいつか消えてしまうかもしれないと昔漠然と思い描いていた恐怖予想図が、現実味を帯びて遊星に襲いかかってくる。 あれから――名もなきファラオの顕現から既に幾らかの時間が経過していた。時刻は深夜を回り、このポッポタイムに今起きて活動している人間は殆どいない。アキは既に遊星のベッドで眠りに就いており、ジャックとクロウは「考える時間が欲しい」とそれぞれ自室に戻った後だった。あれからブルーノは、彼にしては珍しいことに気むずかしい顔をしてコンピューターに向かい合ったままで、軽口を叩き合うような状況ではない。ソファに横になって天井を仰いだ。ぼろくさい天井がいつもと同じ場所に変わらず染みを浮かべていることだけが、今の遊星にとっては唯一の安寧であるように思えた。 十代のことだけではないのだ。《シューティング・クェーサー・ドラゴン》 なる未知のカードのことも気がかりの一つで、遊星はもう何度目になるかわからない困惑の手付きでエクストラからそのカードを引っ張り出して眺めた。《スターダスト・ドラゴン》。不動遊星のエースであり、頼もしく遊星を支えてくれたドラゴンの相棒。遊星はスターダスト以外のドラゴンを持たない。チーム・ファイブディーズの面々は皆一枚ずつドラゴンのカードを従えているが、その誰一人としてエクストラに二枚目は存在しない。 それなのに、「なつかしい」と思ったのだ。シューティング・クェーサー・ドラゴンという未知の名に郷愁に近い感情を抱いた。けれどそのことを遊星は誰にも言っていないし、あまり顔色は変わらないたちだからきっと誰にもばれてはいないだろう。 「俺は、どうすればいいんですか。十代さん……」 返事はない。わかっている。独り言だ。元より、彼に頼りたいと思って言ったわけじゃない。縋りたいという惨めな気持ちを、それでどこかに追いやってしまいたかった。だけど別に意味はなかった。結果としてもっと陰惨な気持ちが遊星の胸を満たし、充満したに過ぎなかった。 『眠れないのか遊星』 この場にいない十代の代わりに、遊星に声を掛けてきたのは名もなきファラオだ。「ええ、まあ」気乗りしないふうに遊星は小さく頷く。「考えることが、あまりにも多すぎて」。 『なるほどそういう夜も、きみには必要かもしれないな。きみが今一番必要なものは恐らく考えるための時間だ。そしてそれは、正直なところあまりない。殆ど残されていないと言ったっていい。多分だが、明日にもきみは某かの決断を迫られるぜ。機械人形達には余裕がない。これは向こうの世界の不動遊星がオレに遺していった言葉だが』 「向こうの俺が」 『ああ』 曖昧に頷いた。並行世界の自分と言っても、遊星からして見ればそんなものは知らない人間とそう変わりがない。英雄らしく、確固たる信念を持ち、何にも揺らがず。目の前の亡霊が語る言葉の端々から見え隠れしていたそんな人物像が、遊星にはにわかに信じがたいのだ。そんな、「十代さん」でもあるまいに、完璧な高みに近付いていこうとしている人間などいるものであろうか? 遊星は首を振る。それじゃまるで、同じ顔をして同じ名前をぶら下げているだけのまったくの別人ではないか。 自分じゃない何かの幻影がちらつくのは、少なくとも愉快な気持ちを遊星にもたらすことはない。胸の中のわだかまりが大きくなっていく。何もかも足りないが、その中で特別に大きなひとつが、欠けているような気がする。まるで目の前にあるアイスクリームが、暗示か何かで全然まったく見えなくなっているかのような気持ち悪さ。 『ヒントが欲しいって顔だな』 この世の存在ならざる《伝説》が、目敏く言い当てた。 『或いは打開策だ。とにかく、前へ進むための切っ掛けが欲しい。そんな塩梅か? きみは今のところ、随分と後ろ向きのようだからな。何があったのか、俺は知らないが』 「あなたに話すようなことじゃ、ないです。ただ……それはきっと、本当に些細なことなんだと俺自身も思います。まだ、自分でもはっきりとは掴めていないのですが」 『ふむ……それじゃ、これは今きみに伝えるのが丁度いいのかもしれないな。……実は、遺言が一つあるんだ』 聞くか? 名もなきファラオが、神妙な面持ちでそう遊星に尋ねた。遺言。不動遊星から不動遊星へ、消えざるべき《最も正しい歴史》から歪められ生まれた《存在しないはずだった歴史》へ。おかしな話だ。あるべき流れに逆らい、しかしそれでも辿り着いたという事実はこうしてここに完成する。 『向こうのきみが、今ここにいるきみに宛てた最期の言葉。正直なところ、オレにはその意図はよくわからない。だがきみが、わざわざオレを使ってまで届けようとしたメッセージだ。意味は必ずあるだろう。それも恐らくは、オレ達が立たされたこの戦局をまるごとひっくり返してしまうほどのだ』 「……聞きます。教えて、ください」 『いいぜ。それも俺の役割のうちだ』 少年の姿をした幽霊が大仰に両手を広げる。額が、心なしか光ったような気がした。ウジャトの眼。千年パズルに掘られたものと同じだ。全てを見通すホルス神の眼が彼の瞳に浮かび上がり、その第三の目と二つの眼球によって遊星をがっちりと捉える。逃げ場などもはやどこにもない、ということをその短い一瞬で遊星は悟った。この言葉からは逃れられない。必ず受け止め、抱いて前へ進まねばならない。 それが不動遊星に課せられた定め。名もなきファラオの言うところの、役割というものなのだ。 例え呈示された答えが、遊星にとって呪いじみたものとなろうとも…… 『〝オレ達はやがて約束の地へと至るだろう。イレイティスの眠る地にて待つ――〟』 名もなきファラオが囁いた。その小さな言葉は、遊星の脳みそを突き抜けるが否や、エコー一つ残すこともなく夜の闇に溶けてどこかへ消えていってしまった。 |