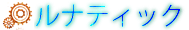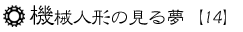長い夜だった。 誰かはそう思ったし、他の誰かは、殊更に短い夜だったとそう思った。 「あ……起こしちゃったかな……」 不動遊星が目覚めて最初に目にしたのは、昨晩最後まで言葉を交わしたファラオの亡霊ではなく、彼を度々朝食へ誘った早起きの同居人でもなく、そして時折起こしに来てくれる幼馴染みの少女の姿でもなかった。伸ばされた手を掴み取って上体をなんとか起こす。鳥のさえずり。窓の向こう、夜明けを迎えたシティの街並みから聞こえてくる目覚めの合唱は遊星をこの二十年間包んできたものと何も変わらない。 世界の終わり。平穏の終焉。幸福の途絶。そんなものがすぐにでも降りかかろうとしているだなんて、とても思えなかった。世界は美しかった。生まれて、今まで足を付けて生きてきたこの世界が存在しちゃいけなかったなんて、遊星にはとても、とても……思えなかった。 「いや、いいんだブルーノ。もう起きようと思っていた。あまりよく眠れなくて……」 「昨日の話……かい?」 「ああ、まあ。考えたんだ。色々なことを。でもよくわからなくて」 「うん」 「きっと頭で何か考えたところで、今の俺には何もわかりはしないのだろうと思った。……あの人ならそう言う」 窓を開け払った。雲の少ない空が広がっていて、朝の風が涼やかだ。それからクローゼットを開けて、いつものシャツに腕を通してジャケットを羽織る。三代目決闘王のトレード・マークの青いジャケット。それに腕を通すと不思議と前へ進むことが出来るようなそんな気がしてくる。 ベッドサイドのテーブルの上に、黄金櫃と千年パズルが乗っている。少し迷った後、パズルを一度櫃に納め直してから手荷物に加えた。流石に名もなきファラオの魂が宿る品を剥き出しで持って行くことが躊躇われたのだ。多分、そうしていいのは……そんなことが出来るのは、今はもうこの世にいない伝説の初代決闘王その人だけだった。 「出掛けるの? 随分と朝早いけど……ジャックどころかクロウもまだぐっすり寝てるよ。アキさんも、まだだと思う」 「ああ、それでいいんだ。三人が起きる前に帰って来られるさ」 「そっか。それじゃ僕、何か朝ご飯を用意して待ってるね。気を付けて……」 「いいや、何を言っているんだブルーノ。お前は俺と来てくれ。早朝のドライブというのもなかなか悪くはないと思う」 「……え? 僕?」 「この部屋に、今他に誰がいるというんだ? 思ったんだ。今、少しだけでもブルーノと話がしておきたいと。その方がきっといい。後で後悔をしたくないと俺の勘が告げている」 部屋の外へ出て行こうとしたブルーノの腕を掴んで、半ば強引に引き留める。遊星がそうして彼を引き留めるのは極めて珍しいことだ。だけれど、ブルーノにその腕を振りほどくことは出来なかった。 ブルーノは知っている。遊星の勘は本当によく当たるのだ。クロウが言うにはそれこそテストのヤマから――本当に大事な時の、嫌な予感まで何もかもが。 「うん……わかった。僕も行くよ。なんだか……遊星と一緒に走るのなんて随分と久しぶりのような気がするね」 「そうだな……」 二人で揃って、なるべく音を立てないようにガレージまで出て行く。耳ざといクロウあたりならば、D・ホイールを発進させる頃には目が覚めてしまうかもしれないが、彼は二人が外へ出るのを止めたりなんていう野暮なことはしないだろう。 ポッポタイムの仲間達の中にはそういう信頼が確かにあって、それはれっきとした事実で、例えこの世界が存在してはいけないものだったとしても変わりようがないものだ。 綺麗に磨き込まれた遊星号に跨り、慣れた動作でエンジンを掛けた。モーメントで作られたエンジンがスムースに動きだし、シティへと走り出していく。 その少し後ろをブルーノが追いかける形で走り出した。二台のバイクは緩やかに加速し、人通りの少ない街路を走り抜ける。 「実際、こうして二人で走るのは十代さんが来て以来のことだ」 走る道すがらで遊星が思い出したように、感慨深く呟いた。ダイダロス・ブリッジを目指して朝日を追いかける。遊城十代があの日空から落っこちてきてから一体どれだけの時間が過ぎ、彼という存在が今どれだけ大きくなって遊星達を引っかき回そうとしているのか、それを考えるとくらくらと目眩がしてくるようだ。けれど不思議と不快感はなかった。 あの人はそれでいいのだ。そこに存在しているだけで周囲を……世界を変えてしまうような破天荒な人にこそ、不動遊星は憧れ、そして破れるのだから。 ◇◆◇◆◇ 「や、何て申し上げればいいんでしょうかね。こういう時は、そうだな……まずはおめでとうございますって、言えばいいのかな?」 「なんだって構わないさ。ただ、一先ずはありがとうってそう言っておこう」 「私としても、大分ほっとしたところですよ。嘘偽りのない言葉です。あなたは――アンデルセン博士は、私の親友ですから。親友の奥方との再会を祝福しないわけにはやっぱりいきませんよ」 食えない笑顔だ。KCのラボで二人を出迎えた男に、ヨハンは「敵わないな」とわざとらしく肩を竦めて見せた。 千年リングを手に、ヨハンと十代がまず訪れたのがここ、不動博士のラボだった。彼が息子に千年パズルを渡したことは昔聞いている。であるならば、コンタクトを図るのは自然の成り行きだと言えるだろう。 不動は慣れた手付きでコーヒーを三人分淹れると、テーブルの上に並べる。ヨハンが何を話したがっているのか彼は薄々勘付いているみたいだった。ラボには常なら命じられた作業をしているはずの助手や研究員達の姿はなく、完璧に人払いがなされていたからだ。 「あなたじゃないかなって、実はゆーくんが連れて来た時から思ってたんです」 勝手知ったる顔でマグを手に取ったヨハンの横で、どうしたものかと窺っている十代にコーヒーを勧めながら不動が言った。初めてこの不動という男に会った時、十代はまったくの男で、遊星の友人という立場だった。だからそれを十代は気にしていたのだ。 「アンデルセン博士の奥方が。確信がありました――だからこそ、うちのかわいいけれど今ひとつ機微の悪い息子に、それとなくではなくわかりやすく釘も刺しておいたのですけど」 「あの日の帰りに遊星の調子がおかしかったの、あんたのせいだったのか」 「それは申し訳ない。ただ私は、こう言っただけです。『彼はいずれ君の前から姿を消す。別れの日が来ることを、覚えておきなさい』と」 「ひっどいな。傑作だ」 「だってそうじゃないですか。博士の口ぶりじゃ、アンデルセン夫妻に付け入る隙なんかなさそうでしたから」 あっても困る、と不動の言葉に同調するヨハンの隣で十代だけが遊星に同情的な顔をして溜息を吐いた。確かにヨハンと十代の絆は深い。何しろずっと一緒だった。だけど遊星も、十代にとってはやはり大事な後輩で…… 「十代。そういうことじゃないんだと思うけど」 などと考えていたところ、ヨハンが口を出してくる。 「遊星君は本気で俺に嫉妬してた。ただまあ自分でもその感情を持て余していて、一時の、流行病のような、そういう熱病だと自身では考えているようだった。彼が十六夜アキという幼馴染みの少女に向ける感情と違う情熱だと捉え、そして最後には半ば諦めた。まあ諦めさせるまでも大変だったわけだが……」 「おまえ、そりゃ、あんだけやればな」 「監視カメラを覗かれていると知ってある程度まで放置したのは事実だ。見せておいた方がいいっていう打算は勿論あったさ。悪いね、不動」 「いやあ、私は全然」 けらけらと笑う。なんて悪い大人達だろう。十代は一人だけ気持ちが子供の方に引き摺られている気がして、それは彼が短くない時間をポッポタイムで過ごしていたからなのだろうけれど、大人ってやだなあと漠然と思う。子供が二人もいて、伴侶もいて、あの哀れな「母」を取り込んだ今十代が大人じゃないというのも無理がある話だったかもしれないけれど、その時確かに十代は子供だった。 「いいんだよ、十代はそれでさ」 「何がだよ」 「うん。君はそれでいい。俺の愛した遊城十代はそういうやつだ。……さて不動、本題に入ろうか。ご覧の通り十代も戻って来て、状況は刻一刻と先へ進みつつある。千年リングの封印が解かれ、それはまた同時に千年パズルの封印が解かれたことも意味している。君ならこの意味が少しはわかるんじゃないか」 何も口に出して言っていないのに、全部知ってる、大丈夫と言わんばかりにヨハンが十代を抱き寄せる。ずっと十代と引き剥がされていたことで活動が慢性化していたはずのユベルの意識レベルが、その瞬間ぶわりと高まったのを感知してまあまあと宥めているうちにヨハンは勝手に話しを進め始めていた。 問われた不動が曖昧に笑う。 「なるほど……ゆーくんに託されたあれが、ですか。でもすみません。実のところ、私もそう多くのことは知らないんです。あれは海馬瀬人名誉会長の勅命で、不動遊星以外何人たりとも閲覧まかり成らぬ、とされたいたものでして」 「でもま、千年パズルぐらいは知ってるだろう?」 「ええ。噂でしか聞き知ってませんけれど」 「そっか。じゃ、こっから先はバクラにも話して貰った方が早いかな」 彼は信頼に値する親友とこういう段取りに至って、それでも情報を秘匿するような男ではない。不動は本当にそれ以上のことは知らないのだろう。それを二人で確かめ合うと、ヨハンがリングを取り出して十代の手に載せた。 リングがまばゆく光り、そこから目つきの悪い白髪の男が現れ出る。不動は精霊視の能力は持ち合わせていないので十代がエネルギーを送って可視化した。科学者としての不動の血が騒ぐのだろう、彼が子供っぽい感極まった表情になる。 「説明はいるか?」 十代が聞くと盗賊王バクラは腕組みをしてふよふよと浮かび上がったまま首を横に振った。 『大体聞いてたからいい。で、結局オレ様の情報便りってワケかい』 「恥ずかしながら。なあ、千年リングの起動条件はパズルの解放が先になされてること……だったよな。パズルの方の起動条件は何か知らないのか?」 『王サマのか? あー……確か、『世界が終わりそうな時に開く』だとか、そういうメルヘンなことを言ってたように思うが』 「すげえ。この状況で聞くと全然まったくメルヘンじゃない」 世界は今まさに終わりかけている。それならば、千年パズルの封が解かれて名もなきファラオがこの地に降り立つのは必定のことだろう。歴史を改竄され、刻一刻と滅びの未来へジャンクションされようとしているこの状況が世界の終わりに近しい瞬間でないのならば教えて欲しい。 『だが前に言った通り、オレ様はそう多くは知らねえんだ。精々が、三幻魔の簡易的なコントロール方法ぐらいでだな』 「……三幻魔」 『ああそうだ。イシズに持たされた――どうした?』 「ははあ、なるほど、そういう……とんでもないですね、あの人は……」 「……不動?」 今までちんぷんかんぷんだというふうに話を黙って聞いていた不動が急にゆらりと立ち上がって、そんな歓喜の声を上げたのはその時だった。 世紀の発明をして公共浴場から全裸で飛び出していった誰ぞの如く、一人で感極まってしまい周りが見えていない。不動はマグをテーブルに置くと急にヨハンや十代に背を向け、つかつかと一際大きなディスプレイに繋がっているコンソールの方へ歩いて行ってしまう。 そのまま、なにやら猛烈な勢いでキーを叩き始め、かと思いきや手はキーボードに触れたままくるりと振り向いて空が青いことに感動した子供のような目をして唐突に語り始めた。 「その言葉で、繋がりました。あんまり人に、というか親友であるアンデルセン博士には教えたくなかったんですけど、そのためにあったとなれば致し方ない。……実はですね、我々《MIDS》の部門局長には代々引き継がれている内緒の実験があるんです。実験の故海馬瀬人社長がプロジェクト発起人になり、当時のI2社最高責任顧問だった天馬兄弟が主となり進めたそれは、彼らの意向で外部にその存在を秘匿されました。そんな内緒の実験を連綿と何百年も進めていくために、副産物だったモーメント・システムを表向きのメインに据えてうちの部署は作られて――まあこれ、歴代の局長しか知らないんですけど」 「不動、ちょいタンマ、うちの嫁さんと用心棒が話について行けてなくてぽかんとしてる」 『おいこらクソガキ誰が用心棒だ』 「いや言葉のあやってやつ……ともかく、海馬社長とか天馬兄弟……天馬兄弟って誰だか俺はあんまり知らないけど……」 『この世界で生きていたヨハン・アンデルセンの義兄どもだろ。ミニオンのトップエリート』 「えっ、そうなのか?! なんかそれ聞くと悪いこと言ったみたいだな。……さておき、その人達がやってた内緒の実験があるんだな。それで、どういう実験なんだ?」 バクラに茶々を入れられながらヨハンがなんとか尋ねると、不動がよくぞ聞いてくれましたというふうに目を輝かせた。それにしてもこの盗賊王、合いの手が妙にうまい。こなれている。彼の宿主は一体どんな会話を常日頃していたんだろうか。 彼らもまた、武藤遊戯と名もなきファラオのように二人でひとつとして生きていたのか。 「最初はモーメント・エンジンの解析と再現から始まったんです」 「モーメントの?」 「ええ。ある事件により、KCとI2最上層部だった海馬兄弟と天馬兄弟のみに閲覧権限を限って提供されたオーバーテクノロジー・ガジェットがありました。当時は技術の着想さえでていなかったモーメント・システムをコアに用いたエンジン。記録によればそれは、時空を行き来出来るD・ホイールから抜き取られた部品だそうです。彼らはある人物の頼みを受け、歴史が不必要に狂わないように情報を秘匿しながらそれの分析を始めました。その結果、そのエンジンが作製されたのは西暦三八六五年、実に二千年近い未来で製造されたものである、との結論がまず出たわけです」 スライドがディスプレイに表示される。小型のモーメント・エンジンが中央にあり、そこに矢印が伸びて細かい書き込みがされている。遊星の文字だ、と十代には直感して分かった。「時空渡航能力」「時空座標」「遊星ギアと遊星粒子」「ツリー・ダイアグラム」などと難しそうな専門用語があの丁寧な筆致で書き加えられていたのだ。 「で、今んとこ解析ってどこまで進んでるんだ?」 「解析自体は海馬社長存命時に終わったんです。流石に稀代の天才を四人寄せ集めただけはあると言いますか……ただ、そこから先の再現過程は難航しました。何しろ構成するパーツを生産出来るように、時代が追い付くまでが長くて。今現在市場に出回っている技術レベルより少し上を用いることで、私の代でようやく満足のいく試作品に至りました」 『……なるほどねぇ。で、それと三幻魔との関わりは何なんだ? イカレ科学者』 「それはこれから説明します」 イカレ科学者呼ばわりされたことをまったく気にする素振りもなく不動がにこやかに受け答えする。ディスプレイが別のスライドを映し出した。でかでかと赤地で「最重要機密」とのデジタル署名がなされており、厳重にその書類が守られていることを示している。「このパーツが一体何の為にもたらされたのかに関する書類なんですよ」と不動が言った。 「我々は目的も知らされず研究に邁進していたわけです。尤もそれだけこの研究が魅力的だったのですが」 「ふむ」 「この機密書類には二通りのロックが掛けられています。パスワード・ロックが二つ。そしてもう一枚がカードスキャン認証システムによるロックです」 「あ、わかった。そのカード認証のキーが三幻魔なんだ」 「その通り。そもそもパスワードでさえ代々片方しか伝えられていなかったのでアンロックは絶望的だったんですけれど、三幻魔なんてお伽噺でしか聞いたことのないようなレアカードですから、今まで誰もこれを解除出来ませんでした。何しろ製造元のはずのI2でさえ所持してないと言うんですからね」 みんな開くなと言われると開きたくなるんですよ……と首を振った不動の姿に、それまでの歴代局長の果敢なアタックが見てとれるようだった。カードはともかく、パスワードは総当たりで片端から試していったのだろう。しかし言語指定も文字数指定も何もないフリーワードを探し当てるというのは、砂漠の砂から星を見つけるよりも無茶な願いだったはずだ。 その結果数多のチャレンジは失敗し、未開封のまま今に至るというわけか。 「あのカード、やばすぎるから俺達の歴史ではアカデミアに厳重保管されてたんだ」 『で、この歴史では海馬が生きてるうちにオレ様の手に渡って封印櫃にドン、だ。そりゃあ見つかるはずもないわな』 「それじゃ後は、最後のパスワードですかね。ヒントは一応あるんです」 「おいおい不動、今日はいやに性急だな」 「あ、すみません。でも……気もはやるってものですよ。なんと言っても、厳重に閉ざされてきた扉がついに開くというその手前に私は今いるんです。隠された謎を解き明かす喜びは研究者にとって何にも代え難いものですから」 照れたように頬を掻く。一応精霊研究の権威なんてものをやっていたヨハンとしては、不動のその気持ちもわからないではなかった。幻魔を取り出した十代に目配せをし、不動の元へ寄る。スキャン認証口を探して十代がその付近にスタンバイした。あとは指示通り、解除を進めていくだけだ。 「わかったよ。それじゃ手早く悲願を達成させるとしようか。不動、一つ目のパスワードは?」 「『Paradox』。今、打ち込みました」 「それじゃ次だ。二つ目のパスワードのヒントは?」 「この研究の提唱者の名前、だそうです。海馬瀬人・天馬夜行・天馬月行の三名は、既にあらゆる言語での入力が試みられていましたが全て不正解でした。こうなるともう手が尽くせなくて」 『――不動遊星だ』 「……え?」 『いいから入れろ。ったく、オレ様の役割はこんなのばかりなのか』 困ったように首を傾げる不動に、バクラの鋭い一声が飛ぶ。不動は相当な戸惑いを見せたが(当たり前だ、不動遊星とは即ち彼の愛息子に他ならない。過去に同姓同名の人間もいなかったはずだから、本来ならば海馬瀬人が主導していた実験に関わっているはずがないのだ)、バクラの剣幕に押されてパスを入力した。 エンターを入力すると間髪入れずにピッ、という認証受理の短い音が響く。「まさか」という驚きの表情を隠せない不動の脇でヨハンだけが「ああなるほどなあ」というしたり顔で頷いていた。 「一番目のパスワードが、暗に二番目のパスワードを示唆してたってわけだ。この研究、パラドックスとのデュエルに現れたっていう正史の遊星君が言い残していったものだったんだな」 「……アンデルセン博士、私なんだかついていく自信がなくなってきましたよ」 「うーん、まあ、話すと長くなるんだ。でも、巻き込んだ以上おいおい説明はしていく。パラレル・ワールドにおいて、遊星君は父親の意思を継いだ非常に優秀な科学者でありその道の権威だったんだ。まあ一つの可能性ってやつで」 「はあ……ええと、それじゃ最後のカード認証ですけれど」 「準備出来てる。こいつを三枚ともスキャンすればいいんだよな」 不動が頷くと、十代はまずウリエルを手にとってスキャナに掛けた。認証されるのを待って更にハモン、ラビエルと続けて行く。 三枚のカードがスキャニングされ、三度、機械が認証受理の音を立てた。ビープ音が発生し、ディスプレイの表示が変わる。機密事項であることを示す赤い文字が溶けて消え、その代わりにアル一人の男の顔が大写しになった。 『――そこにいるのは、遊戯か? それともバクラか。まあいい。どちらでも構わん。貴様らのうち片方でもいるのならば、後で情報を共有しておけ。どちらもいないのであれば即刻システムを落とす。千年アイテムの有無で判断するから偽装しようとしても無駄だ。……なんだリングか。遊戯はどこだ』 「かっ、海馬社長?!」 「十代、これ録画だぜ。今のはセンサーでなんか識別したみたいだな」 ヨハンの仮説は恐らく正しいだろう。画面の中の海馬瀬人は、狼狽えたり驚いたりしている十代達を全く意に介することなく話しを進めていく。仮に海馬瀬人が対面で話していたとしてもこの調子だったのかもしれなかったが、瀬人の視線は先程からカメラのレンズと思しき一点からまったくずらされておらず、それが人工知能による故人の再現などでないことを裏付けていた。 『フン……この情報だけはどうしても漏らすなと念を入れられていたからな。少し厳重に保護させてもらった。それでもこの動画が流れているということは、『そういう』ことなのだろう、あまり信じたくはないが、我が社が存亡の危機に陥っているということだ』 『あ、兄サマにとっては世界滅亡ってイコールでKC滅亡のことなんだぜ。気にしないで聞いてくれ!』 『モクバ! 全くお前は……それで、内容だったな。それだが、一度しか言わん。よく聞け』 後ろからひょこりと現れた海馬木馬の捕捉で意味を察したところに、瀬人が本題に入ろうとする。自然と、その場の四人皆が身構えた。瀬人の表情がいつになく真剣なものになったからだ。 瀬人の唇が開かれる。その唇が紡ぎ上げた言葉にまず不動が少なからぬショックを受けて、辛うじてそこに踏み留まった。続けられた言葉に、ヨハンと十代が眉間を険しくする。 ただ一人盗賊王だけが、『そういうことかよ』と唇を噛みしめた。 ◇◆◇◆◇ 橋の上で陽の光を浴びた。 ダイダロス・ブリッジのど真ん中で、斜線に他の車もD・ホイールもないのをいいことに足を止めて空を仰ぐ。朝の冷たい風が心地よい。それはまるで、遊星の頭を埋め尽くすもやもやとしたものをなぎ払っていってくれるかのように涼やかだ。 遊星の隣で、やはりD・ホイールを止めてそれにもたれかかるようにしていたブルーノが「気持ちのいい朝だね」と言った。異論はない。こんなに爽やかな朝を迎えたのは随分と久しぶりのような気がした。 「お日様の光って、僕、好きだなあ。なんだか遊星みたいで」 「よしてくれ。俺はそういう柄じゃない。そういうのは、むしろ……」 「……『むしろ、十代さんが』?」 「ああ。……ブルーノ? どうした、そんな顔をして」 「ううん……」 ブルーノの顔に僅かに翳りが落ちる。尤も、十代さんが十代さんがと口にする度に顔を顰めたり溜息を吐かれたりするのは何もブルーノに限った話しではなかったし、クロウやジャックの方がもっとあからさまだったのでブルーノの様子を特別おかしいとは遊星は思わなかった。 遊星の十代への感情は、何か行きすぎている。そういうふうに言われても仕方ないなと近頃はちゃんと自覚している。 「あのね遊星。僕は別に遊星が十代に憧れてるの、悪いとは思ってないんだ。十代はすごいよね、人の輪に入っていっていつの間にか中心に立って……本人にはそのつもりがなくても、出会った人みんなに強烈な印象を残してく。だけど僕は」 「なんだ。むくれてるのか」 「違う。……と思う。ねえ遊星、秘密の話をしていいかい?」 「ああ、もちろん」 「ふふ、ありがとう」 D・ホイールから身体を浮かせ、きちんと立ち上がってブルーノが遊星の方へ寄って来る。澄んだ空気の中で秘密の話。ブルーノが、「他のみんなにはないしょだよ」と言って人差し指を唇に添える。 「僕ね、遊星に憧れてるんだ。きっと遊星が十代に憧れるのと、同じように。僕が遊星と会った時のこと、覚えてる?」 「? ああ、確か……浜辺に流れ着いていたというのを狭霧と牛尾に連れられて、俺達に紹介されたんだよな。身寄りもあてもないからしばらく面倒を見て欲しいって。俺は随分面食らったんだ。何しろ牛尾がそんな用件で俺達を頼るとは思っていなかったし、ブルーノ、お前はなんだか不思議なやつで」 「だってジャックのホイール・オブ・フォーチューン、本当に素敵だったんだもの」 「それに最高のメカニックだった。俺はお前に出会うまで、これほどの技術を持つ男には父さんを除けば出会ったことがない。感謝してる」 遊星の青色の、あの澄み渡った宇宙のような瞳がブルーノを見据えた。 この瞳の奥に深淵がある、とブルーノは彼と目を合わせる度密かに思う。永遠に解明されない神秘のような、そんな何かが彼の目の中には宿っている。 ブルーノはその色が好きだ。吸い込まれていきそうな深い青に一目見て、それだけで惹かれてしまった。そのことは誰にも話していないし、きっとブルーノがブルーノである限り誰にも打ち明けることはないだろう。遊星にでさえ。 それは遊星にブルーノが憧れている、それよりももっとさきのとっておきの秘密だから。 「俺はお前のことを尊敬している。だからそんなお前に憧れていると言われると……照れるな」 「だって本当のことだよ。遊星のこと、大好きだもの」 目と目を合わせてそう告げると、彼は珍しく狼狽したような素振りを見せ、顔を少し赤く染めて小さな声で「ありがとう」と、言った。 それからどちらからともなく手を握り合った。男同士で、堅い友情を確かめ合おうとするみたいな、そういう不器用な握り締め方だった。ブルーノの手のひらは温度が低く、対する遊星はまだ子供の体温を少しだけ残している。手袋越しのその温度は、汗ばむほどでもなくて心地よい。 「遊星、僕ね」 ブルーノが秘め事を打ち明ける口ぶりでまた口を開いた。 「僕は遊星の、君の味方でありたい。どんな時も……君が何を目指しても。だけど」 「ああ」 「もし僕が君と違う道へ行こうとしたら。何かを、間違ってしまったら……遊星は自分が信じた道を進むんだ。だから――僕がいつか敵になってしまったら、君の正義を貫いて僕を止めて」 「……ブルーノ?」 「約束してほしいんだ。君がそうしてくれるって。君が今日この時ここへ連れてきてくれたのは、きっとその約束をするためなんだって、僕にもわからないけれど……心の中で、誰かがそう言ってる。そんな気がするから」 ブルーノが言った。潮風が二人の頬を凪ぎ、かもめがどこか遠くの空へと飛び立っていく。 遊星の動きが、ブルーノのいつになく生真面目で、それでいて思い詰めたふうな様子にしばし固まる。ブルーノがチーム・ファイブディーズから離反して何か大事をしでかそうとしている様子はない。彼の目の中には嘘がなく、また、そんなことをしなくちゃいけない理由もわからない。 けれど。遊星は思い至る。ブルーノは記憶喪失の異邦人だ。記憶が戻って遊星の元を離れた十代のように、ブルーノも、そうやって遊星と敵対することを恐れているのだとしたら…… 繋いでいた手を、より強く握り直した。彼の不安が指先から伝わってくる。この震えは信頼と愛情の裏返し。遊星を信じているからこそ、彼はこんな願いを、頼みを敢えて口にしたのだ。 「ああ。約束する」 確かにそう告げると、繋いだ先のブルーノの緊張が少しだけ和らいだような気がした。 穏やかな風がまた二人の間を凪いでいく。まるで世界の終わりの訪れを隠そうとするみたいに、静かに。 |