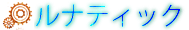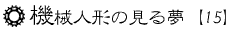夕方になって、ある意味約束を守るかたちで遊城十代はガレージに戻ってきた。ちょっと散歩へ行ってくるという塩梅でポッポタイムを彼が去ってから丸三日だ。その三日の間に何があったのか、遊星は聞きたくて仕方なかったのだが無理矢理に願望をねじ伏せた。尋ねるのは後だ。何もかもが終わった、その後。 いつも通りの赤いジャケットを着て歩いている彼の外見には、これと言ってわかりやすい変化はない。髪が違う色に染まっていたり、目が違う色になっていたり、装飾品が増えていたり……全くそのどれもない。そのくせ、彼は今はもう、ひと目見ただけで何かが違うと理解してしまえるほどに変わってしまっていた。遊星に「きみにあいにきたんだ」と囁いた誰かはそこにはいなかった。彼は彼であって、彼ではない。まったく違うものだ。 だが恐らくそれこそが「完璧な遊城十代」なのだろうという予感はある。異邦人の遊城十代はあくまでも欠けたピースの一つに過ぎず、自己修復の本能に従ってあちこちでピースを収集してきて、そうして完成してしまったのだ。理屈としては非常に単純だった。 十代の傍らには付き添うようにしてヨハンが歩いていた。その後ろから、双子が緊張した面持ちで付いてきている。アキが確認を取ってくれて、二人が毎日「こちらの」両親の元へ帰宅していることはしっかり確認が取れているから、四人はどこかで待ち合わせてきたのだろう。 「……お帰りなさい、十代さん」 胸中でくすぶる感情を出来るだけ抑えるようにして声を掛けたが、十代の返事は歯切れが悪く冴えないものだった。 「あ、ああ……」 「話は概ね、龍亞と龍可から。その他もいくらか」 「そっか」 「まだ、殆ど納得はいっていませんが。でも猶予がないというのは、わかりますよ」 十代のこの反応を見るに、自分の中で渦巻いている感情が、抑え切れていないのかもしれない。感情の制御は難しい。何しろ遊星はそれを必要に迫られたことがなかったから、殆どしてきたことがないのだ。両親がいて、仲間がいて、信頼できる人達に囲まれて……「この世界の不動遊星」は基本的に我慢を強いられたことがない。 遊星は調子を整えるようにして深呼吸をして、それから様子を窺っているクロウやジャックに後ろ手にハンドサインを送った。遊星が前へ出て行くと、十代がひどく困ったような様子で生唾を飲む。うしろめたそうなその様は、「ただいま」という言葉を資格がないからとばかりに呑み込んだみたいだった。そのように少なくとも遊星には見えた。 「十代さん……」 それが最後の引鉄だった。決断を下すのに、十代のそのよそよそしい事後のような仕草は充分すぎたからだ。 ――不動遊星にとって、それが今最も大きな意味を持つ宣告だった。 「遊星、あのさ、おれ、」 「いえ。……いえ、いいんです、もう。十代さんは……少し、待っててください。俺には今、先にやることが出来たので」 「え?」 あの日遊城十代が空から降ってきた時に、全てが始まった。記憶喪失の異邦人。彼のまわりには不思議が多く、おかしなことが頻繁に起こる。彼が何らかの秘密を抱えているのかもしれないなんてことは、拾って三日目にはもうみんな薄々勘付いていた。でもそれでよかったのだ。十代はチームに迎えられたし、彼もそれで満足して、馴染もうと努力もしていて、ものごとは円滑に進んでいた。 あの男が現れるまではだ。 ヨハン・アンデルセンが現れてから目に見えて事態は動き出した。十代とヨハンの間には遊星に見えない何かが現れ、それは徐々に育って急速に結実した。そのうえ、タイミングを図ったようにヨハンの知人であったという父が遊星に釘を刺してくる。牽制に次ぐ牽制。ふたをして、「子供は見てはいけませんよ」と棚に仕舞われるアルコール瓶やシガレットケースのような、そういう曖昧な拒絶感。 だから遊星はヨハンが嫌いだと思った。事実、遊星の立場から見たヨハンは、充分に「いやなやつだ」と言われるに足る条件を備えていた。大人の立場から子供扱いして、含みを持たせた言動で遊星を揺さぶり、そして十代を連れて行った。 ……連れて行ってしまったのだ。決して、もう二度と、遊星の手の届かないところへ。 不動博士が予見した通りに、本当に連れ去ってしまった。 「アンデルセン博士」 こみ上げてくる複雑な感情を呑み込んで彼の名前を呼んだ。その名を口にすると、いつも舌がざらつくように思う。いやだな、という思いが舌を支配するのだ。だけど必要だからもう一度繰り返した。「アンデルセン博士」。思い切り、頭に泥団子でも投げつけてやるような調子でだ。 「俺のことをご指名、ってことでいいのかな?」 ヨハンが自分のことを指さして確認を取った。 「はい。いい加減、はっきりさせておきたいと思ったから」 「それは俺達の関係についてってことでいいかい? 十代を巡る、どろどろの昼ドラみたいなそれについてだ。……おっと、睨まないでくれよな。冗談だ。……十代、冗談だって、ほんとほんと」 まるで緊張などない様子でひらひらと十代に向かって手を振り、ヨハンは遊星にきちんと向き直った。彼に緊張が見られないのは翻って、自信の表れに相違ない。舌打ちを堪えて彼の全身を値踏みする。きちんとアイロンの掛けられたタイを結び、しわのないシャツに身を包んで立っている彼は実に隙のない社会人といった風貌だ。 それなのに、言葉の適当さが全てを台無しにしていた。相容れない。やはりこの人とは「決着」を付けねばならない。 「先に言っておきますが俺はあんたがきらいです」 「おっ、新鮮。遊星くんにあんたとか言われたの、人生で初めて」 「きらいです。憎いわけじゃないが、だいっきらいだ。以前十代さんにも話しましたが、嫌悪と言うよりは苦手意識の方が強い。その理由を、俺はずっと悔しいからだと思っていた。十代さんを、俺がどんなに憧れて焦がれて手を伸ばしたとしても手に入りっこないものを、あんたが平然と奪っていくからだと、信じていた」 「ふうん。それで?」 「今でもわからない。このいやなきもちの、本当の正体が。だけどそのままじゃいけないんだと思う。俺はこの違和感や不快感と戦わなきゃいけない。だから」 今、ここで全ての決着を。甘ったれた自分と、だいきらいなアンデルセン博士への感情、遊城十代への拗れた憧憬。これら全てがうやむやのままでは、不動遊星はきっと何も出来ない。 それでは、たくさんのものが無駄になってしまうだろう。名もなきファラオの思い、未来を委ねた知らない自分の意思。双子の望む世界。そして遊城十代のあるべき場所、還るべき、どこか…… 遊星の身体には、今幾重にも鎖が張り巡らされているみたいなものだった。一つ一つは大したことではないはずなのに、それらが集まって絡まることで重たくなって、遊星をどこへも行かせようとしない。 けれどその鎖を課したのもまた自分自身。本当は知っている。だから戦うのだ。 「俺とデュエルを。俺はあんたを倒し、打ち勝って、答えを手に入れます。そうしてやっと前へ進むことが出来る。もしも本当に世界の終わりがやってくるのだとして、その荒唐無稽な未来を突き進むために、俺はあんたを超えなきゃならないんだ」 遊星がデッキを取り出してヨハンに突き付けると、彼は茶化すような表情をやめてとても真摯な顔を遊星に見せた。何か言いたげな十代を無言で制し、彼もまたデッキケースを取り出して見せる。 双子が心配そうに遊星の顔を見ていた。彼らの顔にはわかりやすく、「ヨハン・アンデルセンは生半可なことでは倒せない強者だ」と書かれていたが無視した。ヨハンが強いなんてことはとっくに分かりきっている。骨の髄まで思い知らされたばかりだ。だってそうだろう、強くなければ、強者でなければ、遊城十代の隣になど烏滸がましくてとても立つことは許されない。 知っている。だって遊星にはそれが出来なかったのだ。 ◇◆◇◆◇ 「えっと……あの。どういうこと? 何が起こってるわけ? 俺にはもう、さっぱり……」 自分を蚊帳の外に置いて突然始まったそれに十代は大変たじろぎ、わけもわからずその場に立ち尽くしてしまっていた。ポッポタイムに居たその場の誰の言葉も聞こうとせず遊星がいきなりデュエルをふっかけ、ヨハンはそれに応じ、ソリッド・ヴィジョンシステムが作動して……それでこれだ。 だが、きょろきょろと辺りを見回して見たところ、納得がいかずに慌てふためいているのは自分と、それからブルーノだけのようだった。色々な物事に聡いアキだけでなくクロウやジャック、双子の子供達でさえうんうんと頷いて何かに納得している。 「せ、説明! 説明してくれよ、誰でもいいから!」 「まあ急だったもんね。でもなんか、うん、わかんなくもないかな」 「そうね。遊星、色々考えてたみたいだし」 「……遊星の考えてることはいつも難しすぎて、俺にはあんまりわからなかった。そういえば」 「わたしも今思い出したわ。ママって、パパ以外の人が考えてることを察するの本当に苦手だったわよね」 龍可が言った。その口ぶりではヨハンの考えは常にわかると言っているようなものだが、こと今に限ってはヨハンの行動も理解出来ているとは思えなかった。 「ジャック、クロウ、アキちゃん、わかりやすく教えてくれ。頼むから」 「……。俺達にしてみればようやく腹を決めたかというところだな。あいつはここのところ常にくすぶっていた。お前が空から落ちてきてからずっとだ。あんなことを口先では言っているが、要は切っ掛けが欲しかったというそれだけのことに過ぎん」 「……どういう意味?」 「よーするにだ、遊星は今、自分自身と戦おうとしてんじゃねーかな。……って、俺ら幼馴染みは思うワケよ」 ふんぎり、ついてなかったんだよな。今まで。ジャックの説明をクロウが更に捕捉する。それでようやく少し事態が飲み込めてきて、十代はああ、と手を打った。 遊星がヨハンを嫌っているのは知っていた。彼は十代に向かって「きらいです」とはっきり、三度も四度も繰り返してそのことを言ったし、しかしそのあとか細い声で「わすれてください」とも懇願した。泣きそうな声で許しを請い、「でもおれのことはきらいにならないで」と、二律背反に追い込まれて。 ヨハンを嫌う気持ちが自分のどういった部分から根幹を成し造り上げられたものなのか? それと向き合い、きちんと対面して受け入れていかなければいけないのではないか。その感情は不可思議で、生理的嫌悪の一言でずっと済ますにはあまりにも複雑すぎる……と遊星自身うっすらと自覚はしていたということなのか。 十代がしどろもどろにそのようなことを尋ねるとアキが腕組みをして厳しい顔で頷いた。 「多分、そういうことなのよ。アンデルセン博士に対する遊星は身勝手だし、子供っぽくて、とてもわがまま。それは恐らく彼の中に『ヨハン』を超えた別のものも見出しているからじゃないかしら。私達はそう考えてる。だからなんとなく、こうなるような気はしていたの。いつか……そう。例えば十代、あなたが本当のことを思い出した日には」 アキの説明に重なるようにして、ヨハンに向かって攻撃宣言をする遊星の声が十代の耳を貫いていく。声音には幾重もの感情が込められていて、ひどく俗っぽい。その声をもう一度聞かされて、自己嫌悪と、自己保身が手を取り合って遊星を板挟みにしている図を十代は思い浮かべた。感情が剥き出しのまま先走って、本体の身動きを封じている。そうして、それらが束になってやがてヨハン・アンデルセンという男の姿を取ったのだ。 「……つまりヨハンは仮想敵……ってことか?」 「それは少し違うと思う。遊星がアンデルセン博士を嫌っているのは、事実でしょうから。遊城十代を取り合おうと思った時、彼は確実に遊星にとっては敵だったのよ。だけど……十代を自分のものには出来ない、不可能だっていうことを最初から知っていて言い聞かせようとする自分もいたわけ。そのいがみ合いに引き込まれて、自己超克のために使われていることをアンデルセン博士は理解している。それで構わないと思ったんだわ……大人は子供の成長に、付き合ってやるべきだとか、そんな理由で」 その上から見下ろすような考えがまた遊星を刺激してるんだけど。アキが溜息を吐いた。それはまったくその通りだとギャラリーの全員が納得出来る事実だった。何しろそんなことを好き勝手言っているその瞬間にも、遊星がヨハンの安い挑発に乗っけられていくのだ。 「遊星のお父様から聞いたかもしれないけれど、彼、今まで挫折とか失敗とかしたことがないの」 「あ、そうそう。それいつだったか確かに言われた」 不動博士の台詞が脳裏に蘇る。『この子は自信過剰ではないけれど、挫折の経験がない。友人には恵まれているのかもしれないけれど、人付き合いは得意じゃない』。 「遊星をお願いしますって、言われた時だ。確か」 「自分の力を過大評価はしないけど、まずもって遊星のポテンシャルが高すぎるから、相対的に自己評価は高くなるし、それに見合う成果をずっと出し続けてきたのね。それこそ挑戦者、壁となるものが自分から身を引いていなくなってしまうぐらいに。遊星の鼻っ柱を折ってやろうなんてやつで、遊星に真っ向から勝れる人間は今まで出て来たためしがないわ。だから彼は挫折を知らない。ものごとに、成功以外の結果が出ることを、そもそも分岐の存在からして、体験として感覚として理解が出来ないの」 「天才すぎたんだよね」 「ある意味そうとも言えるかも。でもそれはちょっと、不幸というか……幸いではなかったように私は思うな。この世界の遊星って、傷付くことを知らない硝子玉みたい。そりゃ私だって、龍亞みたいに抜けすぎてる遊星は嫌だけど」 「る、龍可!!」 「失敗を知らない人間がきちんと前へ進んでいくことは困難を極める、ってむかしパパが言ってたわ。ママは、いっぱいいっぱい挫折と失敗を繰り返してきたから強いんだって」 龍可の言う「パパとママ」が「ヨハンと十代」であることは明白だった。それに双子は、挫折と失敗を乗り越えて強くなり、未来を勝ち取った不動遊星のことも思い出している。その彼の姿と比べると、あの遊星の姿はやはりどうしても幼いのかも知れない。傷が付くことを怖がっている真綿の中の硝子玉。 十代の人生というのは、だいたい、挫折と失敗の繰り返しだった。ように今俯瞰すると思える。一つ山を乗り越えたあとで後悔が要らなかったためしなんて滅多にない。それは今も同じで、海底都市ルルイエでのことの顛末を、形は動であれヨハンと十代は悔恨として共有している。 あの《聖女》を哀れと呼ぶ事が出来ないのは、その気持ちを忘れられないからだ。 「遊星にとって、パパ……ヨハン・アンデルセンは『お父さん』の偶像と似てるのかも。お母さんを、お父さんにどうしても取られてしまう男の子が癇癪を起こすのと縮図にすると一緒。でもそれ、全然、普通のことなのよ。多かれ少なかれどこかでみんな、通って来てるはずのことで」 「親離れかあ。それなら、不動夫妻とやってくればいいのにな、遊星も」 「そりゃ難しいな。あの家は父親が子離れしなさすぎてる」 「不動博士は食わせ物だ。彼は俺が知る限りでも相当な愛妻家だが、それに輪を掛けて息子を溺愛しすぎている。親離れ云々の前に、まず真っ先に疎ましさを感じて遊星は高校卒業と共に親元を飛び出してしまった」 「そう。それで、今に至るわ。どうかしら十代? それで何か、まだ聞きたいことは?」 「いいや、もう大丈夫だ。……俺、思い出したんだ。俺の知ってる『遊星』は、親子喧嘩の仕方とか、知らないんだよな。ほんとは。だからそういうのやっておいた方がいいかもしれないって思った。茶化したりはぐらかされたりしないで、真っ正面から全力、ガチンコで、……男の子なんだから」 デブリ・ドラゴンにチューニングされてスターダスト・ドラゴンがフィールドに舞い降りる。ヨハンのフィールドにはアメジスト・キャットが一体だけだった。魔法・罠ゾーンに紅玉と碧玉が並んでいる。その様子から見て遊星が僅かに優勢のようだったが、ヨハンは笑みを絶やさず余裕の姿勢を崩そうとしない。それに苛立っているのか遊星が舌打ちをして、カードとは裏腹に雰囲気だけは遊星の方が劣勢に見えていた。 ◇◆◇◆◇ 「さあ、これからが本番だぜ。もっともっと――楽しいデュエルをしようじゃないか。そうだろ? 遊星くん」 「俺は……俺は……!!」 「魔法カード《宝玉の導き》を発動。デッキから《サファイア・ペガサス》を召喚し、モンスター効果発動! デッキより《アンバー・マンモス》を永続魔法扱いで魔法・罠ゾーンに置く。更に手札から《宝玉の解放》を発動、《サファイア・ペガサス》に装備する。バトルだ! 《サファイア・ペガサス》で《スターダスト・ドラゴン》を攻撃!!」 「……罠発動! 《くず鉄のかかし》! 攻撃を無効化し、このカードはセット状態に戻る!!」 「なるほど。それじゃ俺はこれでターン・エンドだ。どうかな。そろそろ何かいいものでも、見えてきたか?」 スターダスト・ドラゴン。不動遊星のエースモンスターであり最も付き合いの深いパートナーモンスター。そして、あらゆる逆境をねじ伏せてきた切り札。そのスターダストを持ってして、ヨハン・アンデルセンの牙城にはまったく崩れる気配がない。彼は余裕綽々といった風体で毅然として立ち、カードを繰っている。遊星には経験のないことだ。さっきから「はじめての体験」が多すぎる。 ヨハンを倒す。ヨハンを倒して、そうすれば何かの決着がつくのだと遊星は信じていた。そこには漠然とした「超えなければいけない壁」がそびえ立っていて、遊星の手によって壁はヨハン・アンデルセンと名前を付けられた。 遊星の今までの人生において、越えられない壁や倒せない敵はいなかった。遊城十代や不動博士を超えることは出来ていないが……彼らは目標や憧憬の対象であり、そのようななまやさしい偶像ではなかったのだ。 「――俺のターン」 スタンバイフェイズ、それからドロー一枚。引き当てたカードをちらりと見て息を吸う。遊星はデュエルが好きだ。でもそれはいつだって競技としてのデュエルだった。大会でのそれはもとより、学生時代にデュエル・ギャングもどきの大暴れをしていた時だって、相手との間に力量がありすぎて駆け引きとしては成立していなかった。命がけのデュエルを不動遊星は知らない。身を焦がし、燃やし尽くさんとして、魂を天秤に乗せるような戦い方を、遊星は知らない。 「思うに、君は覚悟が少し足りてないんだ。違うかな」 メインフェイズ。ヨハンは先程からわざとらしいぐらいに挑発じみた言葉ばかり投げて来る。はじめに泥団子でも投げるように見たのが気に障ったのかどうか――それはわからないが、遊星がその挑発にカチンときてうまくいなしきれていないのは事実だった。 「ゆうくん」と自らを呼んではばからない父の姿が被って仕方がない。でもアンデルセン博士は赤の他人だ。それも遊城十代を、遊星の憧れを、太陽のような彼を、連れて行った相手。彼は超えてはいけない相手ではない。 「手札より通常魔法、《シューティング・スター》を発動。《宝玉の解放》を破壊する」 「《宝玉の解放》の墓地発動効果。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、デッキから宝玉獣モンスター一体を永続魔法扱いで魔法・罠ゾーンへ置くことが出来る。俺は《エメラルド・タートル》を選択」 「バトル。《スターダスト・ドラゴン》で《サファイア・ペガサス》を攻撃!」 何かが燃え盛っていた。見たことも感じたこともないような高揚感が遊星の身体中を駆け巡って、囁いているのだ。今なら何か限界を超える事さえ出来そうな気がする。 そう感じた瞬間に視界が妙にクリアになった。 風景がどこかへ消し飛んだかのような錯覚の後、見守っていたギャラリーも吹き飛んだ。フィールドにモンスター達、向かい合って向こうにヨハン。マス目に覆われたみたいな電脳空間じみた四方の壁。遊星の足下に、パズル。 『この問題は、見た限りきみたち個人の問題であるように……つまりオレの果たすべき約束とは関係ないものなのだろうと……見えたのであまり口は出さないようにしていたんだが』 パズルはウィジャトの眼を浮かび上がらせている、黄金の逆三角だ。千年パズル。海馬瀬人の手により武藤遊戯から継承された、「この世界の遊星」だけが手にした特異点。 『オレが寝ている間に考えていたことがある。歴史の分岐と修正、『消えていった不動遊星』が口にした伸縮特性という言葉。パラレル・ワールドは、本当に、まったくの完全に相互不干渉な立場にあるのか? という疑問点。不動遊星を皮切りにイリアステル、それにオレの知らない十代とヨハンがオレ達の世界まで到達したことを考えれば、干渉は可能なのだろう。しかし物事には必ず法則がある。例えばそれは、『同じ時代の同じ場所に同じ人間は存在出来ない』ということ。それから』 世界の可能性は無限に存在する。不動遊星が世界を救う可能性から、そもそも不動遊星が生まれ得ない可能性まで。しかしどこかにスタンダードは存在する。スタンダードをオリジンとして、可能性はあらゆる分岐の枝を広げていく。消えた遊星によれば、最もスタンダードな世界は「武藤遊戯が名もなきファラオと正しく別れを告げた」可能性なのだという。だが、幾人もの手で守り通されたはずのその可能性はヴェルズと成り果てたイリアステルの手によって強引に葬り去られてしまった。 では。 『世界の全ての可能性に注がれるエネルギーは不変だ、と仮説を立てたヤツがいた。お前は非科学的なことが嫌いだったんじゃあないかと訊ねたらこれは非科学的オカルトに基づいた物ではなく云々と……まあどうでもいいんだが、とにかく、注がれ続けるエネルギーは一定だ。にも関わらずその受け皿が一つ減った。するとそこに分配されていたエネルギーはどこへ行く?』 スタンダードが有していた、歴史の核となるエネルギーはどこへ行ってしまうのか? 『海馬は、こう考えていたようだった。恐らく最も許容値の高い次の世界――歴史の再修正を託された、『オレ達』の世界へそれは巡ってくるだろうと』 名もなきファラオは遊星の隣に浮かび上がり、悪戯を思いついた少年を思わせる横顔で力強く言い切る。 『半信半疑だった。だが、どうやらこの現状、仮説は真実だったようだな』 風景が戻る。いつの間にかファラオの亡霊はパズルに戻り、そこにはいない。ヨハンが何かに気が付いたかのように息を呑んだ。遊星は右腕を押さえ、スターダスト・ドラゴンがサファイア・ペガサスに襲いかかるその様を見る。速度が安定しない。世界が早巻きになり、かと思えば途端に減速する。 ……目眩がする。 「ッ……《サファイア・ペガサス》の効果発動! 破壊された宝玉獣は、永続魔法扱いとして魔法・罠ゾーンに表側表示で置くことが出来る。……さて。ここからどうしたもんかな……」 サファイア・ペガサスを破壊されたことでヨハンに通ったダメージは七〇〇。まだ致命傷ではない。だがあの尋常ではない様子からして、手加減をしている場合でもなくなっただろう。 異変に気が付いたギャラリーの方でもざわめきが上がっている。龍亞と龍可が有り得ないと言いたげに遊星が抑えている右腕を見ていた。手袋の下からほのかな赤色が光ってしるしを形作っているのだ。 「《ドラゴン・ヘッド》だ」 龍亞が呆然と呟いた。ではこれがシグナーの痣。噂には聞き知っていたが、ヨハンが目にするのは初めてだ。 「こりゃ、うかうかしてられないね……」 十代がヨハンと遊星を困り果てた様子で交互に見ている。だいじょうぶだよ、と唇の動きだけで彼に声なき言葉を伝えた。ヨハンは自分の心臓の音を聞き、胸の高鳴りを自覚する。ワクワクするデュエルだ。間違いなく、この世界に来てはじめての、とびっきり最高でスリリングな。 |