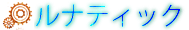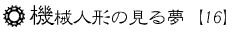伸縮特性とオルタナティブ。 歴史にはただ一つの最も正しい形が存在しており、幾つもの並行世界はその分岐の結果の「パラドクス・エンディング」だと考えるとする。正しい歴史以外は、何かが欠けているので未来へ至ることが出来ず、いずれどこかでどん詰まりになる。そのため全ての歴史のエネルギーは最終的に、「正史」へ向かって集まっていく。 伸縮特性は歴史が正しくあろうとする力。歴史は伸縮特性に従って、正しい形に添うためにエネルギーを集める。正史と異なるエラーコードは、可能ならば代替――オルタナティブ――して、なるべく歴史の寿命を延ばそうと尽力する。 それは、イリアステルという組織に意図的な歴史改革を加えられたこの「ゼロ・リバースのない世界」でも決して変わることのない法則だ。だからこそ、少しでも不確定要素を摘み取らんがためにパラドックスは百年前に武藤遊戯達の前に現れ、……そして正史の不動遊星の前に破れた。 歴史の改竄を成し遂げようとして、歴史の特性そのものに敗北したのだ。 「それじゃこれも……或いはそういうことなのかもな……」 眼前の、「恵まれた不動遊星少年」の右腕を見てヨハンが独りごちる。龍亞が「ドラゴン・ヘッド」と呼んだシグナーの痣は本来なら正史の不動遊星しか持ち得ないはずのものだ。でも確かに今ここにある。 だけどそれは絶対に有り得なかったことではない。不動遊星は、恵まれすぎて、何一つ不自由しないようなこの腑抜けた平穏の中にあってなおイリアステルが「英雄因子」と呼んだ「歴史を大きく揺るがす能力のある特異存在」であり得るのだ。遊城十代と武藤遊戯がそうであったように、彼には歴史を変えるだけの力が眠っている。ただ、今はその使い方を知らないだけで。 そして正史の存在が何処かへと消え去った今、歴史の修正エネルギーは「最も異常の多い場所」へと集中する。だからシグナーの痣はここに現れたのだ。 「遊戯さん! だけど手出しはなしですよ」 『人聞きの悪い。それにオレは遊戯じゃないぜ。武藤遊戯――オレの信頼する相棒は、もう死んだ。オレを遺して逝くという負い目を持たせたまま』 「では名もなきファラオ。遊戯さんは、そんなことはあなたに言いません。それは絶対だ」 ヨハンが言うと十代がそうですよ、と拳を握りしめて肯定した。彼は名もなきファラオがそんなことを口にするのが、少し、いやみたいだった。 「バトル終了。モンスターを裏側守備表示でセットし、更にカードを一枚伏せてターンエンド。……何を話しているのか知りませんが。俺は、あんたに勝ちます。何度も言ったとおり……勝ってその先へ進んでみせる」 遊星の瞳には、意思の炎が燃え上がって揺らめいていた。今までの彼が見せていたような「子供らしい」脆弱さをひねり潰し塗り潰して、彼はヨハンに相対している。 今の彼なら戦っていけるだろう。尤も歴史に立ち向かう気が彼にあるかどうかは別だが……。 であるから、ヨハン・アンデルセンは不動遊星に負けてやるわけにはいかない。 「なかなか言うじゃないか。だがどうかな……遊星くん、君の可能性、俺は今この時点で充分に見せて貰ったよ。君は今、とっておきの切り札へ至る可能性を確かに手繰り寄せたんだ。だがそいつを使うべきは俺に対してじゃあない」 「何を言ってるんです? ……怖いんですか? 俺に負けることが?」 「まあね。愛する家族の前で敗北を見せるのはスマートじゃない。だが……そういうのとも違う。いいかい、遊星くん。『とっておきの、とっておきの、とっておき』は――一番大事な時、大切な人を救うためにこそ、使うのさ。そして今はその時じゃない。俺のターン!」 フィールドに伏せられた二枚のカードから感じる「予兆」めいたものが、ヨハンの肌をぴりぴりと刺激していた。遊星の右腕にはまだ痣が出ている。このまま手抜かっていれば本当にヨハンは負けてしまうだろう。なりふり構ってはいられない。 「悪いが遊星くん、俺は汚い大人だ。そしてそういう大人は得てして手段を選ばないもんさ。そういう意味では……『俺達が』これから立ち向かうべき相手は、俺よりはやりやすいかも知れない。君にとっては最悪の相性だとしても」 「……『達』?」 「そう。君はこのデュエルで俺に勝って、未来へ進むと言ったな。だがこのデュエル、勝つのは俺だ。そして勝利を手にした後俺は君に申し込もう。一緒に戦ってくれと」 握手を求めてそうするように、ディスクを構えていない方の腕を伸ばした。 遊星の瞳を真っ直ぐに捉え、見据えてそう宣言する。彼がきょとんとしてヨハンを見返してきたのがすぐに分かった。全くもって理解出来ないというふうな表情で、目を丸くして、勢いを削がれたように。でも当たり前だ。打ち倒そうと思っていた相手に、手と手を取り合って共に行こうなんて言われたってはいそうですねとは言えないだろう。 特にこの世界の不動遊星少年はそうだ。だから実力行使をする。申し訳ないがヨハンだって負けるのは好きじゃないし、そろそろワクワクするデュエルに出し惜しみはしたくない。ドローフェイズ。ヨハンが手繰り寄せたのは一枚のモンスターカード。この状況から戦局をひっくり返し、制圧して遊星を揺さぶるのに十分な一手だ。 「君の力が必要だ」 囁くような調子で、しかしよく通る声音でヨハンは遊星に言った。 「あんたは……いや、ヨハン・アンデルセン、あなたは、」 「もう一度言う。君の力が必要だ。俺の愛した人が、好きだと言った世界のために」 「……何を……見ている?」 遊星が固唾を呑む。そして束の間の忘我が彼を襲った。ヨハン・アンデルセンの背後に巨躯が影絵となって映し出される。影が吼える。高らかに。 その中に遊星が見出したのは圧倒的な威圧感だった。優男然とした佇まいに似つかわしくない、何か強大なもの。そしてヨハン・アンデルセンという男――今までは少なくとも彼自身は人間だと信じていたのだが――が、まるで全然異なる別種の生き物であるかのような、肌を泡立たせかねない違和感。 「もう少ししたら、俺のとっておきは見せてやるよ」ヨハンが微笑んだ。「でもまずは、先にこいつからだ」遊城十代の隣にやすやすと立ち並んで見せる、あの、遊星がいつもいやな気分になる――笑顔で。 「メインフェイズ。このモンスターは通常召喚出来ない。永続魔法三枚をリリースすることでのみ、召喚が可能だ。俺は永続魔法扱いとなっている宝玉獣三体をリリースし、このモンスターを特殊召喚する。現れよ――三幻魔が一体、《降雷皇ハモン》!!」 雷が落ちた。 文字通り、雲一つなかったはずのガレージの外の空を切り裂くようにして、落雷が近くの避雷針を襲った。 ◇◆◇◆◇ ギャラリーはどよめきで溢れていた。その中でも特に呆然としているのは、意外にも十代で、龍亞と龍可はその中で一番落ち着いて事を静観している。 「とっておき、出しちゃうんだ」 龍可がふうん、と顔に手を当てて呟いた。龍亞もそれに頷く。ヨハンのとっておき、彼が絆を結んだ最強のパートナー。それをぶつけるのは意外ではあったが、二人とも納得は出来ていた。 「とっておき……って、あれか? 今出て来た《降雷皇ハモン》とかいう……確かに尋常じゃない何かを感じるけどよ」 「ううん、違うよ。あれ、俺達見たことないし。だからパパのとっておきはまた別」 「あんなもん出しておいてまだとっておきじゃないのかよ」 「うん……あの精霊も、確かに普通じゃないけど。パパのとっておきはね、パパの半分なの。パパそのものでもある、神の領域に名を連ねる精霊」 「そのものって」 「パパは半分人間で、半分精霊。そう言えばパパとママの話した時にあんまり詳しく言ってなかったかもね。あのね……精霊界に行くと、みんなパパのことをこう呼ぶわ。――『宝玉神』、って」 でも、あれ何? 龍亞の尤もらしい疑問。それには、溜息を吐いて複雑な顔をしながら十代が答えてくれた。《降雷皇ハモン》、星十、光属性雷族。三幻魔と呼ばれる強力無比かつ危険で恐ろしいカードの一枚。バクラが武藤遊戯に預けられ、そこからヨハンと十代へと手渡されたカード。 「百年前の時は、なんか結界張るときの依り代に使ったとか言われたんだけど……俺にはそういうことよくわかんないし。光の護封剣を実体化して運用するのなんかとは訳が違うんだろうしなあ……」 「え……そんな危なそうなモンスター、普通に野良デュエルで使っちゃって大丈夫なの?」 「まあ、俺もまさかヨハンがデッキにあれを入れてるとは思わなかったけど、見た感じ心配はなさそうだな。三幻魔は確かに、一発使い方間違えると全世界のエネルギーを吸い取っちまうようなやつらなんだけど」 「なにそれ。イリアステルがどうこうする前に世界が終わっちゃうじゃない」 「一度そんなことがあったんだ、うん。でも今は俺とヨハンで睨みきかせられるからな」 問題ないぜと何かをもう一度考え直してから十代が明言する。龍可が指を折りながらハモンのレベルを確かめて、それから納得したというふうに手を打った。 「あ、レベル十だから。今は他の二枚は出てないし」 「そっか。パパとママなら、大丈夫だよね」 降雷皇ハモンの効果が発動して、スターダスト・ドラゴンの視線がハモンに釘付けになる。ハモンが表側攻撃表示で存在する限り相手モンスターはハモン以外を攻撃対象に選択出来ない。 遊星は困惑を露わにしていたが、召喚即時反応の罠を発動する様子はなかった。伏せられているカードは防御のためではなく攻撃のためのものだったらしい。彼が悔しそうに唇を噛み、表情を歪めるのがアキやジャック、クロウらには見えた。 「なんだ、警戒して損したかな。そのカード……奈落か何かだったら困るんで、ハモンで警戒除去させようと思ったんだけど」 「……。俺は防御系はあまり入れないんです。くず鉄のかかしぐらいで」 「まあそうだな。君、どっちかというと手数で補って間髪入れず攻めてくるタイプだし。意外と十代の方が慎重で疑り深い。……さて、このまま俺が攻撃してもハモンの一撃はかかしで回避されてしまうだろう。だけどな遊星、俺がそのあたり、全然対策してないと思うか? 面白くなるのはこれからだ」 ヨハンが口端をぺろりと舐め、少年のように瞳を輝かせた。遊星の額を冷や汗が流れ落ちていく。知らず生唾を呑んでしまい、遊星はたじろいだ。怯えている? 今、この男に……自分は。 ヨハンの笑みがますます深まった。ハネクリボーの無邪気な鳴き声が遊星をより一層警戒させる。手札・伏せ、共に心許なし。くず鉄のかかしは健在だが、あんな大言壮語の後だ、対策されてしまうだろう。 肌が泡立つ。右腕の痣に無意識に視線が行っていた。それは依然として遊星の腕に浮かび上がっていたが、彼の志が弱ってしまったからなのか仄かな光になってしまっていた。 「手札から《宝玉獣トパーズ・タイガー》を通常召喚。これで条件は揃ったぜ。罠オープン、《虹の引力》! 自分フィールド上及び墓地に『宝玉獣』と名の付いたカードが合計七種類存在する場合のみ発動することが出来る。自分のデッキまたは墓地の存在する『究極宝玉神』と名の付いたモンスターカードを召喚条件を無視して特殊召喚する。顕現せよ、《究極宝玉神 レインボー・ドラゴン》!!」 虹色の奔流が視界への暴力となってその場の誰をも襲った。 巨大な龍が現れたかと思うと、羽根を伸ばし、吼えて存在を誇示する。白く流麗な体躯には鮮やかな七つの宝玉が埋め込まれ、佇まいは高貴でさえあった。衝撃波が実体を持ってガレージ中を吹き荒れる。ソリッド・ヴィジョンの枠組みを超えてその龍はこの世に姿を現した。 「おい龍可、龍亞! なんだあれは!」 「つうかプレッシャー半端ねえ!! あいつ何者なんだよ!!」 たまりかねてジャックとクロウが叫ぶ。まるで見たことのないモンスターだ。宝玉獣のヨハン――約百年前に没したプロ・デュエリストの公式戦使用デッキには宝玉獣カテゴリのカードこそあれ、このモンスターは存在しなかった。 「レインボー・ドラゴンは宝玉獣を束ねる虹の神。そしてパパの半身。パパは、魂の半分が精霊で出来てる。だから人よりちょっと老けにくいのよ」 「ねえ龍可、それじゃもしかして十代も……」 「ママの半身はユベル……《ユベル−Das Extremer Traurig Drachen》。星十二、闇属性悪魔族。精霊界の女王であるエンシェント・フェアリーは昔私達に言ったわ。パパとママは……、こんなに人間らしい精霊は、他にはいないって……」 アキの言葉を肯定した龍可の声は躊躇いがちだった。彼女は自分達の今際の際、両親を置いて行ってしまった日のことを思い返して俯いていた。 「十代……」 「いや、いいんだ。気を遣ってくれなくって。そういうわけで俺、あんま真っ当な人間じゃないし……最初から遊星と一緒にずっとは、いられなかったんだよな。それに俺、」 「違うわよ。私そんな話がしたいわけじゃないわ。十代あなた、思い込みが激しいって人に言われること、ないかしら」 アキの言葉を遮った十代の台詞を、再びアキの声が押し留めた。十代を遮ったアキは呆れ調子で、声音がいつになく厳しい。 「歴史……パラレル・ワールドが、無数にあるのだって龍亞と龍可は言った。この世界はいつか行き詰まってしまう分岐で、正しい歴史は何者かの手によって葬り去られてしまって……だからそれを取り戻さなければいけないんだって。そして、今ここにいる遊城十代とヨハン・アンデルセンは正しい歴史からやってきた存在。この認識で合ってる?」 「あ、ああ」 「この世界の遊城十代とヨハン・アンデルセンは百年前に死んだわ。病気でも事故でもなく、寿命で。けれどそれでも……あなたたち、歴史をどうにかしようってそう言ってるのよね」 「ああ。それで例えこの世界ごと、今この場にいるアキちゃんやジャック、クロウ、龍亞や龍可……遊星を、消してしまうとしても。俺とヨハンはそうするよ」 「……そういうことね」 アキは憑きものが落ちでもしたかのような顔をして頷いた。十代には彼女が一体何を思って何を結論付けたのかすぐにはわからなかったが、チームメイト達はそうでもなかったらしい。アキの様子にジャックとクロウが仕方ないと言わんばかりに息を吐いて、龍亞と龍可がほっとしたように顔を輝かせたからだ。一人、ブルーノだけがそれにこれといった反応を示さず、あまり表情のない顔をして遊星の方を見ている。 「決めたわ。あとは遊星次第じゃないかしら」 アキが言った。デュエルがバトルフェイズに突入する。降雷皇ハモンが鎌首をもたげ、レインボー・ドラゴンが大きく口を開けた。 ◇◆◇◆◇ あれは、いつのことだったろう? 遊星は眼前に降り立った二体のレベル十モンスター、神の領域に至るそれらを見つめながら雑多に押し寄せる記憶らしきものを視ていた。それらははっきりと時期まで思い出せるものから、こんなことが本当にあっただろうか、と疑問に思うものまで様々だった。その中の一つ、身に覚えのない光景が眼前のそれと被ってちらつく。遊星はあれを知っている。宝玉の神レインボー・ドラゴン、あの龍を……知っている。 『よくも――ヨハンのカードを!!』 「誰か」の思い出の中で、遊城十代が叫んでいた。知らない機械人形がそれを嘲笑う。遊星は何故だかそれが酷く許し難くて……でも本当は何が許せなかったんだろう? 機械人形がカードを奪って使っていたことがか? それとも、遊城十代が、ヨハン・アンデルセンのために怒ることが? 「バトルだ。《降雷皇ハモン》で《スターダスト・ドラゴン》を攻撃。失楽の霹靂!!」 「罠オープン、《くず鉄のかかし》! 攻撃を無効化し、セット状態に戻す!!」 「続けて《究極宝玉神 レインボー・ドラゴン》の攻撃。レインボー・ドラゴンの効果発動、フィールド上の宝玉獣と名の付いたモンスターを全て墓地へ送り、一体につき一〇〇〇ポイント攻撃力をアップさせる。レインボー・オーバードライブ!!」 違うような気がする。そんな些末なことで、あんな気持ちになっていたわけじゃなかった、と思う。遊星はヨハンの攻撃に対応しながら更にその記憶の先を求めた。あの時「誰か」が本当に嫌だったこと。「誰か」が……「不動遊星」が、嫌だったのは。 (何も出来ない……スターダストを奪われて、ただ、遊戯さんと十代さんのサポートに甘んじていた自分が……俺は嫌で……) その時、今まで目を向けようとしなかった事実が見えたような気がした。 「レインボー・ドラゴンでスターダスト・ドラゴンを攻撃! オーバー・ザ・レインボー!!」 攻撃力六〇〇〇にまで至ったレインボー・ドラゴンの攻撃をもろに喰らってスターダストが破壊される。フィールドはがら空き、ライフは残り一五〇〇。 「悪いが、このターンで決着をつけさせてもらおう。俺は手札より速攻魔法、《死者蘇生》を発動する。召喚するのは勿論《宝玉獣サファイア・ペガサス》だ。更にサファイアの効果を発動、サファイア・コーリング!」 「ッ……!!」 「ルビーを選択して魔法罠ゾーンへ。それじゃ、これで最後だ。サファイア・ペガサス! ダイレクトアタック!!」 デュエルの終了を告げるビープ音と共に遊星のライフがゼロになる。敗北だ。それも完敗。ペガサスの足に蹴飛ばされて床に尻をついてしまったその状態で遊星は今一度ヨハンを見上げた。なんてやつだ。 ヨハン・アンデルセンの見る世界を彼の向こうに覗き見て遊星は呆れたように首を横に振る。何を考えて生きてるんだ、この男は。 「さて、俺の勝ちだな。もう一度繰り返すが俺には君の力が必要だ。出来れば、一緒に戦って欲しい。勿論無理にとは言わない。何せ歴史を正したが最後君という存在は消えてしまうかもしれないんだ」 「……。構わない……いや、構いません。『あなた』は……あまりもう、相手にしたく、ない……」 「そりゃ光栄。俺としても十代の大切な後輩をこんなふうに叩きのめすのは良心が痛んで仕方ないからな」 嘘ばっかりだ。朗らかな笑顔でそう宣ったヨハンに遊星は心底敵わないと思った。やはりこの男は父と同族だ。とてもまともに相手にしてはいられない。 肩の力ががくりと抜ける。それと同時に何故だかおかしな気分になってきて、苦笑いが口から漏れた。 「何か面白いことでもあったのか?」 ヨハンが訊ねた。遊星は肩を竦めるとおもむろに立ち上がり、ディスクを仕舞う。 「俺があなたを見ていると嫌な気分になる理由が、ようやくはっきりと言葉に出来るようになったんです。……敵わないんだ。でもきっとそれは……いえ、やめておきます」 「なんだよ、気になるなあ。まあ……俺が思うに、遊星君は本質の所で一緒なんだよ。どんな世界でも」 「……俺にはそれはわかりません」 「それじゃ、俺が保証してあげよう。君は君だ。君は自分が思うように、正しいと信じたことをすればいい」 差し出された手を、今度こそ確かに握り返した。観戦していた仲間達が駆け寄ってくる。「見ててひやひやしたぜ」これはクロウの言。「全くだ。お前は妙にあぶなっかしいからな」とは、ジャック。アキが遊星を抱き締めて「おつかれさま」と囁くのを見て、双子がそれを茶化し始める。 「……ブルーノ?」 その様を一歩引くようにしてブルーノが眺めていた。名前を呼んでも、彼はこちらへ寄ってこない。よく見るとブルーノの肩が僅かに震えているようだった。怯えている。ヨハンにか? そう疑ったが、恐らく彼ではない。 「ブルーノ、おい、どうしたんだ」 「ゆ、遊星、僕……」 「震えが酷いんじゃないか。アキ、ブルーノが……」 「遊星、ダメだ!! こっちへ来ちゃ――伏せて!!」 アキの手をそっと降ろし、歩み寄ろうとした遊星の足がブルーノの彼らしくない叫び声に留められた。耳をつんざくようなそれがガレージ中を駆け巡る。その尋常ならざる様子に遊星らが反射的に身体を伏せるのと同時に、十代とヨハンが叫んだ。彼らの精霊としての本能がいち早く異常を察知したのだ。 直後、爆発が視界と聴力を蹂躙した。 派手な爆発音と共にガレージの入り口がぐにゃりと、火の付いたロウのように歪み溶けた。煙も立ち上り、衝撃波にガレージの中の家具やらが大きく吹き飛ばされる。発火していないことだけが救いと言ってもよかった。瞬く間にチーム・ファイブディーズの拠点が惨状を呈す。遊星はアキを庇う体勢のまま爆心地を見た。一体何が起こったのだ? 煙が薄らいできて、ゆらりと起き上がる影が目に入る。影はあまり大きくない。子供の身の丈ぐらいで……そうだ、丁度龍亞や龍可と同じぐらいの高さだ。 「やっとだ……やっと……わかった……」 影が喋った。少し高い。変声期前の少年特有の甲高さを含んでいるが、焦燥を含んでいて妙に重々しかった。 「僕がしなきゃなんないこと。龍亞をぶちのめすのでも、あの、偽善の固まりみたいなやつをどうにかしなきゃいけないわけでもなかった。簡単だ……ぶっ壊す。それだけ」 煙が晴れる。少年――の姿をした機械人形がブルーノの首を締め上げている。二メートルを超える体躯の青年を両手で掴み上げている様は明らかに異質だった。龍亞がはっとしたように少年の名前を呼ぶ。子供にあるまじき腕力でチームメイトの生命を脅かさんとしている闖入者の名を、けれどその違和感に首を傾げるように。 「る、ルチアー、ノ……?」 「きゃっははははははははっ!! そうそう。よぉ龍亞ァ、なんだよその間抜け顔。全然、ちっとも面白くないよォ?! まあ、お前なんか今となってはどーでもいいし。黙って見てろよ。僕が用があるのはお前らじゃないんだっての」 「え、ええ……? お前俺が嫌いなんじゃなかったのかよ……」 「だーいっきらいだぜ。龍亞も、偽善者面をして憚らないお前らも。けど……もっと吐き気のするヤツが目の前にあるからそっちが先ってだけ。それじゃ、教えてくれよな。お前が何故ゾーンを狂わせたのか。どうやって……何の為に僕達を弄んだのかをさぁ!!」 《ルルイエの聖女》唯一の成功作である機械人形が取り憑かれたようにまた叫んだ。ルチアーノの虹彩のない双眸はブルーノのみを睨み上げ、龍亞にちらりとも視線を寄越さない。 「何か……あったのね……?」 「……」 「お願い、教えて。私、答えによっては……どうしていいのか決めなきゃいけないわ。どうして? 何が起ころうとしているの?」 龍可の声にルチアーノの動きが少しだけ止まった。十代によく似た龍可に、ルチアーノは昔から少しだけ弱く、隠し事があまり上手に出来ないのだ。 ブルーノを締め上げる両手の力は抜かないままに視線を龍可に寄越し、ぼそりと彼が呟く。 「ゾーンが来る。ガレリヤに《聖女》の亡骸を祀り、イコンを掲げたあの心ない狂ったアンドロイドが。だから僕はこいつを壊す。全ての元凶、あらゆる歴史の最大のパラドクス――」 彼の声音の中には悲しみがあり、憎悪があった。お前さえいなければ、という声なき声が見え隠れする。「お前さえいなければ」。ゾーンは狂わなかった。パラドックスは、機械人形のくせに、あんな安らかな顔で棺桶に埋められたりしなかった。ルルイエの聖女は、生まれなくて済んだ。だからルチアーノも、こんな感情を知らなくて良かった。 なのに…… 「エゴで世界の全てを狂わせた、夢見る愚かな機械人形を」 ルチアーノの瞳は悲哀の全てを映し込んでいる。だけど機械人形は泣くことが出来ない。どんなに泣きたくったって、眼球一つ、上手く動かない。 鋼鉄で形作られた指先がブルーノの首筋に食い込む。損傷した傷口から、透明なオイルが流れ落ちて床に滴り落ちた。 |