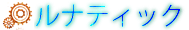この世に神がいるのなら、わたしはそれを殺したい。 ガレリヤは静謐と汚濁でいつも満ち満ちていた。けれど今日は白百合のむせかえるような香りの中ににオイルの鼻をつく臭いが混ざり、違和感が姿を隠し切れていない。へたくそな葬儀の後の臭い。ルチアーノは胸騒ぎの確かさを自覚する――遅かった。 ガレリヤには六つの棺桶が備えてあり、かつてその五つは空箱だった。何もない空虚の棺。だが、今はどうだ。もう「半分も」埋められてしまっている。 ばか、という言葉さえ口から音になって出てはいかなかった。絶句に次ぐ絶句、ただセキセイインコの剥製だけが耳障りにさえずっている。かぶりを振り、諦観を受け入れるため、中央のパイプオルガンを見上げた。そこにはイコンがあった。あの、望んで愛した男に壊された哀れな「おんな」の似姿だった。 「マジかよ……」 いつか、思ったことはある。本物の代わりに出来損ないの偽物を並べ立てて作られたこの聖堂に、彼は偶像を飾るのではないかと。危惧はあった。聖女の死を悼むようなふりをして、まがいものの聖像を造り、掲げるのではないかと…… この部屋に来て、デッドコピーの造物主のことを考えた後吐き気を催さなかったことはない。でも今回のはことさら、一番に、ひどかった。吐き出せるものなんかひとつもないのにひねり出そうとしてルチアーノは喘ぐ。気持ち悪い。きもちわるい。きもちわるい、いやだ、やだ、きもちわるい―― 「――ゾーン、あんたは!!」 ありったけの罵詈雑言の代わりに叫んだ。 棺桶の中には同胞が眠っている。パラドックス、この世界で最初に壊れた機械人形。正史の不動遊星に破れてルチアーノが看取った。次のスクラップはプラシドだ。あの高慢ちきで口先ばかりの役立たず、だけどあいつはルチアーノの一部で、その先の青年期で、アポリアの一かけで。最後のスクラップはホセ。アポリアのパーツは三分の二も失われてしまった。それが誰の仕業か、考えるまでもなかった。 ゾーンだ。 あの狂った造物主、倒錯した処女崇拝を聖女崇拝のうちに拗らせ、ほんものに触れることを許されず偽物のおもちゃでさえ取り上げられた機械人形。 恋を知らない哀れな男。心をほしがった半アンドロイド。自分が何をほしがっているのかさえ自覚出来なかったプログラムエラー。 「母さんは……そこにはもう、いない、のにさぁ!!」 プラシドとホセの死に顔に、表情という表情は見受けられない。そこには一切の恐れがなく、怖れがなく、畏れがなく、涙がなく、心ない。 「あんたもう、変わっちゃったんだ」 絞り出すように呟いてプラシドのマスクに触れた。皮膚を模したカバーがずるりと剥けて、内部構造があらわになる。コードはあちこちが途切れていて、稼働停止原因が複数あることを示していた。コードとコードのつながり方はまるでちぐはぐで、エレメンタリー・スクールの生徒でさえもっとまともなやり方をするだろうと思えるほどだった。 まるで死体のガワに、取り出した臓物をぐちゃぐちゃに詰め直した猟奇殺人の死体みたいな。 機械人形で、何の気はなしに鼻歌まじりでフランクフルト・ソーセージを作るみたいに。 理由は知らないが……大体、そんなものはろくでもない支離滅裂な根拠に基づいているに決まっている……ゾーンは強制的に二体のアンドロイドを機能停止させ、そのうえで二人をばらばらの、ずたずたの、ぼろぼろに、完膚無きまでに解体したのだ。ただのくず鉄にまで還元した。くず鉄の王という我が名を体現でもするかのように……あるいはダイイングメッセージじみて。 アンチノミーとパラドックス、そしてアポリアが友と呼んだ男はもうそこにはいないのだと。 「あんた何がしたいんだよ!!」 答えは返ってこない。棺桶はまだ三つの空きがあって、そこに収まるべき人形は今なお活動を続けているからだ。ルチアーノとアンチノミー、そしてゾーン。今動いているのは、この三つだけ。 だからやけくそみたいな問いかけへの返事はあってはならなかった。 『時が来たのです、ルチアーノよ』 「――ッ?!」 あるべきではなかった返答に思わず振り返ってしまった。見たくなんかなかったのに、目を背けて走り出したかったのに、出来なかった。ルチアーノは己のアイ・レンズに映り込んだ浮遊アンモナイトを見つめて心底辟易する。「……ゾーン」汗を流す機能などないのに、さっと頬が冷えるような心地さえしてくる。 「なんで……」 『私が私の城にいることが、何かおかしいのですか?』 「何が……望みなんだよ」 『歴史が終わる時がやってきました。《聖女》の死をもって方角を定めた歴史は、またしてもあの忌々しき男の思う先へ針を進めようとしています。私には聖女の意志を継ぐ義務がある。あの男をこの先の歴史へ進ませるわけにはいかない』 「意志だって?! おっかしいよ――あんたに母さんの何がわかるって言うんだ?!」 『ではあなたにはそれがわかるというのですか。プラント唯一の成功品の、あなたには?』 ゾーンの声音は心底冷え切っていた。感情が乗せられてはいけないはずのトーンに、絶望がありありと浮かび上がっていた。ルチアーノは信じたくなかった。こんなものが、本当に、不動遊星をルーツに持っているのか? 人間はこうも容易く腐敗するのか。 「……あんた、狂ってる。もうとっくにわかってたけど。プラシドとホセを殺したな。壊したんじゃない。殺した!!」 『彼らは最早不要となったのです。私の志にそぐわなかった。ですから使えない道具は解体します。使える道具は、余計なことでエネルギーを浪費しないよう、プログラムを修正せねば。ルチアーノ、あなたはどちらです? あなたは私の敵ですか?』 「あんたの味方なんか、もうどこにもいやしねーよ!!」 ルチアーノの悲痛な叫びから耳を塞ぐかのように、聖堂のパイプオルガンが爆発した。派手な音を立てて、年代物だったのに(尤もアーククレイドルにおいて、年代に重きが置かれたことなんてなかったが)、一切を惜しむそぶりもなくゾーンはそれを爆破した。セキセイインコの剥製が断末魔をあげる。聖女の愛したラヴ・ソングが途切れる。イコンだけが、無傷のままぴかぴかと保護ガラスを光らせて床に転がる。 爆発の余波を受けて棺桶も吹き飛んでいた。パラドックスのあの安らかな眠り顔も、こうなってはもう、影も形もないだろう。 酷い有様だ。静謐を良しとした聖堂は一瞬で失われ、今やこの城のどこにも聖域はない。ルチアーノも、悪魔ユベルの力を断片的にとはいえ再現出来なければ今の一撃でスクラップになっていただろう。ほんの僅かに期待を抱いてしまい、伺ってはみたが、ゾーンに躊躇う素振りなど微塵も見受けられなかった。愚かな期待だ。 くず鉄の山の奥から、ゾーンが浮上して頂点へとたたずまいを移す。彼は文字通りにルチアーノを見下ろすと、その様子に破壊を諦めたらしく『残念です。とても』と合成音声でこぼした。 『残念です、ルチアーノ。我が同胞よ』 「心にもないことをぺらっぺらと――」 『私はあなたのように彼女から心を与えられなかった。ですからこの思考プロセスを表す適切な言葉を知りません。記憶をシミュレートしても適切な表現が見つからないのです。世界を終わらせなければという使命感、このボディを突き動かすものの正体がわからないのです』 「……それがわかんないようじゃ、あんた永劫にあいつに勝てやしない」 『……そうですか』 ゾーンはしばし押し黙った。ルチアーノの言う「あいつ」が誰なのか、うまく思い当たらないみたいだった。 「……僕さぁ、理解出来ないんだよね」 答えを教えてやる理由もないのでルチアーノは代わりに次の問いを投げかける。 「あんた……なんで、急に歴史の再修正なんか……ゼロ・リバースをなくそうだなんて、思ったワケ?」 けれど返答は思いもよらぬもので、ルチアーノを瞬間だけ拍子抜けさせた。 『私は何も』 「……なにそれぇ?」 『私がそうしようとしたわけではありません。歴史のモデルケースとしては、再修正を行う以前のパターンが最も安定していたのです。ただ、ある日忽然と歴史の可能性からそれが……《ゼロ・リバース》発生という事実が削除された。故に私は再修正を開始し……そして…………ですが……何故……? あまりよく、思い出せない……』 「思い出せないだって?」 そんんばかなことがあってたまるか。機械人形に限って、全ての記憶をメモリチップに書き込んで永久保管出来る歩くデータバンクに限って、そんなこと。 自己離反でも起こしたみたいに「優秀なAI」にあるまじき様子を見せているゾーンは首を横に振り、そして『アンチノミー?』とまるで縋り付きでもするみたいにここにいないボディの名を呼んだ。 「――!」 その時嫌悪が、憎悪が、悪意が、悲哀が、悲壮が、ルチアーノのボディを支配したような気がした。 悪魔ユベルの深層を覗き垣間見る力が、その名前に纏わり付くものを危険だと警告する。「アンチノミー」。まだ壊れていないアンドロイド。不動遊星に焦がれた男。この期に及んでまだ自分の正体を知らず、このねじ曲がった歴史の中でも不動遊星のそばに置かれている―― ユダの名を耳にしたかのような嫌悪と拒絶がありったけわき上がってきて、反射的にその場を飛び上がって離れた。ここにいたくない。彼の前にいたくない。不可解なこと、引っかかり、おかしな点が雨あられと降り注いできて、機械人形の足を動かそうとする。 変だ。ひとつほころびが見つかったことで濁流のように不信感が降り注ぎ始める。 『本当に、よく、思い出せないのです……私が自らを半ばアンドロイドと化すことで不動遊星を移植し、そして半ばで死したあなた方滅四星をアンドロイドに造り直したことは覚えているのに。《ゼロ・リバース》はある日私の与り知らぬ所で不意に失われました。全ての世界から、平等に、復元する手立てさえなく。――子供の癇癪が歴史の全てを否定するように、しかし確かに』 「それじゃ……この棺桶の中に、まだ僕とアンチノミーが、いない理由は……?」 『それは……ルチアーノ、あなたは彼女の忘れ形見です。私は出来る事ならばあなたに手を掛けたくはありません。そして、アンチノミーは…………彼は………そう、そうだ…………私には彼が、制御出来ない、ので…………』 くず鉄の王の眼窩に嵌ったアイ・レンズがぎょろりと蠢く。無意識に誘導されていた事実を受け入れられず、訂正を繰り返そうとしてわななく。この男は危険だ、今もはっきりとルチアーノにはそれが「視えて」いる。 だけどもっと危険なのは、存在してはならないのはコッペリアに狂った哀れな成れの果てなんかじゃない。 ……もしも、世界にゼロ・リバースが起こり得ないのならば。 どうして「ブルーノ」は、驚異でさえない不動遊星の元へ、辿り着いたのだ? 『アンチノミーは、いいえ、彼、《ブルーノ》は……私の造ったアンドロイドではないのです』 かつて自らを偽りの造物主と嘲った男が言った。 ◇◆◇◆◇ 違和感は確かに最初からあった。 ブルーノ=アンチノミーという図式に関してヨハンははじめから知っていたし、不確定要素であることも聞き知っていた。だけどこれまでずっと蚊帳の外だったから可能性から無意識に除外してしまっていたのだ。ブルーノはあまりにも自然にそこに存在していて、歴史に介入してくる様子は一切なかった。彼はただのありふれた、善良な遊星少年の友人だった。 ヨハンよりもさらに強く疑問を抱いていた龍亞と龍可でさえ、ルチアーノの台詞を信じることは難しかった。だから双子ははじめ、自分たちの理解の仕方がおかしいのかと思って彼の方をじっと見たが、「なぁんて、嘘だよ。ばっかじゃないの?」と少年アンドロイドが口にすることはついぞなかった。 「それ、どういうことだよ……」 龍亞の唇が震えている。それでも龍亞なんかはまだましな方だ。見ていられないのは遊星の方だった。表情の起伏がそれほど激しいわけではない彼が一目でそうと分かるほど狼狽し、蒼白な面持ちを見せている。 遊星の瞳を一瞥するとルチアーノは慈悲でもくれてやるかのように指をブルーノの首から離し、彼はそのまま床に崩れ落ちた。滴るオイルとはみ出したパーツが、彼が少なくとも生身の人間ではないことをこの場の全員に証明してしまっている。 「どーも何も、言ったまんまだけど。ゾーンがやったんじゃなきゃ、一体誰があいつの先を打って歴史を無残に引き裂けるって龍亞はさあ、言うわけ? 不動遊星の最高の頭脳をコピーして凡そ人類科学の到達しうる最高峰に近い技術力を駆使し、ダアトの深奥さえ手に入れたゾーンに正体を掴ませない、第三の歴史変革者が現れたとかァ?」 「……ちなみに秘密結社ドーマのセンは?」 「何言ってんのォ? そんなもん大昔にオレイカルコスの神に喰われてそこのファラオにブッ倒されてるに決まってんじゃん。正史でもそうだっただろ、偽善者」 ヨハンの横やりも真っ二つに切り捨て、ルチアーノは苛々と床を踵で突いた。オレイカルコスの力がこの世界で生きていることは海底都市ルルイエで確認済みだが、力それそのものの存続と組織の存亡は関係がないらしい。 「僕が観測した限りじゃ――ゾーンを欺けるのなんてもう、この世界そのものぐらいのもんだよ。それか、身内だ。つまり僕達と同等の技術力を持ったヤツ」 「あなたじゃない……のよね?」 「なわけねーし。それに母さんも違う。あの馬鹿な女は、そんなことをチクチクやってられるほど器用じゃなかった……」 龍可が恐る恐るした問いかけも否定する。ルチアーノとしては、疑わしきを順繰りに検討した結果、消去法でブルーノしか残らなかった……というところらしい。 床に転がっているブルーノはルチアーノの好き勝手な弁舌に異を唱えなかった。出来なかったのだ。気管に当たる部分に穴が空いているのもそうだが、何より、自分自身知らなかったであろう「アンドロイドであるブルーノ」という現実を彼が受け入れられていないのは明白だった。 遊星がしゃがみ込み、ブルーノの髪に触れる。次いで頬に。どちらも人のものと同じ温もりを持っていて滑らかで……それだけに流れるオイルの透明さが残酷だった。 「それに消去法だけじゃあない。今実際にそいつの首を絞めてみてはっきりと分かった。首に傷をつけた瞬間、世界の均衡が同時に揺らいだ……なあ遊城十代。あんた、わかるんじゃん? なんたって僕のこの力の大元なんだしさあ、僕が感知出来るようなことは、すぐわかるだろ」 ルルイエの聖女が模していた本物を何とも付かない眼差しで見上げると彼は言った。悪魔ユベルの心の闇を覗き込む能力は、今は十代の中に戻って来ている。心の闇は誰の中にもある。例外は、心なきもの。例えばアンドロイド――だけど。 「……だってブルーノは、心が、あったから……」 「それが既におかしーんだってば!! あいつはアンドロイド・アンチノミーであるはずだ。作製された段階じゃ、人間の真似事は出来ても心の構築は出来なかった。この歴史でそのプロセスを踏んだのはマザープラント成功作の僕だけなんだからさあ!!」 滅四星たちには元となった人間が存在し、思考プログラムから何から、元の人間のものをそっくりそのまま移植している。例外は不動遊星を移植し未だ生身の部分をボディに残しているゾーンのみ。とはいえゾーンも思考野の大半を遊星のコピーに喰われ、殆ど乗っ取られてしまっているので、感情表現などは生前の思考をパターニングして尤もそれらしい反応をトレースしているだけだ。 しかしこの狂った歴史におけるルチアーノは、《聖女》との関わりを通して感情らしきものを知ってしまった。聖女自身は、気の遠くなるような長い年月を掛けて心を築き上げていた。でもアンチノミーにそれはないはずなのだ。 彼がこの世界で製造されたロボットなら、だが。 「今ここにいるアンチノミーには心がある。それに、製作者であるはずのゾーンが『制御出来ない』だとか抜かしやがった。有り得ないんだよ。僕達は制御可能なゾーンの手駒として復活させられたんだからな。とりわけ、従順な性質のアンチノミーに限っては。でもこう考えれば全部すっきりする」 指さす。虹彩のない機械人形特有のあの眼の向こうに、怯えに身を潜めた見知らぬ誰かが居た。ゾーンの切り札、セフィロト・ツリーの中に潜む十一番目の真理「ダアト」……《時戒神セフィロト》を初めて見た時もこの嫌悪感を覚えた気がする。 それはあってはならない隠されたものへの嫌悪なのだ。 「正史から来たな、おまえ。チェンジリングだ。この世界のアンチノミーと入れ替わった!」 吐き捨てたが、ブルーノは遊星に庇われるように、横たわって何も言わぬままだった。 ――チェンジリング。取り替え子。妖精が子供と子供を入れ替え、或いはそのまま異界へ連れ去ってしまうのだという古いお伽噺。 SF小説の定石通りなのだとすれば、同じ世界の同じ時空に同一人物は存在することが出来ない。だから入れ替わる。しかし入れ替わろうとした相手が戻る場所がなかったら……片方は、どこへ行くのか。 あるべきものの意図せぬ消滅は歴史を大きく揺るがす原因と成り得る。それがルチアーノの提唱。 「でもそれじゃ、パパとママは? もし本当に今ここにいるブルーノが、ゼロ・リバースのあった世界から来たのだとしてよ……それならパパとママだってそうだわ。違うの?」 「そこの二人はあくまで闖入してきたってだけだろ。この世界本来の遊城十代とヨハン・アンデルセンの存在を塗りつぶして上書きしたわけじゃねーし」 「……それじゃ、」 「そーゆーこと。本来この世界で活動してるはずだった『ブルーノ』なんかもうどこにもいない。可能性から追いやられ、世界の狭間で消滅しておっしまい。でもさあ……人ひとり、……あー、人形とは言え《英雄因子》の持ち主である不動遊星を制御するための役割持ったのがさぁ、ポンと消えちゃっていいわけあるぅ? 歴史の転換点において、消えるものとそうでないものは予め決まってるんだ。僕らがそれを握りつぶそうとして、は、そうだよ、上手く行ったことなんかなかった。正史でペガサスを殺すこともこっちで英雄因子を始末するのもままならなかったってのにさぁ」 「なるほど。英雄因子とやらに絡んだ問題は歴史改変においても扱いが難しいわけだ。彼はそれに密接に関係していると」 「それに関しちゃ、ここにいる全員大体そーだけど。だいたい何でこの時代で英雄因子の持ち主が揃っちゃってんのか、理解に苦しむぜ、まったく!」 結局、話に一番に順応して理解を示したのはヨハンだった。ポッポタイムに落ちてきてからブルーノと交流を深めていた十代と違い、この場において最も客観的に、心情を除外して状況を整理出来るのが彼だけだったのだ。他の皆は誰も彼もブルーノに近しすぎた。 「ブルーノ……」 遊星が震える声で彼の名を呼ぶ。幸せな家庭に生まれて満ち足りた人生を送ってきた遊星の声の中に、時折こうしてはっとするほどの幼さを見る時がある。正史の不動遊星がサテライトで暮らした少年時代に棄てざるを得なかったものが彼の中にはまだ生きているのだ。 「本当なのか」 遊星の呼びかけは必死だったが、それでもやはりブルーノは答えない。否、答えられないのだろう。首筋から流れ続けるオイルは床にじわじわと広がり、血が海を成すかのようだった。 ルチアーノは言いたいことを大体言い切ったのか、訝しげにブルーノの動向を注視するばかりでその後は口を噤んでしまった。彼の瞼が開かれないことに、何か苛立っているようでさえある。静寂は異常の現れだった。ここまでわざとらしくアプローチををして、種明かしをしたのに、どうして何も起こらないのだ? ブルーノに負わせた傷は損傷こそわかりやすく目立った位置にあるものの、致命傷にはほど遠いということを傷つけたルチアーノ自身が一番よく知っている。機械人形はあれぐらいじゃ壊れたりしないし、ましてや「死ぬ」なんて尚更だ。パラドックスが死んだのは正史の不動遊星の存在とある種引き替えの全てを受けたからで、ホセとプラシドはバッテリーを抜いて玩具にされたからだ。首を掴んだぐらいで壊れるような代物なら今までに何百回と皆そうなっている。 遊星の腕の中で、ブルーノが僅かに動く。ブルーノ、と遊星がほっとして今一度名を呼ぶと彼はゆっくりと目を見開いた。 遊星が息を呑む。彼が唇を薄く開いたのが瞳に写り込んだ。 「……わかったんだ……」 「え……?」 「ルチアーノの話を聞いて、……僕は分かってしまった。もう分からないといけないところまで、来てたんだってこと……」 「ブルーノ」 「機械人形の見る夢はおしまい。ここから先は、幻想じゃあ、『ブルーノ』じゃあ、いられないって――」 瞳には相変わらず虹彩がなかった。だが今までに見たこともないような色をして、遊星の群青を見据えている。 ブルーノの瞳は紅かった。垂らしたオイルが全部血の色になって瞳の中で凝固したかのような色だった。 それを捉えたルチアーノの視界にシステムアラート・メッセージが明滅する。システムエラー、E3048番。自己統括不能。AIの制御を無視し、統率が取れず、次に何をするかわからないし、何をしでかしてもおかしくない。 セーフティが解除されてしまったアンドロイドの暴走。それはロボット三原則の倫理から逃れることを時として意味する。 「さよなら、遊星」 心臓を貫いた。 泣けないアンドロイドは涙の代わりにオイルを垂れ流す。オイルは眼球を映し込み、赤く照り返していた。まるで血の涙みたいに。 血が流れることだってあるはずないのに、ひどくおかしな話だった。 《機械人形の見る夢/END.》 |