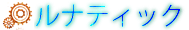かつて願ったものがあった。 身の程知らずに。分も弁えず。倫理を棄て去って。世界を支える理を不相応にも取り払おうと願ったものがあった。 そこに正義はなく、しかし悪意もなく、平等で不公平な世界の真理にそれは自分勝手で身勝手な願いを抱いた。(神様、どうか)神など信じたこともなかったのにそれは願う。(どうか叶えて)。 ハッピー・エンドに恋い焦がれた機械人形、アンドロイドの役割を逸脱したデッドコピーは、彼が憧れた英雄を未来へと送り出した後、D・ホイールと共に果てを彷徨っていた。全てを賭けたライディング・デュエルでの敗北はブラックホールへの転落を意味していて、その奈落にすっかりと吸い込まれた後だった。しかし不思議なことに意識は途切れることなく存続していて、人工知能は演算を繰り返している。願い続けているのだ。 信仰する神さえ失った破滅の未来において、それでも彼が焦がれ続けたのが「不動遊星」というたった一人の男だった。青い英雄はある意味で彼の神だった。唯一神だったのだ。サングラスを掛けたDホイーラーも、記憶喪失のメカニックもそれを直接彼には告げなかったが…… 口にして表すことで、穢されてしまうことを、形が崩れてしまうことを、恐れていたのかもしれない。 神の居城《アーク・クレイドル》は滅亡を迎えた遠い未来のネオドミノシティ。モーメント・エネルギーによる過度な繁栄を享受した挙げ句、モーメントの暴走により機械に滅ぼされた世界の成れの果て。その中枢ほど近くで行われていたデュエルによって繋がったブラックホールは、正確には、宇宙の果てへ続いているわけではなかった。宇宙よりも近く、この世のどこよりも遠い果てに彼は投げ出された。真っ暗な空間には奇妙な白さがあった。破滅の光。破滅したものたちの、残滓の白。 この世を破滅させた奇跡のエネルギー、モーメント。 かつてモーメントの研究者であったゴドウィンはこう言っている。「モーメントは、命ある光。この光は生きている」。 モーメント・エネルギーに全てを奪われたアポリアはやがて知る。「モーメントは人の望みを叶える。欲望を吸い上げ、増幅し、やがて制御を外れて自滅する」。 生きた光モーメント。しかし光そのものに善悪の判断は付かない。人の願いに呼応し、力を高め、その使い道を限定しない。人々は欲望の果て――大衆の堕落した意思の反映――により身を滅ぼしたが、それはモーメントの制裁でもなんでもない。ただ、過ぎた力に身を食われたにすぎないのだ。 (どうか……どうか……) かつて人の望みを叶える石により栄華を極めた都市があった。オレイカルコスの都古代アトランティス。欲望の石オレイカルコスの力を貪りすぎた古代アトランティス人はやがて過ぎた望みの対価として異形へと姿を変えてしまい、混乱の最中で幻の都として海深くへ沈んでしまう。 (たったひとつで構わない) オレイカルコスは心を映す鏡に似たもの。アトランティス最後の王であったダーツは祖国の惨状に心を病み、オレイカルコスの力に取り憑かれてしまう。ダーツは歴史を操る。人類が二度同じ過ちを起こさぬ為と謳い、やがて、ファラオに敗れる。オレイカルコスの神という妄執に喰らい尽くされるようにして……。 (私は……いや……「僕」は……) オレイカルコスは人の望みを叶える強大な力。しかし力そのものに善悪の判断はない。それは星を巡るエネルギーに近しく、ただアトランティスの人々が、石という形になったものを私利私欲のために扱っていたに過ぎなかった。 モーメントもまた一つの星の力だ。不動博士がもしも古代アトランティスと欲望の石オレイカルコスの事を詳細に知っていたならば、彼はもっと早くその危険性に気が付いただろう。 モーメント・エネルギーはオレイカルコスと同じもの。 人の望みに呼応し、その願いに関わらず過ぎた力を与え、人間を遙かに超えた高みから動かせ、狂わせ得る強大な姿なきもの。 人間は姿なき力に、敬意と畏怖の念を込め、こう名を与える。 「遊星と、もっと一緒にいたかった」 「神」よ。 「そのために何を犠牲にしても……!」 どうか願いを叶えて、神様。 |