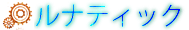心臓を貫いた合成金属の指先が、ゆるゆると戻る。傷口は修復され、ふさがり、元通りに衣服に覆われた。 あらゆるものの位置関係が復元されていく。時の流れが巻き戻り、逆巻いて、あるべき姿へと強制的に回帰させられる。 「あぁ、やっぱ、そーなんだぁ……?!」 ルチアーノの双眸が異様な光を孕んで「それ」を睨みつけた。オレンジと黄緑のオッドアイ。悪魔ユベルの色。彼は機械人形の力にオーバーブーストされたその異能を用いて時の流れを巻き戻したのだ。かつて龍亞に「挨拶」に訪れた際、時を止めたように。 遡った時はそこで停止する。この空間で今時を視認しているのは、ルチアーノと双子、十代とヨハン、遊星、時の流れに縛られない死人である名もなきファラオとバクラだ。 「おい……どうなってる」 十代もまた自らの異能を解放してはいたが、彼は正史でこの時代に何があったかの把握に疎い。一手甘んじる形になり、ルチアーノに説明を求めていた。 「そんなの僕に聞くなよ。こっちだって知りたいぐらいだっつの」 「時間止めてんだろ? そんで……ええと……」 「巻き戻した。確かにそれは僕がやった。不動遊星の死はシナリオにはないから。……あぁクソッ、ほんとさあ、くそったれじゃん! 暴走なんかしやがって!!」 「暴走? 本当にただの暴走なのかよ……あいつ!」 『どうだかな。オレには些か、『あれ』は見覚えがあるように思うぜ……』 総毛立つ。身の毛がよだつ。一瞬で世界が異界に呑み込まれたかのような気持ち悪さに全てを包まれながら彼らは隣人から姿を豹変させたアンドロイドを取り囲んでいた。 時を止められたブルーノの背後を指し、名もなきファラオが口を開く。彼がすっと手を開くと額のウィジャトが光り、ブルーノの背後に奇妙な何かが姿を現した。透き通った……霊体のような、デュエルモンスターの精霊にも似た不気味な姿をしている。 「な、なんだあれ?!」 「精霊……じゃ、ない……?」 ファラオの隣で、バクラがいかにも胡散臭そうな顔をしてそれを眺めた。彼は直接その事件に関わってはいなかったが、ファラオと同じものについて記憶を呼び起こしたらしい。 『ところで、ヨハン』 ファラオが振り返って名前を呼ぶと、ヨハンが反射的に佇まいを直して彼の言葉に耳を傾けた。 「あ、はい。なんでしょう」 『きみはさっき確か秘密結社ドーマのことに触れていたな』 「まあ……海馬社長のレポートで読んだだけなんですけど……」 『そうか。ならその説明からだな。バクラはもう気が付いているようだが、オレの記憶が正しければ『あれ』はそのドーマの首領ダーツが魅入られ、狂わされたオレイカルコスの化身だ』 「へっ?」 『『オレイカルコスの神』。昔オレも倒すのに随分苦労した』 ファラオが名を告げると同時に「オレイカルコスの神」が獰猛な咆吼をあげる。それが合図だったのだろう、瞬間、ガラスが割れるような衝撃が空間を走ってルチアーノの時間操作が解かれた。抱えたままの体勢だった遊星の腕の中からブルーノが立ち上がる。その隙を突いて十代が遊星の体を抱き上げ、ブルーノから引き離す。 ブルーノの瞳はやはり紅く、焦点が定まっていない。その雰囲気はあまりにも偶像とかけ離れていて、見慣れていた「ブルーノ」、チーム・ファイブディーズのメンバーで天才メカニック、遊星の良き友で十代のルームメイトだった男とはまったく似ても似つかなかった。違ういきものが彼のボディを乗っ取って勝手に操作していると言われた方がしっくりくる。 けれど彼は先ほど「さよなら遊星」と言った。遊星を知っているのだ。それでは、やはり、彼はブルーノなのか? 「どうしたんだ、ブルーノ……いったい……何が?」 前に立つ十代の横から顔を覗かせ、怯えて震える声で、遊星はそれでも問いかけた。彼が信じてきた友の豹変を受け入れたくなくて、必死に理由を探している。実は悪いものに憑かれていて。自分の意志では、制御できなくて。そんなふうな「やさしい」理由を求めている。 「ごめん、遊星」 でも世界はもう遊星にやさしくしてくれない。 「出来ないんだ。きみのそばにいられない。機械人形が見る夢は終わってしまった。僕たちは夢から醒めて、この世界は……」 「何故……ブルーノ!」 夢は醒めてしまった。 眠りは解かれてしまった。 時は動き出してしまった。 歯車は回り始め、留まる術を失ってしまった。 「どこにもいけない」 やさしい世界の夢は、もう終わったのだ。 機械人形は夢を見た。不動遊星にやさしく、真綿のようにくるみ、あらゆる不幸と悲しみと苦しみを彼から遠ざけ、美しく保った世界の夢を。 その世界で不動遊星のそばに彼は自らのアバターを置く。それが彼の願いの端を成すものだったから、「ブルーノ」が遊星の元へやってくるのは必然でなくてはならなかった。世界はそれを基準に調整され、そうなるように歴史は自然と改竄され、まず不動遊星を不幸に陥れた第一の原因であった《ゼロ・リバース》が全ての可能性から削除された。 ゼロ・リバースの削除は最も重要かつ甚大な歴史にとっての犠牲だった。その犠牲によって不動遊星が正史で勝ち得た「滅びを迎えぬ未来」はなかったことにされたが、それは機械人形の望みを叶えるためには仕方のないことだった。機械人形は既に願ってしまったのだ。願いは取り消せない。その代償が何であろうと構いやしないいう傲慢な願いを「神様」はもう聞き届けてしまっていたのだから。 「あー、もう最ッ悪。もっと早く気付くべきだった。そもそも『ブルーノ』が不動遊星のそばにいた時点で狂ってたんだ。ありえない。理に適ってないんだよ」 「どういうこと? ルチアーノ、あなた以外はこの場の皆、その理由を理解出来てないの」 「おいおい龍可ァ、頭使いなよぉ? 僕達がその昔アーク・クレイドルを落っことすために何やってたのかもう忘れちゃったワケ? サーキットだよ、サーキット。だからイリアステルの三皇帝は機皇帝を使ってWRGPにまでしゃしゃり出て来たし、アンチノミーはブルーノとして意図的に配置された。サーキットの完成を早めるためにだ。でもさあ、ゼロ・リバースもないこの世界じゃ、アーク・クレイドルは落とす理由がないんだよ。サーキットも必要ない。三皇帝も、必要ない……なのにあいつだけはここにいた! 当たり前のような顔をして、厚顔無恥に!!」 なあ、そうだろ?! ルチアーノの怒声がまっすぐにブルーノへ飛んで行った。「言ってみろよデッドコピー」剣呑などというものではない。「今不動遊星を殺そーとした理由も含めて、全部、諸共に、さあ!!」理屈を飛び越えた純粋な怒りが、少年アンドロイドを支配しかかっている。 「それは、遊星をやさしくない世界にいさせたくなかったから、遊星を止めてしまおうと思ったんだ。だけど……それも出来ないみたい。ルチアーノが時間まで巻き戻せるなんて、ゾーンはそんな機能を付けていたっけ?」 ブルーノは遊星から視線をそらし、ルチアーノに訊ね返した。予想外の切り返しに緊張感と不快感を露わにしつつ、彼は慎重に返答をする。 「僕の機能は正史のアッパーバージョンだ。少なくとも今の僕はそれが出来る。あーそうだよ、母さんの遺産ってやつ?」 「そうなんだ。だけどそれもおしまい。全部終わりなんだ――ごめん」 「ハア? ぜんぜん、意味、わかんねーけど。で? 結局あんた何なんだよ? オレイカルコスの神とやらか? それとも世界の摂理か? アンドロイドの皮被った、どんなモンスターだ? なあ!!」 「僕はアンチノミー。そして、ブルーノ。そうには違いない」 「へえ? でも不動遊星は、どうもそうは思いたくないみたいだけどォ? そりゃそーだよな。心臓、ぶち抜かれたもんなぁ?」 ブルーノの答えは謎かけめいていて、はっきりしなかった。らちがあかないと見て反応を引き出すためにルチアーノが煽る。しかしブルーノは悲しそうな顔をするばかりで、「実はもうとっくに乗っ取られていたんです」などと言い出すような気配はない。 彼がオイルの涙がまだしたたっている両眼を伏せた。胸に手を当てて、しおらしそうな素振りまで見せて。でも後ろのオレイカルコスの神は屹立して吠えたままで、アンバランスさが際立つだけだった。 「僕はね……きみに一度破れた、その果てみたいなんだ、遊星」 ブルーノが言った。龍亞と龍可がお互いに顔を見合わせる。先のルチアーノの台詞を思い出したのだ。――『正史から来たな、おまえ。チェンジリングだ。この世界のアンチノミーと入れ替わった!』 「アーク・クレイドルで、敗北した『僕』だ」 ブルーノの口から出た言葉は紛れもなく先の問いかけへの肯定だった。まるで水を打ったように、どよめきが広がっていく。けれども……その言葉の重さを理解出来ていたのは、ブルーノ本人だけだ。彼がどのような思いでそこへ「辿り着いたのか」を、他に誰もわからない。 何せ彼以外、正史においてブルーノがどのような最後を遂げたのか知らないのだ。他には正史の遊星だけ。けれど彼はもういない。名もなきファラオに未来の自分自身を託し、消えてしまった。 だから十代に庇われている遊星が「そりゃあ、ブルーノとは何度かデュエルをしたが」としどろもどろに呟くと、ブルーノはより一層悲しそうな顔をした。口にこそしなかったが、「そういうことじゃない」「きみはちがうんだ」と言わんとしていることは明白だった。 それに遊星がうちひしがれる。しかしそれに構わず……そういう場合じゃあ、もうなかったのだ……ブルーノは勝手に話を進めていこうとする。 「当たり前だけど……知らない、よね。でもそうなんだ。僕は一度遊星に敗れた。敗北し……遊星を生かすことと引き替えに、ブラックホールへ落ちた。その先で僕は決めたんだ。どんな犠牲を払っても、『遊星にやさしい世界を作らなきゃ』って」 「なるほど。そうして本当にありとあらゆる全てを犠牲にして、歴史を歪めたってわけか。まったく見上げた根性だな」 そんなブルーノの声なき否定でとうとう口を開く余裕も失ってしまった遊星の代わりに答えたのは、ヨハンだった。彼は珍しく糾弾を隠さない口調で、怒りさえ感じさせる声音でまた繰り返す。「楽しかったか? 夢を見ているのは?」目がまるで笑っていなかった。こんなヨハンはそうそう見られないというのに、ルルイエの件から続けてだ。龍亞も龍可も両親にこんなふうに怒られたことなんかない。 「聞いてみていれば、随分とまあ調子のいいことを言っているみたいだが」 「だけどもう撤回は出来ません、アンデルセン博士」 「何故だい?」 「決めた事は、覆らないから。二度と。ミルクピッチャーも水盆も同じ。世界の形を一度変えてしまった以上、僕は、そういうふうに保っていかないといけない。自分の記憶に蓋をして、可能性を殺しても、それでも」 「ふむ、そりゃ、宗教に狂った人間の常套句だな。オレイカルコスの影響を受けたら誰も彼もそうなってしまうっていうのか? あの子もそうだったよ」 ヨハンの脳裏に《聖女》の最期が蘇る。『ヨハンになら、オレは壊されたっていい』と笑った彼女が、『つくりもののオレが、きみのことが好きだって、あいしてるって言ったら、きみは首を振るかい?』と問いかけたことを思い出さずにはいられなかった。 ブルーノが首を振る。 「宗教、というより信仰、かな……あまり意味はないけど」 「そうか。それで?」 「……『僕』が目覚めてしまったから、この可能性を閉じて次の可能性を模索しなきゃいけない。思えばここに十代がやってきた時から、世界はほころび始めてた。遊星にやさしい世界じゃなきゃいけないのに、ヨハン・アンデルセンの登場や遊城十代のままならなさ、コントロール出来ない事象の数々が、歯車をずらしてしまっていた。……ねえ遊星、遊星なら、ギアがずれた機械がどうなるか、わかるよね。そのままじゃ壊れてしまう。存続させるためには、ギアを直さなきゃ――それも、失敗してとうとうゾーンは孤立しちゃったけど……」 「つまりゾーンを狂わせ手駒として利用してたってわけか。それじゃ、ルルイエはなんだ? 副産物か? ゾーンに指示したわけじゃあなさそうだな」 「ゾーンは遊星と思考回路が一緒だから。彼は不動遊星の頭脳をそっくりそのまま自分の脳にコピーしてる。自分自身にメスを入れ切り拓き、電極を挿して造り替えていくことに躊躇いがなかったんだ……それもあって、十代に、惹かれてたのかな……でも後のことはよく知らない。ルチアーノの方が詳しいんじゃないかな」 「祈る神の出来損ない」であった少女を造り、凡そ全ての信じるということを忘れてしまった偽りの造物主をさえ利用して――その意図はなかったのかもしれないが、事実としてはそうだ――モーメント=オレイカルコスに取り憑かれた人形は悪びれるふうもなく謳い続ける。 ひとごとみたいに。 チープなテーブルゲームの盤面を、一瞥だけして放り出すみたいに。 だけどそのくせ、チェックメイト寸前まで追い込まれたからといって盤面ごとひっくり返そうとしている。 十代の腕を遊星が弱々しく取り払った。目をうまく合わせようとしないブルーノを必死で追いかけて、彼は言った。ゾーンが遊星をコピーして云々というくだりさえ、今の遊星の頭にはうまく入って来ずにいる。彼の頭の中には今最悪の可能性ばかり渦巻いていて、一個でも構わないからそれを否定して欲しくって、躍起になっていた。 「ブルーノ」 「……」 「ブルーノ……! ギアが……狂ったら、確かにもう機械は動かない。リペアも出来なくなったら……でも、だからって、なんだって……」 「……」 「なあ、ブルーノ、頼む。嘘だと言ってくれ。全部手の込んだドッキリだったんだって」 不動遊星の懇願というものを、その時十代は生まれて初めて目にしたように思った。恥も外聞も擲って、請うているみたいだった。ゆるして、もう、おねがいだから。でもその下には遊星という青年が決して損なうことの出来ない性質が見え隠れしている。優しさ。偽善。まぶしくて目もくらむような正義。 もう傷付きたくない、おまえを傷つけさせたくない、という子供じみた綺麗事。 「……ごめん。いくら遊星の頼みでもそれは出来ない。だってこれ、嘘でも冗談でもなんでもないんだ。この世界は直らない。放棄するのも仕方ないんだ。そうしたらもう一つ新しいものを用意してやり直すのも、当たり前のこと。だから悲しいけどきみとはお別れなんだ」 でも夢から醒めた現実は残酷だ。 冷酷さしかない。悲しみしかない。苦しみしかない。猶予もなく、いつもぴしゃりと断罪の鎌だけを振り下ろしてどこかへ消えてしまう。 「これ以上は、きっと話しても仕方ない。遊星、きみと一緒にいられて嬉しかったよ。これは本当のことだ。……たぶん」 それだけ言い残すと、十代やヨハン、ファラオ、バクラ、そしてルチアーノ――彼ら全ての干渉を振り切って、冷たい紅目をした機械人形は消えた。 ガレージに残ったのは沈鬱さばかりだ。救いなんかどこにも見あたらない。 ◇◆◇◆◇ 夜の帳は等しく訪れた。歯車を失った壊れかけの世界は、それでも崩壊する最期の一瞬まで、傷一つない完成品を模倣し続けている。チーム・ファイブディーズの面々を襲った精神的ショックは甚大だったが、いつまでもそれに浸っているわけにもいかない。残酷だが、ヨハンは遊星のいる前で話をし続けねばならなかった。不動遊星の力は絶対に必要だ。最初にオレイカルコスの神が殺そうとしたのが彼であったことこそその証明に他ならないはずだとヨハンはまず考えていた。 ルチアーノは既にゾーンと袂を別ちたあとで、行くあてもないのかガレージに留まっている。悪さをするふうもないし、龍亞と龍可もそのことを特に批判しない。過ぎたいざこざより、目前に迫った大局の解決を取ったのか……もしかしたら、ルチアーノが時折十代を見る眼差しの中に何かを見出してタイミングを図っているのかもしれなかった。 「で、思い返してみれば、予兆はあった……ってことなんだな、結局のところ。うまくはめられたもんだ。こんなに近くにあったのに、俺達はずっとゾーンが……イリアステルが、と信じ切って疑いもしなかった」 『ドーマが存続していたこと自体が符牒だった、というわけか? だがオレはそのゼロ・リバースとかいうやつのことはあまりよく知らなかった。情報をもっと早く合わせておくべきだったんだろうが』 『三幻魔があること自体、破滅の光だかなんだかが関わってんだろ? んでその破滅の光っつうのが……』 「白き光モーメント。だから、つまり……ああもう、こんがらがってきた!」 『十代はどこでも考える事が苦手なんだな』とファラオがぽそりと零し、十代がぐっと息を詰まらせる。ヨハンが彼の背を宥めるように撫で、それから遊星とルチアーノの様子をちらちらと伺った。 まずもって早急に行わなければいけなかったのは情報の統合だった。状況把握が皆てんでばらばらだったのだ。これでは話にならない。 「まず俺達が追っかけてた歴史改変の原因は、ゾーンと見せかけてブルーノ……アンチノミーだった。彼は正史のオリジナルモデルだ。同じ時間軸に同一存在は並べられないというルールに則って、この世界のブルーノは消滅している。それでゾーンだが、十代からユベルを抜いて調査に向かう俺達の足止めをしたやつは、アンチノミーの余波でなんかねじ曲がってしまったと」 「今はマジで狂ってるぜ。崇拝を拗らせて突き詰めるとこーなるっていう、モデルケースみたいだ。不動遊星をキレさせるとあーなるんだって、僕は実はあまり信じたくなかった」 「……俺もあんま見たくないな。ここにいる遊星君だけでも結構手を焼いたんだけど。まあ、それで……そんなアンチノミーのエネルギーになってるのがオレイカルコスの神? 遊戯さん、あれ、なんなんですか」 知恵熱でも出しそうな十代の背をさすりながらヨハンが千年パズルの上に佇むファラオの亡霊に問いかける。彼は腕組みをした格好のまま『原始エネルギーみたいなものじゃないか』と首を捻った。 『オレの知ってる限りでは……まず、オレイカルコスは欲望の石、と呼ばれてた。しかしダーツの過去を見た限りでは液状でもあったようだし、まあ、不定形なんだろうな。で、オレイカルコスはまず接触した人間の欲望を増幅させる。増幅した欲望は容易く姿を変え、時に手段と目的を取り違えさせる。ダーツがそうだったんだ。そしてデュエルに敗北しかかったところで、ダーツに取り憑いてたそいつは本性を現した。それがオレイカルコスの神。便宜上そう名を当てている』 「なんかこう……太古のやばい感じのやつってことですか」 『やばい感じと言うか、本当にやばいな。オレもあの時は割と真剣に死ぬか生きるかの瀬戸際だった。だが相棒の肉体を死なせるわけにはいかないのでなんとか生き残った』 オレイカルコスは世界を動かしているエネルギーそのものと言っても差し支えない側面がある。歴史を動かす原動力なのだ。繁栄あるところにそれはあり、オレイカルコス、破滅の光、モーメント……と姿や名前を変えて、人の心に潜む闇へ付け入ってきた。 「なんでか知らないけど、ブルーノはオレイカルコスとかいうやつと接触して歴史を変えちゃった、ってことか。でもなんで? ブルーノの望みってさ、俺、聞いてた限りでは『遊星と一緒にいたい』とかでしかなかったみたいに思うんだけど……パパ、なんか俺見落としてる?」 「いや、俺もそれ以上の理由はなかったんだと思うな。これも海馬社長のレポートからなんだが、『人の願いは、それが純粋であればあるほど、追い詰められた時に絶対的な悪意に変わり得る』という文面を彼は残していた。アンチノミーの願いは唯一、純粋な『遊星と別れたくない』というもの。だけど遊星君を未来に生かして歴史を救うためには二人は別れなければならない。正史がその末路を採択したってことは、それ以外の正解はないってことだ……」 龍亞と話を終え、息を吐く。ヨハンにとってここからが本題だ。「さて」とわざとらしい前置きをするとヨハンは遊星をまっすぐに見据えた。遊星はさっきから可哀想なぐらいに消耗しきっている様子だったが、アキが隣につき、ジャックやクロウにも周囲を固められて、なんとか話が出来るぐらいにはなってきている頃合いのはずだった。 「遊星君」 「……はい」 「聞いておきたいことがある」 「……はい」 「君はどうしたいんだ? 俺はさっき……随分と昔のように感じるが、ともかくデュエルのリターンとして君に協力を求めた。その思いは今も変わってないし、君の力がなければ事態はどうにもならないだろうという予感は今や確信に変わっている。けれどそれでも、君がどうしても向き合いたくないと言うのなら俺は君の意思を尊重する。難しい局面だ。理屈だけじゃ、語れないだろう」 さっきと今とでは随分と状況が変わってしまったし、遊星はしっかり決意していたわけでもない。正史の彼ならいざ知らず、この世界の恵まれた彼では、心変わりがぽんぽんと起こっていたって仕方ないだろう。ヨハンとしてはそういう心構えで訊ねたつもりだったのが、返答は以外にもしっかりとしたものだった。 「……。あいつは……ブルーノは、俺に言いました。約束してほしいと。『僕がいつか敵になってしまったら、君の正義を貫いて僕を止めて』、と」 「……いつだい?」 「ついこの前。話がしたい、と。今思うと……ブルーノ自身、薄々、こういう時が来るのを勘付いていたんだと思う。だから俺は行きます。問題ない。ブルーノは、俺の友だ。……約束は守る」 でも守る、と形容した遊星の声音は強ばり、どことなく「まもらなきゃ」と自分に言い聞かせているような感じが少しした。何を「まもらなきゃ」いけないのか、友をか、自分をか、世界をか、それともその全てでありどれでもないのか……まだはっきりとは見えていないみたいだった。 でもそれでよかった。 「もちろんだ。友達を助けるのは当たり前のことだからな。……それなら君は自分の守れるものを、信じたもの、失いたくないものを守るといい。俺は十代と一緒に世界を……歴史を守るよ。それが俺と十代が今までずっと守り続けて、信じてきたものだからだ。目を逸らしたいわけじゃあないんだね?」 「友達を見捨てろなんて、父さんは俺に一度も教えなかった」 「尤もだ。不動はそういう、いいやつだよな」 そう。遊星の気持ちはそれでいい。まったくもって美しい、素晴らしい志だ。 だけど……一番大きな問題が実はまだ残っているのだ。それを知ってか知らずか、ルチアーノ胡乱な眼差しをした。 「でも、ブルーノを追いかけようと言ったって方法はあるの? 目の前で急に消えたのよ。手がかりはないし、そもそも私達が行けるような場所なのかしら」 アキがとうとう核心に切り込んでくる。名もなきファラオがバクラに振り返り、『問題ないはずだが』と答えた。彼は例の海馬社長のビデオメッセージの場面に居合わせていないので最大のリスクのことをまだ知らない。 『そのための保険がオレとバクラだな。バクラ、KCとI2が共同で進めていた研究、終わっているんだろう。あの渡航技術が云々とかいう』 『あー……まあな……』 渡航技術が云々というのは、かつてパラドックスと交戦した際に遊星が言い残していった研究のことだ。パラドックスのボディから失敬したパーツを元に時空渡航理論を紐解き実用化する、という。それ自体は確かに問題ない。二人の亡霊はその存在をこの時代に伝え、リスクヘッジをするためのメッセンジャーとしてこの世に留まり続けていたのだ。 しかしバクラは何故か歯切れ悪く口ごもると目を泳がせた。 『座標はある。技術も、まあ、一応ある。が、不完全だったんだよ。こんなお粗末な結果を外部に流出させるワケにはいかねえってんで、海馬社長御自らが秘匿してこの度百年越しに陳情してくださったんだが……』 更に歯切れ悪く、バクラはそこで説明をヨハンに投げた。ヨハンは心配そうに覗き込んでくる十代に「大丈夫」と答える代わりに手で触れると、深く息を吸って「それ」を彼に告げる覚悟を決めた。不動博士はあの後「遊星が決めることに、私は異を唱えません」と言ってくれていたが、父親がどう思っていようが本人の心境は別だ。 「結論だが、この世界からアーク・クレイドルに人間が向かった場合、九十八パーセントの確率でその人間の存在が消える」 口がからからに渇いて、一言一言を発するのに尋常ではないエネルギーを要した。こんなことを彼に言いたかったわけではないが、しかし、リスクの説明を投げて騙して連れて行けるほどヨハンも十代も割り切れるたちではない。 「KCのスーパーコンピューターが何度も試算をしてみたが、結果は芳しくなかったということだ。……実を言うと、正史の遊星君が既に消滅している今、痣が転移したことから鑑みても今ここにいる君が全ての歴史における『不動遊星という存在の集約』であることは疑いようがない。つまり……その、このままだと、不動遊星という存在そのものが歴史から消えてしまうかもしれない。そして俺と十代はそれを知った上で君に来て欲しいと打診する。――遊星君。それでもまだ、きみは、友を救いたいと願えるか?」 |