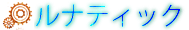たぶん、ずっと、何も知らなかったのだ。 大人になって、親元を離れて自立して、知ったような気分になっていただけで。世界がどんな形をしているのか、どうやってここまで続いてきたのか、どうして人は生きるのか、そんなこと、考えたこともなかったのだ。 でもそれを訊ねたら、あの二人はきっと笑ってこう言う。「そりゃ、当たり前のことだ。ふつうはみんなそんなこと気にも留めないもんさ」……これは赤いジャケットを着た彼が。「仕方ない。俺達だって最初っからそんな、人間のスケールを超えたことを考えなきゃって、思ったことなんかないからね」……これは彼の隣に超然と立ち続ける、あの男が。 それなのに。 今遊星が迫られている選択は、まるっきりそれそのもので、世界の命運を賭けた問いかけで、あまりにも急で、余地がない。「あなたは世界を救いますか?」。知るか、そんなもの。「では友達は? 約束をしたのに?」そりゃ、そうだけど……だって――だって、そんな……。 あんまりだ。あんまりじゃないか。 「俺はあなたのそういうところ、やっぱり好きになれそうにないんです。アンデルセン博士」 振り絞るように言った。イエスとはいの強制二者択一問題を投げかけてきた男に、いや彼だって本当はこんな問いかけをしたかったわけじゃあないのだ、そんなことはわかっているけれど……嫌味っぽい言葉を放り投げてしまう。ヨハンは非常に気まずそうに「そりゃ仕方ないなあ」と返した。多分この男は、家族……とりわけ不動博士にはもう何らかの手を回しているんだろうなと、聞かなくても遊星にはわかった。 「どうせ、何もしなかったらこの世界は消滅して俺達はみんないなくなる。その問いかけ自体がナンセンスだ」 「確かにこの世界はリセットされる。でもそれってゼンマイを巻き戻して、オルゴールを初めから鳴らそうとすることと大差ないんだ。君の存在だけを綺麗に切り取ってゴミ箱にポイするのとは、やっぱ勝手が違うと俺は思うよ」 「今ここで息をして思考している『俺』がそのうち消えるという仮定には変化がない。あなたは丁寧に保険を取ってその確認をしているに過ぎない。あとで思いもよらぬ恨みを買わないためにだ。違うんですか」 「……好きに解釈してくれ」 両手を大きく挙げて「お手上げ」のポーズ。逃げたなと思ったけど、別に言わなかった。 「俺は、ここにいる自分以外の『俺』のことまでわかるわけじゃないんです。どこの俺だって、自分のこと――自分が大事なことに精一杯で、そんなあるかも知らない並行世界の自分とか、責任が持てるわけがない……だけど、だからこそ、わかることや知りうることには必死になれる。がむしゃらに、格好悪く地を這ってでも、守りたいと思う。 それに……俺には世界を救うとか、そういうのはよくわからない。正直なところ、漠然と大きすぎて……。別にヒーローになりたいわけじゃないんです。マーベルの英雄達に焦がれた少年時代もなかった。だけど俺はブルーノと約束しました。その時が来たらあいつを止めると。それが、例え俺の存在と引き換えになることがあったとしても。……なんとなく、思うことがあって」 「なんだい?」 「ブルーノは別に俺を裏切ったとか、そういうんじゃ、ないんだ」 ヨハンは「そうだね」という肯定をしない代わりに、「そうだといいね」という否定もまたしなかった。彼は遊星の肩をまるで父親がそうするように抱いて、「すまない。ありがとう」と、呟いた。 とにかく時間がないというのはわかっていたから、すぐに発とうと言ったヨハンの言に十代やルチアーノは勿論、遊星も特に異はなかった。ブルーノがいつ世界ごと終わらせようとするのかは誰にもわからないし、それにゾーンとかいうやつが(黒幕ではなかったとはいえだ)爆弾を抱えたかのような状態であることに変わりはない。 既に死人である名もなきファラオと盗賊王バクラは、それぞれ『遊星くんの元にいてやるのが、相棒との約束だからな』『俺サマとしちゃあ、あのふざけたロボット共に、教えてやらなきゃならねえことがあるからな。それにガキ共だけじゃあ何かと不安だろうよ』と随行の意思を示す。彼らは冥府に召されるタイミングを見失った時空の迷子だ。心残りはこの地にはない。 遊星やヨハン、十代が心配していたのは残りのチーム・ファイブディーズの面々だった。仲間思いで、遊星を大事にしている彼らが、自分達の存在を省みずに同行を言い出すのではないかと危惧していたのだ。でもそれは杞憂に終わった。 「私は残るわ。フォア・ザ・チーム、今チームのためになすべき役割は、遊星に着いていって彼の負担になることじゃないもの。私はここで遊星の帰りを待ってる。遊星を信じて、遊星の帰る場所を、私が作るから」 「俺達も同意見だ。正直そんな人間様がお呼びじゃねえような戦いによお、俺らみてえなただの人間が行ったって、仕方ねえだろ。遊星にはその痣? みたいなのがあるけどよ」 「クロウの言う通りだ。悔しいが仕方あるまい。聞けば龍亞と龍可の言うところによると、『正史』とやらでは俺達全てに一つずつその痣があったそうだが……俺もクロウも十六夜も龍亞も龍可も身体のどこにもそのようなものを持ってはいない。俺達がいつか別の歴史でイリアステルと戦っていた時もその痣に救われて生きながらえたことが少なからずあっただろう。この生身で力及ばず無様な死でも晒してみろ、遊星を追い詰めるだけだ」 「その遊星の痣だって、完全じゃないもんね。ドラゴン・ヘッドしかないし、たぶん全部揃えて大気圏突破とか、今は出来ないんだよ。……ほんと、ほんとだよ、正史の遊星はマジで大気圏突破したの!!」 「私と龍亞もね、パパとママについていきたいとは思ったの。だけど今の私達、本当にただの、精霊を呼べるだけの子供だもの。命のかかったデュエルでライフがゼロになったりなんかした時……きっともう立ち上がれない。だから、パパやママの戦いでこの世界に変化が出た時、そのために私達は力を使うわ。大丈夫よ。私達みんな、チームだもの」 理由は簡単で、まっすぐで、裏表がない。チーム・ファイブディーズの守りたいもの、守りたい未来は一緒で、だから迷いもなかった。 遊星のことを――家族同然のチームメイトのことを、信じているのだ。 「でも一つだけお願いがあるの」 龍可がおずおずと言うと、五人が一斉に遊星に向かってカードを差し出してくる。彼らの切り札であるシンクロ・モンスターのドラゴン達だ。《ブラック・ローズ・ドラゴン》、《ブラックフェザー・ドラゴン》、《レッド・デーモンズ・ドラゴン》、《エンシェント・フェアリー・ドラゴン》、《パワー・ツール・ドラゴン》。この世界でも変わることなく彼らにもたらされたシグナーの守護竜、彼らの魂と深く結びついたもの。 「連れて行ってあげて。私達みんな、このカードに全てを託すから。チームは離れててもみんな一緒。そうでしょ?」 龍可が目配せした。頷き、差し出されたカードを一枚ずつ受け取る。しなやかなカードのそれぞれに重みがある。魂の重みだ。竜と彼らそれぞれの。 「カードの精霊達はね、世界ごとに少しずつ違うみたい。龍亞のドラゴン、パワー・ツールのままだし。でも、繋がりの力は変わらないわ。遊星になら託せる。ね? アキさん」 「ええ。……遊星、『行ってらっしゃい』」 「ああ。『行ってくる』」 伸ばされたアキの手を握り直した。遊星がずっと寄り添ってきて、一番よく知っているやさしい女の子の手だ。彼女がいて、自分を待っていてくれる限り、九十八パーセントの確率をすり抜けて残りの二パーセントを手に出来るような気がする。なにしろゼロじゃない。それは可能だということだし、なにより……遊星が憧れた遊城十代というヒーローはいつだってそうやって乗り越えてきたのに違いないのだ。 それから少しだけ目を瞑って、他愛のないことを思考する。 今更のようだけど考えてみたい。世界がどんな形をしているのか、どうやってここまで続いてきたのか、どうして人は生きるのか。 ブルーノは、どうして……歴史を変えてしまうほどの願いを、希ったのかを。 ◇◆◇◆◇ 次元の果てにある《神の居城》に一行が辿り着いたのは、ネオドミノシティを離れてすぐ後のことだった。海馬瀬人や天馬兄弟によって進められていた時空渡航技術は賞賛の一言だったし、原動力はあのモーメント・エネルギーなのだから、ある種の納得もある。 不動博士は息子がリスクを理解した上で時空移動に挑むことを止めず、ただ、あの真剣な声で「遊星、後悔はしないように」と息子に囁いた。 そびえ立つアーク・クレイドル――モーメント・エネルギーによって滅びたあるひとつのネオドミノシティの成れの果て――を見上げながらルチアーノが反芻していたのは、出立の直前に龍可が訊ねてきた言葉だ。彼女はもうここにはいないのに、あの声がまだルチアーノの頭の中でくすぶっている。かぶりを振った。どれだけ考えても答えは出ない。 『あなたが今こうしてじっと私達の中に紛れていることが、私、不思議でならないの』 『……なんだよ藪から棒に』 『だってそうじゃない。あなた、龍亞を襲った上にパパとママを突き落としたのよ。そのあとパパとママがした体験からして、もしかしたらわざと狙ってそうしたのかもしれないと考えたりもしてみた。だけど腑に落ちないの。全然、何も、論理だってない……ぐちゃぐちゃでてんでばらばら。どうして? どうしてなの? ……ねえ、教えて。パパとママのこと、あなた今もまだ本当に嫌い?』 『大ッ嫌い。特にヨハン・アンデルセンと龍亞。でも……今は……もっと、ゾーンが……そしてゾーンを狂わせたあいつが……!』 『……憎い?』 『……。わかんない。人間と同じ感情は、もう僕の中にはさ、ないはず、だから。でもあいつが歴史を変えなきゃ、母さんは……《ルルイエの聖女》は、生まれなくて済んだしあんな目に遭わなくてよかった。ゾーンが傾倒しきって狂わなくても、おんなじ』 『そう。それを聞いて少し安心したわ』 『ハァ? なんで?』 『お母さんが大好きな普通の男の子と、考えてることそんなに変わらないもの。ルチアーノはきっとママを傷つけない。大丈夫ね』 『そんな保証どこにもないだろ』 『そうね。でもあなたは、私が言ったことの意味を……答えを、本当はもう知っているのに、違いないんだわ』 龍可の言葉は不可思議で、ルチアーノの理解の範疇を超えていた。彼女は悟りを開いたかのような顔をして……まるで大切な兄弟や、ボーイ・フレンド、それからクラスメートにそうするようにルチアーノの手を握ったのだ。 ルチアーノの手は、あんまり、冷たくないのよね。龍可が囁く。アンドロイドのボディの上に人工皮膚を上張りして限りなく人間に近付くように偽装しているのだ、そんなことは当たり前なのに。 『私、あなたが龍亞を傷付けたこと、パパとママを傷付けたこと、それらは決して許していないの。私はあの時、ルチアーノがとても憎かった。怒っていたわ。あなたをすぐにでも壊してしまいそうな顔を、していた。龍亞も。 ……だけどパパとママを狙ったこと自体は、動機としてはイリアステルとしての役割だったからなのよね。歴史を修正しようとしてる二人は邪魔だから。でも気になっていることがあるの。……パパとママが、ママの喪われた記憶がある場所に落っこちたことについてよ。二人とも、あまり詳しいことは教えてくれなかったけど……』 ルルイエの聖女の手は、冷たい。龍可の手のように、そして恐らく本物の遊城十代のように暖かくない。最後の時でさえあの「おんな」はルチアーノを抱き締めてはくれなかったが、頭を撫でられた時の冷たさがまだ感覚として残っている。 『その場所にパパとママを送り込んだのはルチアーノの意思でしょう。私、龍亞と話したわ。……今ここにいるルチアーノは、人間の男の子よ。どこにでもいる』 龍可の手は尚もルチアーノのつくりもののボディを握りしめていた。人間の男の子? 何故そんなことを言う? この血の通わぬ肢体に、ルチアーノは母の愛をうまく受けることさえままならなかったのに? 「空気、すげー淀んでる。重たいし……なんか、一人では来たくないな。ここが《アーク・クレイドル》? ゾーンとブルーノが、いるのか?」 「歴史をリセットするならここしかないと思うし、ゾーンがいそうなとこ、あそこしか見当つかないし。たぶんそーだよ。アーク・クレイドルは歴史を俯瞰して操作してる場所だから、並行存在が歴史の分岐の数より少ない。尤も僕もここ以外のアーク・クレイドルの座標は知らねーけど」 「オーケー、概ね把握した。それで俺達は今、どこへ向かってるんだ」 「この先にガレリヤがある。そこを抜けた先が大聖堂。名前ばっかの、ただの墓場だけど。カタコンベだよ――もう、死骸ばっかり。一目でやんなるぜ? 特に不動遊星。キャッハハ、あんた、もしかしたらだけどさあ、どーしてああいうつくりなのか、理解出来ちゃうかもしんないからさ……!」 ゾーンのいる場所、そればかりは、すぐ推測がついたし多分正解だろうと信じて疑わなかった。ブルーノを回収しに動くかと思いきや踊らされていたに過ぎないと発覚したゾーンが、では尚更、あの場所を動く理由もないと確信出来たからだ。ひび割れ硝子の聖域、腐り落ちたムネモシュネ、腐敗しきったクロノスタシス。《コッペリアル》に狂った《ヴェルズ・オピオン》。コッペリアルの亡骸を、彼はきっと後生大事に抱えている。彼女を殺した男を待ち侘びて。 不動遊星の成れの果て。彼が拗れ尽くした先に迎えていたかもしれない一つの可能性。 遊城十代を手に入れられなかった男の醜悪な末路。 ガレリヤには変わらず陽が射し込んでいて、しかし、大聖堂にはもうさえずる鳥の剥製はいなかった。機械の臓腑を剥き出しにした無残な残骸が梁の上にわだかまっているに過ぎない。かつてあの鳥も歌をうたっていたのに。聖女の愛した歌――ルチアーノが聞かされていた、あの。 百合の花の香りがひどくきつかった。 「……久しぶりじゃん? もう二度と会いたくなかった――ていうかさあ、それでなんでまだ、ここにいるワケ? ほんっと……知らなかったよ。あんた、もうちょっと崇高な目的とやらを持ってるんだって思ってた……だから歴史を変えようとしてるのかなってさあ、少なくともパラドックスは信じてた。それであんたのために戦って壊れた!! なのに!!」 棺桶はやはり六つ。しかし空箱は二つに減っている。ゾーンとルチアーノの棺だ。アンチノミーの棺などはなからこの聖堂にはなかったのだ。 四つ目の棺に納められた機械人形の顔など、見たくもなかった。だから確かめない。吐瀉物など出せもしないのに吐き気ばかりがこみ上げてくる。 苛立ちが爪先で床を叩く音に現れていた。パイプオルガンに掲げられた聖像、花で埋められた墓標。処女崇拝の混じった聖女崇拝をつくりものの人造聖女に捧げていた妄執を睨み付け、ルチアーノは声高に詰る。 「歴史を再修正しようとしたのも、その女に執着して僕達を使い捨てたのも、全部、全部、全部!! あんたじゃなかっただぁ?! ふざけんなよ。あんたは僕らを裏切ったって、そういうことだ!!」 糾弾は聖堂じゅうの硝子を引き裂いてしまわんばかりに鋭く、痛ましい。びりびりと大気が震える中、遊星が呆然として辺りを見回している。彼が最後にゾーンに視線を定め、「まさかそんな」とでも言うように顔を顰めた頃、十代が伸ばそうとした手をルチアーノは払いのけた。 ルチアーノの思考プロセスは暴走一歩手前で、とてもじゃないが、プリセットされた生前の感情をロードしているのだというシステムの枠を飛び越えて複雑に入り交じり、暴れ狂っている。あの憐れな聖女、決して手に入らないヨハン・アンデルセンという神に恋い焦がれ、その手で自らを殺させることで永遠を手に入れてしまった『母親』、あのひとを、生み出してしまった眼前の男を恐らくルチアーノは憎んでいた。恐らく、と付くのはその名前をこの激情に宛がっていいのか、そも機械人形が憎しみを抱いてもいいのかという葛藤に基づく自問自答が僅かに彼の中にあったからに過ぎなかった。 ブルーノさえいなければ歴史は狂わず、聖女は生まれず、機械人形はこれほどまで苦しみを知らずに済んだ。大元を辿れば確かにそうなる。だからルチアーノはブルーノを罵ったし、首を締め上げたのだ。 でも聖女を作ったのはブルーノじゃない。聖女を作ったのはこの男だ。本物の遊城十代を一度は手に入れ、しかしとても触れることが恐ろしく、結局崇拝するための偶像を作るしか出来なかった《ZーONE》。彼女に《聖女》というくだらない役割を与えてあの陰惨極まる仕事を強要した。心ないロボットが恋をするほどの永い時に縛り付け、救われないデウス・エクス・マキナを、化け物の生産プラント、オレイカルコスのわき出るルルイエの都のシンボル、自己欺瞞ばかり得意な祈る神の出来損ないを……造ってしまった。 なんという傲慢であろう。どいつもこいつも、エゴを後生大事に抱え込んで醜く崇拝対象に擦り付けようとする。 『ルチアーノ。私は以前にも告げたはずです。彼女の忘れ形見であるあなたを傷つけることを、私は望んでいないと』 ゾーンが口を開いた。声帯が潰れてしまったために補助器官の力を借りて紡がれるしわがれた人口音声は、不動遊星とそれほど似ていないような気が今はした。 「それが免罪符になるとか思い上がっちゃってるぅ? もしかして?」 『いいえ。しかし私にはあなたよりも優先すべき対象があります。いつか必ずここへ来ると思っていました。遊城十代に選ばれ……私の神をも殺した男が……』 何にもなれなかった男が、たった一人を指さす。自らがコピーしたオリジナルではなく、オリジナルや自身が焦がれた悪魔でもなく、その悪魔が神にした男を。 『ヨハン・アンデルセン。私は、あなたに相見えるこの時を心待ちにしていましたよ。ええ、嘘ではないのです。いつかこの時が訪れるはずだと、待ち望んでいたのです』 浮遊アンモナイトがパイプオルガンの元を離れる。名指しをされたヨハンはいつもと変わらぬ素振りで立ち、眉を僅かにつり上げてそれを見ていた。殺して欲しいと願ったアンドロイドを手に掛け、妻を取り戻した男の前にゾーンが相対する。仮面の下から覗くしわがれた表皮には最早名のない感情がべとりと張り付き、底が見えない。 『この世に神がいるのなら、私はそれを殺したい』 そう、私は強く願うのです。まるで壊れかけの機械のように彼は宣った。 |