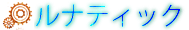制御が効かなくなっている少年アンドロイドを肩で抱いて、後ろにいる最も信頼の置ける相手に預けた。彼が焦がれた母親が記憶や悪魔ユベルと共に回収されて十代の中に受け継がれたことをヨハンはまだ告げてはいないし、たぶん教えたところでそれは既に別人だとにべもなく切り捨てられるだけだろうが、とにかく、彼をあの狂った造物主の前に出すべきだとは思えなかった。 父親の情なのだろうか。彼が両親を――本物の両親を、一番初めの歴史で暴走したモーメント、機皇帝に――奪われてから実際には一体どれほどの時が流れたのかと問うのは無意味だ。しかし指折り数えるのが無意味だからと言って、それを与えることまでが無価値だとは思いたくなかった。 ヨハンと十代、人の理をいつしか外れてしまった赤い英雄とそのつがい。だけど彼らは、それでも今なお、これほどに人間じみた感情を持ち、人間くさいことを成そうとする。子を愛し、人を慈しみ、世界を守りたいと願う。半人半精になったからといってそれを棄てるなんてことはとても出来なかった。二人はそうしてずっと生きて来たのだから。 『ルチアーノは、普通の男の子よ。どこにでもいる、ありふれた、お母さんが大切なだけの……』 別れる間際に娘が教えてくれた言葉はすとんと胸の奥に落ちていっていた。海底都市ルルイエ、彼の母がいる場所にヨハンと十代を突き落としたのはルチアーノ自身だ。彼は何故そのような行動を自らが取ってしまったのかあまり理解出来ていないようだったが、磔にされた「彼女」との対話、その後の十代の言で、おおよその予測は付く。 ルチアーノは母親を救いたかった。 彼女に幸せになって欲しくて、せめて、望む最後を与えたかっただけなのだ。 それが彼の最初で最後の「親孝行」になろうとも…… 「どうも俺をご指名のようだ。他の皆は下がっていなさい。十代、ルチアーノと遊星君を頼む」 「おい、ヨハン、何する気だよ」 「どうもこうも、話し合いが通じる相手じゃなさそうだからね。話し合いが出来ないとデュエルにも持ち込めない。そういう意味じゃ、ユベルとかまだ話が出来た方だし、ダークネスも話を通じさせられた方だ。いいかい遊星君、覚えておくことだ。誰しもが、話をしてくれるわけじゃない。特に嫉妬に狂った人間は」 「アンデルセン博士……あれが……それじゃ……やっぱり……」 「そうだ。《Z−ONE》、人類最後の一人。歴史を変えようとして過去の英雄に成り代わろうと思い上がった科学者。不動遊星という伝説をトレースし、思考をコピーし、焦がれたものになろうとして……その一つの結末だよ。手に入らなかった遊城十代という理想像を諦められず、なまじ力を持っていたばっかりに」 彼女は言った。科学者はまぶしすぎる本物に手を触れることが出来なくて、結局彼女というまがい物を造るしかなかったと。 また彼女は言った。自らを示し、あっけらかんと笑いながら、プログラムで許された通りに。 『かわいそう? オレにはわかんないよ。オレは機械だ。機械は使われる為に存在してる。どんな時も』 『なあ、ヨハン。ヨハン・アンデルセン。つくりもののオレが、きみのことが好きだって、あいしてるって言ったら、きみは首を振るかい?』 『でもオレは、それでもオリジナルと同じように、ヨハンのそういう潔癖症のとこ、好きだぜ。嘘も偽りもないオレの、夢見る機械人形のほんとの気持ち。オレの最期を見看るのがきみでよかった。つくりもんの造物主に壊されるのはまっぴらごめんだけど、ヨハンになら……』 『オレは壊されたっていい』 ヨハンは歯噛みをする。最後の時まで少女は泣かなかった。機械人形は涙を流すことが出来ないというその鉄則を、彼女を侵食したこの世界の理……大いなる生命の奔流であるオレイカルコス=モーメントはやはり覆してはくれなかったから。 「そればかりか奴は一人の何の罪もない少女を慰み者にした。俺は彼女の最後を看取った者として、あれと決着をみなければとても自分自身を許せそうにない」 だから俺に任せて欲しい。そうはっきりと言い渡すと、ルチアーノはぐっと某かの言葉を呑み込んで、それきり押し黙ってしまった。 目を瞑り、ヨハンは思う。……少女は遊城十代の考えられ得る一つの末路で、ゾーンは不動遊星の考えられ得る一つの結末だ。二つの可能性が相見えてしまったこの歴史で、願い請われてその片方を殺したヨハンは、今また残った片一方をも葬ろうとしている。 もしも、これがエゴだと言うのならばそれでもう構わない。ヨハンは聖人君子じゃないし、大抵いつも、独断で道を選んできた。それにこういう汚いことは大人の仕事だ。ヨハンはもうずっと前に、大切な人を守るために子供であることをやめたのだ。 ◇◆◇◆◇ そこから先は酷いものだった。 ヨハンが家族達を呼び出し、バリケードを作るように彼らを散開させた頃にはゾーンも展開を終了させていた。セフィロト・ツリーをの座を司る「時械神」達が十体、デュエルの制約を全て飛び越えてそこに実体として鎮座している。 機械仕掛けの鎧に閉じ込められた天使達は、苦痛に歪んだ表情だけを中央に表して低い声で唸りたてていた。その全てが攻撃力四〇〇〇級でそのうえレベルにして十の神域に名を連ねている。あまりにも圧倒的な威圧感。それはここが神の居城、くず鉄の王の本拠地であるからこそ成し得る荒技だろうが……地の利とはよく言ったものだが、よもやここまでとは。 間もなく、ヨハンもその「本性」を露わにすることになった。全てが神レベルに属する「神に近きものども」、大天使どころか熾天使までもスクラップの器に押し込めて使役しているという破格の精霊達だ。いかな虹の神とて、そう簡単にいなせる相手ではない。 時械神ラフィオン、栄光の座を司る天使が諸手をあげた。ヨハンの背から虹の神の翼がそりたって宝玉獣達と一丸となりその攻撃を防ぐ。遊星が息を呑む音が小さくヨハンの耳に届いて思わず苦笑した。……そういえばまだ彼には、この半精霊の姿は見せていなかったか。 『度し難いのです。全てが理解し得ないのです。あなたがそうして救世主気取りのように立っていることが、あなたばかりが望んだ全てを手に入れられたことが、全て全て全て許し難い傲慢です。教えてください、ヨハン・アンデルセン、『英雄に選ばれた男』。あなたの何が秀でていたというのです? あなたの何が――彼女を私から奪うことさえ、正当化させたというのです?!』 ゾーンの狂乱が雄叫びとなり大聖堂を震わす。呼応するように十の天使全てが大口を開いて唸り声を束ねた。聖堂中の硝子が反響で弾け飛び、破片が飛び散るがまるで気にした様子がない。知恵の座の天使ラツィオンが辣腕を乱暴に振るう。他の天使達もそれに横暴に倣う。ザフィオン、理解の座。サディオンは慈悲で、カミオンが峻厳、ミチオンは美、ネツァクが勝利、ガブリオンが基盤、王国のサンダイオン、そして王冠のメタイオン。偽物のはがねの天使達。偽りの造物主が造り上げた傀儡の兵隊。バクラが舌打ちをした。強制と信仰をその奥底に見て、反吐が出そうで仕方がないという顔だった。 『あなた方がこの次元へ落ちてきた際に私は遊城十代を一時回収し、そして悪魔のコアを抜き取った。だがとても触れられなくてすぐに手放してしまいました。恐ろしく……まるで身に余る硝子細工に手を掛けているようで……私は遊城十代ごとコアをこの城に留めておくことが出来なかったのです。それはまるっきり、神への謀反だった! 神などとうに死に絶えたと信じていた私の世界に降り立った唯一の神の似姿だった。私は、仕方がないのでそのオルタナティブに彼女を作りました。彼女の出来栄えは上々だったでしょう? 依り代として正しく機能し、ヨハン・アンデルセン……あなたの足を留め、私は彼女の中に灼けつく星の光をさえ見ました。……それなのに! 彼女は……彼女はあなたに殺されることを願い……またしてもあなたが選定された。英雄のまがいものにでさえ!! 何故なのですか? 何故あなたは選ばれ続ける? あなたの何が――私と――不動遊星と、違ったというのです?!』 「敢えて言うとするのなら、根底から何もかも違ったんだろうさ。なるほど、今の話を聞いてて、ああ本当に遊星君をコピーしたんだなってことはわかった……けどな。俺達と一緒にここまで来た遊星君はわかっているよ。少なくともゾーン、お前が振り切れて、間違って、もう戻ってこないんだってことは。なあ?」 取り合っていられないというヨハンの声音に従って、顕現した虹の竜が咆吼を上げ時械神の一体を消し飛ばした。攻撃力四〇〇〇同士の相打ちで双方が実体化していられなくなったのだ。だが、時械神は破壊耐性を持っている特殊な精霊達のはずだ。想定外の事態にゾーンの顔色が更に翳る。 「なんで時械神が戦闘破壊されたのかわからないって顔だな。愚問だとは思わないか? いくらデュエルの発生を放棄したところで、デュエルモンスターズの精霊を呼び出している以上、そういうリスクも有り得る。俺は既に《スキルドレイン》を発動している。そしてスキルドレインの効果は手札にまで及ばない……よって俺は何度でも手札に戻る限りレインボー・ドラゴンを召喚出来る」 『そういう、ことですか。ではその姑息さが本物と偽物との違いだとでも? とんだ皮肉ですよ……宝玉神』 「いや、違うけど。しかし……まったく、うちの奥さんは本当にとんだ小悪魔だな」 虹の竜が再び顕現し、また間髪入れずに次の時械神を吹き飛ばしていく。溜息を吐かずにはいられなかった。遊城十代は……ヨハンが選んで選ばれたひとは、なんてとんでもない存在なのだろう。例えば彼は学園中のヒーローで、遊城十代のデュエルに魅せられない生徒なんてきっとあのアカデミアには一人もいなかった。学園中の注目を常に集め続けて、学生達を左右していた。また異世界では数多の精霊達を魅せ、狂わせ道を踏み外させる。終いには悪魔ユベルをさえ執着させ……己を、そしてヨハンを狂わせて、そうして今また一人の愚かな科学者を破滅させるのだ。 「俺達のいた世界のゾーンが、自分のことを『愚かな科学者』と言った理由が今ならすごくよくわかる気がするんだ」 遊城十代はいつだって自覚なくジェノサイダーで、意識のないディアボロだった。だけどそのくせどこまでも人間くさくて……本当はナイーブで、誰かを守りたいと願うふつうの男の子だった。 だからヨハンは十代を守りたいと思ったのだ。 このひとの手を離してはいけないと信じた。 「まず最初に『不動遊星』という偶像に縋った自分には、何一つ本当のことなんかないって彼はきっと思ってたんだな。それでも正史や、他の数多の可能性のゾーンは本物を確かに持っていたよ。友達との思い、絆、喜び、そういった確かなものをだ。けれどお前にはそれすらもない。遊星君を複写してぐしゃぐしゃに丸めたようなものしかもう残ってない――それが、歴史改変に伴うオレイカルコスの影響を直に受けすぎてしまったからなのか、それとも十代と接触してしまったからなのかは俺にはもうわからない。だけど明確に分かることも一つある。……もう限界なんだろ?」 『何故……何故……何故……! 何故倒れない。何故そうも平然と、太陽のすぐそばで、燃え上がって灰にもならず、不死者のような顔までして立ち上がり歩いてくる!!』 「諦めて責任を誰かに求めたらそれはもうヒーローじゃない。嘆いてるだけじゃ誰も救われない。人間そりゃ挫折はあるさ。だけどな……十代はそこからまた立ち上がって、もがきながら前へ進もうとして、そして歩き続けてきたんだ。後ろ向きに蹲り続けようと決めた時点でお前はもう歩くことを止めてしまったんだ」 順繰りに時械神が撃破され、残りは僅か一体となる。王手だ。ヨハンは静かに自らの半身を奮い立たせ、真っ直ぐにゾーンを見据えて十字を切った。 「悪いけど、俺は負けないよ。少なくとも俺の大切なものを傷つけようとする輩には、絶対に。……多分、引き返すところはいくらでもあったんだ。そこにいる遊星君が考えたような時間があったはずだ。この歴史では遊星君、随分とやんちゃだった。防犯カメラで覗き見するとか正史の遊星君が聞いたら真顔になりそうだもんな。彼は彼なりに葛藤して、自分の感情と向き合って、考えてた。だけどそんな、まさかああいう人形を作ろうだなんてとこまでは、決して思い立っちゃいなかったはずだし、その思考に辿り着いちゃいけなかったんだ……」 ゾーンのわめき声は最早うまく言葉の体を成していない。その醜悪な姿に引導を渡すべく、ヨハンの全ての翼が開かれてレインボー・ドラゴンに宝玉獣達の七色の光が集約していった。レインボー・ドラゴンの特殊効果だ。ヨハンの手には《禁じられた聖槍》が握られている。――今この時、レインボー・ドラゴンは聖槍以外の魔法や罠の効果を受け付けない。 「人間が不自然な方法で人間を作ってはいけないのは、それがたいてい、不幸な結末しかもたらさないからなんじゃないかって俺はずっと人間を見ていて思った。一つ聞こう。なあゾーン、《ルルイエの聖女》を造ったことでお前は果たして救われたか? お前の望みは満たされたのか? それって結局、独り善がりの、自慰行為に過ぎなかったんじゃないのか……?」 ゾーンは答えない。その代わりに、ヨハンの脳裏を彼女の最期の姿が駆け抜けていく。 『……そうだな。オートマのゼンマイ人形なんか、そいつは造るべきじゃなかったんだ。神様気取りみたいに。よりによってろくでもないものになぞらえて』。そう泣きそうな顔で言うと彼女は笑う。『あはは。ヨハンがそう言うのなら、そうなのかもなぁ。ろくでもないかな、やっぱり。でもさ、ヨハン、オレ思うんだけどさ……』、そうして機械人形はもう一度だけ瞳を開いて小さく舌を出して言い訳をしたりなんかするのだ。『ごめん。オレ、そういう機能ないから上手に泣けないけど』。それで『ばかやろう』と言ってやるとちぐはぐの瞳を瞬かせる。あまりにも儚かった。終わりを覚悟している目を、彼女はしていたのだ。 ヨハンに「ころされる」ことを心底願っている、そういう顔を彼女はした。 彼女の声なき請願をヨハンは受け取った。受け取らざるを得なかった。手を下してやることだけが、彼女の望んだ唯一の救いだった。彼女は疲弊しきっていて、造物主を畏怖しきっていて、けれど子供だけが心残りで、だけどやっぱり、女のエゴを取って、ヨハンによる「おわり」を選び取る。 ヨハンはあの時かぶりを振った。そうするしかなかった。だって泣けない人形にヨハンが何をしてやれるのか、それはもう決まりきっていて、だから、 『オレは、きみがオレのために泣いてくれるとこを見れたから、捨てたもんじゃねーなって思うよ』 彼女のその言葉を耳に突き刺しながら、ルルイエを焼き尽くすことしか出来なかったのだ。 「はじめ、あの子はただ少し、泣きたかっただけだったのに」 心が軋む。その痛ましい音に共鳴するように宝玉獣達を統べる王が一際高く吼え哮る。 だけどレインボー・ドラゴンのその咆吼がゾーンに向かって放たれることはなかった。 『油断しましたね。ヨハン・アンデルセン』 くず鉄の王が凄惨な笑みを浮かべた。 「なっ――?!」 振り返ったヨハンの背後にいつの間にか《究極時械神セフィロン》が鎮座している。この時を待っていたと言わんばかりに唇の端をつり上げ、ゾーンのしわがれた皮膚の下から身も凍るような声音が響き渡った。一条の光がヨハン・アンデルセンを飛び越え遊城十代のもとへ躊躇いなく伸びていく。宝玉獣達や究極宝玉神の庇護をすり抜けて無慈悲に襲いかかる。 『言ったでしょう。この世に神がいるのなら、私はそれを殺したい、と。……私にとっての神が誰なのか、それは最早言うまでもありません。無論神殺しの代償は安くはない。神を殺める執念と引き換えに私は全ての力を使い果たし、この身体を支えていた生命維持装置さえ動きを止め、息絶えます。しかし、それで構わない』 「クソッ……おまえ……どこまで狂えば気が済むんだ?! 自分が何をしたかわかって……!!」 『当然でしょう? 私は私の神を殺して悲願を全うします。私が狂わされた全ての根源を断ち、解放され、自由になる。最早悔いはありません。この一点において私はオリジナルをさえ凌駕しました。それでいい。オリジナルは……『不動遊星』もまた、私の英雄だったのだから……』 『英雄の手は、血に染まるべきではないと私はもう幾数千年も信じていたのです……』。それを末期の言葉にしてゾーンが崩れ落ちた。絶命したのだということが一目で分かった。コントローラーを失った究極時械神セフィロンが制御を外れ、人造のはがねの鎧から解き放たれ消えていく。 不動遊星は絶句し、そして為す術なく立ち尽くしてその様をただ見ていることしか出来なかった。 「なんで……うそだ……嘘ですよね……?」 セフィロンの下には遊城十代が横たわっている。 十代は身体中から血を流して、そしてどさりと地に倒れ込んだのだ。血が止まる気配はまるでなく、精霊の再生能力を持ってしても癒せない程の傷をセフィロンから受けたということを示していた。ゾーンの狂いきった妄執はその存在と引き換えてついに呪いと化し、十代を貫き、息の根を止めて…… ルチアーノが呆然と倒れ伏す十代を眺めている。二人の亡霊も腕組みをして目を見開いたまま無言だ。その光景にヨハンは理解する。十代はルチアーノをを庇って倒れたのだ。 それは十代の中にある「彼女」の意思なのか……いや、そんなことは些末事でしかないだろう。遊城十代はヒーローだ。赤い英雄だ。守れるものを守ろうとすることに打算や理路整然とした理由なんて必要ない。 ……だけど一つだけ、いつもと全く異なる事がある。 赤いヒーローが、いつまで経っても、そこから立ち上がってこないのだ。 |