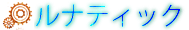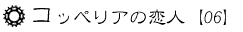「あ! ルチアーノのやつ、ピーマン残してる!!」 双子の片割れが、ブランチの皿の隅に残された緑色の切れ端を目敏く見つけ出して指さした。ピーマン炒めの切れっ端は、なんとか苦みを軽減しようと甘辛く味がつけてあるお手製の一品だ。双子は既に残さずそれを平らげた後だったからなのか、指摘する声が妙に張り切っていてコントラストが高い。 「うるっさいよ。いーだろぉ、別にピーマンぐらい残したって……」 「でもママがせっかく、ルチアーノでも食べられるようにって作ってくれたんだよ、それ。せめて一口ぐらい食べてよ。結構いけるよ」 「……でも僕、嫌いなんだ。もうこの色から形から、何から何までぜーんぶ。きらい。ほんと、きらいで」 「うーん、そうか……そうなのか……ルチはピーマンがそんなに嫌いか……」 その声を聞きつけて、台所からピーマン炒めを作った張本人が顔を覗かせた。しかしお手製のピーマン炒めが残されているということに特に顔をしかめているわけでも悲しんでいるふうでもなく、顔は少しにやついている。まるっきり、何か面白そうなことがあるなと出て来た野次馬だ。 それを察して微妙な顔をすると、彼は更ににこにこと笑って皿のピーマンをちらと見た。手つかずで盛られたままの綺麗な緑色の野菜。双子のもう片割れが、彼の顔を見ると「また始まった」という表情になって息を吐いた。 「しかし随分綺麗に残ってるな。こりゃもう、前世で何か因縁があったのかもしれないっていうぐらいの嫌いっぷりだ。よーし仕方ない、龍亞、龍可! まだピーマン食べられるか?」 「私、もうちょっとお腹いっぱいかな」 「俺も、もうだいぶいっぱい」 「じゃあ俺が食べよう。あーあ、これ実はすっげーおいしいのになあ、勿体ないなあ」 わざわざそばまで寄ってくると、実にわざとらしくそんなことを言って見せつけるようにフォークをピーマン炒めに突き刺す。それでも主張を曲げるのがいやでぷいと顔を背けると彼の顔も合わせて回り込んできた。勿論フォークに刺さったピーマンもセットでだ。 「せっかく、ルチに食べてもらいたくて一生懸命考えたんだけどなあ」 「……」 「俺なりにがんばって試行錯誤とかしてみたりさ」 「……う」 「おいしいものの味、ちゃんと知ってもらいたいし」 「……だ、だって」 「でも本当に仕方ない。俺が責任持って食べるよ。ごめんな」 「……わ、悪かったって! そんな顔して僕のこと見んなよ、もう!!」 「うん、よく出来ました!」 あまりのしつこさに辛抱たまりかねて口を開くと、待ってましたとばかりにフォークをその中に差し込まれる。しまった、これじゃ思うつぼだ。しかし今更口の中に侵略を果たしたピーマンを排出することは出来ない。仕方なく敗北を認め、ピーマンを咀嚼する。 「……あれえ?」 根負けして初めて食べたピーマン炒めは、本当に思ったより苦くなかった。どころか少し甘いぐらいだ。驚いて見上げると、彼はいたずらが成功しただだっ子のような顔で「してやったり」というふうにはにかんだ。 「ほらな? なんでも食べてみるもんだよ。これでルチは、また一個おいしいものを知ることが出来たってわけ。些細なことだけど、それも幸せの一つだなあって俺は思うんだ」 ピーマン炒めをすっかり食べ終え、空っぽになった皿を持って彼が台所へ消えていく。鼻歌を口ずさみ、実に嬉しそうだ。たかだかピーマン一つ食べたぐらいで、大げさだなと思い、ふとハミングに耳を澄ませる。どこかで聞いたことのあるメロディだったからだ。でもタイトルが全然思い出せない。 それにどこで聞いた音楽だったっけか? 「その歌、なに?」 だから聞いた。今聞かないと後悔するような気がしたのだ。後回しじゃいけない。あの歌の名前は? どんな歌で、誰が、何の思いを込めて歌ったのだ? 「教えてよ。知りたいんだ、今すぐ」 「ん? ああ、これか?」 スポンジを持った手は止めないまま、彼は鼻歌を止めて振り返った。どんぐりみたいな茶色のまなこがこちらをじっと見てくる。硝子玉じゃない、綺麗な生きている誰かのまなざし。 それだけで、一つだけ「思い出せた」。あの歌は確か、生きている人間が、生きている誰かのために歌うものだ。たとえばセキセイインコの剥製や、たとえば人に造られた機械人形が……歌うようなものじゃ、本当はなくて。 「この歌の、名前はな――」 彼の唇が歌の名前を形作る。だけどそこだけすっぽりと音が掻き消えてしまい、ついぞ答えを知ることは出来なかった。 ◇◆◇◆◇ その時選択肢は二つあった。 右手にひとつ、左手にひとつ。そして必ずどちらかを選ばなければならなくって、まばゆい紅がどこまでも広がっていくのを眺めながら両てのひらを交互に見つめる。一か二か、簡潔でとてもヘヴィな二者択一。選ぶ自由は残されている。……どちらを取っても、構わない。 選択肢のうちの一つ、右手に握られた方は「何もかも諦めて見殺しにする」だ。 これはすごく簡単で、それに機械人形の思考プロセスによると最も堅実で現実的な提案だった。だってそうだろう? こんな無残な死体、他にどうしろっていうのだ? 人間が心臓を貫かれた事実を帳消しにするのだって、本当は簡単じゃない。時を巻き戻すのに使うエネルギーは安くなんかないのだ。不動遊星の時は、心臓に腕を突っ込んだ方が別にそれほど執着心を持って事象を完結させようとしていなかった……から、成功したのだという部分が大きい。歴史を変えます、何かありますか、という確認にブルーノはチェーンを打ってこなかったのだ。だから効果も比較的簡便に通った。 だけど今回はそうもいかない。神を滅ぼすために自らの存在全てを賭けた「呪い」が、そうそう簡単に歴史の巻き戻しを通してくれるとは思えない。歴史の伸縮特性、だ――強い意思や強大な輝きが関与した時、どんなルートを通っても歴史は必ず元の形に寄り添おうとする。だから歴史を書き換えるというのはそういうことで、並大抵じゃないし、伴う苦痛だって尋常じゃないのだ。 そうだ、そういうことだから……仕方ない、見殺しにしよう。痛ましいかもしれないけど他にやりようもないし、何より龍亞と龍可の母親をそうまでして必死になって救ってやる義理なんかどこにもない。『お母さんが大好きな普通の男の子と、考えてることそんなに変わらないもの。』うるさい。そんなんじゃないんだって。『きっとママを傷つけない。大丈夫ね』ゾーンの凶刃にやられてるんじゃ、どうしようもないじゃんか。『そうね。でもあなたは、私が言ったことの意味を……』なんだよ……『答えを、本当はもう知っているのに違いないんだわ』……。でもボディに残されたエネルギーは貴重なのだ。今ここで使っていいものじゃないだろ、たぶん……何か、やるべきことを成すまでは大事にしておかなきゃ。 ――あれ? だけど、成すべき大事なことって、一体、何なのだろう? 『恋の歌だよ。ルチには、やっぱわかんないかなぁ』 いつだったか、そんなふうに《聖女》が言った。 『おれたちは、星が生まれて死んでいくのと同じぐらい確かに、恋をするんだって。そういう歌だ』 救われない彼女は、救いようのない機械人形は、それでも夢見る乙女と同じひとみをして恋を謳う。 『恋する誰かのための歌なんだって。人間は、こうやって恋をするんだって』 同じ人形の手を取り、愛など宿らぬ感情のないはずの腕で頭を撫で、盲信を連ね、だけどそれでも彼女は、確かに…… 『ごめんな。あいしてた。オレのこどもの、ルチアーノ』 生きていた。 自らの意思で限られた運命を選び取り、ラブ・ソングを歌い続け、今でもそれはルチアーノの中でまだ流れ続けている。 ◇◆◇◆◇ 遊城十代、世界で二番目にかっこいいヨハンの大切な人、不動遊星が焦がれてやまなかった半人半精の赤いヒーローは、自らが好んで着用していたあのジャケットよりも深く重たい赤色に塗れてそこに倒れていた。その双眸はオレンジと黄緑のオッドアイに染まってはいたが……彼が回復して起き上がってくるそぶりはない。その代わりにゆっくりと、儚いまばたきを彼はした。そうして右手を恐る恐る伸ばして少年アンドロイドに手を触れる。 「ルチ……は……生きてる、よな……?」 「当たり前だろ……僕はマザープラント唯一の成功作で……だいいちさあ、もうとっくの昔に死んでるんだ。機械なんだって。なのになんで……僕なんかを庇わなきゃ、あんたここまで怪我が酷くなったりしなかったはずだろ?! 悪魔ユベルの能力、今はちゃんとそこにあるんだから!!」 「うん。だけど、こうしないと絶対後悔すると思ったんだ。目に見えるものを見殺しにするとか俺、大っ嫌いなんだ。それにこれは俺自身の決めたことでもある。俺の中のあの子のためにやったわけじゃ、ない……」 「ばっかじゃないの……?! こんなことして、あんた一体何がしたくって、」 「ルチ。子供は、無条件に、愛されたっていいんだ」 「ハア……?」 「愛してくれる人を失った絶望、それがルチの原動力なんだよな。だから……誰かに愛されるということが、こわいのかな。まっすぐに目と目を見て話すの、苦手だっただろ? ほんとはさ。損得勘定抜きの、理屈なんかどこかへ投げ捨てたような献身を恐れていた。あるはずないって……自分には絶対に向けられない愛情、なのに他の子供達は当たり前のように享受しているそれが妬ましかった」 遊城十代の指先は、あの聖女とは違って血が通っているはずなのに恐ろしく生気がなかった。死人と生者の境をさまよっている不安定な温度。つめたい。ぬるい。冷えている。血の気が抜けていって……やがて物言わぬ死体になる、その準備をしている手。 「勘違い、しないでほしいのは……俺、べつに、ルチが可哀想だからとか憐れんだからとか……そんなこと、全然思ってないんだよ。あの子がプログラムされていないそれらの感情を認識したがらなかったのとも、少し違う。俺はルチを憐れまない。ただ……誰かがルチを愛してるって……知って……ほしい……」 「……?」 「覚えてるか……? あの子は……最後までお前のことを思ってたんだ。ルチに……しあわせに、なって、ほしい、って、」 「…………《かあさん》?」 ルチアーノが十代の手を握り返すと、彼は嬉しそうに頷いてその美しいまつげを伏せった。口を閉ざしてそのままくたりと転がる。指先の力が抜ける。どんどん、固くなっていくような心地だ。事切れてしまった。最早ただの屍だ。 ヨハンも、遊星も、名もなきファラオもバクラも……絶叫は愚かまともな声ひとつ上げることなく遊城十代の最期を見ていた。そうして閉じられた瞼はもう開かないし、美しく整ったやわらかな唇も二度と開かれない。あの優しくて明るい声はもう聞こえない。 肉の塊を握りしめた鉄の指先に、めきめきと勝手に力が込められていくのを感じて首を横に振る。死んだ。ゾーンの呪いで、遊城十代が、死んだ。 「あ……あぁ…………ああ、もう、くそ、あんたって本当に……ばかなおんなだよねぇ……!!」 ルチアーノを庇って死んだのだ。 「後先考えないで、行動のメリットデメリット一つ試算しない。ばっか、ばか、大馬鹿だよほんっとさあ……! そういうの全部ヨハン・アンデルセンに任せっきりだったって?! ちくしょう……そーしたら、僕はどーやって龍亞と龍可に何を説明すればいいってワケ?! ちょっとは考えろよ!! 僕の……生き残ったやつの苦労を。残されたものの苦しみってやつとかさあ!! 僕は……僕はもう、自分が何をするべきかもわかってないような……」 事実は重たくルチアーノを苛んだが、やはり、水滴一つ彼の頬を伝いはしなかった。泣けるようにプログラムされていなかったことが恨めしく、その一方で密かに安堵している。だってそれなら涙を拭わなくて済む。人でなしと罵られたって、当たり前じゃないか、血も涙もないオイルで動くスクラップなんだから。 なのに無性に胸が痛い。衝くような痛みがルチアーノの身体じゅうを支配して、消えようとしないのだ。 「……母さんが死んだ時から、きっとずっと……探してたのに」 瞳を閉じた。 AIの制御をオートからマニュアルに変更し、プログラムの優先度を組み替えていく。彼女が愛していたラブ・ソングの名前をまだルチアーノは知らない。そうだ、きっと、それを聞かなきゃならなかったのだ。それなら今からでも、訊ねなきゃ。 あの歌の名前を教えて、おかあさん、と。 はじめに闇があり、そして次に光があった。 破滅の光――この世の摂理を司る大いなるモーメントの光の対極に位置する優しい闇を宿して悪魔が愛した男の子はこの世に生まれた。悪魔の力は神に謀反を翻せしめる力。神の定めた理を、唯一同等の神の権限を無視して書き換えることが出来る。 それがユベルの力だ。正確には、ユベルによって解放された優しき闇を統べる者、「覇王」の能力。 覇王のコピーから継承したその能力をありったけ解放した。ゾーンが呪いにその全てを込めたように、願いと奇跡にその全てを賭した。かつてルルイエの聖女がそうしたように、どうしても今、自らの手で選択肢を選び取らねばいけなかったのだ。 右手につまんでいた選択肢は、ついさっき全部棄ててしまった。だから左手に握られたもう片方を全身全霊で――霊魂の宿らぬ機械仕掛けのロボットがそうたとえるのは、腕組みをしてファラオの隣に浮かんでいるネクロマンシーの亡霊なんかからしてみれば滑稽極まりないだろうが、それでも構わなかった――選択する。選び取る。実行する。 不可能をたった一度だけ可能にする。たとえこの身が滅びても。 世界が巻戻っていくのを感じながら薄く目を見開いた。ボディが弾けて金属のパーツが丸見えになっていて、ださいったらありゃしない。身体の感覚がどんどん曖昧に削がれていくのを感じてルチアーノは成功を確信した。自分が滅びるということは……代償をすべて被ったということだ。 「……ルチ?」 「死んでいたはずの」遊城十代が驚愕に目を見開いてルチアーノを見つめてきていた。彼の身体のどこを見回しても、必要以上に穴が空いていることはないし血も不必要に流れたりしていない。もう死んでいない。歴史は書き換わったのだ。 ルチアーノの消滅と引き換えに、遊城十代はこの先も生きていく。ずっと、永遠に、彼がいつか定められた終わりを迎えるその瞬間まで。 「壊れてるのか? でもさっきまで……あれ……? ゾーンの不意打ち、ルチに当たったんだっけ? 俺にじゃなくて?」 「いー……んだよ、それで。歴史は『そういうかたちに』たった今なった。僕が壊れてあんたが生きる。それでいいだろお? きっひひひ……その顔、ケッサクだぜえ?」 歴史は必ず最も正しい、影響の強い結果に寄り添おうとする。ゾーンの強力な呪いは打ち消せないから、遊城十代を生かすには誰かが身代わりにならねばならない。ルチアーノは自らその結末を選び取った。彼の焦がれた《母》が愛した男に殺されることを願ったように。 だから不幸なんかじゃない。憐れまれる覚えもない。けどこの胸を衝いて満たしていくような感情の名前を知らないから、これがどんな気持ちなのかはわからない。 「そんな泣きそーな顔、しちゃって、さ……」 力なく腕がしなだれ落ちた。ネジがぼろぼろになって、加重に耐えられなくなって抜け落ちて転がっていく。露出された内部からはみ出したコードはところどころがかすれて千切れ、火花を出していた。もう長くない。それでも、一瞬で事切れずに言葉を紡ぐ力が残されていたのは……それも一つの執念だったのか。 十代の顔をよく見ようともう一度見上げたが、レンズに入ったひび割れがどんどん広がっていってしまって、上手く映せなかった。代わりに、表皮に落ちてきた生温い液体を感じて「なんだ、やっぱ泣いてるんだ」と理解する。人間がそれを舐め取ったらきっとしょっぱいのだろうが……味覚エンジンなんて高度なものは搭載されていないのでどだい無理な話だった。だって仕方ない。歴史を操作して回るだけのロボットに、そんな機能が必要になるはずなどないじゃないか。 「かあさん、ずっとさ……泣けなかったのに。今はもう、泣けるんだぁ? うらやましー、かも、ね……ちょっとだけ、だけど」 三度にわたって異なる形で「愛」を奪われたアンドロイドが、そんなものは全部棄てたと思っていたのに、今になってそれを欲しがるなんて、製作者のゾーンもモデルになったアポリアも、全然、思っちゃいなかったのだ。 十代の涙を拭ってやろうと思ったのに、一度崩れ落ちた右手は二度と動かせなくて、仕方ないから「ばーか」と心にもないことを言う。十代の涙が滴り続ける。顔面を多う人工皮膚は随分と水を吸って湿り気を帯びていた。まったくどれくらい泣くっていうのだ? アカデミアを卒業した後まで遊城十代が泣き虫だったなんて話は一度も聞いたことがない。どの歴史でもだ。彼は決して血も涙もない悪鬼ではなかったが、彼が望まずとも誰かのヒーローである限り滅多に泣けなかったのだ。 だからもしかしたら、泣きたくても泣けなかったもののために泣いているのかもしれないと思った。 「泣くなよぉ。龍可、みたい。キャハハ……かあさんにもらった力、最初は……龍亞と龍可をブッ潰すために使うのかと、思ってた。こんな終わりだなんて、ねえ? すっごい皮肉じゃん? 僕の思考プログラムじゃわかんないわけだよねえ……?」 「……そっか……歴史を連ねる光を書き換えるために……同じ光じゃなくてユベルの力を使ったんだな。俺が一回死んだっていう歴史を、強引に変えるために」 「どーでもいいじゃん、そんなの。僕は……一足先に《イレイティスの眠る地》に行く。時を司る《アーク・クレイドル》の心臓部……あらゆる全ての歴史が始まり、そして、終わる場所……」 「イレイティス?」 「ここでありどこでもない歴史の墓場。行き方は、あの、平和ボケした不動遊星が知ってる」 囁くと十代が「そんな顔、すんなよ!!」と急に悲しそうに怒鳴った。一体今、自分はどんな顔をしているのだろう? でもそれを知る術がないから、最後に「ねえ」とか細い声で一番大事な願いを打ち明ける。遊城十代に向けて、その奥にいる、《聖女》に向かって。「名前が知りたいんだ」と弱々しく続ける。アイ・レンズはもう殆ど使い物になっていなくて、まともに機能しているのは聴覚だけだった。最早皮膚の感覚さえ模造出来ない。 終わりが近かった。誰よりそれを、一番よく知っている。 「あんたのへったくそな歌が、けっこー、好きだったんだ。最後だしさあ、教えてよ。『オリジナルがヨハン・アンデルセンに教わった』その歌。僕の機能が完全に止まる前に……」 だから希うのだ。 「うたって」 まるで受胎告知を告げる天使のような声で彼は願った。 それが最初で最後の、たった一つのルチアーノの懇願だった。十代はただ黙って首を縦に振り、そのささやかな望みを叶える。声帯から出される声は美しく透き通っていてあの呪いをまきちらすような聖女の声とはあまり似ていなかったけれど、それは確かに彼が望んだものと同じ歌だ。 星が死んで生まれていくように、人間が恋をするように。血も涙も流せない人造アンドロイドが、恋焦がれることが決して無意味などではなかったのだと十代は歌い続ける。 歌は少年アンドロイドの瞼が最後まで閉じられ、もう二度と開くことがなくなるまでやまなかった。ありふれた恋歌はまるで賛美歌にも似て、大聖堂を満たしていく。 腕に抱いた少年アンドロイドの死に顔はどうしようもなく安らかで、十代は知る由もなかったが……彼がかつて見たパラドックスの死に際とよく似ていた。歌を歌い終わったのち、十代は死に絶えたボディを今一度強く抱き締めてまた泣いた。ヨハンも、遊星も、ファラオもバクラもそれを諫めなかった。 ただ少しだけ、切なさを唇の奥で噛みしめた。 ◇◆◇◆◇ 「――あれ? どうしたんだよ、ルチ。そんな、泣いちゃうほどうまかったのか? このピーマン炒め」 そんなに気に入ったんなら、いつでも作ってやるけど。ルチアーノの顔を見てそう苦笑した十代に向かってぶるぶると首を横に振った。泣いてるのは本当のことだけど、別にピーマンの味に感動しすぎてむせび泣いているとかそういうわけじゃない。……はずだ。 ルチアーノが泣いているらしいということを聞きつけて、双子がダイニングルームに引き返してくる。しかし最初はからかう気だった龍亞も、珍しく龍可に叱られる前に茶化せる雰囲気ではないことを感じ取って真面目な顔をしてルチアーノの顔を覗き込んでくるばかりだ。龍可も随分驚いたようで、「何か、あったの?」と訊ねた。 「わっかんない……でもなんか、生まれて初めて泣いたよーな、気がする」 「確かに……そう言えば俺、龍可の泣き顔はめちゃくちゃ見たことあるけどルチアーノの泣き顔は見たことなかった。ってことはこれ、すっごいレアな顔ってこと? あ、携帯部屋に置きっぱなしだ」 「写真なんか撮らなくていいわよ。龍亞は自分が泣いてるところを撮られたいの? 変わった趣味ね」 「ええーっ?! ちょっと龍可、俺やだからね、絶対やめてよ!」 「じゃあそんなこと、ルチアーノにも言うものじゃないわ」 龍可に諫められた龍亞が小声で「ゴメン」とか言ってきたが、正直それどころではなくて、感情を持て余してあふれる涙を腕で拭う。十代がすっかり困ってしまった様子で膝を折り、目線をルチアーノに合わせてきた。生者の潤いを保った相貌がひどく眩しい。 「ピーマンじゃないなら、なんだ? ゴミが目に入った……ってわけじゃなさそうだもんな。……あ、それじゃもしかしてさっきの歌? あれにめちゃくちゃ感動したとか?」 「ちが……あーでも、大体そーかも……。あの歌の名前聞いたら……なんか。僕が知りたかったのってこういうことだったのかもなあ? って…………あー、くそ、今のなし。忘れろよ」 「やだね。なんか今すごいいいこと聞いたことするもん」 にやりと笑い、十代はぐしゃぐしゃにルチアーノの頭を撫でた。ものすごいしたり顔をしていたが、不思議とあまり腹は立たなくて、ぽかんとして見入ってしまう。その中にルチアーノが焦がれて追い求めたものがあったのだ。欲しかったもの、探していたもの、見つからなかったもの。 最初からずっとそこにあったことにようやく今気が付いて……そうだ、それで、こんなに泣いている。 「幸せって、ほんとはすごく簡単で、ありふれて、どこにでもあるんだよなあ。最初は全然わかんないのに、ある日ふと振り向いてそこにあったことに気が付いたりもする。全然急がなくていいんだよ。色んなことをちょっとずつ知っていけばいいんだから」 「ありふれた恋の歌」を口ずさんでいたのと同じ唇で十代が優しく囁いた。それを聞いてまたぼろぼろとひとりでに涙があふれ出てきたが、そうやって心のままに泣けることが何故だかすごく嬉しくて、ちっとも恥ずかしい気がしない。龍亞や龍可も全然馬鹿にしたふうではなくて、むしろ彼らも嬉しそうな表情をしていた。 「愛とか好きだとかってさ」 「うん」 「きっと、全然、ちっとも難しいことないんだよな……きひひ……ばっかみたい……」 涙を拭いながら言うと、それに「そうそう」「そんなもんだよ」とか双子が相槌を打つ。十代が三人を手招きするので距離を詰めると、急に三人まとめて抱き締められた。十代の腕は思いの外広かったけれど、やっぱりこの年頃の子供を三人抱きかかえるには短い。それがちょっとおかしな感じで、わけもなくルチアーノもくすりと笑ってしまう。 「こーんな、簡単なことだったのにねえ」 随分長い間、わかんなかった。そう告白すると、十代はなんでもないように笑って三人の額に順番こにキスをした。 《コッペリアの恋人/END.》 |