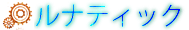棺桶の中に白百合を手向けた。十代自身は、特別この花を好きだと思ったことはなかったが――潔癖で、清廉すぎて、自分に似合わないと思っていたのだ。明日香のような凛とした女性に重ねていた節もあった――少年が望むのはこの花だろうという思いが漠然とあり、またこの場所自体、むせかえるような白百合のにおいに包まれていたのだから、そうすべきであることは自明の理だった。 パイプオルガンのそばに落っこちていた壊れたセキセイインコの剥製は、遊星が直してくれた。「中に、永久発条と楽譜が入ってるんです」彼がジャケットから取り出した予備携行用のキットでインコを直す傍らにぽつぽつと話してくれたことによると、そのインコは、自分の思考に奇妙なほどよく似て設計された構造だということだった。 「だけどこの鳥はやさしい機械ですよ」 遊星の口調は労るようだった。少年アンドロイドが納められた棺桶の隣に座り込む十代の傍らに双子の幻が映り、遊星の視野を掠めてでもどこかへ消えてしまう。あの双子の亡霊はきっと今ここにいる不動遊星が知っている龍亞と龍可ではないのだろう。根拠はないがそういう確信が遊星の中にはあった。遊城十代の腹から生まれ、そして両親に死を看取られた双子の兄妹の、幻影なのだ。 だから遊星は無自覚に、つとめて労るように彼に声を掛けた。 「やさしい機械です。何かを壊すためだとか、傷つけるために造られたわけじゃない。ただ、歌を歌わせたかっただけなのだと……俺は思う」 「そっか。遊星がそう言うのなら、きっとそうなんだろ。だってゾーンは、はじめは本当に遊星の思考をそのまま写し取っただけだったんだもんな」 「……そうですね。俺は、正直言ってあのゾーンという男は吐き気がして認めたくないし、受け入れたくないんですけど。根源にあるものがすごく近いっていうのは、わかったんです。いやでも」 「そうだな。自分の未来の可能性として、極限までねじ曲がった姿を見せられるのは、まあ、嫌だよな」 十代の指先が白百合の花にかけられた。百合を一本つまみあげ、嗅ぎ、そして彼は百合を投げ捨てる。 「だからルチは龍亞のこと、嫌いだったんだろうな」 声はシニカルだったが、顔は泣きっぱなしでぐちゃぐちゃだった。 手持ちぶさたになった手のひらは中央で重ねられ、祈りを捧げるかたちになる。そして目を瞑り、握った祈る手が額につくぐらいに俯き、遊城十代は黙祷を捧げた。あの、祈る神の出来損ないみたいな、ヨハンに恋い焦がれ続けたルチアーノの母親、ユベルと共に遊城十代の中に受け入れられたそれを、祈り続けることで少年アンドロイドの亡骸に落とし込もうとしているのだった。ヨハンがパイプオルガンの椅子に腰掛けて鍵盤に手を置く。パイプオルガンはもうあまり使われていなかったようだが、きちんと調律された音を鳴らしてヨハンの指先に応えた。 「……ヨハンが好きだって言ったやつだったんだ」 「この歌」。ヨハンの演奏が終わる頃になってようやく顔を上げると十代が言った。 ヨハンの弾いた曲は先にルチアーノが死の間際にせがんで十代が歌ったものでもあり、そして聖女が最も好んだ「セキセイインコの剥製が歌う歌」でもあった。ゾーンやルチアーノが追い求めた影はヨハンから端を成し、終わってみた今となってはたった一つの彼らを繋ぐものでさえある。 「昔……裏切られた、と思ったことがあってさ。何度か。俺はみんなを全部守ろうとして必死に戦ったのに、がむしゃらに、何も失いたくなくて、この身をすり減らしてでも戦ったのに、だけど……みんな俺に恨み言を言うんだ。『何故オレたちを犠牲にしてまで』。『友に裏切られ、魂が引き裂かれる痛みだ』。『あなたに裏切られ、葬られる……こんな悲しみを抱くことになるなんて……』。 俺にはその言葉が受け止められなくて……受け入れられなくて……俺はその時、守るため、救うためならこの身を擲ってどんな犠牲を払ってもいいって思ってたのに、みんな俺に冷たい顔をした。俺は……自分が間違ってたのかって聞いたけど……答えは誰もくれなくて……」 「……十代さん?」 「苦しくて苦しくてどうしていいのかわからなくなって、暴れ狂った。じゃあ何も救わなくていいのか、全部見殺しにして、搾取して、屍の上に立てばいいのか、そんな感じ。まあその後友達が助けてくれたんだけどさ。大暴れの俺相手に、そいつもやっぱり必死になって……止めてくれた。そうじゃないって。そしてあいつは……オブライエンは、俺に言ったよ。『ヨハンはまだ生きている』ってね」 十代は目を瞑り、肩を竦めて皮肉げに言った。糸を手繰り寄せるように漏らしたあの異世界での葛藤は、ヨハンでさえ未だ全ては知らない。彼が知っているのは断片的に聞き知ったことだけだし、十代に聞きたいと思ったこともなかった。十代も普段はあまり語りたがらない。けれど、可能性の分岐先としての《聖女》と、母を愛した少年アンドロイドの末期に、思うところがあったのだろう。珍しく十代は自らの過去に饒舌だった。 「そしてヨハンをなんとか見つけて、みんなを元の世界に帰すことが出来て、俺は思ったんだ。俺はずっと子供だったし、そのままでいいと思ってたけど、大人にならなきゃいけないんだって。大人になるから、もう子供のままじゃ……無邪気に疑いも知らず、何でも可能に出来ると無謀に盲信してるだけじゃどうにも出来ないって。無知は何より残虐な罪だ。少なくともあの時の俺にとってはそうだった」 「……だけど守りたいと思う気持ちには、大人だとか子供だとか、そんなものは関係ない。俺がそうであるようにだ。そうだろ、十代?」 「ああ。今、ルチがそうして『母親』を守ろうとしたみたいに。でもな……」 パイプオルガンの椅子から立ち上がったヨハンが、十代の肩に手を置く。かつて異世界で十代は、この手を追い求めたがためにたくさんのものを失った。あらゆる信頼、あらゆる美徳、あらゆる信奉、あらゆる愛。手のひらには孤独しか残らず、何もかもが空っぽで虚しかった。自分以外の何も信じられなくて……いいや、自分さえ信じていなかったのだ。 でも今は、この手を求めてあの時動いて良かったと思う。失ったと思っていたものは別にごっそり損なわれていたわけじゃなくて見えにくくなっていただけだったし、何よりあの時ヨハンをもし諦めていたら、きっと十代は今ここにいない。 「あの子はもしかしたら死に場所を探していたんじゃないかって、俺はすごくそれが……」 けれども、そんな沈鬱な台詞の後に「こわい」という言葉を続けることは出来なかった。十代の独白を遮るものがあったからだ。 『十代。あまり思い詰めるな』 「……ゆ、遊戯さん?」 口を出したのは、腕組みをして事態の成り行きを見守っていた名もなきファラオその人だった。その後ろからバクラが、『王サマにしてはいいこと言うじゃねえか』とこれも珍しく意見の合致を見せている。『きみたちはオレが指導した十代とヨハンじゃあないし、あまり口は出さないようにしていたんだが』と前置きをして、彼は少し強めに言葉を重ねた。 『死者の遺志は生者にはわかるべくもない。彼は思うところがあってきみたちを前へ進ませたんだ。それじゃあ、駄目か?』 『未練たらしく魂だけ留まってるわけでもねえしなあ。ったく、ガキどもがいっちょまえに理屈をこねてるんじゃねえよ。生きとし生ける全ては死に場所を求めて生きてんだ。俺とそこのお偉いファラオ様なんざ、死に損なったっつうのにまーだ探してるんだぜ? なあ?』 『バクラの言い草に同意するのはなんとなく癪だがまあ概ねはそうだ。だから……十代』 「はい」 『もしきみが、あの少年の残した言葉を大切にしたいのならば。さしあたって早急にやるべきは《イレイティスの眠る地》とやらへの行き方を探すことだ。……死者の弔いは長すぎちゃいけない。前へ進めなくなる』 『さっすが、経験者は言うことが違うねえ』 『貴様に言われたくはないな』 最後の掛け合いはお互いに自らを皮肉る調子だった。 彼らがかつて迎えたパートナーの死に際して何を思ったのかを察し、十代はただ頷き、立ち上がる。『祈りはもうじゅうぶんだ』と彼らの眼差しは語っていた。前へ進むことこそ、今生きているものにしか出来ない使命なのだと。 気持ちを切り替える。今やるべきは、前へ進むことだ。 「でも手がかりがあんまりないんだよな。ルチアーノは知ってた……みたいだけど」 「あ……はい。彼が口にしていた《イレイティスの眠る地》っていう単語は、聞いたことがあるんです。未来の……俺自身からのメッセージとして遊戯さんから聞きました。彼はそのためにメッセンジャーとして留まっていたのだと……でもそれだけだ。約束の地……それがどこにあるのかもわからない」 「謎かけみたいだな。チルチルとミチルみたいな結果だと、些か時間がかかりそうだ。でも今は迷ってる場合じゃない……」 しかし現状が手詰まりであることには変わりない。ヒントと言えば、ルチアーノが言っていた台詞ぐらいなのだ。彼は『ここでありどこでもない歴史の墓場。行き方は、あの、平和ボケした不動遊星が知ってる』と口にしていたが、一体どういう意味なのだろう。 どこでもないけど、アーク・クレイドルのどこかにある。隠された部屋、或いは空間ということなのか。ではどうすればその秘密の部屋を見つけることが出来る? ゾーンは死んでしまったし、ブルーノが丁寧に道を開いていてくれたということもないのに…… いや、ある。たった一つだけ、正解に繋がる方法が。 「なあヨハン。俺、思うんだけど。このアーク・クレイドルってゾーンが作ったんだよな? 正史じゃ確かそうだった。それって、どの歴史でも一緒なのかな」 「え? ああ、うん。まあ多分そうだろうな。じゃなきゃ神様が与えたもうたか、だ。俺としちゃ、断然前者を支持するね」 「そっか。なら……そうだな。遊星なら、この答えがわかるはずだ。なあ遊星」 「えっ、俺ですか?!」 突然名指しで呼ばれたことに、不可解な言葉に頭を悩ませている真っ最中だった遊星は酷く困惑した様子だった。しかし十代が「そう。遊星、きみだ」と自信満々に口にするので押し黙る。彼の目は何かを掴んだというふうな色をしていた。それでいて彼は、遊星に賭けを託そうとしているのだ。冗談でも当てずっぽうでもない。 「例えば、遊星がもしも一番大切な秘密をどこかに隠すとして、そのための鍵とかってどこに作ると思う? 玄関か? それとも自室? 或いは宝物をしまっている物置か?」 「え、ええと……」 「それで、鍵を作ったとしてそれをずっと持ってるか、わかりにくい形にしてどこかにそれも隠しておくか……どっちだ?」 「ちょ、ちょっと待ってください。順番に整理したい。まず、鍵は作ります。絶対に。鍵は玄関には仕舞わないし……自室も、候補としては二番落ちする。例えばポッポタイムに仕舞うなら、俺は納戸にします。そして鍵を携行はしません。もし誰かに盗まれたり、意図せず壊してしまったりしたら嫌だから。それにしても十代さん、なんで急にこんな…………あっ」 「そういうこと」 遊星が十代の言わんとすることに気が付いて目を見開いた。十代が人差し指を唇に当て、悪戯っぽく笑む。この笑顔にどれだけのものが狂わされたのか――と少し思ったが遊星にはそう発言する勇気はなかったしそんな必要もない。 ただ、何かを察したヨハンがわかったような顔をして遊星に苦笑して見せたのがやはり癪だった。 「ゾーンは遊星の思考回路で動いてた。そしてこのアーク・クレイドルはゾーンが作ったもので、とするとここの心臓部への鍵を作って隠したのもゾーンのはずだ。今遊星が言った通りにやつが考えたとするなら、『鍵』は必ずこの部屋にある」 「一応聞くけど、なんでこの部屋なんだ? まだどこか、この城の俺達は知らない場所に納戸みたいな場所があるかもしれない」 「それは直感ってやつだな。でもここ、大聖堂、なんだろ? ある意味でゾーンにとっての『心臓部』だったのは、確かじゃないかな。だからほら、たとえばあのパイプオルガンとか……」 「ああ……あのパイプオルガンだったら、中を開けてそこに仕込みますね……」 「らしいぜ。ヨハン、あれ分解出来ないのか」 「俺がやります」 ヨハンに先んじて遊星が答え、そのまま彼はずかずか歩いて行って何のてらいもなくオルガンの解体を始めた。さっきヨハンが座っていた椅子には、座ろうとしない。変なところでまだ意地を張っているのかもしれなかった。 相変わらずポケットの裏から飛び出してくる無数の工具類によって、パイプオルガンは瞬く間にその内部を露見させた。通常の構造らしきものの他に、場違いな金属の部品が掛けられている。箱形のコンソールだ。「かなり厳重にロックされてますね」遊星が検分しながら言った。 「随分用心深いな。……俺がこれだけ厳重にセキュリティを掛けるとするなら、それこそこの世の存亡がかかっているようなものにだけだ」 「まったくもってその通りだからな。慎重にならざるを得なかったんだろうさ」 「セキュリティも、鍵を差し込むとかじゃない。声紋認証と指紋認証、それから虹彩認証……呆れた。こんなに生体認証が必要か? そのくせちゃんと四桁のキーもついているときた」 『必要だったんだろうな。何しろこの世を終わりに連れていける力の大元だ。オレ達みたいな幽霊さえ、全部まとめて。そうだろう』 「ええ。だが……」 遊星の指先を押し当てると、まず指紋認証のロックが解除された。それから虹彩認証。ゾーンは思考回路のみならず、その身の全てを遊星のコピーに自己改造した正真正銘のマッド・サイエンティストだ。それが今、こういう形で道を開く助けになろうとは。 声紋認証で少しもたついたが、ややあって「イレイティスの眠る地へ」と呟くと、それで認証された。未来の遊星からのメッセージそのものがこの答えだった。 残るは四桁のパス・キーだ。こればかりは、何のヒントもない。総当たりをしている場合じゃないし、恐らく三回失敗したあたりでコンソール自体が自壊してしまうだろう。これにはヨハンも十代も押し黙ってしまったが、ややあって、遊星が振り返って訊ねた。 「十代さん。つかぬことをききますが、あなたの誕生日はいつですか」 「へ? 俺の? 八月三十一日だけど」 「ありがとうございます」 「……おい、遊星、まさかおまえ」 「そのまさかですよ」 遊星の長く節くれのない指先が素早くキーを叩き込んだ。「〇八三一」。十代が「おいおい……」と手を振る姿をよそに、最後のプロテクトが解除される。 「……うそだろ」 「俺の誕生日とかじゃ、ないんですよ。ましてやあのゾーンという男が考えるなら絶対にそうだ。勿論父の誕生日でもない。……行きましょう。ここまで来て、今更、立ち止まっていられない。俺は……俺は、」 十代を見つめる遊星の表情は堅く、ひどく強張っていた。でも誰も「大丈夫だよ」だとか、「きっとなんとかなるさ」みたいな無責任な事を口に出来ない。これから起こるかもしれない大事な選択は遊星が決断しなければならないし、手伝いは出来ても、解決はしてやれないかもしれない。 「友達に会いにいかなければならないから」 結ばれた唇もやはり堅かった。パイプオルガンを中心に赤い光が広がり、大聖堂じゅうが包まれる。間もなく視界が焼け付くようなまばゆい光があたりを覆い、彼らが目を開く頃には全てが終わりへと向かい始めていた。 ◇◆◇◆◇ 宇宙だ。行ったことはないし、特段肌に触れる感覚に変わったことは――重力異常とか――なかったが、そこが宇宙だとすぐにわかった。 宇宙と言っても地球の外に広がっているあの広大な銀河系や、その果てとは少し異なった場所なのだ。「あらゆる全ての歴史が始まり、また、終わる場所」。アカシック・レコードや森羅万象、そしてイリアステル……古来から人間が様々な名を付けて探し求めた万物の根源に至る場所。 その宇宙に、彼の姿はあった。二メートルを越す長身ながら相手の警戒心を解きほぐすようなあのどこか間の抜けたやさしい顔を彼はやはりしている。でも、警戒心が解けることは今はもうない。彼の周りの空気はあまりにもぴりぴりと凍り付いて痛ましかったし、おかしな調子だった。 「ブルーノ」 「ゾーンが消えて、ルチアーノも壊れる歴史に至る確率は本当はあまり高くなかったんだ。その後、遊星がすぐに来るような歴史も。数字にしたら、ここまでの流れは〇.〇〇〇〇〇〇〇〇〇三パーセントとか、そのぐらいの低い確率の掛け合わせで成り立ってる。だけど……正史の、遊星がシグナーの仲間達と未来を守る流れとか、十代が異世界から帰還したあとダークネスをどうにかして卒業する流れ、それに武藤遊戯が名もなきファラオの本当の名前を手に入れる流れ……それらすべて、そのぐらいの確率で選ばれた歴史なんだ。そういうの、人間は、こう呼んでる。『奇跡』って」 「奇跡なら奇跡で構わない。なんだっていい。ブルーノ」 「うん。遊星」 「今俺が言えるのは、ここにブルーノがいて、俺はブルーノに会いに来たということだ。……ブルーノ。俺は、おまえを止めたい。理屈とかじゃない。全部壊してやり直すなんて間違ってる」 「うん。『遊星』ならそう言うって、『僕』もわかってる。……でもだめなんだ。もう手遅れなんだ。『僕』が……遊星と一緒にいたい、そのためなら何を犠牲にしたっていいって思って……それが聞き入れられてしまった時には既に、僕は『僕』の手を離れていってしまった」 彼、ブルーノは悲しそうに首を横に振って遊星を拒絶しようとする。背後に立つ巨大な蛇のようなものが激しく威嚇を繰り返した。 オレイカルコスの神だ。その巨躯からブルーノのボディへと伸びる糸が見えるようだった。 「だがそれでも、お前は『ブルーノ』だ。俺の知っている、共に過ごした友だ。そうじゃないのか」 「それは……」 「それが違わないと言うのならば、俺は何度でも、絶対に、諦めない」 遊星がはっきりとした言葉で真摯にブルーノに訴えかけた。ブルーノはそのさまに言葉を失い、うまく返すことも出来なくて、少ししてから振り絞るように「でも、もう、無理だよ。どんなに願ったって!」と小さく呻く。 理屈としては、誰も彼ももうわかっているのだ。純粋な願いは神の如き理に受け入れられ、その力が歴史を変える。歴史を変えた原因はブルーノ=アンチノミーの過ぎた望みだったのかもしれないが、今や彼の力で事象をなかったことにするのは不可能。神の理はブルーノの制御にあったわけじゃない。力は独立した意思として動いていて、そこに人間の都合による善悪のものさしは存在しない。 だけど遊城十代は歴史を変えるためにこの世界へやってきた。ヨハン・アンデルセンも。不動遊星は自分が生きた世界をなかったことにしないためにリスクを背負い、名もなきファラオとバクラは自らが看取った宿主とのあるべきさだめを受けるためにここにいる。 ブルーノの言葉を否定するために遊星は首を強く横に振った。今ここで彼の言葉に迎合するのは自らへの裏切りであり、仲間達への裏切りであり、十代への裏切りであり、そしてブルーノへの裏切りに他ならない。 「願って無駄なら、自分の力で切り拓いてみせる。俺とデュエルだ、ブルーノ!!」 「駄目だ、もうやめて、遊星!!」 けれど遊星の決意を込めた叫び声に覆い被さるようにして、ブルーノの最早哀願に近い叫び声が響き渡り、直後、音と色があたりから消え失せた。 遊星がデュエル・ディスクを構えるのと殆ど同時にオレイカルコスの神がわななき、白い咆吼が遊星達目掛けて繰り出されたのだ。当たったら十代やヨハンでもひとたまりもないような、そういう一撃だった。先にヨハンがゾーンに対して武力であたらなければならなかったのと同じだ。 神に人の言語など通じないのだ。 ヨハンや十代が異能を用いて第一波こそ防いだものの、たった一撃で二人が負ったダメージは甚大だった。遊星を無傷で守った代償に二人は翼を痛め、腕を押さえている。次はない、というのが聞かなくてもわかった。 「だからやめてって言ったのに」 「これがオレイカルコスの神……モーメントの、力だというのか」 「そうだよ、遊星。もう今更、デュエルなんて出来ない。無理なんだ。新しく決めた歴史を――守ろうとしているから、それを変えようとする遊星やみんなに、これは容赦なんかしない!!」 「だが守りたい気持ちは俺も、十代さんも、みんなも同じだ。ここで退くことは出来ない」 「でも!!」 ブルーノの声はますます悲壮さを増していき、沈鬱な気分を助長させた。一歩も退かず彼の願いを聞き入れない遊星なんてものは、ブルーノが願った新しい歴史ではずっとなかったものだ。遊城十代が彼を変えてしまった。確定していたはずの歴史をまた狂わせて、一度壊してやり直さなければならなくなるまでに追い詰めた。 痛みを感じてブルーノは顔を逸らす。遊星の藍色のまなこが、虹彩のないブルーノを捉えて離そうとしないのだ。それを振り払わなければと強く願うと、またオレイカルコスの神が大口を開け、破滅の光が《イレイティスの眠る地》を埋め尽くした。 奔流となってあふれ出したモーメントの光を眺めながら、やってしまった、と彼は思考した。奇妙な虚脱感ばかりが募って一向に達成感なんかわいてこなかったが、これでもう、終わりだ。今度こそ遊城十代やヨハン・アンデルセンは完全に倒れるだろうし、そうしたらもう遊星だって無事じゃ済まない。赤き竜の力が不完全にしか宿っていない遊星なんて、ただの、どこにでもいる、ありふれた男の子でしかない。 せいぜいちょっとした奇跡をデュエル中にもたらすのが関の山で、世界の法則そのものをねじ伏せるような力はもうあの青年の中には存在していない。何も出来ないのだ。無力だ。ここまで辿り着いたことは確かに奇跡だったかもしれない。だけどそれに重ねて次の奇跡を引き起こせる理由は持ち合わせていない。 「……なんで?」 だから本当は、不動遊星はそこで立ち上がっていてはいけないはずだったのだ。 「なんで……立ってるの、遊星……」 ブルーノの声は震えていて、その怯えが伝わったのか、オレイカルコスの神もまた……いいや、そうではない。オレイカルコスの神は今や動きを封じ込められて苦しげにもがいていた。密着していたはずのブルーノと神との間には距離が出来、立ち尽くしている遊星も事の次第におののき、不思議そうに辺りを見回している。 「一体これは……」 薄く膜が張るようにして、ブルーノや遊星達と神を引き離している。同時に、息苦しいまでだったモーメントの気配が薄まっていた。傷を負った十代とヨハンもさっぱりというふうに顔を見合わせて、それから思い出したようにある一点を凝視する。 『何って、結界に決まってんだろ。デュエルが終わるまでは逃がさないぜ』 二人の視線の先にいたのは亡霊だ。彼はしてやったりというふうに腕組みをし、いつの間にか手に持っていたリングを揺らしている。 「何したんだ、これ」 ヨハンが呼吸を整えながら胡散臭いものを見る目で問うと、バクラがなんでもないふうに言った。 『でかい貸しになるが、がらでもねえ人助けをしてやることにしたんだよ。不動遊星はデュエルがしたい――だが、オレイカルコスの蛇が邪魔でそうもいかねえ。ならデュエルが出来るようにすりゃあいい。ま、あんまり幽霊ってヤツを甘く見ないほうがいいぜ……何しろ人間サマの法則を殆ど無視してっからよ』 『いやバクラ、オレが思うに死者や生者といった区切りはこれにあまり関係ないような……というか、十代もヨハンも遊星も何がなんだかまったく追い付いていないみたいだぞ』 『うるせえ空気読めよな王サマ。さて……仕方ないからガキ共のために解説してやるが、千年リングはそもそも呪術儀式の媒介として生み出された呪われしアイテムだ。更にこの『三幻魔』とやらは、破滅の光……要するにヤツに纏わり付いているオレイカルコスだかモーメントだかと同種のエネルギーを受けて生み出されたもんだろ? 俺サマの手にかかりゃぁ、中和させるぐらいは出来る』 そもそもそのあたりは得意分野だしな、と独りごちて彼はリングを胸に当てる仕草を取った。どうやら空間が異常であるために特殊な触媒である千年アイテムには触れられるようになったらしい。 以前にも同様の手法で結界を張ったことがあるバクラならではの所業だった。予測されていなかった事態にブルーノは酷く狼狽し、ディスクを構えようとした中途だった遊星は微妙に情けない体勢のままバクラの方へ困り顔を向けてきている。 『おいおいしゃんとしろよな。この先はなんとかしろ。そこまでのお守りはしないぜ』 「え、いや。……あの。助かった」 『礼なんざどうでもいい』 素直じゃないな、と漏らしたファラオをじろりと睨むとバクラはリングを首から掛け、魂のない虚ろとなったそれをちらりと見た。かつてバクラが表に立つ時、この中には漠良了がいた。でももういない。死んでしまったのだ。バクラに看取られながら…… 『意地を見せてみろ不動遊星。そして証明しろ。お前の生きた歴史を。宿主の……了の生きた世界を』 彼の最後の言葉を、バクラは覚えている。 その言葉をなかったことになどさせてたまるものか。 『さあ――闇のゲームの始まりだ!』 |