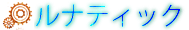聞きたくて聞けなかったことがある。「どうして?」という簡単な疑問。「どうして、××××――なんだ」と、本当に素朴で、簡潔な。 あの時聞けなかったことを、今少しだけ後悔していた。少しだけだ。 だってたくさん後悔して、目の前の出来事をないがしろにしていたら、全てがあっという間に消えてなくなってしまう。 デュエルはいつも楽しい遊びで、また武器だった。不動遊星にとってはずっとそうだ。デュエルに暗い影が落ちたことなんかなかった。あの時までは。遊城十代が空から落っこちてきて、ブルーノが作ろうとしていたやさしい世界が変わり始める時までは。 「《Sp−エンジェル・バトン》を発動! 自分のスピードカウンターが二つ以上ある時、デッキからカードを二枚ドローし、その後手札を一枚墓地へ送る」 あれほど渋っていたのにもかかわらず、バクラが宣告した「闇のゲーム」の開始をブルーノは素直に受けた。「それで遊星が分かってくれるなら」と言ったブルーノの真意が遊星との決別を心から望んでのものだったのか、もしくは全くの真逆なのか……それはこのデュエルの果てで明らかになるだろう。 開始から数ターンが経過し、フィールド上に今立っているのは《エンシェント・フェアリー・ドラゴン》と《ブラック・ローズ・ドラゴン》。先に召喚した《ブラック・フェザー・ドラゴン》及び《レッド・デーモンズ・ドラゴン》は既に墓地へと送られた後だった。相手フィールドには《マシンナーズ・フォートレス》と《TG−ハイパー・ライブラリアン》、それに《TG−ワンダー・マジシャン》の姿がある。D・ホイールの疾走音が大きく鳴り響いて、この荒唐無稽な光景の中、今自分が今サーキットを駆けているのだという現実を押し留めようとしていた。 D・ホイールに跨ってのデュエルになったことや、遊星号やブルーノのD・ホイールがそこにあったことへ対する驚きは流石にもうない。全ての歴史が集約する歴史のゆりかごであり墓場である《イレイティスの眠る地》において、不思議とはむしろ人間の意思の力の方であろう、とヨハンが言ったのも至極尤もだ。イレイティスの眠る地にはあらゆる可能性が眠っている。がしかし、今やその可能性はどれもこれもモーメントという名の神に支配されたもの。その中に人類に真に望まれた未来……人々が自らの意思で立って歩き、進んで行く歴史はない。 手札を繰りながら、遊星の少し後ろをついて走っているブルーノの機体を見遣った。記憶が正しければ、ブルーノは遊星やその他のチームメイトと手合わせをする際は常に【マシンナーズ】デッキを使っていたはずだ。《一族の結束》を積んだシンプルな機械族デッキで、マシンナーズカテゴリのモンスターしか入っていない。切り札は《TGーハルバード・マシンナーズ・ドラゴン》。 でも実のところ遊星はまだ一度もそのエースを見たことがなかったし、遊星以外のチームメイトも皆そうだった。ブルーノが「お守りなんだ。浜辺に流れ着いた時からずっと握りしめてたんだって」と教えてくれた以上のことは誰も知らない。そのカードが一体どんなイラストで描かれていて、どんな能力値を持っているのか。効果モンスターなのか、シンクロモンスターなのか、ノーマルカードなのか……それさえも。 ブルーノは教えてくれなかった。 「ブラック・ローズのレベルを一つ下げ、墓地から《レベル・スティーラー》を特殊召喚する。次いで手札からデブリ・ドラゴンを通常召喚。《デブリ・ドラゴン》の効果で攻撃力五〇〇以下のモンスターを効果を無効にして特殊召喚出来る。《シールド・ウィング》を特殊召喚。レベル一、《レベル・スティーラー》とレベル二、《シールド・ウィング》にレベル四、《デブリ・ドラゴン》をチューニング! 世界の平和を守るため、勇気と力をドッキング! シンクロ召喚! 愛と正義の使者、《パワー・ツール・ドラゴン》!」 「罠オープン。《激流葬》」 「チェーンして罠オープン、《スターライト・ロード》発動。カード二枚以上の破壊効果を無効にし、エクストラデッキから召喚条件を無視して《スターダスト・ドラゴン》を特殊召喚する。集いし願いが新たに輝く星となる。光さす道となれ! シンクロ召喚、飛翔せよ、《スターダスト・ドラゴン》! ……バトルだ。スターダスト・ドラゴンでワンダー・マジシャンを攻撃!」 「《攻撃の無効化》。攻撃を無効とし、更にバトルフェイズを強制終了させる」 「……! 俺はカードを一枚伏せてターン・エンド」 「ごめん。……僕のターンだ」 悉く強力な罠カードで堰き止められて遊星はやむなくターンエンドを宣言する。なんとなく、変な感じがした。ブルーノのデッキが、知っている限りこんなに堅実な汎用カードで固められていた試しなんかないのだ。実際にそれらの容赦ないコンボを喰らった今でもまだ遊星には、奈落の落とし穴だったり、激流葬、神の宣告、そう言ったカード達を使ってくるブルーノの顔が綺麗に思い描けなかった。ちぐはぐしている。 だけど、それって自分勝手で都合のいい思い込みなんじゃないのか? 違和感に自問自答をする。それは「不動遊星の望むブルーノ」であって、「不動遊星に憧れたブルーノ」ではないのでは? 想像を押しつけているだけなんじゃないか。それって……ブルーノが「やさしい世界」を願ったのと、何か、違うのだろうか。 (人間のエゴ……と、あのひとたちなら、多分言うだろうな) しかしであるならば、人の原動力にエゴイズムでないものなど、存在するのだろうか。 ブルーノの足がアクセルを踏み込んで、D・ホイールの速度がまた一段と増した。何か仕掛ける気だ。遊星もアクセルを全開に踏み込んでそれに追随する。フィールドにいるモンスターの数では今は遊星が勝っている。けれど攻撃力の面で言えば突出したものはなく、こんな状況はいつ圧倒的にひっくり返されてしまうのか分かったものじゃない。 スピードカウンターの数をちらりと確かめて、ブルーノを懸命に追いかけた。彼の姿を追うように走るのも、そういえば殆ど初めてのことだったような気がした。 ◇◆◇◆◇ 「引っ掛かってることがあるんだ」 遊星が走り抜けて行くのを見送って十代が呟いた。オレイカルコスの神に負わされた傷は消えてはいないが、結界のおかげで影響が薄れたのか、話が出来る程度には回復している。 D・ホイールがオート制御で走る上で行われるライディング・デュエルは常にデュエリスト達が高速で移動を続けるために、実況がないと肉眼で追うのが難しい。特にライディングに馴染みのないファラオとバクラには試合の様子を追うのがきつかったようで、彼らは自然と、ソリッド・ヴィジョンが出してくれるライフやスピードカウンターの表示を追いながらも異なる話題に興じ始めていた。 「ブルーノと遊星がデュエルをして、その決着が付いたからって……ブルーノはそりゃ止められるかもしれない。けどさ……オレイカルコスの神、歴史を変える力そのものは止められるのか? 本当に?」 『まあ無理だろうな』 「そこで即答するんだ?!」 ヨハンの声にバクラが『耳元で叫ぶんじゃねえよ!』としかめっ面をした。気むずかしい顔をして例の両腕を組んだポーズのまま舌打ちをする。 『理論的に考えて筋が通らねえだろうが』 「じゃ、じゃあなんのためにあんた結界まで張って……」 『弱体化にはなるだろうって踏んだのさ。それにヤツの願いが成就すれば次の願いが通ってリセットされる……かもしれない』 『どちらにせよ遊星の勝利は最低条件、か。……というより、気になっていると言えば、バクラがいやに協力的なのもオレは気に掛かっているんだが……』 ファラオが訝しげにバクラを見遣った。バクラは基本的に自己中心的で、他人に手を貸す時には必ず裏がある。宿主達の高校時代は少なくともそうだった。それ以降何度か、宿主の漠良了に対してはそうと限らない姿も見せていたような気がするが…… するとバクラは腰に手をあて、あっけらかんとこう言い放つ。 『あの野郎こともあろうか宿主の生きた世界を否定しやがった。ただじゃあおけねえだろ。理由なんざ、それで充分さ』 『漠良くんの?』 『オレ様の認識する世界っつうのが、本来存在するはずがなかった可能性だってのは、理解出来なくもない。王サマもオレ様も目的を果たせずにこんな場所にいるんだからな。正しい歴史とやらでは王サマはすっかり成仏してるって言うじゃねえか。……ま、それはいいんだよ。が……それでもこの歴史で宿主が辿った生涯もまた事実だ』 バクラの複雑な横顔に、ファラオはイタリアで漠良了の住まいを訪れた時の彼の様子を想起する。悲しみに心を閉ざしてしまった了の代わりに日々を過ごしていたバクラ。違和感なく馴染んでいた住居。彼はその時もう既に……。 『ねえ、もう一人のボク。ボクはきみに言ったはずだ。ボクは、バクラくんを信じている』。パラドックスとのデュエルの最中で相棒である遊戯が確からしく告げた言葉が耳に焼き付いていた。あの優しい宿主、名もなきファラオのたった一人の相棒は、危なげに見える反面、いつだって人の本当の姿を見ていた。 『不動遊星が戦うのは、同時に自らが生まれ育った歴史の存在を賭けて戦うことでもある。オレ様はそいつに賭けてみてもいいと思ったのさ。どうせもう自分のデッキも持ってきちゃいねえしな』 バクラが首を横に振った。デッキがないというのは、デュエリストにとって剣を持っていない……場合によっては手足さえもがれてないことと同じだ。慌ててヨハンと十代は自分のデッキを確認した。大丈夫だ。揃っている。今遊星が戦っているデュエルに水を差すことは出来ないが…… 「そっか、二人ともデッキ、ないんだ。三幻神とか久しぶりに見たかったのになあ」 『十代、あんまり簡単に言ってくれるな。三体の神のカードは同時に高いリスクも背負っている。相棒の死後は……確か、墓守に一枚、KCに一枚、I2に一枚、それぞれ渡っているはずだ。尤も……彼らのカードの精霊とでも言うべきものは、どうもオレの魂に結びいているようだが……』 『そりゃ当然だ。三枚の神のカードこそが王の証、王の記憶の在処を示す鍵だからな』 「そうなんだ……俺、なんかすごいカードってことしか知らなかった」 『おいおいマジか? そもそも千年アイテムだってただのオカルトグッズじゃあないからな』 「そんなのもっと知らないって。遊戯さん達が活躍してた頃の話、曖昧な噂でしか聞いたことないのに!」 『はぁ……仕方ねえなあ……』 十代の目が「知りたい」と言いたげにバクラをじっと見つめてくるものだから、バクラは途方に暮れてしまって頭を掻いた。しかし言われてみればそうだ。千年アイテムの正確な効果など、はじめ、パズルを解いた武藤遊戯でさえ知らなかった。後世に正しく伝わっているようでは、墓守の名折れですらある。 ソリッド・ヴィジョンの表示を確かめたがデュエルは相変わらず膠着状態のようだった。ターンプレイヤーは遊星だったが、フェイズがメイン2から移り変わってエンドフェイズへ移行しようとしている。 『手短にだけだ。そもそもオレ様や王サマが眠っていたように、千年アイテムは魂を宿す器としても機能出来る。時を超えて古の心を宿すことが出来る墓標……ってワケだ。物や他人、カードに魂を抜き取って宿すことも出来る。こいつはリングや眼、ロッドあたりの専売特許だな。で……千年アイテム自体は王サマの記憶と一緒に大いなる闇を七つに分けて封印している鍵。こいつをコンプリートし、神のカードを揃えることで失われたファラオの記憶を見つけ出す条件が揃う……ハズ、だった。だが王サマが今もこうしてくだを巻いている姿を見りゃわかる通り千年アイテムは七つ揃わなかった。闇の扉も開かれず……憐れ亡霊二人は成仏ならず……さ』 「ああ、ファラオの記憶……って、聞いたことあるな。こっち……正史じゃ、それを遊戯さんがなんとか取り戻して名もなきファラオを冥界へ送り出したって。ファラオの失われた名前が冥界の扉を開けるためのキーワードだったんだ」 『な……十代、それは本当か?!』 「あっ、は、はい! 遊戯さんに昔聞いたんです。その、正史の遊戯さんがファラオと別れてずっと後のことですけど。でも名前は教えて貰えなかった」 『そうか。そうだな……すまない』 十代が独りごちると、ファラオがものすごい剣幕で十代の両肩を掴みあげる。十代はいきなりのことだったので驚いたが、気持ちは理解出来るので、隣から口を挟もうかどうか悩んでいたふうのヨハンに目配せをすると知っていることを答えた。ファラオがみるみるしょんぼりとした顔つきになるが、知らないものは知らないので仕方がない。 『その名前さえわかりゃあ、状況もちょっとばかし違ったかもしんねえなあ。ないものねだりを言っても仕方ないが……そういや、オレイカルコスの神と以前に戦った時はどうしたんだよ』 『デュエルで弱らせた後、こう……三幻神を全て呼び出し、一斉攻撃で撃破して……それでもまだしぶとく怨念で動いていたから……』 『そんで?』 『この星の心の闇を全て受け止めて解決した』 『……ハア?』 バクラがまるでさっぱりだというふうに眉をしかめた。 『というかその時ちゃんとトドメをささねえからこういうことになってんじゃねえのか』 『いや、オレはあの時確かに消したと思ったんだ』 『その時どこかの誰かの願いに呼応して地上に出てきた分がってことか。まあ……今起きてることは今更撤回出来ねえ。今はデュエルの結果を待って……あ? そういや、オレ様も一つ引っ掛かることがあるな……』 サーキットを駆け巡る二台のD・ホイールを見た後思い出したようにバクラが首を捻る。どうした? とファラオが訊ねたが、『大したことじゃないとは思うんだが……』とやはり歯切れの悪い返事が返ってくる。 『ちょっとばかりな……三幻魔だが、ありゃ器の遊戯が言ったことにはイシズ・イシュタールがタウクで視てオレ様に持たせたもんだろ? このガキ共に必要だとか言って……』 『ああ、そうだ。イシズと……マリクも共にいたな。だがイシズが何を視たのか正確には教えて貰えなかった。墓守の秘密だとかなんとか言って……それが一体どうしたというんだ?』 『簡単な疑問だ。実際、この場で三幻魔を必要としたのは別にこの二人じゃなくて不動遊星だった。しかしそれじゃあ、イシズ……タウクが視た未来が外れたことになる……』 『……! 確かにそうだ』 まあ前例がなかったワケじゃねえけどな、とバクラがぼやく。かつて海馬瀬人は青眼の白龍の力でタウクの預言を覆した。しかしそれは、ロッドが海馬に干渉したからだ。千年アイテムは十代にもヨハンにも何の干渉もしていない。 『そいつがどうも引っ掛かるって話さ。そもそもあの墓守の一族が関わってて、これ以上なんの仕掛けもねえってことがあるのか……? つうか………いや、まさか……おい王サマ!!』 『な、なんだ』 『幻魔がオレ様の手に渡った頃、千年アイテムの所在がどうなってたか覚えてるか?! オレ様がリングと眼、王サマがパズル、イシズがタウクで……』 『錠と秤はやはりシャーディーが所持していたはずだ。今どこにあるのかは知らないが……残るロッドはマリクだな。……それがどうしたんだ?』 『そいつだ! マリク・イシュタール!!』 バクラががばりとファラオの両肩を掴み、ぐらぐらと揺らす。ファラオの目が驚愕に見開かれ、肩掛けされた学生服がなびいた。バクラの言わんとすることに気が付きはじめたのだ。 『待て……だが、三幻魔には既に貴様や十代くんたちも触れていたはずだろう』 『ロッドの能力は洗脳と封印だ。それもオレ様のリングよりも更に『抜き取って封印する』方向に特化している。ロッドでならば、オレ様に気付かれないよう偽装することも可能だろうよ』 「や、ちょっと待ってくれ。二人で一体何の話をしてるんだ? 俺も十代も全然ついていけてないんだけど……」 『こういうことだ』 幻魔のカードを右手の指で美しく開き持ってバクラが言った。遊星がデュエルを終えた後、よくやった、お前の意思を無駄にはしない、あとは任せろ――そうやって迎えてやるための活路が、もしかしたら残されているかもしれない。 『三幻魔に封印されているかもしれない魂こそ、イシズの預言そのものじゃあないかってことさ。今のところ、オレ様とガキ共が触っても何も感じ取れなかった。残るは王サマだけだ』 ◇◆◇◆◇ ターンプレイヤーがブルーノに移り、彼がドローをした。スピードカウンターが一つ上がる。アクセルを踏み込んだブルーノを懸命に追いかけ、決して視界から逃したりしてしまわないように遊星は必死だった。今ここで見失ったら、もう二度と、彼の姿は見えなくなってしまうように思えたのだ。 「遊星とデュエルするのが、夢だったんだ」 「……なんだって?」 先のターンまで黙ってデュエルの進行にだけ力を割いていたブルーノが、ふいにぽつりと漏らした。声色は平坦で、表情を伺わせようとして口を開いたわけではないと暗に語っている。 それにしても妙な言い草だ。ブルーノとのデュエルはこれが初めてではない。スタンディングの野良が殆どだったが結構な数をこなしたし、ライディングだって二、三回は交わしたことがあったはずなのに。 そんな遊星の疑問を察してか、ブルーノが「違うよ遊星」と切り返した。 「この世界で……じゃない。もっともっと昔……僕がアンチノミーですらなく、ただの、D・ホイーラーのジョニーだった頃。不動遊星の伝説というのは、それはもうすごかった。幻の初代決闘王にも勝るとも劣らぬ人気ぶりで……彼のデュエルは人々の憧れと希望の体現だったんだ。それは彼が没した後に生まれたジョニーにとっても同じだった。叶うならこの人とデュエルがしたい。この英雄と。友達になりたいなんてそんな傲慢なことは思ってなかった。だって不動遊星は死んでたんだもの。ふつう、死んだ人とは友達にはなれない。デュエルも出来ないけど」 独白だ。それは遊星に向かって語りかけているような体でありながら、彼に向けて話しているつもりはブルーノの中には存在していないのだろう。語り口はドライで、合いの手を欲しているふうでも、ましてや聞き手を求めているふうでもない。その言葉の宛先は誰でも良かったし、誰もいなくても良かったのだ。まるで自分を落ち着けるために話しているみたいで、言葉達はひどく独り善がりだった。 「でも……アンチノミーになって、そこからブルーノになって……僕は過去へ送り込まれて君と出会った。本物の、生きている不動遊星に。絶対に会えないと思っていた憧れの英雄に。彼は僕が思っていたよりもずっとずっとすごい人で、最高のメカニックで、たくさんの仲間に囲まれた幸福なデュエリストだった。メカニック同士ということもあってか、ジャックやクロウが『人と打ち解けるのがそんなに得意じゃない』って言っていたわりに、僕はすんなりと彼に受け入れてもらえた。遊星は優しくて……僕は……僕は……」 「ブルーノ……?」 「本気で心から、不動遊星のことを信じて、心を許してしまった。おかしいよね。その時の僕は既に心のないアンドロイドだったのに」 おかしいよね、と言って笑うブルーノの声音は陰惨で、暗い翳りが落ちていた。自嘲するようでいて、そのくせ助けを求めて嘆くような調子だった。先に見たルチアーノが、自らを心ないアンドロイドと罵ったのともまた違う声音だ。 その時遊星は理解する。 この男は冥土の土産として自己満足のためにこの益体もない話を語って聞かせたのだ。 「おしゃべりは、おしまい。僕は手札から《TG−ギア・ゾンビ》を特殊召喚。このカードは自分フィールド上にTGと名の付いたモンスターが表側表示で存在している時に特殊召喚出来る。この効果で特殊召喚に成功した場合、このカード以外の自分フィールド上に表側表示で存在するTGと名の付いたモンスター一体の攻撃力を一〇〇〇ポイントダウンさせる。僕はハイパー・ライブラリアンを選択。……続いて手札から《TG−ドリル・フィッシュ》を通常召喚。レベル一、《TG−ドリル・フィッシュ》にレベル一チューナーモンスター、《TG−ギア・ゾンビ》をチューニングし、《TG−レシプロ・フライ・ドラゴン》をシンクロ召喚!」 「それが……そんな独り善がりな嘯きがお前の答えなのか、ブルーノ!!」 「レベル二、《TG−レシプロ・フライ・ドラゴン》とレベル五、《TG−ハイパー・ライブラリアン》にレベル五チューナーモンスター、《TG−ワンダー・マジシャン》をチューニング。限界を超えたスピードの先へ! アクセルシンクロ!! これが僕の切り札……僕の望み、僕の願い――現れよ、《TG−ハルバート・マシンナーズ・ドラゴン》!!」 遊星の言葉を振り切ってブルーノが初めて、彼のエースを顕現させる。「そうだよ」とも「ううん、違うんだ」とも言わず、卑怯にも黙することを答えとし、無骨な機械の竜を立てて遊星との対話さえ排しようとする。 一端認識してみると、その姿勢は頑なとさえ言える程なのではないかと思えた。記憶を取り戻し、自らの正体を明かした時からブルーノは遊星と本当の意味で対話を持っていない。常に別のカードを切り、遊星の追求からは逃れ、遊星の言葉をきちんと聞こうとなんかしていない。 もしかして……怖いのか。 不動遊星の言葉に耳を貸すことが? 「ハルバート・マシンナーズ・ドラゴンの効果。このカードの召喚に成功した時、相手フィールド上の全てのモンスターを破壊する。この効果の発動は無効化出来ない」 それで、何かを失ってしまいそうだから? 「君のフィールドはこれでがらあきだ。遊星の残りライフは四〇〇〇……そしてハルバード・マシンナーズ・ドラゴンの攻撃力も四〇〇〇。残念だけど、この攻撃で楽しい時間も終わり。さようなら不動遊星。今度こそ本当にお別れだ」 「……どうだろうな」 「なんだって……?」 それは正しくもあり、また同時に真逆の意味でもある。 ブルーノは遊星の言葉を聞いて「心」を揺すぶられ、再び夢を見てしまうのが怖いのだ。 「お前がずっと隠そうとしていた『心』が、今ようやく垣間見えたんだ。こんなところでデュエルを終わらせたりしないさ。まだ俺はお前に何も伝えられていない。何も話せてない。後悔と心残りばかりだ。こんなざまじゃ仲間達に顔向け出来ない」 「……! 結果はすぐに出るよ。バトルだ! ハルバート・マシンナーズ・ドラゴンで遊星にダイレクトアタック!! このカードが攻撃をする時、相手プレイヤーは罠・魔法カードを発動することが出来ない。その伏せカードがくず鉄のかかしだってことは知ってる。でも無駄だ。これで終わりで……そうじゃなきゃ、いけないから……!」 「そいつはどうかな。俺の策がくず鉄のかかしだけだなんて言った覚えはない。――手札から《速攻のかかし》のモンスター効果発動。このカードを手札から墓地へ捨てることで相手モンスターの攻撃を無効化し、バトルフェイズを終了させる!」 「なんだって……?!」 攻撃態勢を取っていたハルバート・マシンナーズ・ドラゴンの動きがぴたりと止まり、すごすごと自分フィールドに戻っていく。ブルーノの顔はかつてないほどの驚きに塗り込められ、信じられないと言いたげに遊星を凝視していた。「ありえない」というごく小さな呟きが風に乗って流れてくる。「ありえない……こんなこと、あっていいはずないのに……」。 「どうして……今の遊星は、きみは、《シューティング・クェーサー・ドラゴン》どころか《シューティング・スター・ドラゴン》も持ってないんだ。アクセルシンクロさえ出来ない君に勝ち目はない。だからこの攻撃は、防がれていいはずがない……!! このイレイティスの眠る地で!!」 「ああ。そのモンスターのことは、俺は確かに遊戯さんからの又聞きで名前ぐらいしか知らない。そのモンスターがどんな姿なのかを知らないし、勿論持ってもいない。けれど……今ここにいる不動遊星は、『正史の』不動遊星じゃない。そうである必要はない……だからそのカードを追い求める必要はないんだ。俺には既に信じられるものがある」 「ッ……カードを一枚伏せてターンエンド」 「わかった。俺のターンだ」 スタンバイフェイズに入り、スピードカウンターが上がる。カウンターの数は七。ドローするためデッキに掛けた指先に自然と力がこもる。ブルーノは揺らぎ始めている。奇跡を起こすのならば、今だ。今じゃないといけない。今しかないのだ。 右腕が燃え上がる、あのヨハンと相対した時にも感じた熱が宿り始めた完食を覚える。あの時ヨハンは「それを使うべきは俺に対してじゃあない」と言って遊星に赤き竜の力を使う暇を与えてくれなかった。龍亞や龍可も「シグナーの痣としては不完全だから、そんなにたくさんの力は使えないかもしれない」というようなことを言っていたから、きっとこの痣は一回こっきりの奇跡の片道切符なのだ。 「信じてることがあるんだ。ほんの僅か、たったそれだけの事実で俺は前へ進んで行こうと思えるんだって、最近になってまた色々な人に教えられた。アンデルセン博士とのデュエルは……全然楽しいデュエルじゃなかったような気がするが、でも俺にとってとても重要な一戦だったんだと今は素直にそう感じている。……ブルーノ」 デュエルが楽しいだけのものじゃなくなってしまっても、不動遊星にとり、変わらなかったことがいくつかある。 デュエルは人と人を結びつけるものであるということ。そこに己の全てを賭け、託す意味があるということ。そしてデュエルを信じてさえいれば、絶対に不可能なんてないのだということ―― 「シンクロは……俺の絆の形。俺は……絶対に諦めない。仲間達が俺を信じていてくれる。アンデルセン博士が俺の力が必要だと言って、十代さんは、俺をここに連れてきてくれた。遊戯さんも、バクラ……さん、も。そしてブルーノ、お前もだ。俺は一人じゃない。俺の心はいつも仲間達と共にある。わかったんだ。もうずっと、それはきっとどんな世界でも変わることがないんだって――だから!」 祈りにかえて、ありったけの願いを込めて、運命の一枚をドローした。 カードを手にした遊星の右腕に赤き竜の痣が光り輝いた。まぶしく、焼けつくほどに熱く、燃えている。 「俺は、俺の限界を……可能性に掛けられた鎖を破って歴史のくびきをも超えてみせる! 手札から通常魔法、《Sp−シンクロ・パニック》を発動。このカードは自分のスピードカウンターが七つ以上ある時発動できる。このデュエル中にプレイしたシンクロモンスターを可能な限り特殊召喚する。俺が選ぶのは勿論俺と仲間達の五体の竜。この効果で特殊召喚したモンスターの攻撃力はゼロになり、効果は無効化される……更に!」 「ありえない……君は何をするつもりなんだ、遊星!」 「速攻魔法、《Sp−ミラクル・シンクロ・スター》を発動! 自分のスピードカウンター全てを使って効果を発動する。フィールド上にいる全てのモンスターを除外して、エクストラデッキからシンクロモンスター一体をシンクロ召喚扱いとして特殊召喚出来る!! いくぞブルーノ。集いし星が一つになる時! 願いの絆は未来を変える……! 光さす道となれ!!」 遊星の叫びに呼応するように痣はますます赤く燃えあがり、エクストラデッキがまばゆい閃光に包まれた。遊星のエクストラデッキに残されたモンスターは、ジャンクと名の付く機械族のモンスターだけだ。 しかし遊星には今、絶対的な自信があった。この痣が力を与えてくれている。屁理屈をこねて閉じこもってしまった友の心の殻をぶち破るための力を持ったシンクロ・モンスターを呼び出す力がこの指先に宿っている。脳裏に見覚えのない強大なドラゴン・モンスターの姿が鮮明に浮かび上がった。遊星は知っている。このモンスターは《シューティング・スター・ドラゴン》ではない。《シューティング・クェーサー・ドラゴン》でもない。正史の不動遊星が操ったどのドラゴンでもない、この世界の遊星が呼び起こした奇跡の可能性。 「これが俺の願い、俺の絆! 奇跡の光、《コズミック・ブレイザー・ドラゴン》!!」 未だ誰もが姿を見たことのなかったドラゴンが赤き竜の力を受けてこの世に降臨し、存在を証明するかの如くに雄叫びを上げた。《コズミック・ブレイザー・ドラゴン》。かつてはじまりの歴史で、ゾーンが憧れた英雄が操ったエース。正史では現れることのなかった、歴史を動かす奇跡を持つ切り札。 「ブルーノ!! お前の心に、俺の心を全て届ける。思い出してくれ。俺達が共に過ごした時間はどんな歴史でだって本物だ。何一つ嘘なんかない。お前はきっと、それを忘れているだけなんだ」 長い夢を見続けながら、その実一番に夢見ることを恐れていた機械人形に向けて真っ直ぐな思いを向ける。コズミック・ブレイザー・ドラゴンの中に、エースを託してくれた仲間達全ての思いが繋がり、また込められているのだと強く感じて遊星は手応えを確信した。 絆はいつもそこにあり、ずっと、繋がっていくものだ。ブルーノはそれから目を背けている。勝手に「自分にはもうない」と言い聞かせて目を瞑り、すぐ隣にあるものがないのだと泣いている。 「バトル! コズミック・ブレイザー・ドラゴンでハルバート・マシンナーズ・ドラゴンを攻撃!! スターダスト・コズミックバースト!!」 攻撃宣言に躊躇いはなかった。間もなくして目を見張るような星屑の奔流が広大な結界じゅうを埋め尽くして、ビッグバンのように弾け飛んだ。 |