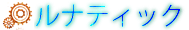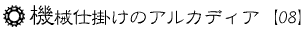「遊星。ねえ、遊星……あなた、これ何度目? いい加減可哀想だわ。あなたのお父さんだって、封も開けずに破り捨てられるために手紙を書いているわけじゃないんだから」 ゴミ箱の中から、丸めてぐしゃぐしゃになった手紙を拾い上げてアキが唇を尖らせた。未開封のその手紙の差出人は遊星の父。父――不動博士はあの手この手を駆使して遊星に手紙を送りつけてくるが、遊星は滅多にその手紙を読まない。大体書いてあることは決まっていて、「大好きなゆーくん、元気にしてますか? 連絡をください。パパは寂しいです。ゆーくんの顔がみたいな。たまにはお家に帰ってきてね、パパはすごく寂しいです。また手紙を送るね」みたいなことが、文脈を微妙に変えたり変えなかったりして書いてあるだけだ。しかも大体の場合、二回は「寂しいです」というアピールが入っている。五回ぐらい書いてあったことさえあった。 今回もきっとそのような内容だろう。遊星はアキの小言を聞き流そうと努めたが、「ねえ。こっちを向いてちょうだい」今日のアキはことのほか強情で、どうも流しきれない。仕方ないのでアキがずいと差し出してきたよれよれの手紙を受け取って開封した。中から、今時珍しい几帳面な手書き文字が連ねられた便せんが出てくる。 『パパの愛しいゆーくんへ。まためっきり連絡が減ってしまって、パパはすごく寂しいです。この前大会に出てたね。優勝おめでとう、パパはすっかり誇らしい気持ちになって同僚や部下に自慢をして回りました。チームメイトの仲間達とは上手くやれているみたいで、パパも一安心。またお家に帰ってきてほしいな。今度はいつ帰ってきますか? ママと今度の誕生日は家族でお祝いしたいなあって話をしたんだ。パパは本当に、寂しいんだよ。この前I2の人に愚痴ったら、すごく共感してくれました。子供が成長するって喜ばしくも寂しいことだね。本当に本当に寂しいけど、大人になるってそういうことなのかな。でもやっぱり寂しいので、今度の日曜、帰ってきてね。アキちゃんのご両親にも話をしておいたので、よろしく。 ゆーくんが大好きな寂しがり屋のパパより』――記録更新だ。六回も書いてある。 「あら、それじゃ次の日曜日は私も一緒ね。お父さんとお母さんがそわそわしてると思ったらそういうことだったの」 「……誕生日までまだ一週間はあったと思うんだが」 「当日はチームの友達と一緒がいいだろうって汲んでくださったんでしょ。それにあなたのお父さん、そんなに暇な人じゃないのだし」 「余計なお世話だ。まったく」 文句を言いつつ、しかしアキが一家で呼ばれている以上無視することも出来なくてカレンダーのところまで歩いて行ってペンを手に持った。日曜日の欄に「アキと実家へ」と書き込み、立ったついでにコーヒーを淹れようと台所へ向かう。アキの分もと気を利かせて彼女のマグを取り出したところで、「手伝うわ」と彼女にマグをひったくられた。 「今日はあなただけ?」 「ジャックはカーリーに引っ張られてどこかへ出掛けた。クロウは朝から配達に出たっきりだ。龍亞と龍可は……今来たな」 「たっだいまー遊星! あれっ、なになに? 今俺達の話してた?」 「遊星、それにアキさんも。あ、お茶、私も手伝うわ。ママがケーキを持たせてくれたの。アップルパイだって」 折良く、ガレージの階段を下って双子がやってくる。一度自宅に寄ったらしく、既に制服を脱いで私服へ着替えた後だった。アップルパイが入った箱を受け取りながら「どう? 調子は」と尋ねると、龍亞が露骨にげっそりとした顔つきになる。 「アキねーちゃん、それ、聞いちゃう? ここで?」 「あらごめんなさい。そんなにひどかったの」 「アキさん気にしないで。いつもいつも変わり映えが見られない龍亞が悪いんだから」 「そういう龍可はどうだったんだ」 「やだ、今日の遊星なんだか感じ悪い。私は普通よ。まあまあ」 小分けする皿を並べながら龍可がじっとりと遊星を見た。アキがくすりと笑って、仕方ないわよ、と遊星に目配せをする。 「この人、お父さんから手紙が来て一度顔を見せに行かなきゃいけなくなったものだから不機嫌なのよ」 「なにそれ。遊星、こどもっぽい」 「ほんと。俺だってそんなことぐらいで不機嫌にならないよ」 「龍亞は、もっと別の所で遊星よりずーっと子供よ。……あら?」 龍亞をたしなめた後、龍可が何かに気が付いてしゃがみ込む。「遊星、何か落ちてるけど」と彼女が拾い上げたのはくしゃくしゃになった紙切れだった。丸め方から見て、先程読んだ手紙の中に同封されていたものだろう。受け取った紙切れはカード状で、裏面に何か走り書きがしてある。 「写真……?」 表へ返すと、何かの式典の後なのだろうか、スーツを着て花束を抱えた知らない男が映り込んでいた。覗き込んできた双子やアキが、視線で「この人は誰? 遊星は知っているの?」と訴えかけてきている。もう一度写真を裏に返して今度は走り書きを読んだ。手紙と同じ、不動博士の筆跡だ。 「『遊星に会わせたい人がいます』」 遊星は思わず空を見上げた。ガレージの天窓は空気を入れ換えるために開け放たれており、よく晴れた青空が顔を覗かせている。 太陽の光がまぶしい。まぶしくて、何故だか、泣きたい気持ちになってきてしまう。 「……遊星、どしたの?」 龍亞が空を仰いだまま止まってしまった遊星の様子を不審がって、不思議そうに尋ねた。遊星は泣きたい気持ちを抑えて視線を戻し、首を横に振る。手の中で写真が握りしめられ、より一層しわくちゃになってしまったが、気に留めなかった。気に留める余裕がなかったのだ。 「何でもない。ただ、空から誰か、落っこちてくる気がして」 「ええ? 空から? そんな、あるわけないじゃん。天使でもないのにさ」 「ああ。気のせいだ。あまり……気にしないでくれ」 コーヒーを淹れる作業に戻ろうとしたところでようやく写真を握りつぶしていることに気が付いて、遊星は息を吐くと写真を広げて台に置いた。写真の中で不器用にカメラに笑いかけているスーツの男が誰なのか、やはり遊星は知らなかったが、何となく彼はエンジニアのような気がした。それもメカニックの方の。 ◇◆◇◆◇ 「いらっしゃい、遊戯くん。わざわざ来てくれてありがとう。えへへ……嬉しいな。友達を家に呼ぶなんて滅多にないから……」 「ううん、こちらこそ呼んでくれてありがとう。イタリアには一度来たいと思ってたんだ。そうしたら丁度十代くんも行きたいっていうから」 お言葉に甘えちゃった。そう言って遊戯は漠良に笑いかけた。彼の後ろには弟子である遊城十代がやや縮こまって様子を伺っている。「彼が漠良了くん。ボクの友達」と紹介され、十代は「は、はじめまして!」とぎこちなく頭を下げた。 「遊城十代、遊戯さんの弟子です。宜しくお願いします!」 「……十代くん、きみ、そんなに人見知りする方だったっけ?」 「だ、だって遊戯さんのご友人ですよ?! 失礼とかないようにって俺ヨハンにもこの前言われたばっかりで」 「いや……きみは変にかしこまるぐらいなら、普通にしていたほうがいいとボク、思うけどね……」 十代と遊戯の遣り取りに漠良も楽しそうに微笑む。「いい子だね」と彼がこぼすと遊戯は「ボクの自慢の弟子だもの」と微笑み返した。 「そっか。それじゃ、上がって。お茶……コーヒーと紅茶、どっちがいいかな」 「ボク、紅茶かなあ」 「あ、俺コーヒー! よければ、手伝います」 「ううん、大丈夫。すぐ出すからリビング少しだけ待ってて」 漠良が先立って進み、後を倣うように廊下を通り抜けた。リビングルームにはテーブルとソファが備えられており、クッションがふたつ載せられていた。コーヒーメーカのそばにあるマグもふたつ。ダイニングに出ているパン皿もふたつ、そういえば通りすがった洗面台の歯ブラシも…… 「漠良くん」 「なあに? 遊戯くん」 「そっか。今日は……この日、だったね」 「……うん」 漠良の足が止まる。振り向いた彼は変わらず優しい瞳をしていたが、どこか寂しげだった。けれどきちんと地に足が付いている。遊戯はそれに安堵して息を吐いた。 「遊戯くんが思った通り。今日でちょうど、バクラがいなくなって十年目」 「……調度品がふたつずつあったから、ちょっと心配になった。でも……大丈夫そうだね。きみはちゃんと、前を向いて生きてる感じがするもの……」 リビングルームの壁には額縁が掛けられていて、それに気が付いた十代がふらふらと引き寄せられては額縁をまじまじと眺めていた。納められているのは数枚のカードだ。《ダーク・ネクロフィア》、《ウィジャ盤》、《ネクロフェイス》……どれも通好みのカードばかりだった。あまり漠良の雰囲気と合わないチョイスで不思議だったが、十代はそれを漠良に尋ねることをせずにおく。既に遊戯が別の問いかけを彼にしていたからだ。 「一個だけ聞いてもいいかな。……ふたつずつものを揃えるのは、どうして? 何か理由があるの?」 「約束したんだ」 「……なんて?」 「それは、遊戯くんにも秘密」 漠良が人差し指を唇に当てて笑う。明るい笑顔だ。遊戯はそれを見て、それ以上の追求を止めた。約束の内容はきっと悪いことじゃないはずだとそれでもうわかったからだ。 ◇◆◇◆◇ 「いや、大変だった。まあ、おかげで色々と面白い体験は出来たと思うけど」 「それは何よりです。私も、あなた方なら大丈夫だろうと思ってはいましたが」 「君ねえ……」 カフェテリアのテラス席に深く座り込むと、ヨハン・アンデルセンは深々と溜息を吐いて目の前の男を見遣った。 雑踏を望むテラス席はほどよく混み合い、様々な人々の他愛ないお喋りが飛び交って会話を人混みの中に消してくれる。それを確かめてからヨハンはコーヒーマグに口を付け、話を切り出した。 「途中から連絡、取れなくなるし。君から最後に聞いた言葉が十代にかまかけすぎるなっていうお小言にならんとした時はどうしようかと悩んだもんだ」 「ああ、あれは私も些か焦りました。しかし歴史が統合された余波で、全ての存在があの次元の私に集約されかかっていたので……」 「まあなんとかなったし、別にいいけど。それに回り道のおかげで十代の新たな魅力を発見出来たからチャラにしておこう」 「おい待てヨハン、それ、どういうことなんだよ?!」 ヨハンの横でずるずるとアップルティーソーダをすすっていた十代がぎょっとしてヨハンに食いつく。顔を真っ赤にしてヨハンに抗議をせんとした十代の様子に、男が「変わりませんね」と曰くありげに微笑んだ。その言葉に十代がぴたりと口を噤み、ヨハンは「君こそ」と大仰に肩を竦めて見せる。 「相変わらずと言えば君の方だろ。何か間違ってるか? ゾーン――いつかどこかで人類最後の一人になった科学者くん?」 「あなたにそうやって揶揄されるのは久方ぶりです」 たっぷりと皮肉を込めて言ってやると、男――不動遊星とまったく異なる顔つきをした科学者が困ったように苦笑した。 「あの時、光の創造神ホルアクティの力で世界は根こそぎリセットされた。暴走していた願いが別のものに書き換えられていた上にホルアクティが発現したのは全ての可能性に連なる深淵の地だ。歪められていた歴史はあるべき姿へと戻り、彼らは最も適した可能性の世界へと戻された。確認出来たわけじゃないが、名もなきファラオと盗賊王は成仏しただろうしあの遊星くんは両親が生きていてかつ誰かが夢見たものじゃない世界へ戻ったことだろう。そして俺達も、あのスクラップの世界へ戻るものだとばかり思ってた。何故かここにいるけど」 「それも、考えてみれば当然のことでは? あの荒廃した世界自体、正史がそのまま時を進んでいれば辿り着き得ない分岐の先ですからね。歪みの影響はその時点で既に甚大だった。本来あなた方が生きるべきはこういった世界だったのですよ」 「まあ……そうかもしれないな。色々覚えてることに関しても、俺達は歴史が書き換わる現場にいたし……半分精霊だから何か作用が違ったのかもしれない。だからそれでいい。ただ俺が気になるのは君でさ」 「ええ」 「君、何で覚えてるんだ? 見たところ遊星君への自己改造手術もしてないのに」 アーク・クレイドルの最深部である《イレイティスの眠る地》で歴史があるべき形に修正され、あの場にいた存在は皆還るべき場所へ還元された。不動遊星は仲間達が待つ先へ。ファラオと盗賊王は召されるべき冥界へ。遊城十代とヨハン・アンデルセンは彼らが守り続けてきた正史へ。そこまではヨハンにも十代にも理解出来る。ここは最早とうに正史の不動遊星も没している遠い未来だったが、歴史を修正するために飛び出して行った二人にとっては最も「現在」に近い座標だ。 しかし疑問が残るのはゾーン……正確には彼はまだゾーンという名ではないはずだが……だ。彼はイレイティスの眠る地にあの時いなかったはずだし、精霊の半身を持っているわけでもない。 「ああ、そのことですか?」 「そう。それ」 「何故でしょうね。私にも実を言うとよくわからないのですよ」 しかし問うてみれば彼はあっけらかんとそんなことを言う。あまりにも軽い調子で「さあ」と返されてしまい、逆に十代とヨハンは面食らってしまった。 「何故っておまえ、いいのかよそんなんで」 「仮説を立てることは可能です。そもそも光の創造神ホルアクティ云々は今聞き知りましたし、私が覚えているのは、歴史を修正すべくあなたがたに協力を頼み支援をしていたところまでで」 「あ、そうなんだ」 「記憶が途中でぶつ切りになっているのは歴史改変に呑まれて消えたからなのでしょうね。そのホルアクティという存在が何をしたのか私の与り知る所ではありませんが……当事者のあなた方がリセットが行われたと感じるのであれば、そうなのでしょう。その過程で、本来正史から分岐するはずではなかった荒廃の未来は消えてしまい、この歴史に統合された」 「……???」 「そして私の存在も正史に統合される。しかし正史ではモーメントの暴走が起きず、科学者も不動遊星になろうと願いません。なので、統合されたはいいもののデータの送り先はこのただの科学者になってしまったのではないかと」 「よ、ヨハン、助けてくれ。俺もう何言われてんのかぜんぜんわかんねえ……」 ぺらぺらと饒舌に喋る科学者の声は未だ若く、不動遊星とはまったく違う低めのテノールだ。アンモナイトのような延命装置に乗っていた時のしわがれ声からは連想出来ない。ヨハンは再び溜息を吐くと助けを求めてきた十代の頭をくしゃりと撫で、一言でざっくりと纏め上げた。 「要するにこれも一種のタイム・パラドクスってやつか」 「過去を変えた結果未来も変わる。ありふれた理屈です。ただ、もし記憶が残っているのが我々だけなのだとすれば……」 「俺達は自分のいるべき世界以外にべらぼうに干渉して回ったからな。光の創造神ホルアクティのやり方は少し強引だったし、カバーしきれなかったんだろう。そういうことにしておこう」 その理屈で言えば、正史の遊星あたりは何か知っていたのかもしれないが、彼は既にこの歴史にはいない。生きているうちに聞けば良かったが、しかし彼が生きている頃の十代やヨハンはそのことを知る由もなくて――考えていくうちに堂々巡りに追い込まれてヨハンでさえ思考がこんがらがってしまい、すぐに考える事をやめた。タイム・パラドクスの結末を知るものは誰もいないのだ。 「なあ……ヨハン」 ヨハンが考え事を止めたタイミングで、十代が突いてくる。「まだ気になることがあるのか?」と聞き返してやると十代はこくりと頷いた。 「あいつ――ブルーノのやつ、どこに帰ったのかなって」 「そりゃ……正史じゃないか? 彼は正史からやって来たんだから」 「うん。でもそうするとさ、あいつの居場所、もう……」 十代が言い淀む。アンドロイド・アンチノミー=ブルーノは正史では不動遊星に破れ、その後ブラック・ホールへ呑まれて消滅したはずだ。アンチノミーとしての部分だけなら、ゾーンのようにこの時代のどこかで生きているジョニーに継承されたのかもしれないが、歴史を狂わせてしまうほどの「ブルーノ」の願いもそこへ辿り着いたのだろうか? どうもそうではないように十代には思えるのだ。「ブルーノ」はアンチノミーでありながら、「アンチノミー」ではない。特にあの時遊星とデュエルをしたブルーノは。そうしたら、彼はどこへ行くのか。ブラック・ホールの向こう? それとも…… 「いいや。きっと問題ない」 それを察し、表情を曇らせ俯いてしまった十代の肩をヨハンは抱いた。「そうかな」と十代は尚も不安そうだ。記憶喪失の間部屋を共にした相手として、相当に感情移入してしまっているらしい。 「そうに決まってる。ブルーノが最後に願ったのは遊星を守ろうとした場所……そうだろ?」 そのまま背を撫でてやると、十代は祈るように「そうだな。きっとそうだ」と呟いた。その様にルルイエで見た少女の面影を思い出す。彼女の思いは、今もまだ十代の心の中に住まっている。ユベルと共に。 ◇◆◇◆◇ 一枚目、ターボ・シンクロン。二枚目、くず鉄のかかし。三枚目、ニトロ・シンクロン。四枚目、シールド・ウィング。そして五枚目、ハイパー・シンクロン。遊星のドローが彼の限界を超え、奇跡を我がものにする。シューティング・スター・ドラゴンの三回連続攻撃が決まってアンチノミーの残りライフ一八〇〇が弾け飛んだ。 (そう……この時を、私は……「僕」はきっと、待っていた……) 遊星の限界を超えた可能性の力を目にすることを、ずっと待っていたのだ。 光さえ抜け出すことが叶わぬ空間に二人して引き摺り込まれ、暗黒に呑まれる。ようやくデュエルの勝敗がついた今、アンチノミーが残れば遊星は先へ進むことが出来る。 「遊星……見せてもらったよ、君の、可能性を……。遊星、この世界を、救ってくれ」 「な……に……」 「この世界を救って、そしてゾーンを救ってやってくれ」 「どういうことだ。お前はこの世界を破滅させるために戦っていたんじゃないのか?」 遊星が困惑を露わにしてアンチノミーを見つめてきていた。当然だろう。アンチノミーはゾーンの友、滅四星の一人。そのアンチノミーにこんなことを請われれば、戸惑うに決まっている。 「僕は君達と過ごした時間の中で、何度となく不可能と思われる壁を打ち破る君の姿を見てきた。そして記憶を取り戻した時、僕は決意したんだ。遊星の可能性を信じようと。……君なら絶対に出来る! 遊星なら、自分の限界を打ち破ることが出来る! だから僕は、新たなデュエルへと導く為にこのデュエルを始めたんだ。……それがデルタ・アクセルだ!!」 しかしアンチノミーの決意は何よりも確かで、固い。不動遊星という男を心の底からいっぺんのくもりもなく信じ抜くことが今の彼には出来ていた。彼の心にもう弱さはなく、恐れもない。「一度間違えた」後だからこそ――全てを彼に託していける。 「遊星。君なら、君自身のデルタ・アクセルを見つけることが出来る」 「お前は……最初からそれを俺に伝えるために……」 「遊星とは、違うかたちで出会いたかった。そうすれば、本当の仲間になれたかもしれない……」 遊星は必ず、彼自身の新しいデルタ・アクセルを見つけ出してゾーンを救うだろう。そして彼は歴史を救う。その場所にブルーノはいないけれど、それでいい。彼のそばにもっといたいと今でも思わないわけじゃない。だが、夢を見るのはもう十分だ。終わりのない、醒めない悪夢など遊星は望まない。彼には似つかわしくない。 だからアンチノミーはまなじりを下げ、悔いるようにそう告げた。遊星の守ろうとした場所を、今度こそ守り抜く。それが彼にとっての唯一の贖罪でもある。 だがそんな彼の耳に届いたのは思いもよらぬ言葉だった。 「アンチノミー……いや、ブルーノ! お前は俺達、チーム・ファイブディーズの……俺の仲間だ! ブルーノ!!」 「……?!」 思わず頭を上げ、目を見開く。そこには遊星の拳が突き出され、その言葉を確かに肯定している。胸中に様々な思いが渦巻き、また去来して、噛みしめるように「仲間」という言葉を口にした。遊星の拳は揺らがなかった。何度確かめても、確かにアンチノミーに向かって伸ばされていた。 「この僕を、仲間だと言ってくれるのか、遊星」 遊星が無言で頷く。過ぎ去った思い出が、走馬燈のように駆け巡った。セキュリティのロックを解除しようとやんちゃをしたこと、チーム太陽のD・ホイールを遊星と修理したこと。チームで走る遊星を応援して、彼の姿を見るのが本当に嬉しかったこと。 「ブルーノ」は、仲間達と戦っている遊星を見ているのが好きだった。その姿に無限の力と可能性を感じていたからだ。それが彼の言葉であふれんばかりにわき上がり、胸を覆い尽くしていく。 D・ホイールの後方部からスパークが飛び散り、クラッシュ音が響いた。速度が落ち、遊星との距離が開き始める。「ブルーノ! 飛び移れ!!早く!!」遊星が叫んだ。だがアンチノミーはその手を取ることを選ばない。 今度こそ、遊星の可能性を最後まで全身全霊で信じ切るために。 「無駄だよ」 「ッ?!」 「言ったはずだ。このコースを抜け出すためには、どちらかが消滅するしかないんだ」 遊星の顔色が、焦りに雲ってゆく。彼にそんな顔をさせてしまうのは本当に忍びない。けれど……それでも、代えられない思いがある。 「君達と過ごした時間は、最高に楽しかったよ」 「……ブルーノ?! 何をする気だ、ブルーノ……」 「遊星! 君は僕の希望だ! アクセル・シンクロは光をも超える! 光を超え、未来を切り拓くんだ!! 行け――遊星!!」 D・ホイールに残された全てのエネルギーを放出し、玉突きの要領で遊星号を思い切り後ろから押し上げた。遊星が何度も名を呼んでいる。だがアクセルを踏み込んだ足は決して緩まず、猛烈にスピードを増して彼を光の向こうへと送り返すために限界を超えていく。 (遊星……) 遊星は振り向いて手を伸ばそうとしたが、彼を押し切った反動でアンチノミーはどんどんと光さえ届かぬ場所へ遠ざかって行った。このままアンチノミーは、素粒子レベルまで破壊されてこの世から消滅するだろう。 「君に出会えて、本当に良かった」 それで構わない。これでブルーノの最後の願いは、叶うのだ。 いつか心を得た人造アンドロイドが、抱いた疑問がある。もしも血の通わない、涙も流せない自分達が電気羊の夢を見たり、星が生まれ人が生きるように恋をして、偽りの造物主が人形達を造ったことでさえ意味を持っていたのだとしたら。 怒りと憎悪を募らせ憐れみの賛歌を紡いだその口で、何かを心から愛することが出来るのだろうか、と。 ブルーノはその答えをもう知っている。彼は本当に母親を愛していた。当たり前の人間のように、愛してくれたひとを、愛した。 ブルーノが不動遊星に焦がれたみたいに。 そうして、友が限界を超え、彼が守ろうとしたものを救う未来を、信じたように。 《ルナティック・END》 《機械仕掛けのアルカディア/END.》 |