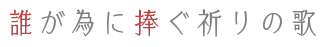
02:この世で最も美しいもの
今日の夢もひどい内容だった。舞台はベッドの上じゃなくて夢ノ咲学院で、季節は多分冬。酷い内容だ。本当に。
これが失われた記憶だというのなら正直同情する。
『おまえのせいだ』
月永レオが、怒りと憎しみに満ちた顔で、泉を睨んでいた。ああ、あの天真爛漫でかわいい男の子が、こんな顔を出来るのかというほど、痛ましく歪んだ表情だった。見てられない。こんなれおくん見たくない。でも、夢の中の泉は、そこから逃げることも出来ず立ち尽くしている。
『おまえが笑ってくれなきゃ、おれはもうだめなのに……!』
怒りは、取り憑いた怨霊のようにばかでかかった。そこでぶちりと画面が落ちる。世界はブラックアウトし、一瞬ノイズが混じり、かと思えばパッと光って次の地獄を映し出す。
『ごめんね、ごめんねセナ』
今度は、レオは地面に頭をこすりつけて延々と謝り続けていた。それを泉は扉に手をかけた状態で為す術なく見ている。ごめんね。ごめんね、ごめんね、ごめんね。謝罪の言葉がノンストップで流れ続けて、ゲシュタルト崩壊してしまいそうだ。
『ごめん……おれのせいだ……ごめんセナ……待ってて、今、すぐ、曲を作るから! できるんだ……できなきゃ、もう、おれには何の価値もないのに。傑作を作れなきゃ、おれは、おれは、セナにさえ見捨てられちゃう……』
なんてみじめな生き物だろう。矮小で、とるにたらない、ゴミみたい。
これがあの光に愛された天才の末路なのかと思うと、虚しくて悔しくて胸がはちきれてしまいそうだった。そんな世界を許せないとさえ思った。泣かないで。俺が仇をとってあげるから。れおくんをこんなふうにした世界を、俺が、俺が必ず、
『だけどあんたに一体何ができたわけ?』
その気持ちを切り裂くように、冷え切った男の声が心臓を撫で回す。
泉は振り返った。そこには夢ノ咲学院の制服を着た瀬名泉が立っていた。彼の手にはどす黒く汚れた心臓が載っていて、弱く、微かに、それでもまだ生きている。
『れおくんが一番辛いときに、あんたは何か、あいつにしてやれた?』
あいつは勝手に生き返るよ、と唇が嘯いた。いつの間にか泉の周囲は無数の唇に囲まれていた。唇たちは一斉に呪いを紡ぐ。勝手に生き返るし、勝手に憎むし、勝手に怒るし。勝手に愛して、勝手に恋して、それから――
『勝手にキスして、勝手にセックスするよ。当たり前でしょ』
唇の輪唱は冷徹に続いていく。
泉はそこで耐えきれなくなって、叫んだ。
助けて!
「――いやっ……!」
自分が出した声の大きさに驚き、泉は跳ね起きた。心臓がばくばく言っている。身体中冷や汗がすごい。パジャマはぐっしょりと濡れ、幽霊にでも遭ったかのよう。
「……セナ? どしたの? ……怖い夢でも見た?」
心臓を抱き抱えてぜえはあと荒い呼吸を繰り返していると、隣で寝ていたレオがまぶたを擦りながら緩慢に寝返りを打った。ああ、起こしてしまった。まだ目覚ましも鳴っていないのに。カーテンの隙間からこぼれる朝焼けの光が、午前五時を示すデジタル時計をかすかに照らしている。
「ごめん、変な声出して……。起こしちゃったよね。でも大丈夫だから、寝てて」
「そんな青い顔して、どこが大丈夫なんだよ……。ほっとけない、おれも一緒に起きる。仕事、昼からだし」
「う……うん」
「シャワー浴びるか。セナ、身体がべたべたしてるの嫌いだもんな」
泉が戸惑っているちに、レオはあっという間に寝台から降り、てきぱきと事を進めていく。泉の手を取り、立てる? と訊ねてきたので、慌てて頷いて飛び降りた。ここで「立てない」と答えようものなら、この男は泉を抱きかかえてでもシャワールームに連れて行く。しかもいわゆる「お姫様だっこ」とかいう体勢で。というか二週間前にやられた。
……意外と力持ちなのだ、この男は。ろくに鍛えてもいないし、紙とペンぐらいしか握ってなさそうなのに、なんでなんだろう。
「セナ、手握って」
「ううん、平気、本当に。これ以上れおくんに迷惑かけるわけにいかない」
隙あらば泉を抱き上げようとする細腕を振り払い、泉はぺたぺたとスリッパの音を立てさせながらシャワールームへ急いだ。放っておいたらたぶん水場の中まで着いて来る。怖い夢を見ただけなのだから、別に身体ぐらい一人で洗えるのに。二十二歳のレオは過保護だ。なんでもやってくれようとするし、なんでも任せてと言う。
……あんなに手が掛かる奴だったのに。すぐ壁とか床に落書きするし、何度言ってもメモ帳一つ持ち歩かないし、TPOとか一切合切度外視して霊感のままに生きてて、社会不適合者まっしぐらだったのに。泉が見ている限り、レオはこの一ヶ月で一度も、壁に楽譜を書こうとしたりしていない。
(確かに、今のあんたになら任せられるのかもしれないけど。だけどそんなことしたら馬鹿になっちゃうよ……)
サニーサイドアップ以外の料理がへたくそとか、掃除が適当で四隅の埃が取れてないとか、キャベツとレタスの見分けがつかないとか、そういうの全部別としても、こんなに甘やかされていたら人間として駄目になってしまうと思う。
優しくされて当然だとつけあがってしまいそうだから。
「贅沢に慣れた豚になるのだけは御免……」
コックを捻ると、すぐにお湯が出てくる。泉がパジャマを脱いでいる間に、レオが給湯器の電源をオンにしておいてくれたのだ。泉はほとほと嫌になってかぶりを振った。頭の中で、先日逆先夏目に言われた言葉が、ぐるぐると渦を巻いている。
シャワーを浴びて居間に出ると、いつもより少し早い朝食の準備が出来ていた。昨日泉が作ったグラタンの残りが小分けに暖められていて、トーストの隣で湯気を上げている。
それらの準備をしたであろうレオはというと、ほかほかの朝食へは目もくれず、ダイニングテーブルから少し離れた場所にあるソファにどかりと座り込んでいた。近づいて覗き込むと、なにやら、紙にペンを走らせている。五線紙。曲を作っているのだ。ちゃんと専用の紙に記入をしていたので、泉はちょっと感動してしまった。
「ふうん、五年も経てば、五線紙常備するようになるんだ……」
「んー、セナがいっぱい買ってくれたから。……っておお、セナ! もう出たの? 今日ちょっと早いな」
「べつに……シャワー浴びるだけならこんなもんでしょ。それよりれおくん、ご飯の準備してくれたんなら食べちゃおうよ」
「待って〜、あと三小節だけ! 宇宙人が教えてくれたメロディがどっか行っちゃう前に書き留めなきゃ。宇宙世紀最大の傑作が失われちゃうから……!」
「ガ*ダムだよそれは」
小声で指摘してやってから、なんとなく負けたような気分になる。レオが上機嫌で「わかるか!? わははっ☆」とか言い出したせいなのだが、認めるのも癪なので黙殺する。
「まったくもう……」
仕方ないので話をずらすことにして、泉はレオの隣にぽすんと腰掛けた。パジャマのままのレオからはちょっとだけ寝汗の匂いがして、不思議と、そばにいると安心してしまう。
「で、今度は何の曲?」
……いけない。なんだか今、よくないことを考えてしまった。邪念を振り払い、気を取り直して訊ねる。
するとレオはうーんと小さく唸り、
「恋の歌」
昨日失恋したばかりの女の子みたいな、耳の奥に引っかかる声で小さく答えた。
泉は瞬きをして、五線譜にペンを走らせるレオの手をじっと見た。
珍しいこともあるものだ。月永レオは愛を歌う曲をしょっちゅう作るけど、恋歌の類はあまり請けない。結果的にラブソングになったものでさえ、歌詞を付けられるまでそうだと知らされず作曲してた、なんて言っていたのを聞いたことがある。確かあれは、十六歳の冬のことだ。
その時「どうして」と聞くと、レオは笑った。「だっておれは恋がよくわからないから」。
「……仕事?」
「いちおう、そういうことになる」
「ふうん……」
だけどこのレオは、ラブソングをそうと知りながら作曲出来るのだ。恋を知っているから。
……誰が歌う曲なんだろう。気のない返事をするふうを装い、楽譜をちらりと盗み見た。アップテンポで、かわいい旋律。ちょっと早いリズム。ポップでキュートな、幸せそうなメロディたち。
ああ、いいな、この歌。歌ってみたいな。まあ、泉のために書いているものじゃないんだろうけど。デモテープの音声入れるぐらいなら、手伝ってやれないことも……。
そんなふうに考え込んでいると、不意に、レオの指先が泉の頬を突く。
「……ちょっと、何?」
「わはは☆ 触りたかっただけ! ……それよりセナ、興味あるならこの曲の歌詞書いてくれよ」
びっくりして顔を上げると、上機嫌のレオがそんな提案をしてくる。泉は一瞬「え」と間抜けな声を出し、それから、楽譜から視線を逸らして首を横へ振った。
「できないよ。恋なんかしたことないのに、ラブソングの歌詞とか」
「ふうん。じゃ、おれにしてみる? そしたら、きっと書けるよ」
「は、はあ!? 馬鹿なこと言わないで。あんた、もう恋人いるでしょ!」
「うん。おれはセナの恋人……♪」
「だから、そういう意味じゃなくって……」
――第一、あんたの恋人は二十二歳の瀬名泉でしょ。
喉まで出かかったその言葉を、だけど泉は、苦虫を噛み潰したような顔で必死に押し戻した。そんなことをいくら言ったって仕方がない。この男にとって、二十二歳の泉と十七歳の泉は同一存在なのだ。地続きで繋がっている。泉の認識と違い、乖離していない。
「……そもそもさあ、れおくん、なんで二十二歳の俺と付き合ってるの?」
「ん〜?」
「その……どこが良かったわけ。自分で言うのもなんだけど、めんどくさいじゃん、俺って。顔以外に取り柄とかないし、あんた俺の顔には、そういう興味なかったでしょ……」
だから泉は、否定する代わりに、恐る恐るそう訊ねた。
思えばこの一ヶ月間、レオが今の泉をどう思っているのか、はっきりと聞いたことはなかった。泉の方が避けていたからだ。泉は否定されることが怖かった。「おれが好きなのは大人になったセナだよ」とか言われてしまったら、立ち直れないような気が、本当はずっとしていた。
だけど……今レオは、はっきり言ったではないか。「じゃあおれに恋をしてみるか」と。「おれはセナの恋人だ」と。
それって、もしかして……。
「セナ、おいで」
泉の胸に淡い期待が芽生える。それを肯定するように、レオが自分の膝の上をぽんぽんと叩いて示した。ここに座れよ、と彼の目が言っている。「あのさ、俺、れおくんより身体大きいけど」と一応言ってみたが、「いいよ、慣れてる」となんでもないふうに返され、泉は抵抗を諦めた。もうどうにでもなれ。
腰を下ろすと、当然のように後ろから抱きすくめられた。身体中をレオのにおいで包まれて、本当にどうにかなりそうだ。
「確かに、おれはセナの顔……ううん、美貌が好きだよ」
泉のくせっ毛を撫でながら、レオが耳元へ吹きかけるように言った。単に体勢の関係でそうなってしまっただけなんだろうなと思っていても、すぐそばでそんな言葉を囁かれるのは、想像していたよりはるかに拷問に近く、泉の心臓を、きりきりと舞い上がらせる。
やめて。これ以上好きだとか言わないで。
やめて……この人は知らない人、あの純真無垢な月永レオとは、別人なのだ。そうでなくちゃいけないのに。
「あと声も。それらはさ、神さまがセナに与えて、そしてセナ自身がずっとずっと磨きあげてきたものだから。おれはそれをね、この世で最も美しい芸術作品だとまで、思ってる。
――けどつきあい始めたのは、そういう理由からじゃないよ」
「じゃ、何なの……」
「セナがおれのこと好きだって言ってくれたから」
「えっ」
「びっくりした。……嬉しかったよ。それでね、おれは考えた。今までおれがどれだけ、セナのくれたものに支えられてきたか。そのことを思うと、おれはもう、セナのことを手放せなくなっちゃった」
懐かしむようにレオがはにかんだ。
一瞬、心臓が、音を止めてしまいそうなぐらいに強く高鳴った。たぶんその音は、レオにも聞こえているだろう。泉は息が上手に吸えなくなり、膝の上に乗せた手を強張らせる。背中に、温もりがへばりついている。
「昔も、今も……セナが隣にいると、息がしやすいんだよな。満ち足りて霊感がいっぱい湧いてきて、無限に曲が作れる。それって全部さ、セナがくれた愛のおかげなんだ。そのことに気付いた時が、おれにとっての恋のはじまり」
だから。セナが愛してくれたからおれはセナに恋したんだよ。
二十二歳の月永レオは臆面もなく、そんないたずらに優しい言葉を言ってのけた。
十七歳の時と同じように、まっすぐな声で。
「――ずるい……」
泉は息を呑み、歯噛みして、身体を縮こまらせた。
レオの答えには一切混じりっけがなくって、「もしかして肉欲が恋人という関係を受け入れさせたんじゃないだろうか」なんてことを疑っていた自分が申し訳なくなるぐらい、ピュアできれいだった。
ああ、この男は、どこまで行っても「こう」なのだ。泉はひとり、そう決めつける。泉の身体なんか最初から求めてなかったんだ。彼は泉の心だけに寄り添っていた。泉は己を恥じた。「この男も俺に抱いた性欲を我慢しているのだろうか」とか考えた事実を抹消したくなった。
「なんでそんなきれいなこと言うの……」
「うん? どしたの、セナ。顔をあげて? きれいなのは、おれじゃなくてセナだろ〜?」
「俺なんかそんないいもんじゃないよ……」
――そっか。あんたは今でも、そんなきれいな感情を、恋と呼ぶんだね。
『わははは☆ おまえ、いいな! 最高だ! 大好きだっ、おまえの顔も、声も、だけどなによりその気高さが……♪』
記憶の中で、十七歳の月永レオが笑っている。今、泉を抱きしめてくれている二十二歳のレオと同じ声で。きっと顔も同じだ。子供みたいに無邪気で、明るくて優しくて、ごみために差した光みたいな面差し……。
十七歳の瀬名泉が守ろうと思っていたものが、まだ、そこで咲いている。
「セナ……?」
泉は俯き顔を背けた。どんな顔をしていればいいのか全然わからない。
――こんなきれいな生き物、尚更、俺みたいな人間が好きになっちゃ駄目じゃん。
『もし月永レオが変わってしまったというのなら、それは月永レオの決断であって、君の関与するところではない。――彼を変えてしまうなんて思い込みは、驕りだよ』
夏目の言葉は本当だったのだ。泉はレオの腕の中に囚われたまま、唇を噛みしめて密かに泣いた。変わってしまったのはきっと泉だけだったんだ。それが悲しくて辛くて、二十二歳の泉は、彼に釣り合いを取ろうとした。せめてまだ汚れていなかった頃の自分に戻ろうとした。きっと、そうに違いない。
「だけど無意味だよ……俺の恋はどうしたって穢れてるんだから……」
そのことを思うほどに、何故だか、例の不思議な歌が脳裏を過ぎるのだった。主よ召しませ、祈りの歌を。主よ赦したまえ、憐れみたまえ。ああどうか赦してください、この醜い恋心を、俺じゃこのひとに釣り合わないの、相応しくないの!
だから神さまに赦してと願い続けている。
あの歌はきっとそういう意味なのだ。
歌詞を付けたやつはひどい皮肉屋だと思った。
◇◆◇◆◇
早起きした割に朝食を摂るのが遅れてしまったせいで、仕事が出来るコンディションになるまで、いくらかの時間を必要とした。その日の予定が、嵐とのモデル仕事だけだったのは不幸中の幸いだった。あんな気持ちになったばかりでレオと一緒に仕事が出来る自信はなく、その日ばかりは、「じゃあおれ別の場所で収録あるから、あとはナルによろしく」と消えて行ったレオの後ろ姿にほっと安心したものだ。
「泉ちゃん、今日すっごく緊張してたわねぇ。王さまと何かあった?」
撮影が終わり、スタジオの廊下を歩く途中、嵐が泉の顔を覗き込んでくる。泉はわざとらしく大きく息を吐くと、肩をすくめて首を横へ振った。
「あったよ、あったけど、だから何……」
「やだぁ! 喧嘩? 喧嘩はよくないわよォ?」
「言葉と表情が一致してないんだけど、なるくん。楽しそうに聞かないで、チョ〜うざぁい」
「あら、ごめんなさい。でもねえ? 恋なんて感情のぶつかり合いだし。王さまは泉ちゃんが大好きだけど、ちょっと不器用なところがあるでしょ……」
「……。今朝のは、れおくんが悪いわけじゃないし。俺が一方的に辛かっただけ。この話はここでおしまい」
「ちょっとお、泉ちゃんったら適当に誤魔化すんだから――あらっ?」
雑にあしらわれて唇を尖らせた嵐の小言が、急に途中で止まる。何かあったのだろうか。気付けば、嵐は嬉しそうにぱたぱたと手を振って、廊下の向こうへ駆けて行ってしまっていた。泉が「何?」と訊ねる暇もない。
「みかちゃん! みかちゃんじゃない! お久しぶりね、元気にしてたかしら♪」
そして曲がり角に到達するや否や、嵐は、そこを通りがかった黒髪の青年にぴょんと飛びついた。
「んあ、なるちゃんやん! おひさし〜……☆」
飛びつかれた方の青年も、どうやら嵐の知り合いのようだった。彼は急に出てきた嵐に嫌そうな声一つ出さず、親しげに応対している。泉はゆっくりと彼らの方に歩み寄り、目を凝らす。
……どこかで、見たことがあるような顔だ。でも思い出せない。向こうも泉に声を掛けてこないので、泉とはあんまり接点がない人間なのかもしれないが……。ああでも、やっぱりどこかで見たことはある。どこだっけ。確か、そうだ、あれは……
「Valkyrie……?」
半信半疑でその名を口にするのと同時に、別の男の声が、泉の思考を遮った。
「――瀬名? 瀬名じゃないか。相変わらず君は美しいね……!」
ああ、この声は、聞き覚えがある。泉はふいと面を上げた。そこにはやはり見知った顔がある。
「げっ、斎宮。じゃあやっぱりValkyrieで合ってるのか」
「げっ、とはなんだ、げっ、とは。汚い言葉を使っては、君の美しい魂が穢れてしまう。改めたまえよ」
斎宮宗――Valkyrieの首魁にして泉の元クラスメート――が、何故かものすごく嬉しそうな顔をして泉の顔を覗き込んで来ていた。その姿を認め、泉は大きく溜め息を吐く。
宗のことは嫌いではないが、今はそれ以上に引っかかるものがあって気が重い。なにせ、ただでさえ頭の中はレオのことでいっぱいなのだ。そうほいほい「五奇人」に出てこられても、脳の処理が間に合わない。
勘弁してくれ。
立ち話では何だからと誘われて無碍に断ることも出来ず、気がつけば、泉は宗と向かい合ってカフェテリアの隅に腰を下ろしていた。同じ店の少し離れた席には、嵐と影片みかが座っている。
「影片は彼のことを大層好いているようで、すまないね」
聞いてもいないのに、宗がまめまめしく教えてくれる。昔から、そういえば宗は泉に親切だった。顔以外ろくに取り柄のない、プライドばかり高い泉を、煙たがらずむしろ積極的に構ってくれる、数少ない人間でもあった。
「べつに……いいよ。なるくんも、友達に会えて嬉しいでしょ」
「だろうね。僕も瀬名に会えてとても嬉しい。影片が彼に構っている間、我々は我々で語らっていようではないか。……個人的に、君の様子が気に掛かっていたしね。いい機会なのだよ」
「俺に? 何でまた」
「月永がやらかした――と、風の噂で聞いている。奴がやらかして君という芸術品が軋んでしまったら一大事だ。世界の損失がまたひとつ増えてしまう。あと、普通に君の美しい顔が見たかったというのも理由ではある」
「……あんた、本当臆面もなく俺の顔を褒めるよねえ。いいけど。綺麗って言われて悪い気はしないしさ」
泉は小さく息を吐くと、紅茶のカップをテーブルに戻した。レオに「きれい」とか言われるのは心臓に悪いが、宗の「綺麗」という言葉は逆に落ち着く。彼のそういった言葉には絵画を褒める趣以上の意味がないことを知っているせいかもしれない。それに斎宮宗には裏表がないのだ。だから接しやすい。
「ところで斎宮、れおくんがやらかしたって……どんな噂になってるの。週刊誌に変な記事すっぱ抜かれたりしたら嫌なんだけどぉ」
「ああ、心配するな。僕の言い方がよろしくなかったな。噂になっていると言っても、『五奇人』の間でのみの話だよ。逆先が珍しく占った相手の心配をしていると思ったら、瀬名、君の話だったものだから。僕などはつい、気になってしまってね」
世間話のように聞けば、宗の方も気軽にそれに答えてくれる。泉はふうんと小首を傾げ、宗の言葉を咀嚼した。五奇人の間で噂になるってどんな状況だ。
「いや、それ逆に怖いんだけど。クラスメートだった斎宮はともかく、あんたたちみたいな天才が俺を気に掛ける理由とかないでしょ」
「どうかな。月永の剣たる君の実力には、我々は常に一目置いていたよ」
生半な生き物ではあれの相手は務まらんよ、と宗が呟く。泉は露骨に顔をしかめた。本当に勘弁してくれ。どこまでレオとセット扱いされているのだ自分は。
(どんなふうに思われていたことやら……)
相棒とか、剣とか、そういうのならまだいいのだけれど。零とか渉とかは平気で「女房役」なんて言い出しそうなので業腹である。実際二十二歳のレオと泉は付き合っているはずなので、それが嘘にならないであろうことも腹が立つ。
一気に気分がくさしてくる。ふとそこで、泉は悪戯を思いついた。そこで場当たり的に、意趣返しのようなことを訊ねる。
「……ねえ、斎宮。あんた今、好きな子とか、いるの」
効果は、泉が想定していた百倍ぐらい、てきめんだった。
「――ッ!? い、いきなり何を言い出すのかね君はッ!!」
「いいから。……いるの、いないの」
「い、い……いい、いる、と言えばいるし、いないといえば、いないのだよッ。瀬名ッ、本当になんなのだね……?」
泉の方が驚いてしまうぐらい大仰に慌てふためき、宗が派手に取り乱す。あまりの動揺ぶりに、泉は非常にいたたまれない気分になった。
「別に……愛とか恋とか、斎宮なら真面目に答えてくれるかなと思って。聞いてみたんだけど」
それでお為ごかしのようにそう続ける。すると今度は、すぐに生真面目な顔になって、「ああ、そういうことかね」と宗が呟く。
斎宮宗は、改めて泉の方を見つめ直すと、こほんと咳払いをし、
「君、今月永と暮らしているのだっけ」
それから突然、そんなことを泉に訊ねた。
「え……そうだけど。って、どんだけ五奇人に筒抜けなの、うちの事情」
「ふん。僕が知っているのは、それと、あとは君が記憶喪失らしいという話だけだ」
「いや、十分すぎるぐらい明け透けだよどうなってるの」
「ノン! 遮るんじゃあないよ、瀬名。……僕もね、正直、今までは半信半疑だったのだ。君の仕事ぶりは、変わらず輝きを放っていたからね……しかし今ので逆先めの戯言を信じる気になったのだよ」
「……なんで?」
「以前君は、僕にまったく同じ質問をしたことがある。君は基本的に合理主義者だ、同じ轍は二度踏まない。となれば君は過去の質問自体を忘却しているのだ」
そうだろう、瀬名。宗が断定的に問いかける。泉はそれに何も答えなかった。藪蛇を突いてしまったような気がしてきたが、今更、手遅れだった。やめてくれと言ったって宗は止まらないし、泉には、彼の言葉を聞く義務があるように思う。
「あれは、半年ほど前のことだったかな……」
泉が黙っていると、宗が再び唇を開いた。そこから流れる水のように、十七歳の泉が知らない、未来の話が始まった。
「その日君は、僕にこう訊ねた。『恋とは醜いものだろうか』と。僕にはその正確な答えはわかりかねた。僕は『愛』を尊ぶ……愛は至高の芸術品に類別されるもののひとつだ。しかし『恋』は、剥き出しのままでは爆弾と変わらない。芸術品に仕立て上げ、翻案してやる必要がある。なので僕はこう助言した……」
泉は食い入るように宗の話へ耳を傾けた。宗の指先がそっと空を撫でる。その所作にぞっとして、何も無い場所を凝視してしまう。
身体中から、どっと冷や汗が吹き出ていく。拒否反応だ。忘却した記憶に触れる事を、本能が拒んでいる。悪寒が酷く、耳を塞いでしまいたくなったけど、それは宗という芸術家に対して最も失礼な態度だ。そんな抵抗は赦されない。
「――『瀬名、君は詩を書くだろう。そしてそれを歌う。その儀式を通せば、君の恋心とやらはきっと昇華される』」
だから泉は、まるで冷や水を浴びせられるように、真っ正面から毒をかぶらねばならなかった。
ひっ、と、喉が引き攣れる。そんな話は覚えていない、だって半年前の記憶なんかないのだから、けれど、その内容には、思い当たる節がある。
……最悪だ。
「……なくしたはずの記憶の中で、ひとつだけ、今も覚えてるものがあるの……」
気がつけば、唇は勝手に、そのことを宗に話していた。
「歌、なんだけど。歌詞もメロディも暗記してるのに、何の歌なのか全然わからなくて。……でも、今の話を聞いたら、急に……分かっちゃった。たぶん、その歌、俺が歌詞を書いたやつなんだ。きっとその、半年前に俺が書いた詩なんだよ」
「――歌詞の内容を訊いても?」
「神さまに、赦しを請う歌……」
震える唇が、あの不思議な歌詞を紡ぎ上げる。「主よ、召しませ、祈りの歌を。命、言祝ぎ、生誕の歌を。あなたの愛を讃えましょう。あなたの夢を偲びましょう。どうして力は、優しいあなたを苛むのだろう。私の心は、地に墜ちる。罪深き罪人の調べ……」。
それこそ神さまに赦しをねだるように、泉は一つずつ詩を並べていった。それが最後まで済むと、斎宮宗はどこまでも優しく微笑み、泉の手を取る。
「美しい詩だね」
彼が言った。芸術家のまっすぐな賛美だ。泉は絶望的な心地になった。
「美しい詩だ。瀬名、君と同じぐらいに。間違いはあるまい、君の作詞だろう」
「……斎宮がそう言うんじゃ、そうなんだろうね……」
「ああ。そしてこれも間違いはない。君の恋は、この詩になることで確かに昇華されたのだろうよ」
「……そんなことない。そんなことあってたまるか……」
最低、最低だ。泉は頭を抱えた。こんなこと、気がつきたくなかった。出来損ないの賛美歌が、もっと出来損ないのラブソングだったかもしれないなんて、そんなこと。
二十二歳の瀬名泉がどんな気持ちを持っていたかなんて、知りたくない。
「あいつ、れおくんの事を汚れた目で見てたくせに」
――恐らくは。
二十二歳の瀬名泉は、自分の恋心が酷く醜いものだと自覚的だったのだ。ちゃんと知っていた。だからそれを、せめて美しい詩へ変えようと足掻いた。
この言葉たちを唯一の清いものとして、気持ちを封印しようとした。この詩はそうして生まれた。そうに違いない、そうであってほしい、でなければこの詩の存在自体、無意味になってしまうから。
「なのにどうしてれおくんは俺の恋人なんか名乗ってるの……!」
そして二十二歳のレオが見せる態度が、結局、泉の努力を無為に帰す。
ほとほと嫌気が差した。天才ってやつは、どうしてどいつもこいつも、みんなわけがわからないのだ。
「斎宮」
泉はひりついた喉をそれでも叱咤し、やっとの思いで宗の名前をひりだした。
「なんだね、瀬名」
「俺はね、多分、ずっと、れおくんに大人になってほしくなかったんだよ。ううん、純粋で無知でかわいい、赤ん坊でいてほしかったの」
「……そうか」
「こんな詩まで作って、神さまにお祈りしてたんだ。なのに……なのに……あいつ、勝手に、大人、に、なっちゃって」
「うん」
「今のあいつはね、自分のこと、俺の恋人だって言うの、恋してるって。だけどそんなのってあんまりだよ……」
好きになっちゃいけないのに、大好きだよって言ってくれるの、きっと好きの気持ちを棄て去るために俺は記憶まで棄てたのに。
泉が呻く。宗は辛そうに眉根を潜め、彼の肩を撫でた。肩は小刻みに震えて怯えていた。プライドの高さが辛うじて泉を支えている状態で、ここが外でなければきっと泉は泣き出していた。
「君は本当に美しいね、瀬名」
「全然……俺なんてぐちゃぐちゃの泥沼だよ。こんなに醜い恋心を抱えて、詩にしても浄化しきれなくて、その重圧に耐えかねて記憶を手放した、弱い人間……」
「いいや。その事実を認められる君だからこそ、僕は、誇り高き君の白百合に似た美を尊ぼう。君は美しい。墓場で愛を抱きしめている今も、変わらず」
「……そっか。ふ、ふふ。……あ〜あ。なーにが、『おれにしてみる?』だ。あのバカ殿」
好きになっちゃだめ。好きになっちゃだめ。恋を知ってもきれいなままだったあの子を、今度こそ本当に汚してしまうから。俺はれおくんの恋人にはなれない。十七歳の瀬名泉は潔癖症で、臆病者で、大人が大嫌い。二十二歳の泉と違って、月永レオの恋人になることを許せない。
「れおくんのバカ。ば〜か」
その日十七歳の瀬名泉は、二十二歳の瀬名泉を呪った。
今朝方見た悪夢に出てきた汚れた心臓を思い出し、死にたい気持ちになった。あの微かに鳴動する、どす黒い心臓。あれは泉の心臓だ。
ボロボロになるまですり切れて汚泥に塗れて、一度は殺そうとして、それでもまだ虫の息で動いている、二十二歳の瀬名泉が抱いていた恋心。
「それでも……」
きっとあいつは、みじめな心臓のことなんか何にも知らないんだ。それで自由に愛を歌い、恋を知ったとはにかみ、勝手にキスして勝手にセックスして、勝手に大人になって。昔より生ぬるくなった指先でレオのことを抱きしめて、おまえの恋人だよと笑っている。
「それでもれおくんのそばにいたいの……」
一体何を信じたらいいんだろう。
泉は自嘲気味に笑った。いくら賛美歌を歌ったって、救われるところがどこにもない。神さまの国は死んでしまった。誰が作ったのかもわからない曲に乗せられた歪な恋詩は、ただ残酷なだけの現実を泉の前に突きつけていた。