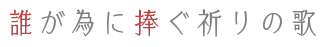
03:臆病者の歌
たぶん、あんな話を斎宮としたせいだと思うんだけど。
その日泉は、レオへうたを贈る夢を見た。
『――見つけた! れおくん、電話ぐらい出て? おかげで学院中探しまわっちゃったでしょ』
『んんん? ……おおっ、本当だ、着歴がナイアガラの滝みたいになってる。すまん! 携帯鳴ってるの、気付かなかった!』
『はあ、まあ、そんなとこだろうと思ったけど……』
夢ノ咲学院の制服を着た泉が、手のひらに何か紙束を握り締め、中庭でレオが陣取っている場所へ駆けてくる。『頼まれてた曲に歌詞つけといたから』、と泉は息を切らしながら教えてあげた。『何に使うのか知らないけど、ラブソングの歌詞なんて初めて書いたんだから。感謝してよね』。
『うんうん、おまえは最高だっ、愛してるぞ〜セナ!』
『あんた本当、すぐ愛してるって言うよねえ。狼少年って知ってる? 安売りしてると、ここ一番で信用してもらえなくなるよ』
『わは、耳が痛い。でもしょうがない! おれはすぐみんなのことが愛おしくなっちゃうから。……ま、だから恋歌とか、ちょっと苦手分野なわけだが……この歌詞がついてれば、さまになるよ。ありがとな』
泉から受け取った紙束に書かれた言葉をざっと流し見て、レオが呟く。身を焦がす恋をつづったラブソングの歌詞に満足げに頷いて、『セ〜ナッ』レオは泉へ急に抱きついた。
『ちょ、ちょっとお、何するのあんた!』
あまりのことに驚き、泉が体勢を崩す。そのまま中庭へ仰向けに倒れてしまい、あれよという間に、泉の上にレオが覆い被さるような体勢になってしまう。
これじゃまるで、押し倒されてるみたい。そのことに一人で動揺して、顔を真っ赤にして。そんな泉の心なんかきっと知りもせず、レオがにこにこ笑顔で訊ねてくる。
『ねえセナ、セナに聞きたいことあるんだけど!』
『な、なに!? 早くして!』
『この前セナが鼻歌で歌ってたメロディ、もらってもいい?』
こんな感じのやつ、とレオが鼻歌でそのメロディを教えてくれた。そのメロディに泉は心当たりがなかった。たぶん、本当に何気なく適当に歌っていたのだろう……曲でさえない旋律。だけどレオの手に掛かると途端に優れた芸術作品のように聞こえてくるのだから、不思議なものである。
『〜ッ、勝手にすればあ!?』
泉はレオの女の子みたいにかわいい顔から目を逸らして、つんけんした態度で、そう言い棄てた。
玲瓏で凛としたきれいなメロディだねだなんて、口が裂けても言ってやるもんかと思った。
れおくんの曲になるのが嬉しいだなんて、なおのこと、死んでも言うもんかと思った。
『……歌詞付けるときは言いなよ。きれいな歌にしてあげるから……』
その代わりに、小声でそう言ってあげる。それはとても、組み敷かれながら頬を赤らめて囁くような内容じゃなかったけど。でも仕方がない。その時ふたりは、それ以上の言葉を持っていなかったのだ。
まだ友愛が恋慕になる前の、昔の夢だから。
◇◆◇◆◇
凛月がパーソナリティを務めているラジオ番組には週替わりでゲストが入る。その今週の当番が、泉。それで今、ラジオ局の控え室に来ている。
そこまではいい。
「やっほ〜じゃよ、瀬名くん☆」
でもこいつはよくない。なんでいるんだ、こんなところに。
「なんなの、あんたたち。揃いも揃って暇人の集団か、五奇人」
泉は信じられないものを見るように目の前の真っ黒い何かを凝視した。実際信じたくないのだが。あの五奇人がひとりにして闇夜を統べる魔王、朔間零が、何故か今泉の向かいに座っているだなんて。
「セッちゃん、ごめんねえ……俺もやだって言ったの、兄者がいると毎秒俺のストレス値が上昇してくし。でもコイツマジで聞かなくてさあ、厚かましさ選手権優勝かって感じで、阻止出来なかったんだよね……」
「そうそう、我輩ちいとばかし面の皮が厚くてのう。なので凛月のことは責めんでおくれ? どうしても瀬名くんとなかよししたかったんじゃ♪」
「くまくん、翻訳して」
「『ちょっかい出したくて野次馬に来ました』」
「直球に最低で来たねえ!?」
どかりと控え室の椅子に座り込み、いかにも「キレてます」という態度を隠さず相対する。それを見て零が「瀬名くんは最高じゃの〜☆」とか笑うので、もう泉は何もかもが面倒くさくなり、朔間零という存在について考える事を止めた。
と同時に、遅まきに違和感が襲い来る。なんだ、「じゃが」とか。じゃがいもか。
「っていうか、朔間、あんたそんなキャラだっけ? もっとオラついてなかった、確か。隠居老人みたいになってるけど……」
「おおう、一周回って新鮮じゃな、その反応。我輩随分前に、まさに隠居を決めたのじゃ。そうかそうか、今の瀬名くんは本当に十七歳以降の記憶とかないんじゃな」
「くまくん、この野次馬どうにかなんないわけえ?」
「あっひどいのじゃ、同窓生がいじめる! 我輩たち、かつては『零ちゃんチーム』として共にかわいさを高めあった仲じゃろ〜!?」
いや、そんなこと言われても本当に知らないんだけども。
まったくめげる様子のない零の態度にいよいよ泉は思考を放棄し、「用があるなら手短に済ませて」と肩をすくめて見せる。ついでに、「用がないならもう出てって」と付け足すと、朔間零はすうと目を細めて老獪に笑んだ。悪魔か魔物のする顔だ。
「ま、話というのは他でもない、月永くんとのことなんじゃが。どうじゃ? ちかごろは。なんぞ悩んでおるとかいう話じゃけども」
「うわ、マジでうざぁい……あんた地獄耳だの楽屋雀だの、しょっちゅう言われてるんじゃないの」
「ふはは、もう慣れた。おじいちゃんじゃもの、多少の罵倒で乱されたりはせんよ」
本当に微塵も堪えた様子のない表情で、零が嘯く。「濃縮還元一〇〇%トマト」とプリントされた缶ジュースを手慰みにし、「そうじゃのう」なんてもったいぶって呟いている。
「いうて我輩、月永くんとはびっくりするほど接点とかないんじゃけどな! 斎宮くんとかに比べると、な〜んも知らんというほど知らんし。じゃが、状況はおおまかに聞き知っておる。おぬしらに掛けられた
魔王はニコニコと微笑み、泉の方へむけてぴんと人差し指を伸ばしてみせた。
「は? 呪い?」
泉はブラックの缶コーヒーを両手でしっかり握り締めたまま固まった。この科学技術が発達した現代で「呪い」とか、突拍子もないにもほどがある。
「うむ。悪い魔法使いさんから情報の横流しがあってのう、君の過去と未来を繋ぐ、うつくしくも物悲しい呪いの歌がある……と聞いておるよ」
「誰だよ、悪い魔法使い……。あんたたち兄弟はちょっとファンタジーの世界に生きすぎ。ここ、現代日本なんだけど」
「人々が神秘を忘れつつあるこの土地でも、信仰と因習がある限り、海神も吸血鬼も魔法使いも……消えてはなくならん。魔法と呪いは実在する。我ら五奇人もそうして葬られたのじゃ。人の意志というものは斯くも恐ろしい」
「……。まあ、確かにあの歌詞を書いたのが、いつかの俺なんだとしたら。殆ど呪いみたいな歌詞だとは思うけどぉ……」
「そうそう、言霊の概念じゃな。しかし呪わしきは詩のみに非ず、と我輩思うておる。……なのでちょっとここで歌ってはくれんか? 旋律が知りたい」
手のひらを広げ、零がそう要求する。わざわざ凛月のあとをついてきたのはそのためだ、と念まで押して。
「ええ……なんでこんなとこで」
「よいから。直に聴かねば真贋もわからぬでな」
あんまり気乗りがしなくて食い下がるが、零の声色は強く、有無を言わせぬ調子があった。思わず気圧されてしまい、息を飲む。泉はやや躊躇い、それから、少し離れたところで事の成り行きを見守っている凛月にちらりと目をやった。凛月はすぐに、眼差しで泉の心に答える。「いいよ」。「余計な流布はさせない。王さまに誓って」。
……仕方ない。大きく息を吸い込み、泉は、密やかに恋を懺悔する歌を歌唱した。
「――主よ召しませ、祈りの歌を――」
アカペラで、小さく密やかに、しかしぴんと気持ちを張り詰めて。この歌につけられた歌詞には複雑な気持ちを抱いていたが、メロディライン自体は綺麗で好きだし、歌うとすっと気持ちが晴れやかになっていく。
一番の歌詞を歌い終わる頃には、もう意識が歌う行為に飲み込まれていて、殆ど、トランスしたように唇を動かしていた。泉は透き通った声で、透き通った気持ちのまま、その旋律を奏でた。
「――主よ赦したまえ、憐れみたまえ、愛しい人への子守歌……」
最後まで歌い終わり、唇を閉ざす。ほどなくして、ぱちぱちと、朔間零は手放しで拍手をした。彼は泉の目を見吸えたままゆるりと微笑む。
「いい歌じゃ。はりつめてもの悲しくて、ゆえに透き通り……誰もがはっとして、振り返る。まさに君の如し歌じゃな」
「……ああそう、どうも……」
「うむ。故に呪われている。痛ましいほど、愛に焦がれてな……。
――時に、瀬名くん」
「なに」
「君、その曲を書いたのが誰かは知っておるのか?」
相変わらずニコニコ笑ったまま、零が訊ねた。泉は口を噤む。言われてみれば、知らない。それに今まで一度も、そんなことを考えてはみなかった。
「……わかんない」
素直に答えると、零が得心したように頷く。
「やはりのう。しかも、ただ判然としないだけではなく、見当もつかない。そうじゃろ?」
「言い方は腹立つけど、そう。多分……れおくんの曲ではない、と思うんだけど……あいつの手癖っぽい旋律が殆どないもん。百パーセントあいつが書いた曲なら、俺が分からないはずない」
「ちなみにそれ、月永くん本人には確かめたのかえ?」
「きいてないけど、あいつの前で何度も歌ってるのに何にも言われたことないし、違うんじゃない」
言い切ってから妙に自信がなくなってきて、歯切れの悪い言葉だけが後に残った。でも多分……多分、違うはずだ。泉はこれまで、レオの曲を山ほど聴いてきた。それこそ、ヴィジュアル系ロックバンドに依頼されたサウンドから、ティーンの少女アイドルたちが歌うかわいらしいJ-POP、小学校の校歌、果てはゴスペルまで、あらゆるジャンルで作曲されたレオの曲を聴いている。
レオは究極のノンジャンル作家で、それこそなんでも頼まれれば書いた。だけどそれでも、なんでも出来る天才ゆえに、癖のようなものが強く出がちな面もあって、泉はその癖を頼りに彼の歌を判別していたのだ。
だけどこの歌には、彼らしい癖のある旋律は、見つからない。主旋律からしてもう違う……。
「ではまず、それを本人に問いただしてみることじゃな」
辿々しくそう述べると、朔間零は強めの声でそう提案する。泉は顔を顰めた。泉を誘導したいというのが見え透いていてどうもいい感じはしないし、あの朔間零ともあろう男が、ほぼ縁もゆかりもない泉にそうまでして気を掛ける理由がわからないのだ。
「……朔間、あんた何が狙いなの?」
「おや、不安がらせてしまったかのう? あんまし、警戒せんとくれ。くたびれた老人は、ハッピー・エンドの蒐集が大の好物なんじゃ。…………かつて共に机を並べた友が破滅していくのを黙って見ているのは、性に合わんのでな」
「いや、俺別にあんたと同じクラスになったことないけど……」
「月永くんとな。三年生の頃、同じクラスだったんじゃよ」
「……れおくんと?」
「そうじゃ。じゃから我輩は、厚顔無恥にも月永くんの友人を名乗ろう。そして友であるからには心配させておくれ。代償に何を支払わされるのかを考えもえせず、悪い魔法使いさんに願い事をしてしまったあの子の」
まあ、実際のところは、考えなかったというよりその余裕がなかったというのが本当じゃろうな。零が淡々と語る。Knightsのメンバーは誰も彼も、クールを気取って直情径行だから。
うるさい、と言ってやろうかと思ったけれどぐっと堪えた。事実にいくら反論しても虚しいだけだ。実際、レオは何度も彼の思うままに行動して泉を振り回してきたのだから。
……でも、近頃の……大人になったレオは、そういうのが随分なりを潜めていたように思うのだけれど。
もしかして泉の勘違いだったのだろうか? それにしたって……。
「で? 代償って……なんなわけ」
「さあて、それは我輩の口から語るようなものではない。我輩が老婆心を余らせて語ることは、あと一つ。瀬名くん、君は真実を追い求めるがよい。欠損した記憶の意味を、まだ呪いが解けるうちに決めておこうぞ。記憶を取り戻すか否かに関わらず――君は本当の事に向き合うべきじゃな」
呪い。また、お伽話のような言葉。
泉は砂を噛むような心地で零の話を聞いていた。真実? 真実ってなんだよ。泉が十七歳から先の五年間で育てあげたであろう、醜い恋心のことか? それとも、月永レオがどのようにして大人の階段を昇っていったのか、その詳細か?
確かなのは、どちらとも知りたくないということだ。そんなものがなくても生きていけると、泉は思い込みたかった。この一ヶ月間そうやって暮らしてきた。だから泉は何も知らない。朔間零の言葉は、そういうことだ。
「本当のことなんて、知ったらそのぶんだけ不幸になるだけかもしれないじゃん」
「知らぬが仏とかいう言葉は、一時しのぎのお為ごかしじゃよ。……では、ここまで言った方がよいのかのう。『その曲を書いたのは月永くんじゃ』、恐らくはな。あの子は君に隠し事をしておる。君のことを想って、いくつかの嘘を吐いておる。……君と過ごした五年の月日は、月永くんにとっても大きな価値を持つものじゃ。時は人を変える。子供を大人にしてしまう。シンデレラの魔法も、いつかは解ける」
放っておけば、あの子は永遠に本当のことを話しはしないだろう、と零が言った。月永レオは決して秘密主義なわけではないが、自己完結が過ぎる故に多くを語らない。稀に語ろうとしても感情の出力が上手く出来ない。論理は万人に理解されない。泉はなるべく彼のことを理解したいと願っているけれど、事実としては、すれ違いと齟齬ばかりが残されがちだ。十七歳の時からずっと。
だから話をするべきだ。優しい嘘にばかり守られていては、事態は何も進展せず、ゆるやかに全身へ毒が回るだけ。なるほど、零の言葉は、一理ぐらいはある。確かに……この一ヶ月、泉はレオとちゃんと向き合ってこなかった。そのつけを支払うのがあとになればなるほど、しっぺ返しは甚大だろう。
意外にこの吸血鬼、有益なことを言うものだなあ。
だからそんなことさえ思ったのだけれど、一分と経たないうちにその感心は露と消えてしまうことになった。
「じゃから瀬名くん、月永くんとデートとかしておくとよいぞ、今のうちに」
「…………。…………はあ?」
泉はあんぐりと口を開けて、急にわけのわからないことを言い始めた例
零を胡乱な眼差しで見た。
「何? もう一回言わんとわからん? じゃから〜、瀬名くん、月永くんとデートするとよいぞ♪ 遊園地とかどうじゃろ? 吊り橋効果で本当のことが見えてくるかもしれんしの!」
「はあ〜〜〜!?」
――ああ、一瞬でも見直した自分がバカだった。
後ろで、凛月が面白半分、懺悔半分の複雑な表情で黙りこくっている。「ちょっとくまくん!」泉は藁をも掴むような気持ちで叫んだ。凛月は少し咽せ込み、面を上げると、「いいんじゃない、面白そうだから……」と目を逸らしがちに答える。
「う、裏切ったなこの!!」
泉は叫んだ。四面楚歌だ。この控え室には泉の敵しかいない。
……いや、デートしたくないかと聞かれたら、まあ正直、したいんだけど!
◇◆◇◆◇
「――って、マジで全然何の意味もないんだけどぉ!!」
そんなわけで泉は、夜の遊園地でそんな嘆き声をあげている。隣で手を握ってくれていたレオが、「どうした、セナ!?」と急に顔を覗き込んできて、泉は勢いよく咽せ込んだ。レオの顔が視界いっぱいに映り込んでいて心臓に悪い。
「なあセナ〜、ほんとにどしたの? ……あっ! もしかしてお腹痛いとか!?」
「いや、違う違う。ただ今更ながらに、無責任な吸血鬼に怒ってただけ……」
「吸血鬼〜? リッツのこと?」
「その兄貴の方」
「あ〜、レイかあ〜。……おまえ、レイと知り合いだったっけ?」
「全然」
あんな言いたいだけ言い放題してさっさと消えたはた迷惑な男と知り合い認定を受けたくない。泉がぎろりと睨むようにして否定すると、さしものレオもその必死さを感じ取ったのだろう、それ以上は何も言わなくなった。
ラジオの収録をなんとかかんとか終え、局まで迎えに来てくれたレオと合流したあと。泉は、ものはためしでレオを遊園地に誘った。デートしたいから、みたいなことは別に言わなかった。ただ遊園地に行きたいと話すと、レオはその場でスケジュールを確認して、「いいよ、今から行こう」と泉の手を引いた。
……よく考えたら、この男が自分のスケジュールをちゃんと自分自身で把握しているのってものすごい進歩だ。やっぱり彼は大人になってしまったんだろうなあ。頭にキャラクターもののカチューシャを付けてばかでかいバスケットからポップコーンを食べている姿を見ると、あんまりそう感じられないけど。でも大人になった。それは決して、悪いことだけではないのだ。
(真実、ねえ……)
零の忠告をなんとなく頭に思い浮かべては、はしゃいでいるレオの横顔を何度もちらちらと盗み見た。レオは昔から楽しいことが大好きだから、遊園地とか、わりと好きなタイプだ。なにせ遊園地のコンセプトには争い事がほとんどない。レオにぴったりなのだ。生き馬の目を抜く芸能界によく適応出来たなと感心するぐらい、十七歳の泉が知っているレオは、人を傷つけたり誰かを蹴落とすのが苦手で、世界中誰も彼もが幸せになることを願っている、夢想家だった。
「な〜セナ、あのチュロスうまそう。食べる? あ、返事してくれなくてもいいよっ、食べたいかどうかおれが考えて買ってくる……☆」
「アップルハニージンジャーのホットがいい」
「ああっ!? 妄想の隙もない! でも的確に教えてもらえると、まちがいがないから助かるな」
ぴょこぴょこと売店へ寄っていき、チュロスとホットドリンクを一つずつ注文する。程なくして手渡されたそれを分配し、ふたりで吸い寄せられるように、大観覧車の待機列に収まった。楽しそうにいただきますをしてレオがチュロスをかじる。すぐに「うん、うまい」と笑顔のお墨付きがくだる。それから、レオがチュロスを泉に差し出してくる。
「はい、セナもひとくち、どうぞ」
「……それ、砂糖の塊の揚げ菓子でしょ」
「でもうまいぞ。食べて?」
「……うん」
そう屈託のない笑顔で押し切られると、何も断れない。泉は口を控えめにあけて、レオの持つチュロスにかぶりついた。ブラウンシュガーの甘ったるい味。確かにおいしい。美容の大敵だけど、食べた分絞らないといけなくなったけど、でも、悪くはない。
「わはっ、間接キス〜なんちゃって」
「ええ……」
「あっセナ、口のまわりに砂糖ついてる」
「そう? 拭うから紙ナプキンちょうだい……って、ちょっと!」
チュロスと一緒に渡されたナプキンをねだるより早く、レオの舌がぺろりと泉の頬を舐めた。唇のほど近くを。「間接キス」なんて嘯いたその唇で。
「な、なに……?」
脳味噌がフリーズする。思考がおぼつかない。顔があつい。前がまともに見えなくなる。
「口のまわりの砂糖、全部とれたよ」
「そ、それだけ?」
「え? なに? キスしてほしかった?」
間接キスじゃ物足りない? とレオが訊ねてくる。泉は実に困り果てた顔でレオの顔を見上げた。ちがうの、という言葉が、うまく唇から出ていかない。するとレオが、何を思ったのか「ああ、ごめんな?」と小首を傾げて泉の腰を抱く。
「本当のキスはしないよ。……セナ、そういうの嫌だろ」
囁くレオの目は笑っていなかった。ああ、この言葉は本気のそれだ。恋人を名乗るのにキスもしない。記憶があるうちはセックスだってしていたはずなのに。
不意に、零との会話が脳裏に蘇った。曰く、月永レオは嘘をついていて。それは泉を想ってのことなんだという。嘘ってなんだろう。やっぱり、泉に「記憶が戻らなくていいよ」と言ってくれた、あのことか。廃教会でそれを教えてくれた時、繋いだ指先は震えていた。
そこでちょうど観覧車にのる順番がやってきて、考えごとを抱えたまま、狭い密室に押し込められる。二人がけが二席の構造になっているゴンドラの片側に並んで乗って、そのまま、出発した。泉が手を差し出すとレオは何も聞かずに握り締めてくれた。手のひらの温度は生ぬるくて、今日もやっぱり、震えている。
「――♪」
ゴンドラが少しずつ天へ上っていくその最中で、泉は唐突にあの歌を歌い始めた。
レオの目が、ちょっとびっくりしたふうに開かれる。そのまま数度のまばたき。努めて気にしないことにして歌を続行する。歌い進むほど、レオの手のひらは、ぎゅうと強く泉の手を握り込んだ。ああ、魂ごと離しちゃうと思ってるのかな。そんなふうに考えると少しおかしい。ワルキューレの歌でもあるまいに。ではさながらこれはニーベルンゲンの歌か? いや、それなら、ユニット名からして斎宮の専売特許ではなかろうか……。
考えごとをしながら歌を歌い終わる頃には、ゴンドラはもうてっぺんのほど近くに上り詰めていた。
「……セナ、ここが好きだったこと覚えてたの?」
顔を合わせると、レオがきょとんとして唇を開いた。泉はううんと首を横へ振った。
「ぜんぜん? なに、思い出でも、あったの」
「二十歳の時、ふたりで乗ったんだ。Knightsのみんなで遊園地に来ててさ……ゴンドラは四人までしか乗れないから、ふたりと三人で別れて。その時セナ、なんだかすごく嬉しそうだった」
「……そっか。でも全部覚えてないよ」
繋いだ手のひらがひくりと動く。泉は深呼吸をしてレオに顔を近づけた。鼻と鼻がくっついてしまいそうなぐらい近くて、当然レオの顔が視界いっぱいに映っていて、心臓が大運動会を繰り広げている。でもこのぐらい近くなくちゃだめだと思った。本当のことを知ろうと思ったら、近寄っていかなきゃ。
「ねえ、れおくん。あの賛美歌みたいな曲、あんたが作ったの?」
そのことを訊ねた瞬間、観覧車の動きが、がたんと止まった。
次いで、ぱっとゴンドラ内のあかりが消える。窓から見える地上はぎらぎらとネオンサインが渦巻いているのに、世界から取り残されたように、あたりが真っ暗闇になる。こんなに近くにいるのにレオの顔がよく見えない。皮膚の感覚だけが鋭敏に研ぎ澄まされ、泉にレオの鼓動を伝えてくる。
「……うん。そうだよ」
心臓の音が、少しだけ早くなった。
「あの曲、ぜんぜんどこにもあんたの手癖なんかないのに?」
「ん。だってあれ――セナの鼻歌が元だから。めちゃめちゃにアレンジしてあるけど、主旋律の元がセナだから。あんまりおれっぽくないんだとしたら、理由はそれかな……」
どくり、どくり、どくり。レオの鼓動はずっと早まっていって、最後に、泉の鼓動と同じ速度になって違いがわからなくなった。手も、お互いに震えているせいで、レオが震えているのか泉が震えているのか、もう判別がつかない。
「あの歌詞、俺が書いたんだよ、多分」
「うん、知ってる。おれが楽譜あげたら、つけてくれた」
「……いつ頃?」
「セナの二十二歳の誕生日」
この前の十一月に、とレオが言った。
しばらくの間、二人は暗闇の中でじっと押し黙った。何も喋らなくても、心臓の音はばかみたいにうるさかった。月永レオはうそつきだ。零の言葉と、廃教会で自分が抱いた気持ちが重なり合う。だけどどうしてだろう、この心臓の音を、かんたんに嘘だと言って糾弾したくはない。
(あ〜あ……)
この前の十一月、だって。ついこの間のことではないか。斎宮の話によれば、詩自体は、その前から作ろうと思っていたみたいだから……ちょうどよかったのだろう。
(ここが暗闇の中でよかった……)
泉は今この瞬間、お互いに顔がよく見えないことを神さまに感謝した。出来損ないのラブソングで、神さまにずっと赦しを請うていた、その見返りが少しぐらいはもらえたのではないかと思った。こんな恥ずかしい表情をれおくんに見られたくない。きっと今自分は、初夜を迎えた少女と同じように頬を染め、だけど苦虫を噛み潰して、眉を下げているのだ。
(結局、また好きになっちゃった)
泉がいつかあげたメロディで、レオが曲を作って。その曲に泉が歌詞をつけた。歌詞には泉の恋心がありったけぶち込まれている。手を繋ぎたい、一緒にいたい、キスしてほしい、セックスしたい、そういうのを全部入れて、きれいな歌にして、封殺して。
プラトニックのまま無理矢理交わったみたい。あんなに恋しちゃだめとか穢しちゃうとか言いながら、毎日、ハードポルノみたいな歌を歌っていたのだ。逆に笑える。
(本当、なんでこの歌だけ覚えてたのかわかんないけど……こんな曲歌ってて好きになっちゃだめとか、自分で言ってたことだけど何言ってんのって感じ。本当に呪われてるじゃん。無理でしょ。絶対無理。あ〜、もう、さいあく)
繋いだ指先の神経がぐずぐずに溶けて、消えてなくなってしまいそうだった。息づかいが近い。こんなに近くにいるのに、気持ちだけ、どこまで行っても平行線。
(――ねえ、れおくん。俺のこと今でも本当に好き? あんたのこと信じていいの? 俺の心は十七歳のままだけど。それでも好きって、この前の言葉は適当なんかじゃないよって、言ってくれる……?)
ねえキスしてもいいよ、という言葉は、だけどどうしても口から出て行ってくれなかった。これからふたりで家に帰って、同じベッドで眠るのに、自分たちはその間いちどもキスをしないだろうなという確信が心の中で生まれていく。月永レオの嘘を暴くのが怖い。彼の愛が恐ろしい。この前書いていたラブソングのこともまだ胸に引っ掛かっている。
ねえ、それならさ、いっそのこと告白してしまった方が、楽になれるのかな。失敗しても成功しても、どっちでも……。
そう思って唇を開きかけたところで、ぐらり、とゴンドラが揺れる。
「あ。電気ついた」
途端に、消えていたあかりがぱっと戻って、オペレーターのアナウンスが鳴り響いた。マシントラブルで停止していましたが、ただいま復旧しました。お客様には大変ご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。このあとも引き続き、素敵な時間をお過ごしください――。
「ん? セナ、どしたの? 今なんか言おうとした?」
「……ううん、なんでもないよ。なんにも。帰りに、ケチャップでも買おうかなって思っただけ」
……結局泉は、瀕死の恋心を押し込めて、レオに嘘を吐いた。
自分と同じところまでレオが堕ちてきてくれなきゃ、なんにも出来ないのだ。そのことを、まざまざと思い知らされた瞬間だった。レオがいくら手を伸ばしてくれたところで、それは天上からの蜘蛛の糸に過ぎない。そんなものとても掴めやしない。
――ああ、きっと今日の夜は、またれおくんに抱かれる夢を見るんだ。
最低だけど、今は、初めて抱かれる夢を見た時のようにそのことを糾弾出来そうにない。むしろ彼にそうされていただろう二十二歳の瀬名泉を羨ましいと思う。
そのあと自分がどれほど絶望するかを薄々知りながら、棚に上げて――ただひたすらに、そのことが妬ましかった。