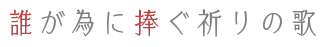
04:破瓜の時をゆめにみる
キスをする夢をみたの。
いつものベッドの上、ふたりとも裸で、ぐちゃりと重なり合って。しっちゃかめっちゃかに散乱した布の上、ふたり、キスをしていた。
『れおくんのキスってなんだか赤ちゃんみたい……』
呟くとれおくんは笑った。キスしてなくても赤ちゃんみたいだと思った。下半身まるだしで、さっきまでそこにぶらさがっているものを俺の中に突っ込んでいた、そのあとだというのに、赤ちゃんみたいに笑っていた。かわいい。俺のきれいなれおくん。好きだよ、ねえ、だからもう一回キスしてほしいな。
『セナは、なんでだかおれのこと、しょっちゅう赤ちゃんあつかいするな?』
『だってあんた、赤ん坊みたいに我が儘で自分勝手じゃない』
『んん〜? まあ……全部の否定をするのはむつかしいなっ。でもそう言うセナはいったいおれのなに? お母さんかっ? 昔からそう思うことはよくあったけど!』
スオ〜もおれの子供みたいなもんだったから、わは、そしたらおれたち家族だな〜。れおくんが俺を腕の中に抱えたままのんびりと呟いた。リッツとナルも王さまの我が子だから、五人家族の大所帯だもんな。頭をわしわしと撫でて――手のひらがちょっとべたついているような気がしたけど、気のせいだと思うことにした――俺の耳たぶを甘噛みする。
ほら、甘えん坊なんだから。
『ば〜か。あんな大きな子供たちは知りません』
『ええ〜。じゃあなんでおれだけ赤ん坊なの。不公平だ〜、家長制度の崩壊だ、異議を申し立てる!』
『くまくんもなるくんもかさくんも、俺の耳にかじりついてきたりなんかしないし。あんただけだよ、こんなことするの……』
『――うん、こんなことするのは、セナにしていいのは、おれだけだもん』
そうだろ、おれの鞘。
おれのセナ、大好きだよ、とれおくんが嘯いた。
『あぁ……あんた、ねえ、も、朝……なっちゃうよ……』
れおくんの指先が俺の下腹をまさぐる。おへそのあたりをなぞられると、変な気分になってきて、ぞわぞわする。ん、と鼻から抜ける声を漏らし、俺は身体の全てをふたたびれおくんへ委ねた。ああ、この指先になら、何をされてもいい。キスされても、耳を食まれても、いやらしい気持ちでいっぱいにされて乱暴に抱かれても、なんだってゆるしてあげる。
『あはは。赦されたいのはセナのほうだろ?』
…………。ああ。うん、そうだね。
少しだけ温度の低くなった手のひらに下肢をまさぐられ、身体の感覚が溶けてなくなっていくのを感じながら、俺は緩慢に頷いた。そうだね、分かってる。赦されたいのは俺の方。傲慢で思い上がりで浅はかな二十二歳の瀬名泉。ううん、十七歳だろうと、その醜さは変わらない。
あんたにこんなふうにされたいんだ。俺は昔から、ずっと心のどこかで、そういうことを考えていたのかもしれない。
れおくんの作った曲を歌う唇でキスをねだった。あの子の賛美歌を紡ぐ舌で恋に焦がれた。手渡されたマイクを握り締める手で、居眠りをする彼の頬を、何度なぞったのかわからない。
ねえステージの下のお姫さまたち。どうかこの醜い俺を赦さないで。
神さまが赦してくれなくたって、俺自身が赦せなくたって、この気持ちに嘘を吐き続けるなんてもう限界だよ。
――え? なに? キスしてほしかった? 間接キスじゃ物足りない?
――ああ……ごめんな。
――本当のキスはしないよ。……セナ、そういうの嫌だろ。
夢の中のれおくんは俺を抱いてくれるけど。
本物のれおくんは、手を繋ぐより先のことをしてはくれない。
彼はその理由を瀬名泉を愛しているからだと言う。
◇◆◇◆◇
「ねえ泉ちゃん、王さまとキスとかちゃんとしてる?」
うららかな午後の日のことだった。夜から雨という予報がにわかには信じられないぐらいよく晴れた日で、控え室の窓から入る冬の陽射しは暖かい。
そんな状況で、なんでこんなわけのわからない言葉が飛んでくるのか。
泉は飲んでいた缶コーヒーを噴き出しそうになり、慌てて口を押さえ、飲み干すとじっとりとした眼差しを嵐へ送った。
「はあ!? いきなり何言い出してるわけこのクソオカマ!!」
「うわ、怖っ。振られたばっかりのOLみたいな反応じゃん。ナッちゃん、やっぱその話まだ早かったんだよ〜……」
「そうねえ……時期尚早だったのかしら……でもねえ? 泉ちゃん、王さまと暮らしてもう随分経つでしょう。だから、ねえ……そう思ったのだけれども」
「……あの。そもそも皆さん、何の話をしていらっしゃるのですか」
私たちは次の仕事の打ち合わせをしに集まったはずでは? と司が唇を尖らせる。不穏な話題に割り込んで制止した末子の純真さに、泉はかつてないほどに感謝をした。ありがとうあまり記憶にない後輩よ。きっとおまえは手が掛かるけどかわいい子だったに違いない。
「というか何故、Room Shareしているからと言って瀬名お兄さまとLeaderがKissすることになるのですか。次のLiveでそういったPerformanceをするという話も、出ていないですよね」
「そうそう、しない、しない。当たり前でしょ、キスはファンサに入りません」
――今朝方見た夢では、現実でしてもらえない分べたべたにキスしてもらってたんだけど。それも妙にふわふわして甘ったるいやつ……。
しかしそんな情報を凛月や嵐に与えてはどんなことになるかわかったものじゃないので、おくびに出しもせず、泉はぶるぶると首を横へ振った。
すると凛月がしなやかな動きでこちらに寄ってきて、「へ〜」とか、全然信じてなさそうな顔をぐいと押しつけてくる。嫌な予感がして泉は後ずさろうとするが、残念ながら、すぐ後ろは壁だった。
「ん〜、ライブでしようって話じゃないし。ただ、一緒に住んでて向こうは恋人名乗ってるのに、まだなんだ、ふ〜んってだけ」
「べつに……れおくんはそういうことしないし。あいつ、迷子の猫を飼ってるみたいな感覚なんでしょ。手つないで……膝に乗せてもらって……そのぐらい……」
「ド健全じゃん……」
80年代少女漫画か何か? と凛月が呟く。そんなの読んだことないから知らない、と答えると凛月は何故か「食わず嫌い……ううん同族嫌悪かな……」と泉をしげしげと見ながらぼやいた。
「まあ、とにかく。キス、した方がいいと思うけどなあ。ほら、古来より悪い魔法使いの掛けた呪いって、王子さまのキスで解けるもんじゃん。セッちゃんの記憶喪失も、治るかもよ」
「あんた兄貴の言ってた与太話信じてるわけ……? キスしたぐらいで記憶が元に戻るっていうのなら、あのアホがとっくに実行してるでしょ。朔間の話は言葉の綾だよ」
「あ、そう。まあ王さま、にぶちんだからな〜。ていうか、あのひとの感情の動き、俺には予測できないんだよね。セッちゃんの方はこんなにわかりやすいのにさ」
「うひゃあっ!? ちょっ、顔近づけんじゃないっ、ニヤニヤ笑いがむかつく……!」
凛月の顔を無理矢理手のひらで押しのけ、椅子に座り直す。するとプリントを持ったままの司が、「瀬名お兄さま……」と頬を微かに赤らめてこちらをじっと見た。ああ、何か、嫌な予感がする。あの表情……もしやあらぬ誤解を生んでしまったのでは?
「もしかして……そ、そういうことだったのですね?」
司がちょっと照れながら俯きがちにそう呟く。
「ちょっとかさくん、何、何を言おうとしてるの」
「学生時代の謎がひとつ解けたなと思いまして……。――私、あの頃はLeaderに子供あつかいされてばかりだったのです。まあ、Unitの中でも一番に不出来な若輩者でしたから、その評は甘んじて受け入れましょう。しかし……あとから気付いたのですが、あの方どうやら、私を本当に子供みたいなものだと思っていた節もあったのですよね。私をというか、私や凛月先輩、鳴上先輩を、まとめて『Knightsのこどもたち』として見ているような節がありました」
「あいつ、自分が子供のくせに」
「それで……一度、言われたことがあるのです。『パパは忙しいからママのところへ行きなさい』と。あの時は、それがどういう意味なのかわからなかったのですが」
「え、かさくん、ストップ」
「つまり瀬名お兄さまはKnightsの母だったとそういう」
「――はいストップ!! この話は終わり!!」
司の唇を勢いよく手のひらで塞ぐ。もごむぐと口を動かし、まだ何か言いたそうな様子だったが、息苦しくなったからか、やがて司は抵抗を諦めた。その様子を見て、凛月がけらけらと笑う。
「あっははは、あはは、ス〜ちゃん、深呼吸しよ、深呼吸。息、へいき? 俺がチューして人工呼吸してあげよっか?」
「ぷはっ、はぁ、はあ……いえ、必要ありません。うう、こうして考えると先輩方はどうもこう、KissとかSkin shipに関してゆるいですよね……」
「舞台の上でのお喋りと同じかしらねえ。夢ノ咲の悪しき伝統……あるいは美徳よ、司ちゃん」
「そ。俺たちが仲いいとお客さんも喜ぶからね。セッちゃんと王さまが舞台で近づくと、黄色い声がすごいし。……はあ〜、それにしても、傑作。セッちゃん、お母さんだって」
手しかつないでもらえてないのにね。凛月がからかうように呟いた。うるさいな。というかそもそも、レオが司に向かって自分を「パパ」と言ったことがあるだなんて初耳だ。しかも言うに事欠いて「ママのところへ行きなさい」とはなんだ。早速育児放棄しているではないか。
そのことを口に出しかけ、でも噤み、顔を上げる。凛月は実に上機嫌で、指先でテーブルを叩いて薄く唇を開く。
「ま〜、確かにね。Knightsは……王さまがセッちゃんのために作ったものだし。王さまを父に据えたら、セッちゃんが妃と捉えられないこともない……のかもね」
「はあ!? なにそれ。俺は騎士なんだけどぉ。だって俺はあいつの剣で……盾で……それで……」
「『冠』だよ、セッちゃん」
セッちゃんが欠けたらあのひとは王さまたり得ないんだよ、と凛月が囁いた。傅く騎士がいなければそれは裸の愚王だけれど、侍る冠と剣がなければ王でいることさえ赦されないから、と。
泉はその台詞にぽかんとして言葉を失ってしまう。
「いや、俺がいなくたって、Knightsのリーダーはあいつでしょ」
「どうかしらねえ。王さま、いちどKnightsを解体しようとしたじゃない。あの時、何か言ってた気もするのよね……」
「は? 解体?」
「『ナイトキラーズ』っていうのを結成して、アタシたちが腑抜けてるから粛正する〜って戦いを挑んで来たのよォ。も〜本当、あの時は、王さまに反旗なんか翻すもんじゃないって思ったわァ。蟻が象と戦おうって言ったようなものだったもの。まあ、窮鼠猫を噛むというか、そんな感じで、アタシたち全員で必死に食らい付いて……最後は司ちゃんが、勝ったんだけどもね」
閉口してしまった泉へ畳み掛けるように、「騎士殺し」という趣味の悪い名前がぶすりと刺さった。
嵐がぺらぺら喋る内容の半分は、泉の頭には、うまく入っていかなかった。なに? どういうこと? あの、優しくて綺麗で純粋で……人を傷つけるのがなにより大嫌いな男の子が、騎士殺しだって?
「それって、なに、【ジャッジメント】ってこと? あの『チェス』でばかすか始まってた……」
「そ。Knightsの十八番の【B1】だね。……ま、あの頃の王さまはボロボロだったし、もう、人殺ししかやり方がわかんないみたいなところもあった。そのせいなのかなあ、セッちゃんを棄てるような真似をしたのも」
だからあのひとの考えてることは未だに難しく感じるのかな……。
その台詞が、たぶんとどめだった。
泉は衝動のままにがたりと立ち上がり、凛月の首根っこを掴み上げる。「瀬名お兄さま!」司が慌てて手を伸ばしてきたが、それも振り払った。凛月は冷えた瞳で泉を見据えている。その射貫くような眼差しが、余計に泉を苛立たせる。
「――なにそれ。なに? くまくん、何が言いたいの? れおくんが俺のこと棄てたって……なに!?」
「何って言われても、ほんとのことだよ。王さまはセッちゃんのためにKnightsを作って、そして壊れた。少なくとも周囲は一度、あのひとにそういうレッテルを貼ったんだ。デュエルとジャッジメントにまみれて、勝つための音楽しか書かなくなった月永レオにね。……セッちゃん、昔俺に話してくれたじゃん。王さまはモーツァルトが嫌いだって。お金や名誉のために作曲してたっていう歴史が残されているモーツァルトに、同族嫌悪を抱いてたんじゃないかって。だから王さまにはそうなってほしくないって……」
だけどね。凛月の鋭利な声音が、泉の耳の中を切り裂いた。胸ぐらを掴まれたまま微動だにしない赤い瞳が、怖かった。
目が離せない。耳が塞げない。
どうしていいのかわからない。
「だけどね、一度は人殺しの味しかわからなくなるまで王さまを追い込んだのも、セッちゃんだったんだよ。王さまはなんでもする。セッちゃんのためならなんでも。王さまがス〜ちゃんのパパを自称したのも、セッちゃんがママみたいだったからっていう、コロンブスの卵みたいな理屈かもしれないし?」
「知らない……そんなの、覚えてない……!」
「……無責任だよ、とは言えないけど。セッちゃんはそろそろ、逃げてないで王さまの愛を確かめておくべきだよ」
凛月が言った。心臓を強く揺さぶられるような醜悪な気分だったけど、それ以上の反論は出来なかった。月永レオのことを瀬名泉は何も知らない。泉は胸を押さえ、息を整える。
「……だからキスしろって言うの、あんたは」
「ご明察〜。がんばれ、セッちゃん☆ 王さまの愛は重いぞ♪」
「あ、あんた……なに、この状況で『がんばれ』とか」
「ん。出過ぎた真似して、ごめんねえ? だけど俺、セッちゃんにちゃんと幸せになってほしいんだもん」
なのにあのひとときたらさ、凛月が犬歯を覗かせてあははと笑う。愛し方が歪で、重苦しくて、高圧的で支配的で、有無を言わせず、ひどい真似するよね、なんて言いながら唇だけが笑っている。
「セッちゃんはさあ、なんか、『月永レオ』っていう男のことに、ものすごく夢を見てるみたいだけど……実際、十七歳の月永レオは、愛と夢と希望しか知らない、かわいい男の子だったのかもしれないけど。だけど俺が知ってるある時期の『王さま』は、もっと暴君で恐ろしくて、戦って傷つけることしかわからなくなった、大量破壊兵器みたいなやつだったよ。
――今の王さまは、そこまで荒んでないけどね。だけど確実に、その延長線上に立ってるんだ。そんな男がどうしてキスひとつしないでセッちゃんを囲ってるんだと思う?」
問いかけに、泉は答えられなかった。体勢だけ見れば泉が有利を取っている状況だけど、精神的な駆け引きで、泉は壁際限界まで追い詰められている。
「ねえ、セッちゃん」
凛月はうす紅色の唇を動かし、自分の胸ぐらを掴む泉の手にそっと冷たい手のひらを添え、嘯いた。
「あのひとの恋心はね、そんなきれいなもんじゃないよ」
◇◆◇◆◇
そのあとの打ち合わせは散々だった。あんな話をされて普段通りにふるまえるほど、今の泉の心は頑強じゃない。嵐も司も、掴み上げられた凛月本人も泉の行動を責めたりはしない。だけどそれがかえって泉の心を動揺させて、しんどい。
そんな経緯もあり、帰り道には、凛月と嵐の同行を拒否した。ふたりのことは友人として好きだし、別にさっきの遣り取りで特別へそを曲げているわけではなかったけれど、彼らは泉が喪った未来を全て知っているのだ――と改めて考えたら、急に恐ろしくなってしまったのだ。
「……生き物がみんな死滅したあとみたい」
さざなみが寄せては返す浜辺で、水面をぼんやりと眺めながらそう呟いた。局を出たあと、足の赴くままに歩いていたら、いつの間にか海へ辿り着いていた。
そんな泉の様子を、司が、少し離れたところに立って伺っている。つかず離れず、だけど干渉しないように。泉のささくれだった気持ちをこれ以上荒立てないよう、気を遣ってくれている。
(真面目な子……)
レオがいない時はKnightsの誰かが、という取り決めを一番まじめに遵守しているのは、たぶんこの子なんだろうなあと泉は朧に思う。彼がレオという王の忠実な騎士であることに、最早疑いようはない。矜持に従い、泉を守る騎士であろうとしている姿は、どこか、レオに仕える剣であろうとした己の姿に重なる。
そんなに慕われるような先輩だったのかな、自分は。
波打ち際を眺めていると、そんな益体のないことばかりが脳裏に浮かんでは消えて行った。
あんな話をされたばかりだというのに、笑えるぐらい、記憶が戻る兆しはない。「ナイトキラーズ」とか、ショッキングな単語も出てきたけれど……凛月と嵐が語った以上のことはわからない。きっとろくな思い出にまつわる単語ではないだろうし、良かったのかもしれないけど。
「どうしたいんだろうね、俺は」
記憶を取り戻したいのか、それとも永遠に忘れたままでいたいのか、どっちなのかな。
それさえも、日々曖昧になっていく。
少し前までは、絶対に思い出したくはなかった。思い出したらきっと穢れた大人に戻ってしまうから。だから嫌だった。……けれど思い出さなくたって穢れていることに変わりはないのだと認めてしまった今、喪われた記憶や未来は、そのまま、十七歳の泉にとって羨望の対象でもある。
「…………――♪」
そこまでごちゃごちゃと考え、泉はぶるりとかぶりを振った。こんがらがった毛糸玉を何もかも放り投げて、自由になりたい。だからあの呪いのような歌を舌の根で転がす。余計なことを忘れて、神さまに赦してくれともう一度おねだりしてみよう。
誰も赦してくれなくてもいいよ。そうやって紡がれた歌声を、だけど広大な海は、決して聞き逃してはくれない。
「――きれいな、『うた』ですね〜♪」
不意に、どこからか声がした。海の向こうからだ。泉は慌ててあたりを見回した。司は相変わらず離れたところでじっとこちらを伺っているし、その他に人影はない。
「だ、誰……?」
「ぷか、ぷか……♪ ここです、ここ〜♪」
「え……。あ――う、うそ」
不審がってもう一度だけ周囲を警戒する。すると、泉の呼び声に応えるように海面が震えた。直後、ばかりと水面が割れ、その真ん中から何かが飛び出してくる。
「に、人間!?」
頭から胸元ぐらいまでを水の上に浮かべたそれは、泉が見た限り、人間の形をしていた。顔には目と鼻があって、唇があり、ぴょんと跳ねた水色の毛が印象的だ。
「はい……☆ 『うたごえ』がきこえたので。つられて、よってきてしまいました」
「嘘でしょ、なんで人間が海の中から出てくるわけえ!? だいいち今、真冬なんだけど……!」
「こまかいことは、きにしない〜。……ううんと? あなた、どこかで、みたことがありますね……。う〜ん、う〜ん…………あ! おもいだしました。あなた、ちかごろ、うわさの……『ないつ』の、ひとですね?」
「そう、だけど。あんたは」
「ぼくは、『しんかいかなた』。あおいほのおは、しんぴのあかし。あおいうみからやってきた〜……りゅうせいぶるう! です……☆」
ぱしゃぱしゃと水をはねさせ、そいつが元気よく指を掲げる。「流星ブルー」。「深海奏汰」。――ああ、たしかこの前、雑誌でその名前は見た。流星隊の副隊長だ。夢ノ咲で連綿と続く伝統あるユニット、その卒業生が、芸能界で再結成した「最も輝ける流星隊」の一人。
そしてなにより、彼は……。
「また『五奇人』か……」
「むう〜? ぼく、そのよばれかたは、すきじゃないです。どっちかというと、おきがるに『りゅうせいぶるう』と呼んでほしいですね〜?」
五奇人、と口にした途端奏汰が唇を尖らせて抗議をする。どうも琴線に触れてしまったらしい――泉は素直に謝罪して、呼び名を改める。
「ああ、ごめん。深海」
「ふふ、いいですよ〜。すぐ、なおしてくれましたので。うふふ……『ないつ』のひと、なにかおこまりですか?」
「……なんでそう思うの?」
「『うみ』にくる『にんげん』は、たいてい『おなやみちゅう』なので。あなたもそうなのかなって、おもったんです〜。……ぼくでよければ、『おはなし』、ききますよ?」
ゆるゆると笑い、奏汰がぱしゃりと水を跳ねさせた。その純粋な笑顔を見ているとふと心を過ぎるものがあって、泉は「じゃあ聞いてよ」と彼の申し出に頷いてしまう。奏汰は「はぁい……☆」と笑い、ずるりと浜辺へ上がってきた。頭にヒトデが乗っかっていた。びしょびしょだけど拭くものは、と訊ねたら「いりません〜」と返される。
「だいじょうぶです。『うみ』は、すべてのいのちの『はは』ですから。それにあてられてしんじゃうようなことは、ぼくにかぎってはありませんね」
言っていることはいまいちよくわからないけれど、無邪気な表情が、どことなくレオを彷彿とさせる。
泉は黙って彼のとなりに座り込むと、ぽつぽつと今日の出来事を彼へ話した。
相談事の内容は、主に打ち合わせで出た「母親ポジション」の話に終始した。ナイトキラーズの話とか、レオの愛が重たい云々のことまでは、明かす気にはならなかった。
泉の説明を聞くたび、奏汰はふんふんと興味深そうに頷いてくれる。それから、一段落がつくたびに、彼なりの意見を少しずつ話してくれた。
「なるほど〜。あなたは、『ないつ』で『おかあさん』みたいなやくわりをしていたんですねえ」
「らしいね。俺今さあ、記憶喪失で……その時期のことは覚えてないからわからないんだけど」
「おや? では、あのはなばなしい『じゃっじめんと』や『すたふぇす』のことも、ごぞんじない?」
「うん。……どんなだった?」
「きれいでしたよ〜、とっても。とくに、『すたふぇす』は……けっしょうでさいごまでたたかっていたので、よくおぼえています。『おうさま』のしきでうごく、よにんのきしを……まとめていたのが、あなたでした。だから、おぼえています……☆」
当時のKnightsは三年生ふたりと二年生ふたり、一年生がひとりの構成。だからなおのこと、末子の司に対して父や母のような役割をあてがいやすかったのではなかろうか。奏汰の意見を総括すると、そのような内容だった。
「さんねんせいがいちねんせいをしどうすると……なんだか、『おやこ』っぽくなっちゃうんですよね〜。なずなのところは、『きょうだい』みたいだったけれど……あれはかわりだねですね。ぼくたちの『りゅうせいたい』も、どちらかといえば、『おやこ』……ううん、かぞくが、ちかかったのでしょうか」
「流星隊が? 俺が覚えてる流星隊は、守沢と三毛縞ぐらいしかろくに記憶にない集団なんだけど……あんたたち一年後はそんな感じになってたの」
「はい。ぼくと、ちあきと、さんにんの『こどもたち』で、ごにんそろって『りゅうせいたい』です。
――ぼくもちあきも、『こどもたち』がだいすきでした。だから、あのこたちがりっぱにせいちょうしたいまも……ときどき、『こどもあつかい』してしまいます。みんなかわいい、ぼくたちのこ……♪」
「……。あの子も……俺やれおくんにとって、そうだったのかなあ」
「あのこ? ……ああ、あそこにいる、おとこのこですか?」
「そ。朱桜司くん……なんでか、今俺の事『お兄さま』って呼ぼうとしてるけど。ふん、慣れてないんだから、やめたらいいのに」
「そうなんです……?」
岩陰に隠れてこちらを伺っている司の方を、奏汰がそっと見遣る。しばらく彼は「う〜〜〜ん?」と唸りながら、司をじっと観察していた。ちらちら横目で見ると、どんどん、司が居心地悪そうにもぞもぞしていくのがわかった。それでもその場を動かず逃げないのが、本当に健気だ。
時間にして、ざっと五分ほどであろうか。奏汰は実に真剣に司を観察し、それからぽんと手を叩いて、スッキリした顔で泉に向き直る。
「わかりました〜。たぶん、『のろい』にまつわる『おやくそく』でしょうねえ、それは」
奏汰が言った。泉は首を横へ捻る。
「は? 呪い? かさくんに何の関係があるの」
「『のろい』をほきょうする、てじゅんのひとつかなあ〜、と。いまのあなたは……きおくそうしつで、ちがう『やくわり』をもとめられている、みたいですから。もとのよびなだと、もとの『やくわり』がえいきょうしてしまうんです。たぶん。だからですね〜? 『こども』まで『のろい』につかうのは、ぼく、あんまりかんしんしません」
「……全然わかんない……」
「んう、まあ、ぼくも『まじない』はもんがいかんですから。『おはらい』と『おきよめ』はとくいですけど、かけるほうとなると、いささか。……う〜ん、こうしてじかにみていると、ちょっとこれはほうっておきにくいですねえ……」
あなたにかけられている「のろい」はほんとうにねぶかいですよ、と奏汰が唸りながら教えてくれる。そして、本当は関わるべきでない問題なのだが、「正義の味方」としては……見て見ぬ振りをするのも居所が悪い、と。
奏汰のひたりと濡れた人差し指が、つつ、と泉の頬をなぞった。ふっくらとした指の腹は、順繰りに皮膚をなぞって泉の額へ到達する。「ここに」奏汰が囁く。「あなたのひみつがねむっています。あなたの『きおく』が。ぼくはそれをとりもどすてだてを、しっています」。
「ねえ、ないつのひと。『まほうつかい』のいどころを、しりたいですか」
「魔法使い?」
「はい。ぼくが、ふだん『まほうつかいさん』とよぶのは、なっちゃんのほうなんですが。そっちじゃなくて……もうひとりの、ほうです」
ほんにんはじぶんをまほうつかいだとはおもっていないみたいなんですけどね。奏汰がしんとした声で告げる。だけどあのこはまほうつかいですよ、ひとびとがそうとしんじるものをつむぐかぎり。
「しりたいですか。『まほうつかい』を――あなたの『ほんとう』を。『かこ』にうずくまっているか、『みらい』をゆめみるか。えらぶ『けんり』は、あなたにあると……ぼくたちはみんなそうおもっているんです」
奏汰の声は、泉の心臓に、ひんやりと寄り添って染み込んでいった。泉は少しだけ考えて押し黙った。主に、今も自分が抱え込んでいる、瀕死の心臓について思案した。自分がどうなりたいのか。レオとどうしたいのか。何を未来に望んでいるのか……それらを考えた末に思い浮かんだのは、朔間零の言葉だ。
『記憶を取り戻すか否かに関わらず――君は本当の事に向き合うべきじゃな』
そう。本当のことを知るからといって、記憶を戻さねばいけないわけではないのだ。現に今日だって、『ナイトキラーズ』とやらの話を聞いても喪われた未来は何一つ戻ってこなかった。ただ困惑が積み重なっただけだ。知っている苦しみより、知らないことによる苦痛の方が、泉にとっては大きい……。
「わかった。教えて」
泉は決心をし、奏汰の手を自ら握り取った。奏汰は神妙な顔をしてそれに頷く。唇をやわらかに開き、秘密の言葉を、泉の耳に滑り込ませる。
それを聞いた途端、泉は弾かれたように立ち上がり、浜辺から街の方へ走り出した。
◇◆◇◆◇
「え、ちょっと、瀬名お兄さま――待って!」
さあっと顔を青ざめさせ、司は岩陰から飛び出した。自分が張っていたのとは別の方向に、泉が駆けて行く。司を置いて。たぶん、振り切るつもりで。
いけない、このままでは。司は混迷する頭を一度叩き、スマートフォンを取り出すとダイヤルを繋げた。
「――Leader! 申し訳ありません! 瀬名お兄さま……いえ、瀬名先輩を取り逃しました!」
コールが三度と鳴り終わる前に、相手が電話に出る。もしもし、という受け答えの返事を待つ暇もなく、司はきりきりと痛む心臓を叱咤して王へ報告を重ねる。
「本当に申し訳ありません、全て私の不徳の致すところです。どのようなお叱りも甘んじて受けます……」
『別にいい。今はそれよりセナの行き先のが大事だろ。どこだ? おれの金糸雀はどこ行った?』
司の言葉を遮って、電話口から酷く冷たい声が届く。氷に心臓を鷲掴みにされたような心地がして、ひっ、と司の口から怯えの声が漏れた。『どこだ?』王はなおも冷徹に訊ねかける。『おれのセナはどこだ?』だけど離れて見守っていたゆえに、ふたりの囁き声まではわからない……。
「ええと、それは……」
舌がもつれて、しどろもどろになる。ああ、怒られる。確かに司は、レオから仰せつかったのだ。泉のことを死守せよと。それを果たせないとなれば、どんな沙汰が下るか……そう思って身をちぢこませた司の肩を、誰かがぽんと叩く。
「――『はいきょうかい』、ですよ。ないつの『おうさま』」
救いの主は、先に泉を行かせた、深海奏汰その人だった。
『……誰?』
「『りゅうせいたい』のしんかいかなたです。でも、いまはそんなことはどうだっていい。『きし』さんは、『まほうつかい』のところへ行かせました。ぼくじしんが、そうするべきだとおもいましので。だってあなた、おうぼうですよ。かわいい『わがこ』に、こんなに、おびえたかおをさせるなんて」
『……流星隊か。悪いけど、これはうちの問題だ、他人にとやかく言われる筋合いはない』
「いいえ。ぼくはあのこにそうだんをうけました。だからもう、むかんけいではいられません。そうでしょう? 『おうさま』」
司からスマートフォンを奪い取り、いつになく厳しい語調で奏汰が詰る。司は呆然として奏汰を見ていた。レオに仕える騎士として、泉を守るためとして……司は、ある程度の事情を知らされている。だけど奏汰の言い方は、まるで、それ以上の内実を掴んでいるかのようだ。
「あなたは、一体……」
「ぼくは、ちあきの『りゅうせいぶるう』です。はなして、わかりましたけど……あのこと、すこしだけ……にたようなたちばなんです。だからあなたのやりかたは、こころがいたみます。『かこ』と『みらい』のどちらをえらぶかは、じぶんじしんが、きめなきゃ。ちあきはそうしてくれましたよ」
『だからセナを行かせたの? あいつがどれだけ傷付くかも知らないで?』
「きずつくかどうかをきめるのは、ほんにんですよ。あなたじゃない……『おうさま』、いいえ、『わるいまほうつかい』さんのおともだち」
奏汰がその言葉を告げた瞬間、しんとあたりが静まりかえる。奏汰も、司も、電話の先にいるレオも誰も喋らない。さざなみの音だけが電波にこだまする。
「いくなら、はやくいったほうがいいですよ。あなた、まほうがとけたらこまるんでしょう。――しあわせな『おわり』いがいはいやです、いちどはみじめに『ざんさつ』されたぼくたちだから。『やさしいうそ』のげんかいは……だれより、わかっているんです……」
夕暮れの中に奏汰の声がこだまする。
司のスマートフォンの向こうで、地面を蹴り上げる音がした。それからすぐに電話が切れる。それを確かめて、奏汰が「よく、がんばりましたね」と司の頭を撫でてくれる。
司はぽかんとしたまま、どうしようもない子供の不安そうな顔で、ちいさく訊ねた。
「……Leaderと瀬名先輩は、これからどうなってしまうのですか?」
それはかれらじしんがきめることです、と奏汰が言った。
走る。足がもつれて転びそうになって、そのたびまた姿勢を取り直して。月永レオは夕暮れの街を必死に走り続けた。頭の中は焦燥でいっぱいだ。ああ、セナ、おれのかわいいセナ! 瀬名泉がもし心に傷を負ってしまっていたらと思うと、もう、気が気でない。とても平静ではいられない。
――ああ、あとでスオ〜にも、謝っとかないとなあ。
奏汰の糾弾を全て認めるわけではないが、『我が子』同然の司に、悪事の片棒を担がせていた自覚はある。なんとなく察してそれでも手を貸してくれた凛月や嵐と違い、司は額面通りに言葉を受け取ってしまいがちなのだ。そういう純真さは尊ぶべきものだが、今回それにつけこんでいいように利用したのは、事実だった。
「――セナ! そこにいるのか、セナッ!!」
古ぼけた教会の前に辿り着き、中へ駆け込んで叫ぶ。ぼろぼろの屋根、雨漏りして腐った木造の床、錆びた聖像の匂い。
それらに包まれた中央に、瀬名泉が蹲っていた。レオは慌ててそこに駆け寄っていく。しかし何かに阻まれ、泉に触れ、抱きしめてやることは叶わない。
「おやおやおやおやっ☆ 王子さまのご登場ですね、クライマックスですねえ! ……ああ失敬、あなたは北斗くんとは違って、正統な戴冠を済ませた『王さま』でしたか。ですがまあ……少々、遅かったみたいですね?」
大きく穴が空いた天井から、ふわりと人影が落ちてくる。綺麗に編まれた長く青みがかったシルバーの髪、全てにおいて芝居がかった所作、胸ポケットには刺のある薔薇。レオは舌打ちをした。出てくるだろうとは思っていたが、こうして実際に邪魔をされると、腹が立つ。
「……おまえにかまってる暇はないんだけど?」
五奇人、日々樹渉。
この物語における「魔法使い」はレオにひらりと一礼をし、胸元から純白の鳩を幾羽も取り出すと夕暮れの中へ飛ばして消した。
「ああ、せっかちはいけません。軽挙妄動は破滅のもとですからね! 彼には、今は少し、眠っていただいています。うん、やはり今の彼にとって、真実を知ることは些か負担が大きすぎたようです。しかしご安心ください、ここにはナイフがありませんので、『あの時』のようなことにはなりませんよ」
あなたが泣きついた時のようにね。渉がもったいつけて囁く。レオが渉の言葉を無視していると、更にたくさんの鳩が躍り出て、腐った地面に真っ赤なアネモネがわっと咲いた。――花言葉は、「はかない恋」「恋の苦しみ」「見放された愛」。つまらない意趣返し。
「いい加減にしろよ、奇術師?」
「ふふふ! 親の仇でも見たような表情ですねえ? 素晴らしい、憎しみは感情のひとつの最果てです! ……けれどまあ、あまり焦らすのも可哀想ですかね。さてそれでは、感動のご対面といきましょう。高らかに、地面に額をこすりつけ、神に慈悲を乞うて! Amazing Grace……☆」
渉が右腕を高く掲げ、ぱん、と指先を弾く。蹲っている泉の身体がぴくりと動く。レオは渉の身体を押しのけて泉に寄り添った。腕の中に抱え入れ、起こしてやる。
「……れおくん」
泉の目が、ゆっくりと開かれた。目の周りは微かに赤く腫れていた。泣きはらしたあとなのだと、一目でわかった。
「あんたやっぱり、俺に嘘吐いてたの?」
涙に滲む空色の瞳が、潤んでいる。レオは息を呑んだ。悲嘆にくれた双眸は、だけどそれでも、月永レオを信じて、その先に救いを求めている。
レオは首を横へ振るった。
「……セナはその質問、肯定してほしい? それとも、否定してほしい?」
「本当のことを言って欲しい。つまらない嘘はやめて」
「……わかったよ」
泉の瞳は揺らがない。呪いは、魔法は、まだ効いている。
それでも泉は真実に辿り着いたのだ。この気高く誇り高い男に、レオは誠意を示さなければならない。レオは覚悟を決めて息を吸い込んだ。泉を抱きかかえる腕が震えた。ああ、これで、全部終わりなのかな。
おまえがおれのそばからいなくなってしまったら、おれはどうしたらいい? セナ。
だけどもう、彼に嘘は吐けない。
「そうだ。おれはずっと、嘘を吐いてた。
――おまえから五年間の記憶を奪ったのはおれだよ、セナ」
泉の瞳の奥に宿る光が、そして消えた。