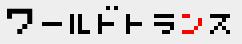Ⅲ EMPRESS:有里湊という少年
『二百十一階番人『天罰のダイス』、強敵です――気を付けて!』
オペレーター役である風花の鋭い声が遠隔ナビとしてメンバーの頭に響く。その声掛けに彼は「了解」となんら気負うことなく、ただ平然と当たり前のようなこととして返事をした。真剣をくるん、と一振り手首で回し弄ぶ。切れ味鋭い正真正銘本物の刃だ。本来高校生などが持ち得るはずのないそれであるというに、異様なまでにそのモーションは彼に馴染んでいた。
標的である、タルタロス第五エリア「焦燥の庭ハラバ」の番人シャドウ「天罰のダイス」を半円形状にパーティの四人で取り囲み、各々武器を構える。リーダーである彼がまず一番に引鉄を絞り、戦闘が始まった。
「マハラクカオート――マハタルカオート――ペルソナ『タナトス』、戦闘始めます。いつも通り僕は基本オール、安定したらバックアップで。いいですか」
「ええ、わかってますって。『ガンガン』行きますよ」
天田がかの有名なRPGのコマンドを暗に示して答える。そこにはリーダーである「彼」への揺るがない信頼が確かに感じて取れた。彼は誰からも信頼されている。寡黙であるゆえに、そしてその強力無比、絶大極まりない戦闘能力と指揮能力のゆえにだ。
「では。タナトス、『ブレイブザッパー』」
号令と共に死神のペルソナが吼え、軽やかに獰猛に駆け上がって手に持った剣を振り回した。強烈な物理スキルだ。ペルソナの物理スキルは強力であればあるほど術者の生命力を削り取っていくものなのだが顔色一つ変えずにけろりとしている。彼はいつもそうだ。いつも、こうやって表情を変えぬまま刃を、持てる強大なペルソナ能力を振るう。さながら神啓のように。圧倒的に優美な暴力であるかのように。
何かに衝き動かされているかのように。
「山岸さん、解析は」
『少し待ってください……ごめんなさい、正確にはわかりません。ただ、魔法にちょっと嫌な感じがあります』
「わかりました。――総員、物理スキル一辺倒で。僕が全体回復をしますから残りHPは気に掛けないで……」
「おうよ。ガンッガン行かせて貰うぜ。トリスメギストス、『デスバウンド』!」
「了解であります。湊さんの指示に従うであります。パラディオン、『ヒートウェイブ』」
「僕だって負けませんよ、カーラ・ネミ、『マッドアサルト』!!」
パーティメンバーはリーダーへの信頼に基づいて自らの能力を余すことなく発揮出来る。物理スキルで体力を削る傍から、彼が多様なペルソナで操る多種のサポートスキルがパーティを回復し支援していた。メディアラハン、マハスクカジャ、テトラカーン、マカラカーン。ナビゲーターの少女の『敵、弱ってきています。もう一息です!』の掛け声で彼はサポートペルソナを引っ込め再び引鉄を絞った。黒衣に鎖で繋がれた棺桶を翻して死神が再臨し吼え猛る。『ブレイブザッパー』の命令で彼のペルソナは運命アルカナのサイコロのようなシャドウを斬り裂き貫き、そこでこの戦闘は決着を見た。
パーティのメンバーは然程喜ぶわけでもなく、彼と頷いたりアイコンタクトを取ったりしてまたすぐに次のフロアへ向けて歩き出す。疲弊もそんなにないのだろう。それは彼らにとってこの光景、遣り取りが日常茶飯になっていることを示しているようだった。彼が圧倒的な強さを誇ることも、彼の指示の元この「滅びの塔」タルタロスを登ることも、シャドウという未知の敵と交戦することも、それらの全てが「S.E.E.S」、「特別課外活動部」にとっては当たり前のことで、それこそが日常だったのだ。
リーダーの少年を囲む日々がありふれた通常だった。あの日が訪れるその時までは。
「有里」
「……真田先輩。……何か?」
「飯でも食わないか。俺の行きつけで奢ってやる」
「……お言葉に甘えて」
「あーっマジっすか?! 俺も俺もー!」
「ちょっと順平、馬鹿丸出し。天田君の方がよっぽどしっかりしてて大人じゃない」
「仕方ないな。全員で行くか」
「っはー! 流石真田サン、話のわかるお人だぜ!!」
順平がガッツポーズをして勢いよくラウンジのソファから立ち上がる。スプリングの反動でそばに座っていた天田の小柄な体が跳ねた。それを見てゆかりや風花がくすりと微笑む。「彼」も、どこか微笑んでいるような柔和な表情だった。
そういう経緯で訪れた「はがくれ」の店内で、その日真田は「彼」の隣を取った。彼は特に訝ることもなく視線だけでちらりと、「何か話ですか」と問い掛けてくる。真田は「まあな」と曖昧に頷いて割箸をぱきりと割った。中央から綺麗に真っ二つだ。
「お前と話したいことがあった。……他愛のない話だ。食いながら流し聞いてくれればいい。……俺が戦おうと思ったきっかけを」
「……」
真田と彼の間にはラーメンをすする音と、真田の話し声だけが静かに響く。彼は時折相鎚を打つような仕草をしながら静かに真田が語る生い立ちと覚悟、そして荒垣とのことを聞いていた。妹の美紀が死んで。もう失わずとも済むような力が欲しくて。それでも結局のところ自分は子供に過ぎなくて、荒垣に色々な意味で置いていかれて、ようやく何かを手に出来たような気がして――
「だから、真田さんのペルソナが変わったんですね。あなたという人の在り方が根本から覆ったんです。……羨ましいって、少しだけ思います。僕にはそれがない。僕は停滞している。それが僕のスタイルで、だからこそ僕には無数の仮面があるんですけれども。根幹となるものが皆に比べて希薄っていうか、薄っぺらいんじゃないかって時々思うんです」
彼は薄く笑んだ。
「有里……ならお前は、何のために戦っているんだ?」
「あの塔を登った先に、答えがある気がするんです。僕が生まれた意味が。この体を、能力を与えられた意味が。今こうして言葉を交わして心臓を鳴らしている意味が――僕という記号が僕のかたちを成している理由が」
「……おまえ」
「あ、大丈夫です。皆と学生生活を送るのは楽しいし、シャドウと闘う時も何らかの充足感を得ています。ただそれでも、僕は僕である限り停滞している、停滞せざるをえないのだろうと。僕がペルソナを呼ぶのはきっと、世界を守らなきゃだとかそういう立派な大義のためじゃない。もし僕がいつも心の片隅で感じている『どうでもいい』が根こそぎ『どうでもよくない』に切り変わって、新しくなったとしたら、」
誰よりも強くけれどどことなく無気力で、大食いで、よく眠ってそのくせ要領が良くて、何をやらせてもそつのない彼『有里湊』は、灰色の瞳を細めてにこりと背筋に何か走るぐらいに綺麗に真田に笑い掛けた。およそ高校生の少年がする表情ではなかった。達観し切っていた。死の間際に我が生涯に一片の悔いなしと言い切る爺のようですらあった。
彼の薄い灰ねずみの目には「終わり」が映り込んでいた。どうしようもなく、確定的に、終末と永遠が宿っていた。その時は知らなかったが、それはきっと彼が『死』そのものを身に宿していたからなのだと思う。世界の全てを滅ぼすニュクスの息子、死の体現にして宣告者デス。死という終末と死という永遠。死神に魅入られた少年はずっと最初から何もかもを察知していたのだ。
「きっとその時、僕は僕じゃなくなってしまうと思うんです」
優しい少年、愚者のアルカナを持つ彼はごちそうさまを言ってどんぶりを置いた。はがくれの特盛が入っていたその器の中は既に空っぽで食い尽くされた後だった。
◇◆◇◆◇
有里湊は永遠になる。有里湊は死になる。有里湊は終焉になる。有里湊は封印になる。有里湊は楔になる。終末になり、再生になり、そして彼は有里湊ではなくなる。
死を封じる扉に縛られて宇宙になる。
『本当は世界が終わるはずだったその日、湊君は自らの存在と引き換えに世界の滅びを回避しました。大抵のことを『どうでもいい』で済ませていた彼はあの時恐らく初めて執着を持ったんじゃないかと思うんです。あらゆる形、可能性を持っていた不定形の少年は『どうでもよくない』という確固たる意志を手にして堅固なものになった。そしてユニバース、宇宙を示す封じられたアルカナを割り当てられた瞬間に有里湊は有里湊ではなくなった。彼という概念は死を迎え、死である僕と共になりニュクスから人々を遠ざけていた……だから湊君は有里でなく神郷であることに拘るんじゃないかなって僕は思います。ここで活動している自分は決して生き返ったかつての彼ではないから』
「……それで湊は、寂しそうなんだね」
決して長くなかった真田と綾時の昔語を黙って聞いていた洵がぽつりと漏らす。人間の群れの中に一人で異質として紛れている気持ちを思うと、よくわからなくなってきて胸を締め付ける苦しさが訪れた。そのうえここに訪れたのも「影時間をなくすため」――つまり自らに原因があると感じている事態の沈静化のためだ。
「影時間が綾凪に現れた原因も自分だって、自分のせいだって、思ってるんだね」
『まあ事実問題として原因のいくらかは湊君にあるからね』
「どういうことだ?」
『この世界の法則を歪めてしまえる存在が湊君に目を付けてたっていう話です』
綾時が顔に翳りを帯びさせて答える。
『確かに何でも抱え込んで一人で解決してしまうのは湊君の悪癖だけど、今回に限っては明確に湊君がまいた種なんですよ。ニュクス降臨のあの夜に湊君が残したほんの小さな感情が結果的に綾凪に影時間を呼び寄せてしまった。綾凪が選ばれたのは、半年前に大規模なペルソナ絡みの事件があって磁場が揺らいでたからじゃないかなって思うんですけど……』
「有里が残したもの、とは何を指しているんだ。あの日あいつが残したのは勝利の結果だけじゃないのか」
『そりゃ、そうでしょう。彼は自分と引き換えに平穏を残したけれど、それがどういうことなのか真田さんは考えませんでしたか? 考えたはずですよね。あの無限にループした寮、コロッセオ・プルガトリオで湊君を引き戻すべきではないとした態度からしてそれは明らかです。――あの選択は、本当は人間一人が選び取るものには重すぎたんです。まして有里湊はたった十八歳の少年で、まだ未来ある若者だった。有里湊はふつうの人間だった』
「……コロッセオ・プルガトリオ」
『知ってますよ、僕も湊君も。全てではないけれど知っていることは』
綾時が暗示するように言う。コロッセオ・プルガトリオ――「有里湊」を巡る特別課外活動部メンバーの仲違いから出現したデッドレス・コロッセオ。彼を取り戻せるのならばと武器を手に取った者、決意を無下にするべきではないと立ちはだかった者、中立の立場ながら見ていられないと立ち上がった者、そしてただ真実を求めて全てを討ち倒した心を閉ざした人形。その果てに待っていたのは巨大な未練の塊で、ただ醜い妄執だった。有里湊に投影されていた万能の幻影と羨望、愛、執着――擬似的な有里湊のシャドウ。
けれどそれは明確には湊のシャドウではない。課外部メンバーの意識の中のヴィジョンに過ぎない。何故なら有里湊はペルソナ使いでありながら、今の今まで自らのシャドウ、抑圧された心の暗部に触れたことがないからだ。七歳の時体内にデスのかけらを押し込まれたことで有里湊は異質な存在になってしまった。人でありながら意志を持つ特大級のシャドウと日々を共にした少年はいつしか、自らの抑圧された心をデスの影に追いやり、縮こまらせ、忘れ去ってしまった。それ程までにデスは強大な存在だった。
しかしそれが彼の精神バランスに異常をきたす。迷いなく世界のために引鉄を引く姿は普通ではない。でも、有里湊は人間の器に収まっていた。そうである以上それでも彼は人間だったのだ。
本当は何でも出来る超人でもなんでもない。
『僕は、湊君と同じものだった頃があるから知ってるし、わかる。『有里湊』は決して周囲が思っているような万能の超人じゃなかった。人間だから、ちっとも完璧なんかじゃなかった。有里湊にも本当は人並の感情があって、怒りも憎しみもあって、迷いも悲しみも恐怖もあった。――自らを生贄に世界を救ったことへのほんの僅かな後悔も』
◇◆◇◆◇
「僕は、そのニャルラトホテプって奴のことはあまりよく知らないんだ。……達哉が一番詳しいんだろうけど、その達哉ともろくに会話をしてないし」
部屋の隅っこで湊は黒猫にそう語り掛けた。ピアスを付けた黒猫、ナオはにゃあごと鳴く代わりに器用にも肩を竦める仕草をして人語で返答をする。
『俺も達哉程はわからない。ただまあ性格が悪いってのだけは確かだ。そしてこの世からなくせない理であるってこともわかる。嫌応にも理解してる。人間の心がどっちに傾くかを人生ゲームのプレイヤーとか、TRPGのマスタープレイヤー気取りでにやにや眺めてる。神取もある意味ではつけ込まれた被害者の一人だったわけだし……』
「そっか。ナオは戦ってるんだもんね」
『達哉の話を聞く限りじゃ、俺が倒したのはほんの片鱗、末端にすぎなかったみたいだけどな』
ナオはあの真っ黒くて昼も夜もわからない気の狂いそうな空間で、達哉が自分達の自我を守る目的も兼ねてぽつりぽつりと話してくれた内容を思い返しながら息を吐く。世界のあらゆる憎悪を一手に受けるかのような理不尽に晒されたかの少年は、しかしその実何が悪かったわけでもない。ただ不幸なだけだった。並外れて不幸なことに《這い寄る混沌》、「ニャルラトホテプ」に目を付けられ玩具として特に気に入られ、人生を握り潰された。可能性を根絶された並行世界という箱庭の中に戻った彼にはやはり自由などなく、鳥籠の中の雛鳥のような「続き」が待っていたのだという。
周防達哉は強固な精神を持ちうるがゆえに最大の被害者となった。ナオから言わせて貰えば、彼は優しすぎたのだ。そして少し甘ちゃんであったこともまた否めないとそう思う。
『あいつはきっと一人でなんでもかんでも背負い込みすぎてるよ。俺を逃がした時もそうだ……俺が閉じ込められたこともまた自らの負うところだと思っていたに違いない。だがそれは間違いだ。達哉が仮に生まれなかったとしたってどっちみち俺は奴に目を付けられただろう。フィレモンに名を告げた時点でわかりきってた』
「フィレモン?」
『……知らないのか?』
首を傾げる湊にナオが逆に驚いた声を出した。ナオの常識では通常ペルソナ使いというものはあの空間でフィレモンに自らの名を告げることでペルソナ使いとして目覚めるための「契約」が始まる、そういうことになっている。自身もそうだったし仲間達もそうだった。達哉も例外なくそうであった。しかし湊はあの超常の存在に本気で心当たりがないらしい。
『じゃ、お前はどうやってペルソナ使いになったんだよ。どこかで自らの名を告げることが契約になってるはずなのに』
「……契約はしたんだ。あの子が……ファルロスが差し出した契約書にサインをして、ベルベットルームでイゴールから説明を受けた。僕は死そのもの、十三番目のアルカナと契約を結んだんだと思う。あの子は死であり、そして僕の内なる仮面でもあった。僕の『タナトス』はあの子が残した『死』そのものの塊……」
『よくわからないんだが、つまりお前はペルソナそのものと契約を結んだって、そういうことなのか?』
「さあ、僕にもわからないよ。ただ、もしかしたら僕はあの時死に僕自体を明け渡していたのかもしれないって少し思わなくもない。後悔は全然してないけど。僕が僕であるために必要なことは守られたから……綾時は『やさしい死』だ。這い寄る混沌は逆に、生の地獄を達哉に与えている気がする」
長いこと死と生とを隔てる門に同化し、死そのものと繋がっていた湊は死に近い存在だった。ナオも、綾時が「やさしい死」であるという言葉はわかるような気がする。
絶対回避不可の絶望を見るぐらいなら緩やかで穏やかな、恐怖も何もない死という救いを――有里湊と契約を結んだファルロスという少年はそういうものだった。対照にニャルラトホテプは苦しみであり痛みだ。悲しみだ。這い寄る混沌、神すら嘲る愚なるもの。己の欲望のために人間という「掃いて捨てるほどある下等な玩具」をぐちゃぐちゃのばらばらにする力ある何か。
ペルソナ使いが通常まず名を告げる「フィレモン」は「ニャルラトホテプ」を影とするのなら光にあたる存在なのだという。人間に希望を見出して希望を託し、ペルソナ能力を顕現させる手助けをしているのだそうだ。ペルソナとは元来己の内に住まう未知なる自己であり、そして抑圧された自己である。ペルソナは自分だ。目を向けてやればはじめからそこにいるが、気がつかなければ声を上げることもないゆえに死ぬまでそれに気付くことはない。
(……だとすれば、やっぱ、湊はおかしいぜ)
(……和也)
(ペルソナの方から声を掛ける、ってのは有り得ない。力を約束され名を吐き出すことを要求されたってことだ。あの、何も考えていなさそうなデス――綾時に。生存本能なんだろう、とは思うけどな)
カズがひそひそと、明らかに不機嫌そうな声でナオだけに言葉を寄越す。ナオは鼻で息だけ吐いてカズを肯定した。湊がペルソナ使いとして異端の立ち位置にいることに関してはナオとしても同意見だ。湊はペルソナ使いが乗り超えるべきイニシエーション――自己と向き合い、受け入れるという当たり前の通過儀礼を通っていない。世界を救ってなお、自分の弱さに出くわしていない。ナオがカズを許容したように、達哉が自らの影と対峙し肯定したように湊はそれをこなしていない。
湊自身は、綾時が自身の影なのだという。綾時という人格は確かに有里湊によって育まれたものだからシャドウとしての側面はある程度持ちあわせているだろう。だが、綾時は湊に従順すぎる。そして純粋に湊の抑圧された精神から生まれた存在ではない。
湊には望みや欲望といった感情が薄かった。基本的に自らのシャドウはトラウマや欲望の裏返しで出来るものだから、そのせいなのかと疑ったこともある。だが今、湊の違和感を再び肌に感じてそうではないとナオは思った。ナオにとってのトラウマ、兄である和也の死とそれにまつわる経験、ピアス、自己肯定の欲求――それらに匹敵するか上回るほどのトラウマを湊は持っているはずなのだ。忘れているだけで、目を背けているだけで。
僅か七歳の子供が体内に「死のかたまり」を埋め込まれ、一時に両親を失くすというその出来事がトラウマにならないというのなら、どんな出来事がトラウマになりうるのだ?
(だから俺は綾時が信用ならねえ。疑いたくて仕方ない。あののんびりした面で『湊君は僕が守る』だなんて簡単に言う。ペルソナである以上は宿主の精神力がなきゃ、何も出来ないくせにだ。気に入らない)
(和也は湊のこと、好きだからね)
しっぽを揺らし、ナオはカズにそう投げて湊の懐に潜り込んだ。ゆえあってやつしている猫の身だが、この生活もなかなか快適であるとは思う。人間の体には代え難いが慣れてしまうとなかなかどうして便利な時も多い。
『ともかく、だ湊。いろいろ不可思議なことは多いがまずは現状の打破だ。達哉もそうそう長く保つかわからない。満月シャドウをただ手をこまねいて待ってるわけにもいかないだろ』
「それに関しては、大丈夫……だと思う。向こうもそのつもりで再現してるのかもしれないけど……綾凪は程度こそ劣るものの今の状態が珠間瑠市に似てるんだ。だから次の満月まで、一週間もないんじゃないかな」
『……それって……あー、そういうことか? 達哉が言ってた……』
「うん、使い方次第だよね。便利な道具だけどそれは向こうにも同様ってことだし。でも月齢を早めるぐらいなら僕への悪影響はないよ。だから当分は思う存分便利に使わせて貰う」
湊はナオの毛並を撫でながら気怠く頷く。珠間瑠市というのは例の達哉の町だ。達哉の故郷であり幾つもの戦いが発生した、かつての御影町とも違う異界と化していた不可思議の地。
そこでは大衆の意見が優先され、ナチス・ドイツの隠し精鋭部隊である聖槍騎士団が町中を跋扈するなどという眉唾ものの妄想すら大衆の支持を得ることさえ出来れば現実になってしまう、そういうふうに昔達哉は言っていた。
「何しろ噂が現実になる」
だから満月までの周期を縮めるぐらいわけないよ。そう言って、湊は何でもないふうに目を閉じた。
オペレーター役である風花の鋭い声が遠隔ナビとしてメンバーの頭に響く。その声掛けに彼は「了解」となんら気負うことなく、ただ平然と当たり前のようなこととして返事をした。真剣をくるん、と一振り手首で回し弄ぶ。切れ味鋭い正真正銘本物の刃だ。本来高校生などが持ち得るはずのないそれであるというに、異様なまでにそのモーションは彼に馴染んでいた。
標的である、タルタロス第五エリア「焦燥の庭ハラバ」の番人シャドウ「天罰のダイス」を半円形状にパーティの四人で取り囲み、各々武器を構える。リーダーである彼がまず一番に引鉄を絞り、戦闘が始まった。
「マハラクカオート――マハタルカオート――ペルソナ『タナトス』、戦闘始めます。いつも通り僕は基本オール、安定したらバックアップで。いいですか」
「ええ、わかってますって。『ガンガン』行きますよ」
天田がかの有名なRPGのコマンドを暗に示して答える。そこにはリーダーである「彼」への揺るがない信頼が確かに感じて取れた。彼は誰からも信頼されている。寡黙であるゆえに、そしてその強力無比、絶大極まりない戦闘能力と指揮能力のゆえにだ。
「では。タナトス、『ブレイブザッパー』」
号令と共に死神のペルソナが吼え、軽やかに獰猛に駆け上がって手に持った剣を振り回した。強烈な物理スキルだ。ペルソナの物理スキルは強力であればあるほど術者の生命力を削り取っていくものなのだが顔色一つ変えずにけろりとしている。彼はいつもそうだ。いつも、こうやって表情を変えぬまま刃を、持てる強大なペルソナ能力を振るう。さながら神啓のように。圧倒的に優美な暴力であるかのように。
何かに衝き動かされているかのように。
「山岸さん、解析は」
『少し待ってください……ごめんなさい、正確にはわかりません。ただ、魔法にちょっと嫌な感じがあります』
「わかりました。――総員、物理スキル一辺倒で。僕が全体回復をしますから残りHPは気に掛けないで……」
「おうよ。ガンッガン行かせて貰うぜ。トリスメギストス、『デスバウンド』!」
「了解であります。湊さんの指示に従うであります。パラディオン、『ヒートウェイブ』」
「僕だって負けませんよ、カーラ・ネミ、『マッドアサルト』!!」
パーティメンバーはリーダーへの信頼に基づいて自らの能力を余すことなく発揮出来る。物理スキルで体力を削る傍から、彼が多様なペルソナで操る多種のサポートスキルがパーティを回復し支援していた。メディアラハン、マハスクカジャ、テトラカーン、マカラカーン。ナビゲーターの少女の『敵、弱ってきています。もう一息です!』の掛け声で彼はサポートペルソナを引っ込め再び引鉄を絞った。黒衣に鎖で繋がれた棺桶を翻して死神が再臨し吼え猛る。『ブレイブザッパー』の命令で彼のペルソナは運命アルカナのサイコロのようなシャドウを斬り裂き貫き、そこでこの戦闘は決着を見た。
パーティのメンバーは然程喜ぶわけでもなく、彼と頷いたりアイコンタクトを取ったりしてまたすぐに次のフロアへ向けて歩き出す。疲弊もそんなにないのだろう。それは彼らにとってこの光景、遣り取りが日常茶飯になっていることを示しているようだった。彼が圧倒的な強さを誇ることも、彼の指示の元この「滅びの塔」タルタロスを登ることも、シャドウという未知の敵と交戦することも、それらの全てが「S.E.E.S」、「特別課外活動部」にとっては当たり前のことで、それこそが日常だったのだ。
リーダーの少年を囲む日々がありふれた通常だった。あの日が訪れるその時までは。
「有里」
「……真田先輩。……何か?」
「飯でも食わないか。俺の行きつけで奢ってやる」
「……お言葉に甘えて」
「あーっマジっすか?! 俺も俺もー!」
「ちょっと順平、馬鹿丸出し。天田君の方がよっぽどしっかりしてて大人じゃない」
「仕方ないな。全員で行くか」
「っはー! 流石真田サン、話のわかるお人だぜ!!」
順平がガッツポーズをして勢いよくラウンジのソファから立ち上がる。スプリングの反動でそばに座っていた天田の小柄な体が跳ねた。それを見てゆかりや風花がくすりと微笑む。「彼」も、どこか微笑んでいるような柔和な表情だった。
そういう経緯で訪れた「はがくれ」の店内で、その日真田は「彼」の隣を取った。彼は特に訝ることもなく視線だけでちらりと、「何か話ですか」と問い掛けてくる。真田は「まあな」と曖昧に頷いて割箸をぱきりと割った。中央から綺麗に真っ二つだ。
「お前と話したいことがあった。……他愛のない話だ。食いながら流し聞いてくれればいい。……俺が戦おうと思ったきっかけを」
「……」
真田と彼の間にはラーメンをすする音と、真田の話し声だけが静かに響く。彼は時折相鎚を打つような仕草をしながら静かに真田が語る生い立ちと覚悟、そして荒垣とのことを聞いていた。妹の美紀が死んで。もう失わずとも済むような力が欲しくて。それでも結局のところ自分は子供に過ぎなくて、荒垣に色々な意味で置いていかれて、ようやく何かを手に出来たような気がして――
「だから、真田さんのペルソナが変わったんですね。あなたという人の在り方が根本から覆ったんです。……羨ましいって、少しだけ思います。僕にはそれがない。僕は停滞している。それが僕のスタイルで、だからこそ僕には無数の仮面があるんですけれども。根幹となるものが皆に比べて希薄っていうか、薄っぺらいんじゃないかって時々思うんです」
彼は薄く笑んだ。
「有里……ならお前は、何のために戦っているんだ?」
「あの塔を登った先に、答えがある気がするんです。僕が生まれた意味が。この体を、能力を与えられた意味が。今こうして言葉を交わして心臓を鳴らしている意味が――僕という記号が僕のかたちを成している理由が」
「……おまえ」
「あ、大丈夫です。皆と学生生活を送るのは楽しいし、シャドウと闘う時も何らかの充足感を得ています。ただそれでも、僕は僕である限り停滞している、停滞せざるをえないのだろうと。僕がペルソナを呼ぶのはきっと、世界を守らなきゃだとかそういう立派な大義のためじゃない。もし僕がいつも心の片隅で感じている『どうでもいい』が根こそぎ『どうでもよくない』に切り変わって、新しくなったとしたら、」
誰よりも強くけれどどことなく無気力で、大食いで、よく眠ってそのくせ要領が良くて、何をやらせてもそつのない彼『有里湊』は、灰色の瞳を細めてにこりと背筋に何か走るぐらいに綺麗に真田に笑い掛けた。およそ高校生の少年がする表情ではなかった。達観し切っていた。死の間際に我が生涯に一片の悔いなしと言い切る爺のようですらあった。
彼の薄い灰ねずみの目には「終わり」が映り込んでいた。どうしようもなく、確定的に、終末と永遠が宿っていた。その時は知らなかったが、それはきっと彼が『死』そのものを身に宿していたからなのだと思う。世界の全てを滅ぼすニュクスの息子、死の体現にして宣告者デス。死という終末と死という永遠。死神に魅入られた少年はずっと最初から何もかもを察知していたのだ。
「きっとその時、僕は僕じゃなくなってしまうと思うんです」
優しい少年、愚者のアルカナを持つ彼はごちそうさまを言ってどんぶりを置いた。はがくれの特盛が入っていたその器の中は既に空っぽで食い尽くされた後だった。
◇◆◇◆◇
有里湊は永遠になる。有里湊は死になる。有里湊は終焉になる。有里湊は封印になる。有里湊は楔になる。終末になり、再生になり、そして彼は有里湊ではなくなる。
死を封じる扉に縛られて宇宙になる。
『本当は世界が終わるはずだったその日、湊君は自らの存在と引き換えに世界の滅びを回避しました。大抵のことを『どうでもいい』で済ませていた彼はあの時恐らく初めて執着を持ったんじゃないかと思うんです。あらゆる形、可能性を持っていた不定形の少年は『どうでもよくない』という確固たる意志を手にして堅固なものになった。そしてユニバース、宇宙を示す封じられたアルカナを割り当てられた瞬間に有里湊は有里湊ではなくなった。彼という概念は死を迎え、死である僕と共になりニュクスから人々を遠ざけていた……だから湊君は有里でなく神郷であることに拘るんじゃないかなって僕は思います。ここで活動している自分は決して生き返ったかつての彼ではないから』
「……それで湊は、寂しそうなんだね」
決して長くなかった真田と綾時の昔語を黙って聞いていた洵がぽつりと漏らす。人間の群れの中に一人で異質として紛れている気持ちを思うと、よくわからなくなってきて胸を締め付ける苦しさが訪れた。そのうえここに訪れたのも「影時間をなくすため」――つまり自らに原因があると感じている事態の沈静化のためだ。
「影時間が綾凪に現れた原因も自分だって、自分のせいだって、思ってるんだね」
『まあ事実問題として原因のいくらかは湊君にあるからね』
「どういうことだ?」
『この世界の法則を歪めてしまえる存在が湊君に目を付けてたっていう話です』
綾時が顔に翳りを帯びさせて答える。
『確かに何でも抱え込んで一人で解決してしまうのは湊君の悪癖だけど、今回に限っては明確に湊君がまいた種なんですよ。ニュクス降臨のあの夜に湊君が残したほんの小さな感情が結果的に綾凪に影時間を呼び寄せてしまった。綾凪が選ばれたのは、半年前に大規模なペルソナ絡みの事件があって磁場が揺らいでたからじゃないかなって思うんですけど……』
「有里が残したもの、とは何を指しているんだ。あの日あいつが残したのは勝利の結果だけじゃないのか」
『そりゃ、そうでしょう。彼は自分と引き換えに平穏を残したけれど、それがどういうことなのか真田さんは考えませんでしたか? 考えたはずですよね。あの無限にループした寮、コロッセオ・プルガトリオで湊君を引き戻すべきではないとした態度からしてそれは明らかです。――あの選択は、本当は人間一人が選び取るものには重すぎたんです。まして有里湊はたった十八歳の少年で、まだ未来ある若者だった。有里湊はふつうの人間だった』
「……コロッセオ・プルガトリオ」
『知ってますよ、僕も湊君も。全てではないけれど知っていることは』
綾時が暗示するように言う。コロッセオ・プルガトリオ――「有里湊」を巡る特別課外活動部メンバーの仲違いから出現したデッドレス・コロッセオ。彼を取り戻せるのならばと武器を手に取った者、決意を無下にするべきではないと立ちはだかった者、中立の立場ながら見ていられないと立ち上がった者、そしてただ真実を求めて全てを討ち倒した心を閉ざした人形。その果てに待っていたのは巨大な未練の塊で、ただ醜い妄執だった。有里湊に投影されていた万能の幻影と羨望、愛、執着――擬似的な有里湊のシャドウ。
けれどそれは明確には湊のシャドウではない。課外部メンバーの意識の中のヴィジョンに過ぎない。何故なら有里湊はペルソナ使いでありながら、今の今まで自らのシャドウ、抑圧された心の暗部に触れたことがないからだ。七歳の時体内にデスのかけらを押し込まれたことで有里湊は異質な存在になってしまった。人でありながら意志を持つ特大級のシャドウと日々を共にした少年はいつしか、自らの抑圧された心をデスの影に追いやり、縮こまらせ、忘れ去ってしまった。それ程までにデスは強大な存在だった。
しかしそれが彼の精神バランスに異常をきたす。迷いなく世界のために引鉄を引く姿は普通ではない。でも、有里湊は人間の器に収まっていた。そうである以上それでも彼は人間だったのだ。
本当は何でも出来る超人でもなんでもない。
『僕は、湊君と同じものだった頃があるから知ってるし、わかる。『有里湊』は決して周囲が思っているような万能の超人じゃなかった。人間だから、ちっとも完璧なんかじゃなかった。有里湊にも本当は人並の感情があって、怒りも憎しみもあって、迷いも悲しみも恐怖もあった。――自らを生贄に世界を救ったことへのほんの僅かな後悔も』
◇◆◇◆◇
「僕は、そのニャルラトホテプって奴のことはあまりよく知らないんだ。……達哉が一番詳しいんだろうけど、その達哉ともろくに会話をしてないし」
部屋の隅っこで湊は黒猫にそう語り掛けた。ピアスを付けた黒猫、ナオはにゃあごと鳴く代わりに器用にも肩を竦める仕草をして人語で返答をする。
『俺も達哉程はわからない。ただまあ性格が悪いってのだけは確かだ。そしてこの世からなくせない理であるってこともわかる。嫌応にも理解してる。人間の心がどっちに傾くかを人生ゲームのプレイヤーとか、TRPGのマスタープレイヤー気取りでにやにや眺めてる。神取もある意味ではつけ込まれた被害者の一人だったわけだし……』
「そっか。ナオは戦ってるんだもんね」
『達哉の話を聞く限りじゃ、俺が倒したのはほんの片鱗、末端にすぎなかったみたいだけどな』
ナオはあの真っ黒くて昼も夜もわからない気の狂いそうな空間で、達哉が自分達の自我を守る目的も兼ねてぽつりぽつりと話してくれた内容を思い返しながら息を吐く。世界のあらゆる憎悪を一手に受けるかのような理不尽に晒されたかの少年は、しかしその実何が悪かったわけでもない。ただ不幸なだけだった。並外れて不幸なことに《這い寄る混沌》、「ニャルラトホテプ」に目を付けられ玩具として特に気に入られ、人生を握り潰された。可能性を根絶された並行世界という箱庭の中に戻った彼にはやはり自由などなく、鳥籠の中の雛鳥のような「続き」が待っていたのだという。
周防達哉は強固な精神を持ちうるがゆえに最大の被害者となった。ナオから言わせて貰えば、彼は優しすぎたのだ。そして少し甘ちゃんであったこともまた否めないとそう思う。
『あいつはきっと一人でなんでもかんでも背負い込みすぎてるよ。俺を逃がした時もそうだ……俺が閉じ込められたこともまた自らの負うところだと思っていたに違いない。だがそれは間違いだ。達哉が仮に生まれなかったとしたってどっちみち俺は奴に目を付けられただろう。フィレモンに名を告げた時点でわかりきってた』
「フィレモン?」
『……知らないのか?』
首を傾げる湊にナオが逆に驚いた声を出した。ナオの常識では通常ペルソナ使いというものはあの空間でフィレモンに自らの名を告げることでペルソナ使いとして目覚めるための「契約」が始まる、そういうことになっている。自身もそうだったし仲間達もそうだった。達哉も例外なくそうであった。しかし湊はあの超常の存在に本気で心当たりがないらしい。
『じゃ、お前はどうやってペルソナ使いになったんだよ。どこかで自らの名を告げることが契約になってるはずなのに』
「……契約はしたんだ。あの子が……ファルロスが差し出した契約書にサインをして、ベルベットルームでイゴールから説明を受けた。僕は死そのもの、十三番目のアルカナと契約を結んだんだと思う。あの子は死であり、そして僕の内なる仮面でもあった。僕の『タナトス』はあの子が残した『死』そのものの塊……」
『よくわからないんだが、つまりお前はペルソナそのものと契約を結んだって、そういうことなのか?』
「さあ、僕にもわからないよ。ただ、もしかしたら僕はあの時死に僕自体を明け渡していたのかもしれないって少し思わなくもない。後悔は全然してないけど。僕が僕であるために必要なことは守られたから……綾時は『やさしい死』だ。這い寄る混沌は逆に、生の地獄を達哉に与えている気がする」
長いこと死と生とを隔てる門に同化し、死そのものと繋がっていた湊は死に近い存在だった。ナオも、綾時が「やさしい死」であるという言葉はわかるような気がする。
絶対回避不可の絶望を見るぐらいなら緩やかで穏やかな、恐怖も何もない死という救いを――有里湊と契約を結んだファルロスという少年はそういうものだった。対照にニャルラトホテプは苦しみであり痛みだ。悲しみだ。這い寄る混沌、神すら嘲る愚なるもの。己の欲望のために人間という「掃いて捨てるほどある下等な玩具」をぐちゃぐちゃのばらばらにする力ある何か。
ペルソナ使いが通常まず名を告げる「フィレモン」は「ニャルラトホテプ」を影とするのなら光にあたる存在なのだという。人間に希望を見出して希望を託し、ペルソナ能力を顕現させる手助けをしているのだそうだ。ペルソナとは元来己の内に住まう未知なる自己であり、そして抑圧された自己である。ペルソナは自分だ。目を向けてやればはじめからそこにいるが、気がつかなければ声を上げることもないゆえに死ぬまでそれに気付くことはない。
(……だとすれば、やっぱ、湊はおかしいぜ)
(……和也)
(ペルソナの方から声を掛ける、ってのは有り得ない。力を約束され名を吐き出すことを要求されたってことだ。あの、何も考えていなさそうなデス――綾時に。生存本能なんだろう、とは思うけどな)
カズがひそひそと、明らかに不機嫌そうな声でナオだけに言葉を寄越す。ナオは鼻で息だけ吐いてカズを肯定した。湊がペルソナ使いとして異端の立ち位置にいることに関してはナオとしても同意見だ。湊はペルソナ使いが乗り超えるべきイニシエーション――自己と向き合い、受け入れるという当たり前の通過儀礼を通っていない。世界を救ってなお、自分の弱さに出くわしていない。ナオがカズを許容したように、達哉が自らの影と対峙し肯定したように湊はそれをこなしていない。
湊自身は、綾時が自身の影なのだという。綾時という人格は確かに有里湊によって育まれたものだからシャドウとしての側面はある程度持ちあわせているだろう。だが、綾時は湊に従順すぎる。そして純粋に湊の抑圧された精神から生まれた存在ではない。
湊には望みや欲望といった感情が薄かった。基本的に自らのシャドウはトラウマや欲望の裏返しで出来るものだから、そのせいなのかと疑ったこともある。だが今、湊の違和感を再び肌に感じてそうではないとナオは思った。ナオにとってのトラウマ、兄である和也の死とそれにまつわる経験、ピアス、自己肯定の欲求――それらに匹敵するか上回るほどのトラウマを湊は持っているはずなのだ。忘れているだけで、目を背けているだけで。
僅か七歳の子供が体内に「死のかたまり」を埋め込まれ、一時に両親を失くすというその出来事がトラウマにならないというのなら、どんな出来事がトラウマになりうるのだ?
(だから俺は綾時が信用ならねえ。疑いたくて仕方ない。あののんびりした面で『湊君は僕が守る』だなんて簡単に言う。ペルソナである以上は宿主の精神力がなきゃ、何も出来ないくせにだ。気に入らない)
(和也は湊のこと、好きだからね)
しっぽを揺らし、ナオはカズにそう投げて湊の懐に潜り込んだ。ゆえあってやつしている猫の身だが、この生活もなかなか快適であるとは思う。人間の体には代え難いが慣れてしまうとなかなかどうして便利な時も多い。
『ともかく、だ湊。いろいろ不可思議なことは多いがまずは現状の打破だ。達哉もそうそう長く保つかわからない。満月シャドウをただ手をこまねいて待ってるわけにもいかないだろ』
「それに関しては、大丈夫……だと思う。向こうもそのつもりで再現してるのかもしれないけど……綾凪は程度こそ劣るものの今の状態が珠間瑠市に似てるんだ。だから次の満月まで、一週間もないんじゃないかな」
『……それって……あー、そういうことか? 達哉が言ってた……』
「うん、使い方次第だよね。便利な道具だけどそれは向こうにも同様ってことだし。でも月齢を早めるぐらいなら僕への悪影響はないよ。だから当分は思う存分便利に使わせて貰う」
湊はナオの毛並を撫でながら気怠く頷く。珠間瑠市というのは例の達哉の町だ。達哉の故郷であり幾つもの戦いが発生した、かつての御影町とも違う異界と化していた不可思議の地。
そこでは大衆の意見が優先され、ナチス・ドイツの隠し精鋭部隊である聖槍騎士団が町中を跋扈するなどという眉唾ものの妄想すら大衆の支持を得ることさえ出来れば現実になってしまう、そういうふうに昔達哉は言っていた。
「何しろ噂が現実になる」
だから満月までの周期を縮めるぐらいわけないよ。そう言って、湊は何でもないふうに目を閉じた。
Copyright(c)倉田翠.