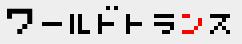Ⅴ HIEROPHANT:もしも奇跡を願うなら
一人には慣れていた。
暗闇にもだ。ずっとそうしてきた。人を遠ざけ馴れ合いを良しとせず殻の中に引き籠もった。
自分が何か行動する度に何かを失った。いつもいつも結局最後には失敗して手のひらから大事なものを取りこぼした。世界は冷徹で、自らは浅薄だ。人間一人の力というのは酷くちっぽけで、思い知らされるようだった。
《這い寄る混沌》に目を付けられた周防達哉の、それが罪であり罰だった。
「……ここにも随分慣れた」
闇に慣れた視界の中でぼんやりと浮かび上がる、火の点かないライターを手の中でもてあそぶ。カチカチというさびれた音に思い出すのは失われてしまった世界のことだった。かつて達哉が生きていた世界。そして一時だけ身を置いた「やり直した世界」……兄は、舞耶に惚れていた克哉は彼女と上手くやっているだろうか? 仲間達は。世話になった人達は幸福な世界を享受できているだろうか。噂に造り変えられたりしない、失敗しなかった世界を……
周防達哉の犠牲の元成り立つ世界を。
「舞耶姉は、兄さんだから任せるんだからな。俺の知らないどこぞの男に取られてみろ。一生恨むぞ。俺の初恋の人なんだ」
這い寄る混沌ニャルラトホテプはフィレモンと対を成す存在だ。人の可能性を見出し希望を託すフィレモンとは逆に人の欲望を拡大し傀儡化し利用して時には世界を滅ぼそうともする。しかしその行為に理由はない。快楽主義者なのだ。面白い玩具か否か、行動原則はそこに集約されている。
周防達哉はニャルラトホテプに見初められた玩具の中でもとりわけ良く出来た一つだった。世界一つ作り出す程の精神力を持ちながら人間らしいエゴイズム――欲望を捨て切れなかった。生々しく醜悪な人間。達哉は強大な力をその内に秘めた可能性であったが、しかし最後には整合性を乱す特異点にしか成り得なかった。この崩壊したかつて世界であった場所に還ってきた時ニャルラトホテプは嗤ったものだ。『ああ、周防達哉、貴様は失敗したのだ。愚かしい、実に愉快極まりない。貴様は所詮その程度でしかない!』……不愉快なことに正論だった。
「ペルソナ……心の仮面、抵抗するための力。ここじゃ、あんまり上手くは使ってやれないが。藤堂は上手くやっているだろうか」
かの南条や桐島らの友人であるというピアスの青年は非常に不幸なことに、ニャルラトホテプにあちら側から捕まえられてきてしまったらしかった。あの迷惑な存在が理由なく行動を起こすのはいつものことだが、罪と罰を抱える故にこの仕打ちも然るべきかと思える達哉に対して藤堂尚也にはそこまでのいわれがない。理不尽に思った達哉の悪足掻きと外界からの何か大きな力を持つ「少年」の働きかけが偶然噛み合ったために、なんとか彼をここから外に出してやることには成功したがそれも完全ではなかった。彼が還るべき時空ではなく少年のいる未来にあたる時間へしか脱出出来なかった上、人間の姿を保てなかったのだ。しかしそれでもここに囚われているよりは幾らかマシだろう。この暗闇はそういう場所だ。
それにしても、思い返してみると例の「少年」はたいそうおかしな存在だった。彼の内には死と世界が同居していた。一応ペルソナ使いなのだろうとは思われたが、それにしてはアルカナに節操もないようだ。
彼は無限で永遠で終焉だった。神ではない。そんなものはいない。ニャルラトホテプやフィレモンのように外から覗き見る者でもない。だが、人間でもない。どっち付かずの青色の少年。紺碧の髪に隠れた灰色の眼には、死と希望が映り込んでいる。
『僕は……湊。昔は有里湊って呼ばれてた。あのさ……達哉』
『必ず君を助けるから。僕の《ユニバース》を使っても。たとえ世界がそれを阻んでも。運命なんてくそくらえだ』
「『運命なんてくそくらえ』か。俺も……」
少しだけ見た少年の姿を思い浮かべて達哉は目を閉じる。闇が濃くなる。僅かなノイズも立ち消えて気が狂わんばかりの静寂に辺りが支配される。
「――ずっとそう思ってる」
だけど運命は絶対の拘束力を持って達哉を離そうとしない。
沈むような眠りに落ちていく最中で達哉は遠い世界のことを思った。最後に人の住む世界に立っていたあの別れの日からどれ程の月日が経ったのだろう。あれから知人達はどうなったのだろうか。幾つの歳を重ねているのだろうか。達哉にはそれがわからない。
自問自答に意味はなく答えもない。それは眠りに就く度に繰り返す、もう幾度目かもわからない儀式にも似た何かだった。
◇◆◇◆◇
「本当にあんなのが十二体も出るんだな?」
「全部でだよ、慎兄。もう一体は葬った後だし。それにこの辺はまだまだ大したことない。最後の『ハングドマン』をどれぐらい速く片付けられるかは正直自信ないけど……」
ペルソナ「アベル」を顕現させて走り、遠目に《満月シャドウ》を見上げながら慎は尋ねた。湊はけろりとして立っている。ヘッドホンを耳から外して首に掛け、「綾時」と彼の守護者の名前を呼んだ。
「解析」
『分かってる。――ボスタイプシャドウ『プリーステス』、アルカナは女教皇。呪殺・破魔無効、氷結反射。さほど強くはないよ。君ならすぐに終わる』
僕が出る程でもないね、と綾時が結果を言い渡す。湊はぱちくりと目を見開いて「さほどって、丸っ切りってこと」と拍子抜けな声を出した。
「ってことは、この前の魔術師ももしかして弱かった……というか記録のままの強さだったの?」
『うん……恐らくね。君の全力はちょっとオーバー過ぎたかも。でもその分わかったこともある。その体じゃ、あんまり無理は出来ないんだ。デスを使用し続けると体力に限界が来ちゃうのかな、君がこの前僕を無理矢理引っ込めたのってそういうことでしょう』
二人の会話を横に聞きながら慎は湊と出会った時のことを回想した。意識をぷつんと失ったみたいにペルソナが消滅し、急速に落下していた小柄な体。能力が強すぎて容れもののポテンシャルが追い着かないのだ。オーバーフロー状態に陥っていたのだろうがしかし、自分の能力限界を計り切れずに自滅してしまってはどうしようもない。
湊のペルソナ能力が酷く強烈なのだということは一応自覚しているつもりだったが、よもやこれ程までとは。子供の姿をして慎を兄と慕ってはいても、その中身は決してそんなに生易しいものではないのだと改めて思い知らされたようなそんな心地になる。
『どうしてかはわからないけれど、今の君は万全の状態じゃないんだ。この前は運よく助けて貰えたけど毎回そういうわけにもいかない。実戦で色々試しながらリミッターの原因は探すとして、まずは倒れないようにコントロールするのが先だと思うよ』
「……か。ま、デスはとびきり負荷が大きいししばらくは封印しよう。ごめん綾時」
『なんで君が謝るの』
「だって、暴れ足りないでしょ」
違うの? と灰色の瞳が尋ねて来る。否定をし難い視線というものを体現したらこうなるのだろうと思った。湊の持つオーラというべきか、魅力、カリスマ性の高さが滲み出ている気がする。そういえば真田が昔話をする時ぽつりとこう漏らしてはいなかったか。「有里は変な奴だったが、学園中探してもあいつを嫌ってる人間というのはいなかった。誰も彼もが好ましく接していた。今思えばあのカリスマ性はどこか異常だったとも思う」、と。
しかし綾時はその視線に一秒足りとも揺れることなくきっぱりと首を振って「ううん」、とこともあろうに否定の意を躊躇いなく示した。
『それは君が、でしょ。尚也と和也もそうみたいだけど。第一僕は平和主義者なんだよ。女の子は好きだけど、戦うのは別に好きでもないし』
「嘘つけ。本当の平和主義者っていうのは節操なく女の子に声をかけてハーレム状態を作ったりしない」
『……湊君、きみ、それそっくりそのまま返されても文句言えないよ?』
それに僕の大事な人は君一人だけだし。綾時はそう言って湊の中に引っ込んだ。湊も当たり前にその言葉を受けて、それから何もなかったみたいに澄ました顔で召喚銃の引鉄を引き抜く。ぱきん、というお決まりのサウンドとあの青白いライトエフェクトを伴って「綾時」でもなく「デス」でもないペルソナが召喚される。
「行こう、慎兄。時間取らせちゃってごめん。洵兄も待ってくれてるし、さっさと終わらせよう。慎兄は好きに動いて、僕がそれに合わせる」
「あ、ああ。……時に湊、つかぬことを聞くけど」
「何?」
「その冷蔵庫みたいなペルソナは一体」
「キングフロスト。フロスト族の王様。ジャックフロストが集まって出来た伝説のキングらしいよ。かわいいから結構、好き」
「そうか……」
マイペースに走っている。そうこうしている内に「プリーステス」との距離も戦闘に適したラインまで詰まり、二人はそこで足を止めた。顔面を何か呪いめいた文字に埋め尽くされた包帯で覆い、ゴルゴンのような髪をくゆらせている。近付くにつれて大気が冷えていく感覚に体を震わせた。先に「氷結反射」と綾時が言っていたように思うが、なるほどこの寒さは確かに氷を得意とするシャドウならではのものだろう。
プリーステスが敵対者二人の姿を認めたしく、口裂け女よろしく大口を開いて耳をつんざくような悲鳴を上げる。
「タルカジャかけるから、物理で押して! それとラストアタックは任せてもいいかな。『ペルソナを切り離す異能』がどういうふうに作用するか見てみたい」
「任せとけ。――アベル!」
慎の意思に反応してアベルが空へ飛び上がる。二回目の満月シャドウ討伐は、然程の混乱を生むことなく終わるだろうとこの時湊は考えていた。
◇◆◇◆◇
時間は、影時間よりもいくらか前に戻る。
桐条美鶴は真田明彦と向かい合って、陰鬱な面持ちで両腕を組んでいた。一言で言えば、しょげている。桐条という一大組織を気丈に一人で支えている女王然とした彼女が今この場においては叱られた子供同然に落ち込んでいた。
「……私は想定していなかったんだ。勿論『彼が』いるという事態も想定していなかったし、よもや彼がああまで頑なに……拒絶をすると、思っていなかった。とんだ甘えだ。私達は彼一人に全てを押し付けたというのに」
「美鶴。あいつが言っていたこと、聞こえていなかったのか? あいつは『仲間のことは好き』なのだと言ったし、突き放すつもりもなかったとそう言っていたぞ」
「しかし私は……私には、彼がどうしても『有里湊』にしか見えないのだよ。姿が子供返りしていても、いくら否定されようとも。あの少年は私にとって紛うことなく特別課外活動部リーダーの少年なんだ。十年と少し前に息を引き取ったはずの、あの」
「……だが」
「みなまで言わずともいい。感情の問題なんだ。理論としては……わかっている」
有里湊は死んだ。メティスの言葉によればそれは肉体の死で、精神は今も例の扉に括り付けられて生きているのだというが、しかしそれは決定的に紛れもなく「人間としての死」であるのだと彼女は断じていた。だからきっと今綾凪に現れた「ヘッドホンの少年」は有里湊の精神、もしくはそれの残留思念、そういった類のものが肉体を得て活動しているに過ぎない存在なのだろう。そういう意味で神郷湊は確かに有里湊では有り得なかった。肉体の識別コードがまるっきり別物だ。
だが、と美鶴は呟く。それでも有里湊を知る者にとって神郷湊は、そう名乗る少年の存在はあの日奇跡を起こした少年と同一の存在だった。
死で出来上がった、死と夜の女王そのものに成り果てたと自らを断じた湊の姿は痛ましくさえあった。あのぞっとしない表情。「奇跡を一つ起こしたら」、と彼はそう言った。自分一人のために行使出来る奇跡なんて誰も持ちあわせてはいない。使えるのは汚い手練手管ばかりだ。
酷く複雑な気分だった。彼に再び出会えた喜びは罪悪感と動揺とで帳消しどころかマイナスにならんという勢いだ。
「そういえば……彼はコロッセオ・プルガトリオのことに触れていたな。今となってはあれすらも懐かしい過去だ。彼は……厭うていたのだな、呼び戻されることを。ゆかりが聞いたら泣き出しそうだ。一度だけ彼女を絶対に味方すると前々から決めていた私にとってもあの場所はなかなかしんどいものがあったというに、それをああもすげなく拒否されたとなっては」
「岳羽か……。彼女はまだ『岳羽』なんだったな、確か。いや、岳羽に限らないか。俺達はあいつに……有里に縛られ過ぎていたのかもしれない。あの『三月三十一日』にそのことに思い当たったはずなんだがな。それでもまだ……」
「……」
「俺達はどこかで期待してしまっていたのだろうか」
《王居エンピレオ》で一行を待ち受けていたのは「特別課外活動部の未練」だった。彼へ向けられた愛憎であり、執着であり、羨望であり、……そして迷いだ。未練。彼の姿を真似て、最後にはグロテスクに崩れ落ちていった漆黒の「シャドウ」。覆いが溶け皮膚を剥がれ、剥き出しの筋繊維を晒しそれすらも消え……まるで「彼」を解体するかのように見せつけて崩壊と消滅をしたそれに、最後まで確たるかたちを持って残されていたのは銀色に光るヘッドホンだった。それすらも蒼い蝶になって失われてしまったが、光と文字コードの粒子に分解されていく中で一際存在感を放つあれが、恐らくは「有里湊」の象徴であったのだろうと思う。
両手を広げた姿はまるで死の再宣告をしているかのようだった。死が構成されていくのだ。爪から浮かび剥がれていった「DEATH」の五文字。死神を宿し魅入られていた少年が『死』そのものになったことを、今思えばあの光景は暗示していたのかもしれなかった。
如何なる人間であれ、人である以上、肉体を失った以上死から逃れることは出来ないのだと。
「さて……美鶴。取り敢えずは目下の問題だな。今夜は満月だそうだが、お前はどうするつもりだ」
話に区切りを付け、一応聞いておくが、と前置いて尋ねた真田に美鶴は即答する。
「影時間にか? 決まっている。巡回だ」
「そう言うと思ったよ……」
「なんだ。文句があるのか」
真田は頭を抱えてこれみよがしに溜め息を吐いた。美鶴の表情がやや険しくなる。
「大有りだ。俺達はもうペルソナを使えないんだぞ。慎達から聞いた話じゃ、大型シャドウに近付かなくとも無数の下級シャドウがポップして市街地はとてもじゃないが安全とは言えない状況だそうだ。少しは自分の身を案じてくれ。美鶴はいつもそうだ、お前、まさか自分の今の立場が分からないわけではないだろう」
「下級シャドウぐらい大した敵ではあるまい。私の剣の錆にしてくれる」
「油断は死を招くぞ。桐条の組織を路頭に迷わせる気か」
「無論そのような気はないとも。なんだ明彦、歳を取って随分と臆病になったんじゃないか? 昔はそんな弱音を吐く男ではなかった」
「臆病になったんじゃない。慎重になったんだ。命あっての物種、ということを嫌というほど味わってきたからな」
「それを臆病だと言うんだ。――まあいい。誰が何と言おうと私の選択は変わらない」
しれっとしている。せめてアイギスでも連れてきていれば状況は違っただろうが、彼女は彼女で忙しく駆り出されていて今回はスケジュールが噛み合わなかったらしい。
時計の針は午後十時を少し回ったあたりを指して、規則正しくカチコチと時を刻み続けている。どうあろうと二時間後には市街地に立っているのだろう。そう思った。
真田は遅まきに湊が「気を付けて」ではなく「目を離さない方がいい」と言った意味を否応もなく改めて思い知らされた。そうだ。美鶴はこうと決めたことには一歩も退かない。手綱を握れない以上真田に出来るのは「目を離さず」、出来る限り彼女を守ってやることだけだ。変わらないな、と内心で呟いた。
変わらない。図体ばかりでかくなって、あの頃からずっと。
そして場面は再び、影時間へ戻ってくる。
湊が向かったのとは別の場所へ飛び出し、現状の調査及び認識を行う。こういった事態のお決まりのパターンで、美鶴の打ち出したプランは途中までは上手くいっていた。確かに雑魚シャドウは街中を跋扈していたが、基本的に湊の方に集中して出現しているらしく、命に関わる程の強さでも量でもない。「マーヤ」「グビド」系の下級種ばかりでリポップの頻度も低い。二人は知らないが、それは黒猫が先回りして道を開いていたからだ。しかしナオの手回しにも限度がある。湊との連携が完全になるよりも速く二人がそこへ辿り着いてしまったことはナオにとっての誤算だった。
《満月シャドウ》「エンプレス」及び「エンペラー」。
今真田と美鶴の正面に屹立しているのは間違いなく、十年前に「山岸風花救出作戦」の際交戦した二体のボスシャドウそれそのものだった。データとしては覚えている。特性はアルカナシフト、数ターンごとに弱点及び得意属性が切り変わる面倒な技だ。今思えばニュクス・アバターの持つ能力の叩き台だったのかもしれない。まあそれは蛇足だ。
当時こそ苦労したもののこの二体のポテンシャルは然程高くもなく、せいぜいがレベル十六かそこらであろう、と後にアナライズをしたシャドウのデータをまとめている折に風花はそう言っていた。その能力値それそのままなら、確かにこの二体のボスシャドウは強敵ではない。
しかしそれもある一定の強さに達したペルソナ使いにとっては、だ。
「……ニュクス・アバターよりは遥かに弱いだろうが」
生憎と所持している武器はコルトライトニングやレベッカ等の銃器類に留まる。美鶴は一応レイピアを携行していたようだが、まずその装備で相手に出来る敵ではない。せめて、と歯ぎしりをした。ニュクス・アバターと戦闘をした時に湊が用意した武器があればまだ違ったのだが。
尤も体はあの頃に比べれば幾らも鈍っているだろうし、若さもない。何より、気力がまるで足りていなかった。
「美鶴。撤退するぞ。どうにか有里達のところまで戻れば何とかなるだろう、俺達ではどうにも出来ない」
「……しかし!」
「無駄だ、と言っているんだ。わからないのか?!」
真田が叫ぶ。さしもの美鶴もその鬼気迫る表情に思うところがあったらしく、言葉を収めた。じり、と足を動かすが二人の存在に気付いてしまった二体もまた歩を詰めて来ている。追い着かれるのは時間の問題だった。余裕はない。
やや離れた屋根の上に隠れ、シャドウのマーク範囲外で状況を見ていた黒猫が構えを取る。ナオとカズが今回湊に言われたのは、「ぎりぎりまで二人を信用して欲しい」というお願いごとだった。しかしそのぎりぎりとはどのラインなのか。注目を集めてしまうことを避けるために今はペルソナも召喚していない。召喚には秒単位だがラグが生じるからそこも見極めて動く必要がある。
(……どうするよ、おい)
(死んだら取り返しが付かない。だが俺達がペルソナを喚べば必然、敵のターゲットがこっちに向く。湊は真田なら出来るはずだと言っていた。俺としても、湊を疑うつもりはないんだけど……)
(だよなあ……。あの人にはその気がない。本当に、喚べるのか?)
カズが濁した言葉を引き継いでナオがぼやく。銀色のピアスが紅の月光を浴びて鈍く光った。美鶴は知らないが、少なくとも真田は召喚安定用の媒体を携帯しているはずだ。だがそれを取り出そうともしない。完璧にただのお守りだ。いくら素養があったって、本人が「喚べるはずがない」と思い込んでいたらどうしようもないのだ。
満月シャドウとの距離はますます詰まっていく。状況の悪さにとうとうカズが堪え切れなくなったようで、苛立たしげに鼻を鳴らした。
(湊はああ言ったけど俺は真田を信用し切れない!)
(まだもう少しだけ待てって、最後まで結果はわからないんだ)
(だーもう、これだから理屈屋は! 尚也体貸せっ、俺のリリムで一先ず足止めるぞ!)
(おい待て、和也!)
痺れを切らして主導権を奪うと黒猫――カズは走り出す。飛び上がり、ナオの制止を振り切って月アルカナのリリムを呼ぼうと意識を集中し出した。ナオによってチャージされていた皇帝アメン・ラーが人格の交代によってキャンセルされたところに精神操作系を得意とするペルソナの姿を思い描く。しかしカズはリリムの召喚を成功させることが出来なかった。
「な……?!」
猫の姿のまま、カズが思わず声を上げる。やんわりと、しかし確かに、どこからともなく現れた二つの人影が黒猫を咎めていた。
「――美鶴!」
粉塵があがる。悪視界で銃器は使用出来そうにもない。エンぺラーとエンプレスが出現してから雑魚が寄ってこなくなったのが唯一の救いだったが、そんなことは気休めにもならない瑣末なことだった。圧倒的だ。生身の人間がなんとか出来る相手ではない。
ペルソナ使いが一人でもいれば勝手は違っただろう。湊がそれを見越していなかったとは思えないから、恐らく彼は真田を信用していたのだと思う。真田なら美鶴の抑止力になり得るだろうと考えていたのか、或いはもしかしたら自衛が出来るかもしれないと期待していたのか。
(……無理だ。俺はもうペルソナの「定年」を迎えている)
反射的に美鶴に駆け寄って、状況がどれ程絶望的であるのかを真田は瞬時に理解した。せざるをえなかった。エンペラーが嬉々として不愉快な声音を張り上げ、両腕を振り回す。左腕が直撃した箇所からひびが入ってコンクリートのビルが崩壊していった。状況は困難を極めていて、命をまともに守れるかどうかすら既に怪しい。
ペルソナがあれば、と今更になって思う。こんなに悔しい思いをせずに済んだ。美紀を助けられなかった時と同じだ。力がないばかりに、無力であるばかりに、また失うのか。情けなかった。
「ここまでか」
力無く項垂れる。しかし、無力とは罪だな、と弱々しく繰り返して面を上げるとそこで真田は信じられない光景を目にした。
先程まで豪速で行動していたシャドウが、世界中の時が止まってしまったかのようにのんびりと動いている。それだけじゃない。懐かしい後姿が視界に映り込んでいた。真田は思わず息を呑んで目を見開く。指先が震えているのが自分でも分かった。
だがそれも仕方のないことだろう。真田の目に映った人影は、十年前に天田を庇いストレガ・タカヤの凶弾に撃たれて命を落とした朋友の姿だったのだ。
荒垣真次郎。
『また諦めンのかよ、アキ』
「――シンジ?」
荒垣の亡霊は真田の問い掛けに返事を寄越さない。だからこれはやはり、真田が造り出した幻覚に過ぎないのだろう。死の間際に見ている都合の良い幻だ。だがそうだとしても、それが如何程のことか、そう思えた。亡霊がふん、と鼻を鳴らす。その隣にもう一人男が現れて眼鏡を指で押し上げる仕草をした。やや神経質そうな横顔で溜め息を吐く。
男は一年前まで綾凪の警察署長として働いていた神郷兄弟の長兄でありまた警察組織に入ってからの真田の仲間であった。
『君は、やれる筈だろう』
二人の亡霊がスローモーションで動く世界の中に降り立って真田を見返している。
『震えてる場合じゃねえだろ』
ぶっきらぼうに声を掛けて荒垣が指し示す。エンペラーのブリキの兵隊のような腕が徐々に徐々に真田と美鶴に迫ってきていた。質量は計り知れない。これをまともに喰らったらおしまいだ。
『急げ。君の意思が《年齢制限》に、誰かが定めた愚にもつかないルールに勝るというのならば』
諒が言った。エンペラーの腕との距離は既に頭一つ二つ分に過ぎない。生唾を呑む。右手に召喚銃を握り込み、そして徐に頭部に当てた。心音が早鐘のようだ。『行け、アキ!』、荒垣が語調を荒くする。諒もだ。『守るべきもののために!』
「――ペルソナ!」
我武者羅に叫んだ。
真田は銀色のくすんだ引鉄に指を伸ばし、迷うことなくそれを引き抜く。最早躊躇う理由などなかった。どこにもだ。
召喚銃から発生した煙の中から真田の心の形、ペルソナ「カエサル」が長い沈黙を破って降臨する。屹立する皇帝の姿に二体の満月シャドウが攻撃の手を止め、たじろぐのを認めると真田は額の汗を拭った。心臓は高鳴っていたが、頭は不思議な程に冴えている。
「目には目を、歯には歯を、女帝皇帝には女帝皇帝を宛がおうってか。面白味がないな。むしろ滑稽だ……」
鎮座する満月シャドウは「エンプレス」「エンペラー」の二体。対して、真田が宿す「カエサル」もまた「皇帝」アルカナを司るものだった。そして、かつて前線で駆けていた美鶴のペルソナ「アルテミシア」が司るものも「女帝」。ここまで綺麗にお膳立てされているといっそ笑えてくる。
地にへたり込んでいる美鶴を庇うように立ち回り、カエサルに威嚇のマハジオを撃たせて真田は息を呑んだ。酷く気分が高揚するのを感じて、生唾を飲み込む。
戦闘に際してこうしてまじりっけなく「ワクワク」するのはいつぶりだっただろうか。随分と久しぶりのような気がする。荒垣が死んだあの時から、こんな気持ちになる余裕などなかった。それからは責任と気負いと後悔が真田に付いて回った。やがて「年齢制限」を迎えて「大人」になって、無責任な少年の心はどこかへ行ってしまった。
「……一杯食わされたな、有里に」
少年の輪郭ばかりがあどけない顔が甦る。ふと、あの抑揚の乏しい少年は今の真田の姿を見てどんな顔をするだろうかと考えた。ひょっとしたら少しぐらいは驚いて見せるのだろうか? いや、そんなことはないか。あの全てを見透かしているかのように達観している少年は、口端でにやりと笑いながら「ほら、だから僕言ったじゃないですか」などと意地悪く言うのだ。
「明彦……」
「美鶴。少しだけ待ってろ。さっさと倒して有里を捕まえる」
『引鉄を引くことの意味を、あなたは知っているはずだから』――真田は「ああ、わかっている。わかっているとも」、そう繰り返す。撃鉄の起きた銃がこの手には握られていて、その引鉄を引くことが出来る。理由はたった一つしかない。とても単純で明快だ。
「女一人守れないようじゃ、会わせる顔がない」
――ならば守るべきもののためにこの引鉄を引こう。
カエサルがジオダインを放つのと同時に、真田は二体のシャドウ目掛けて真っ直ぐに飛び上がった。
暗闇にもだ。ずっとそうしてきた。人を遠ざけ馴れ合いを良しとせず殻の中に引き籠もった。
自分が何か行動する度に何かを失った。いつもいつも結局最後には失敗して手のひらから大事なものを取りこぼした。世界は冷徹で、自らは浅薄だ。人間一人の力というのは酷くちっぽけで、思い知らされるようだった。
《這い寄る混沌》に目を付けられた周防達哉の、それが罪であり罰だった。
「……ここにも随分慣れた」
闇に慣れた視界の中でぼんやりと浮かび上がる、火の点かないライターを手の中でもてあそぶ。カチカチというさびれた音に思い出すのは失われてしまった世界のことだった。かつて達哉が生きていた世界。そして一時だけ身を置いた「やり直した世界」……兄は、舞耶に惚れていた克哉は彼女と上手くやっているだろうか? 仲間達は。世話になった人達は幸福な世界を享受できているだろうか。噂に造り変えられたりしない、失敗しなかった世界を……
周防達哉の犠牲の元成り立つ世界を。
「舞耶姉は、兄さんだから任せるんだからな。俺の知らないどこぞの男に取られてみろ。一生恨むぞ。俺の初恋の人なんだ」
這い寄る混沌ニャルラトホテプはフィレモンと対を成す存在だ。人の可能性を見出し希望を託すフィレモンとは逆に人の欲望を拡大し傀儡化し利用して時には世界を滅ぼそうともする。しかしその行為に理由はない。快楽主義者なのだ。面白い玩具か否か、行動原則はそこに集約されている。
周防達哉はニャルラトホテプに見初められた玩具の中でもとりわけ良く出来た一つだった。世界一つ作り出す程の精神力を持ちながら人間らしいエゴイズム――欲望を捨て切れなかった。生々しく醜悪な人間。達哉は強大な力をその内に秘めた可能性であったが、しかし最後には整合性を乱す特異点にしか成り得なかった。この崩壊したかつて世界であった場所に還ってきた時ニャルラトホテプは嗤ったものだ。『ああ、周防達哉、貴様は失敗したのだ。愚かしい、実に愉快極まりない。貴様は所詮その程度でしかない!』……不愉快なことに正論だった。
「ペルソナ……心の仮面、抵抗するための力。ここじゃ、あんまり上手くは使ってやれないが。藤堂は上手くやっているだろうか」
かの南条や桐島らの友人であるというピアスの青年は非常に不幸なことに、ニャルラトホテプにあちら側から捕まえられてきてしまったらしかった。あの迷惑な存在が理由なく行動を起こすのはいつものことだが、罪と罰を抱える故にこの仕打ちも然るべきかと思える達哉に対して藤堂尚也にはそこまでのいわれがない。理不尽に思った達哉の悪足掻きと外界からの何か大きな力を持つ「少年」の働きかけが偶然噛み合ったために、なんとか彼をここから外に出してやることには成功したがそれも完全ではなかった。彼が還るべき時空ではなく少年のいる未来にあたる時間へしか脱出出来なかった上、人間の姿を保てなかったのだ。しかしそれでもここに囚われているよりは幾らかマシだろう。この暗闇はそういう場所だ。
それにしても、思い返してみると例の「少年」はたいそうおかしな存在だった。彼の内には死と世界が同居していた。一応ペルソナ使いなのだろうとは思われたが、それにしてはアルカナに節操もないようだ。
彼は無限で永遠で終焉だった。神ではない。そんなものはいない。ニャルラトホテプやフィレモンのように外から覗き見る者でもない。だが、人間でもない。どっち付かずの青色の少年。紺碧の髪に隠れた灰色の眼には、死と希望が映り込んでいる。
『僕は……湊。昔は有里湊って呼ばれてた。あのさ……達哉』
『必ず君を助けるから。僕の《ユニバース》を使っても。たとえ世界がそれを阻んでも。運命なんてくそくらえだ』
「『運命なんてくそくらえ』か。俺も……」
少しだけ見た少年の姿を思い浮かべて達哉は目を閉じる。闇が濃くなる。僅かなノイズも立ち消えて気が狂わんばかりの静寂に辺りが支配される。
「――ずっとそう思ってる」
だけど運命は絶対の拘束力を持って達哉を離そうとしない。
沈むような眠りに落ちていく最中で達哉は遠い世界のことを思った。最後に人の住む世界に立っていたあの別れの日からどれ程の月日が経ったのだろう。あれから知人達はどうなったのだろうか。幾つの歳を重ねているのだろうか。達哉にはそれがわからない。
自問自答に意味はなく答えもない。それは眠りに就く度に繰り返す、もう幾度目かもわからない儀式にも似た何かだった。
◇◆◇◆◇
「本当にあんなのが十二体も出るんだな?」
「全部でだよ、慎兄。もう一体は葬った後だし。それにこの辺はまだまだ大したことない。最後の『ハングドマン』をどれぐらい速く片付けられるかは正直自信ないけど……」
ペルソナ「アベル」を顕現させて走り、遠目に《満月シャドウ》を見上げながら慎は尋ねた。湊はけろりとして立っている。ヘッドホンを耳から外して首に掛け、「綾時」と彼の守護者の名前を呼んだ。
「解析」
『分かってる。――ボスタイプシャドウ『プリーステス』、アルカナは女教皇。呪殺・破魔無効、氷結反射。さほど強くはないよ。君ならすぐに終わる』
僕が出る程でもないね、と綾時が結果を言い渡す。湊はぱちくりと目を見開いて「さほどって、丸っ切りってこと」と拍子抜けな声を出した。
「ってことは、この前の魔術師ももしかして弱かった……というか記録のままの強さだったの?」
『うん……恐らくね。君の全力はちょっとオーバー過ぎたかも。でもその分わかったこともある。その体じゃ、あんまり無理は出来ないんだ。デスを使用し続けると体力に限界が来ちゃうのかな、君がこの前僕を無理矢理引っ込めたのってそういうことでしょう』
二人の会話を横に聞きながら慎は湊と出会った時のことを回想した。意識をぷつんと失ったみたいにペルソナが消滅し、急速に落下していた小柄な体。能力が強すぎて容れもののポテンシャルが追い着かないのだ。オーバーフロー状態に陥っていたのだろうがしかし、自分の能力限界を計り切れずに自滅してしまってはどうしようもない。
湊のペルソナ能力が酷く強烈なのだということは一応自覚しているつもりだったが、よもやこれ程までとは。子供の姿をして慎を兄と慕ってはいても、その中身は決してそんなに生易しいものではないのだと改めて思い知らされたようなそんな心地になる。
『どうしてかはわからないけれど、今の君は万全の状態じゃないんだ。この前は運よく助けて貰えたけど毎回そういうわけにもいかない。実戦で色々試しながらリミッターの原因は探すとして、まずは倒れないようにコントロールするのが先だと思うよ』
「……か。ま、デスはとびきり負荷が大きいししばらくは封印しよう。ごめん綾時」
『なんで君が謝るの』
「だって、暴れ足りないでしょ」
違うの? と灰色の瞳が尋ねて来る。否定をし難い視線というものを体現したらこうなるのだろうと思った。湊の持つオーラというべきか、魅力、カリスマ性の高さが滲み出ている気がする。そういえば真田が昔話をする時ぽつりとこう漏らしてはいなかったか。「有里は変な奴だったが、学園中探してもあいつを嫌ってる人間というのはいなかった。誰も彼もが好ましく接していた。今思えばあのカリスマ性はどこか異常だったとも思う」、と。
しかし綾時はその視線に一秒足りとも揺れることなくきっぱりと首を振って「ううん」、とこともあろうに否定の意を躊躇いなく示した。
『それは君が、でしょ。尚也と和也もそうみたいだけど。第一僕は平和主義者なんだよ。女の子は好きだけど、戦うのは別に好きでもないし』
「嘘つけ。本当の平和主義者っていうのは節操なく女の子に声をかけてハーレム状態を作ったりしない」
『……湊君、きみ、それそっくりそのまま返されても文句言えないよ?』
それに僕の大事な人は君一人だけだし。綾時はそう言って湊の中に引っ込んだ。湊も当たり前にその言葉を受けて、それから何もなかったみたいに澄ました顔で召喚銃の引鉄を引き抜く。ぱきん、というお決まりのサウンドとあの青白いライトエフェクトを伴って「綾時」でもなく「デス」でもないペルソナが召喚される。
「行こう、慎兄。時間取らせちゃってごめん。洵兄も待ってくれてるし、さっさと終わらせよう。慎兄は好きに動いて、僕がそれに合わせる」
「あ、ああ。……時に湊、つかぬことを聞くけど」
「何?」
「その冷蔵庫みたいなペルソナは一体」
「キングフロスト。フロスト族の王様。ジャックフロストが集まって出来た伝説のキングらしいよ。かわいいから結構、好き」
「そうか……」
マイペースに走っている。そうこうしている内に「プリーステス」との距離も戦闘に適したラインまで詰まり、二人はそこで足を止めた。顔面を何か呪いめいた文字に埋め尽くされた包帯で覆い、ゴルゴンのような髪をくゆらせている。近付くにつれて大気が冷えていく感覚に体を震わせた。先に「氷結反射」と綾時が言っていたように思うが、なるほどこの寒さは確かに氷を得意とするシャドウならではのものだろう。
プリーステスが敵対者二人の姿を認めたしく、口裂け女よろしく大口を開いて耳をつんざくような悲鳴を上げる。
「タルカジャかけるから、物理で押して! それとラストアタックは任せてもいいかな。『ペルソナを切り離す異能』がどういうふうに作用するか見てみたい」
「任せとけ。――アベル!」
慎の意思に反応してアベルが空へ飛び上がる。二回目の満月シャドウ討伐は、然程の混乱を生むことなく終わるだろうとこの時湊は考えていた。
◇◆◇◆◇
時間は、影時間よりもいくらか前に戻る。
桐条美鶴は真田明彦と向かい合って、陰鬱な面持ちで両腕を組んでいた。一言で言えば、しょげている。桐条という一大組織を気丈に一人で支えている女王然とした彼女が今この場においては叱られた子供同然に落ち込んでいた。
「……私は想定していなかったんだ。勿論『彼が』いるという事態も想定していなかったし、よもや彼がああまで頑なに……拒絶をすると、思っていなかった。とんだ甘えだ。私達は彼一人に全てを押し付けたというのに」
「美鶴。あいつが言っていたこと、聞こえていなかったのか? あいつは『仲間のことは好き』なのだと言ったし、突き放すつもりもなかったとそう言っていたぞ」
「しかし私は……私には、彼がどうしても『有里湊』にしか見えないのだよ。姿が子供返りしていても、いくら否定されようとも。あの少年は私にとって紛うことなく特別課外活動部リーダーの少年なんだ。十年と少し前に息を引き取ったはずの、あの」
「……だが」
「みなまで言わずともいい。感情の問題なんだ。理論としては……わかっている」
有里湊は死んだ。メティスの言葉によればそれは肉体の死で、精神は今も例の扉に括り付けられて生きているのだというが、しかしそれは決定的に紛れもなく「人間としての死」であるのだと彼女は断じていた。だからきっと今綾凪に現れた「ヘッドホンの少年」は有里湊の精神、もしくはそれの残留思念、そういった類のものが肉体を得て活動しているに過ぎない存在なのだろう。そういう意味で神郷湊は確かに有里湊では有り得なかった。肉体の識別コードがまるっきり別物だ。
だが、と美鶴は呟く。それでも有里湊を知る者にとって神郷湊は、そう名乗る少年の存在はあの日奇跡を起こした少年と同一の存在だった。
死で出来上がった、死と夜の女王そのものに成り果てたと自らを断じた湊の姿は痛ましくさえあった。あのぞっとしない表情。「奇跡を一つ起こしたら」、と彼はそう言った。自分一人のために行使出来る奇跡なんて誰も持ちあわせてはいない。使えるのは汚い手練手管ばかりだ。
酷く複雑な気分だった。彼に再び出会えた喜びは罪悪感と動揺とで帳消しどころかマイナスにならんという勢いだ。
「そういえば……彼はコロッセオ・プルガトリオのことに触れていたな。今となってはあれすらも懐かしい過去だ。彼は……厭うていたのだな、呼び戻されることを。ゆかりが聞いたら泣き出しそうだ。一度だけ彼女を絶対に味方すると前々から決めていた私にとってもあの場所はなかなかしんどいものがあったというに、それをああもすげなく拒否されたとなっては」
「岳羽か……。彼女はまだ『岳羽』なんだったな、確か。いや、岳羽に限らないか。俺達はあいつに……有里に縛られ過ぎていたのかもしれない。あの『三月三十一日』にそのことに思い当たったはずなんだがな。それでもまだ……」
「……」
「俺達はどこかで期待してしまっていたのだろうか」
《王居エンピレオ》で一行を待ち受けていたのは「特別課外活動部の未練」だった。彼へ向けられた愛憎であり、執着であり、羨望であり、……そして迷いだ。未練。彼の姿を真似て、最後にはグロテスクに崩れ落ちていった漆黒の「シャドウ」。覆いが溶け皮膚を剥がれ、剥き出しの筋繊維を晒しそれすらも消え……まるで「彼」を解体するかのように見せつけて崩壊と消滅をしたそれに、最後まで確たるかたちを持って残されていたのは銀色に光るヘッドホンだった。それすらも蒼い蝶になって失われてしまったが、光と文字コードの粒子に分解されていく中で一際存在感を放つあれが、恐らくは「有里湊」の象徴であったのだろうと思う。
両手を広げた姿はまるで死の再宣告をしているかのようだった。死が構成されていくのだ。爪から浮かび剥がれていった「DEATH」の五文字。死神を宿し魅入られていた少年が『死』そのものになったことを、今思えばあの光景は暗示していたのかもしれなかった。
如何なる人間であれ、人である以上、肉体を失った以上死から逃れることは出来ないのだと。
「さて……美鶴。取り敢えずは目下の問題だな。今夜は満月だそうだが、お前はどうするつもりだ」
話に区切りを付け、一応聞いておくが、と前置いて尋ねた真田に美鶴は即答する。
「影時間にか? 決まっている。巡回だ」
「そう言うと思ったよ……」
「なんだ。文句があるのか」
真田は頭を抱えてこれみよがしに溜め息を吐いた。美鶴の表情がやや険しくなる。
「大有りだ。俺達はもうペルソナを使えないんだぞ。慎達から聞いた話じゃ、大型シャドウに近付かなくとも無数の下級シャドウがポップして市街地はとてもじゃないが安全とは言えない状況だそうだ。少しは自分の身を案じてくれ。美鶴はいつもそうだ、お前、まさか自分の今の立場が分からないわけではないだろう」
「下級シャドウぐらい大した敵ではあるまい。私の剣の錆にしてくれる」
「油断は死を招くぞ。桐条の組織を路頭に迷わせる気か」
「無論そのような気はないとも。なんだ明彦、歳を取って随分と臆病になったんじゃないか? 昔はそんな弱音を吐く男ではなかった」
「臆病になったんじゃない。慎重になったんだ。命あっての物種、ということを嫌というほど味わってきたからな」
「それを臆病だと言うんだ。――まあいい。誰が何と言おうと私の選択は変わらない」
しれっとしている。せめてアイギスでも連れてきていれば状況は違っただろうが、彼女は彼女で忙しく駆り出されていて今回はスケジュールが噛み合わなかったらしい。
時計の針は午後十時を少し回ったあたりを指して、規則正しくカチコチと時を刻み続けている。どうあろうと二時間後には市街地に立っているのだろう。そう思った。
真田は遅まきに湊が「気を付けて」ではなく「目を離さない方がいい」と言った意味を否応もなく改めて思い知らされた。そうだ。美鶴はこうと決めたことには一歩も退かない。手綱を握れない以上真田に出来るのは「目を離さず」、出来る限り彼女を守ってやることだけだ。変わらないな、と内心で呟いた。
変わらない。図体ばかりでかくなって、あの頃からずっと。
そして場面は再び、影時間へ戻ってくる。
湊が向かったのとは別の場所へ飛び出し、現状の調査及び認識を行う。こういった事態のお決まりのパターンで、美鶴の打ち出したプランは途中までは上手くいっていた。確かに雑魚シャドウは街中を跋扈していたが、基本的に湊の方に集中して出現しているらしく、命に関わる程の強さでも量でもない。「マーヤ」「グビド」系の下級種ばかりでリポップの頻度も低い。二人は知らないが、それは黒猫が先回りして道を開いていたからだ。しかしナオの手回しにも限度がある。湊との連携が完全になるよりも速く二人がそこへ辿り着いてしまったことはナオにとっての誤算だった。
《満月シャドウ》「エンプレス」及び「エンペラー」。
今真田と美鶴の正面に屹立しているのは間違いなく、十年前に「山岸風花救出作戦」の際交戦した二体のボスシャドウそれそのものだった。データとしては覚えている。特性はアルカナシフト、数ターンごとに弱点及び得意属性が切り変わる面倒な技だ。今思えばニュクス・アバターの持つ能力の叩き台だったのかもしれない。まあそれは蛇足だ。
当時こそ苦労したもののこの二体のポテンシャルは然程高くもなく、せいぜいがレベル十六かそこらであろう、と後にアナライズをしたシャドウのデータをまとめている折に風花はそう言っていた。その能力値それそのままなら、確かにこの二体のボスシャドウは強敵ではない。
しかしそれもある一定の強さに達したペルソナ使いにとっては、だ。
「……ニュクス・アバターよりは遥かに弱いだろうが」
生憎と所持している武器はコルトライトニングやレベッカ等の銃器類に留まる。美鶴は一応レイピアを携行していたようだが、まずその装備で相手に出来る敵ではない。せめて、と歯ぎしりをした。ニュクス・アバターと戦闘をした時に湊が用意した武器があればまだ違ったのだが。
尤も体はあの頃に比べれば幾らも鈍っているだろうし、若さもない。何より、気力がまるで足りていなかった。
「美鶴。撤退するぞ。どうにか有里達のところまで戻れば何とかなるだろう、俺達ではどうにも出来ない」
「……しかし!」
「無駄だ、と言っているんだ。わからないのか?!」
真田が叫ぶ。さしもの美鶴もその鬼気迫る表情に思うところがあったらしく、言葉を収めた。じり、と足を動かすが二人の存在に気付いてしまった二体もまた歩を詰めて来ている。追い着かれるのは時間の問題だった。余裕はない。
やや離れた屋根の上に隠れ、シャドウのマーク範囲外で状況を見ていた黒猫が構えを取る。ナオとカズが今回湊に言われたのは、「ぎりぎりまで二人を信用して欲しい」というお願いごとだった。しかしそのぎりぎりとはどのラインなのか。注目を集めてしまうことを避けるために今はペルソナも召喚していない。召喚には秒単位だがラグが生じるからそこも見極めて動く必要がある。
(……どうするよ、おい)
(死んだら取り返しが付かない。だが俺達がペルソナを喚べば必然、敵のターゲットがこっちに向く。湊は真田なら出来るはずだと言っていた。俺としても、湊を疑うつもりはないんだけど……)
(だよなあ……。あの人にはその気がない。本当に、喚べるのか?)
カズが濁した言葉を引き継いでナオがぼやく。銀色のピアスが紅の月光を浴びて鈍く光った。美鶴は知らないが、少なくとも真田は召喚安定用の媒体を携帯しているはずだ。だがそれを取り出そうともしない。完璧にただのお守りだ。いくら素養があったって、本人が「喚べるはずがない」と思い込んでいたらどうしようもないのだ。
満月シャドウとの距離はますます詰まっていく。状況の悪さにとうとうカズが堪え切れなくなったようで、苛立たしげに鼻を鳴らした。
(湊はああ言ったけど俺は真田を信用し切れない!)
(まだもう少しだけ待てって、最後まで結果はわからないんだ)
(だーもう、これだから理屈屋は! 尚也体貸せっ、俺のリリムで一先ず足止めるぞ!)
(おい待て、和也!)
痺れを切らして主導権を奪うと黒猫――カズは走り出す。飛び上がり、ナオの制止を振り切って月アルカナのリリムを呼ぼうと意識を集中し出した。ナオによってチャージされていた皇帝アメン・ラーが人格の交代によってキャンセルされたところに精神操作系を得意とするペルソナの姿を思い描く。しかしカズはリリムの召喚を成功させることが出来なかった。
「な……?!」
猫の姿のまま、カズが思わず声を上げる。やんわりと、しかし確かに、どこからともなく現れた二つの人影が黒猫を咎めていた。
「――美鶴!」
粉塵があがる。悪視界で銃器は使用出来そうにもない。エンぺラーとエンプレスが出現してから雑魚が寄ってこなくなったのが唯一の救いだったが、そんなことは気休めにもならない瑣末なことだった。圧倒的だ。生身の人間がなんとか出来る相手ではない。
ペルソナ使いが一人でもいれば勝手は違っただろう。湊がそれを見越していなかったとは思えないから、恐らく彼は真田を信用していたのだと思う。真田なら美鶴の抑止力になり得るだろうと考えていたのか、或いはもしかしたら自衛が出来るかもしれないと期待していたのか。
(……無理だ。俺はもうペルソナの「定年」を迎えている)
反射的に美鶴に駆け寄って、状況がどれ程絶望的であるのかを真田は瞬時に理解した。せざるをえなかった。エンペラーが嬉々として不愉快な声音を張り上げ、両腕を振り回す。左腕が直撃した箇所からひびが入ってコンクリートのビルが崩壊していった。状況は困難を極めていて、命をまともに守れるかどうかすら既に怪しい。
ペルソナがあれば、と今更になって思う。こんなに悔しい思いをせずに済んだ。美紀を助けられなかった時と同じだ。力がないばかりに、無力であるばかりに、また失うのか。情けなかった。
「ここまでか」
力無く項垂れる。しかし、無力とは罪だな、と弱々しく繰り返して面を上げるとそこで真田は信じられない光景を目にした。
先程まで豪速で行動していたシャドウが、世界中の時が止まってしまったかのようにのんびりと動いている。それだけじゃない。懐かしい後姿が視界に映り込んでいた。真田は思わず息を呑んで目を見開く。指先が震えているのが自分でも分かった。
だがそれも仕方のないことだろう。真田の目に映った人影は、十年前に天田を庇いストレガ・タカヤの凶弾に撃たれて命を落とした朋友の姿だったのだ。
荒垣真次郎。
『また諦めンのかよ、アキ』
「――シンジ?」
荒垣の亡霊は真田の問い掛けに返事を寄越さない。だからこれはやはり、真田が造り出した幻覚に過ぎないのだろう。死の間際に見ている都合の良い幻だ。だがそうだとしても、それが如何程のことか、そう思えた。亡霊がふん、と鼻を鳴らす。その隣にもう一人男が現れて眼鏡を指で押し上げる仕草をした。やや神経質そうな横顔で溜め息を吐く。
男は一年前まで綾凪の警察署長として働いていた神郷兄弟の長兄でありまた警察組織に入ってからの真田の仲間であった。
『君は、やれる筈だろう』
二人の亡霊がスローモーションで動く世界の中に降り立って真田を見返している。
『震えてる場合じゃねえだろ』
ぶっきらぼうに声を掛けて荒垣が指し示す。エンペラーのブリキの兵隊のような腕が徐々に徐々に真田と美鶴に迫ってきていた。質量は計り知れない。これをまともに喰らったらおしまいだ。
『急げ。君の意思が《年齢制限》に、誰かが定めた愚にもつかないルールに勝るというのならば』
諒が言った。エンペラーの腕との距離は既に頭一つ二つ分に過ぎない。生唾を呑む。右手に召喚銃を握り込み、そして徐に頭部に当てた。心音が早鐘のようだ。『行け、アキ!』、荒垣が語調を荒くする。諒もだ。『守るべきもののために!』
「――ペルソナ!」
我武者羅に叫んだ。
真田は銀色のくすんだ引鉄に指を伸ばし、迷うことなくそれを引き抜く。最早躊躇う理由などなかった。どこにもだ。
召喚銃から発生した煙の中から真田の心の形、ペルソナ「カエサル」が長い沈黙を破って降臨する。屹立する皇帝の姿に二体の満月シャドウが攻撃の手を止め、たじろぐのを認めると真田は額の汗を拭った。心臓は高鳴っていたが、頭は不思議な程に冴えている。
「目には目を、歯には歯を、女帝皇帝には女帝皇帝を宛がおうってか。面白味がないな。むしろ滑稽だ……」
鎮座する満月シャドウは「エンプレス」「エンペラー」の二体。対して、真田が宿す「カエサル」もまた「皇帝」アルカナを司るものだった。そして、かつて前線で駆けていた美鶴のペルソナ「アルテミシア」が司るものも「女帝」。ここまで綺麗にお膳立てされているといっそ笑えてくる。
地にへたり込んでいる美鶴を庇うように立ち回り、カエサルに威嚇のマハジオを撃たせて真田は息を呑んだ。酷く気分が高揚するのを感じて、生唾を飲み込む。
戦闘に際してこうしてまじりっけなく「ワクワク」するのはいつぶりだっただろうか。随分と久しぶりのような気がする。荒垣が死んだあの時から、こんな気持ちになる余裕などなかった。それからは責任と気負いと後悔が真田に付いて回った。やがて「年齢制限」を迎えて「大人」になって、無責任な少年の心はどこかへ行ってしまった。
「……一杯食わされたな、有里に」
少年の輪郭ばかりがあどけない顔が甦る。ふと、あの抑揚の乏しい少年は今の真田の姿を見てどんな顔をするだろうかと考えた。ひょっとしたら少しぐらいは驚いて見せるのだろうか? いや、そんなことはないか。あの全てを見透かしているかのように達観している少年は、口端でにやりと笑いながら「ほら、だから僕言ったじゃないですか」などと意地悪く言うのだ。
「明彦……」
「美鶴。少しだけ待ってろ。さっさと倒して有里を捕まえる」
『引鉄を引くことの意味を、あなたは知っているはずだから』――真田は「ああ、わかっている。わかっているとも」、そう繰り返す。撃鉄の起きた銃がこの手には握られていて、その引鉄を引くことが出来る。理由はたった一つしかない。とても単純で明快だ。
「女一人守れないようじゃ、会わせる顔がない」
――ならば守るべきもののためにこの引鉄を引こう。
カエサルがジオダインを放つのと同時に、真田は二体のシャドウ目掛けて真っ直ぐに飛び上がった。
Copyright(c)倉田翠.