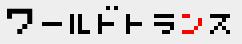Ⅵ LOVERS:君の面影、こびりついた残滓と
「アベル」の剣が、プリーステスの体を掻き消した。断末魔が悲痛な叫びとなって周囲に響く。湊はペルソナをティターニアに付け変えて神々の加護を受けた回復魔法を即座に慎に送った。慎が荒く息を吐いてアベルを納める。
「……終わり、か?」
「一応、今回は。やっぱり凄いね、慎兄のそれ……」
「ん? ああ、これ、ね」
アベルの持つ剣には「一切の副作用を伴わずにペルソナを保有者から引き剥がす」特異能力が宿っている。言うならば人間の精神、意識と無意識の狭間に強引に干渉し得る「理論的に本来存在してはならないもの」だ。
この能力は始めからアベルが持っていたものじゃない。後天的に付与されたものだ。神郷夫妻の忘れ形見だった。
祝福であり、また一つの戒めでもあった。
湊が補助に出していたペルソナを引っ込めると、間を置かず綾時が現れて『湊君』と主に声を掛ける。湊はいつもの特に高低差のない声で「慎兄の、どうだった」と問い掛けたが彼は首を振って、『それは後でね』と珍しく湊を遮った。
『湊君、感じてる? ここから北東に離れた位置で強力なペルソナ反応を検出した。同時に、ボスタイプシャドウも二体。はっきりと確定は出来ないんだけど恐らく『エンプレス』と『エンぺラー』だと思う』
「そのペルソナ反応っていうのは誰の。ナオやカズじゃなくて、僕達の知らない誰かのもの?」
『それも、断定は出来ない。でも、これはきっと真田さんの『カエサル』だ。僕が知ってる、懐かしい感じがするもの』
「……そっか。真田さん、上手く行ったんだ」
『善戦してるみたいだよ。尚也達はペルソナ、出してないみたいだね。尚也はともかく和也は我慢しきれなくなって突撃していきそうなものだけど』
「ギリギリ間に合ったのかも。荒垣さんとかひやひやして口出してきそうだし」
冗談めかして言うと、綾時がそうかもね、と頷く。『優しくて強い光を感じたような気がするんだ』と後ろ手にはにかんで、湊の肌に触れているように手のひらを添えた。
『僕にとっての君みたいなものだよ。ねえ湊君、僕は君と出逢えたことにすごく感謝してるんだ。君がいたから僕がいる。真田さんと荒垣さんもそうなんだろうね。それってとても幸せで、素晴らしいことだって僕はそう思うよ』
「そうだね。僕も……同意する。真田さんも美鶴さんも、順平、ゆかり、山岸さん、天田君、荒垣先輩、僕に関わってくれた人達……それから、綾時。ひととひとに囲まれて変わっていくのは、人間の特権なんだ。だから多分、あの時は僕も人間だったんだろうな」
『……なんで君は、この流れでそういうことを言うかな……』
「でもそれもまた一つの事実だ。綾時、思うに僕はね、愚者のコミュニティをマスターして審判のコミュニティを開いた辺りで、恐らく一線を超えてしまっていたんだよ。もう二度と後戻り出来ないっていう最終セーフティラインを乗り越えた。ポイント・オブ・ノーリターン、世の中にはそういうものが確かに存在するって今ならそう断言出来るね」
『相変わらずだ、君は』
「だってそうだろう? 僕が人間のままだったら、今ここにはいないよ」
だからこれでいいんだ。少年の姿をした何かは言った。躊躇いもせずに。
「これでいい。だから僕は、慎兄と洵兄に会えた。結祈に名前を貰った。ここに降り立つことになったのも、一つ一つ意味のあること」
綾時にはそれが少し切ない。
◇◆◇◆◇
影時間が明けかけて、空にはうっすらと緑色の残滓が残っている。だがそれもすぐに消えて、月がいつもの黄金色を取り戻した。冷めた海風がゆるゆると吹きつけて、海辺の砂浜に座り込んでいる真田の肌をほのかな磯の匂いでかすめていく。
カエサルはもう真田のそばに出てはいなかった。召喚銃の中の形のない銃弾――真田の心の中、に還っていったのだと思う。
隣でぴんと背を伸ばして立っている美鶴はどこか不満気な色を覗かせて海の向こうを見ていた。地平線より遠いどこかに、荒垣と諒の亡霊が消えていったとでも考えているのかもしれない。
それとは別に、彼女が不満そうな理由は考えるまでもなく二つあった。一つは美鶴の知らない男が荒垣と共に現れたこと。もう一つは、真田だけがペルソナを呼び出せたことだ。年齢制限は、二人揃って数年前に迎えていた。
「明彦、彼は」
「俺の同僚で……警察組織内部での信頼出来る人間で……『共犯者』だった。『神郷諒』。神郷兄弟の長兄だ。昨年亡くなった」
「……そうか」
「美鶴には言っていなかったな、そういえば。伏せていたと言えば、そうだ。お前に余計な心配を掛けたくなかったし、プライドめいたものもあった」
異例の出世を遂げている真田には何かとやっかんでくる者も多い。くだらない妬みや痛ましい羨望、ありとあらゆる妨害、そういったものを一人で対処していくのにも限度がある。はじめはそういったきっかけで知り合い、やがて二人は互いの秘密を知ることになった。ペルソナ能力だ。
神郷諒は図抜けた能力を持つ、弟の慎と同じ特A潜在者としてリストに名を連ねられていた。基本的に特別課外活動部に所属していたメンバーも自然覚醒者であるためそこに並べられるのだが、やはり普通はそうそうひとところには集まらないものらしい。諒が真田に興味を持ったのはそういった理由もあっただろう。ただ、最後には、心と心で確かに繋がり合えたとそう信じている。
「諒は、望んで逝った。あいつは兄弟を、残された家族を守るためにその彼らさえも謀って、誤解から謗られて、それでも家族を守り通したんだ。シンジに少し似ているな。……寡黙で、必要以上にはものを言わない男だった」
「そうか」
「いい奴だった」
「ああ。私も、その言葉を聞いて安心した」
身を屈めて美鶴が真田の顔を覗き込んでくる。「なんだ。泣いてないのか」と茶化すような声音で言ってから頬に手のひらを当ててくる。細い指。この少し力を込めただけで折れてしまいそうな体で彼女は世界の桐条を支えている。
その感触にふと、湊の「そろそろまずいんじゃないですか」という不躾極まりない台詞を思い出して真田は急に渋い顔になった。二十八という年齢はなんというべきか、相当にぎりぎりだ。
「……美鶴は」
「どうした、明彦」
「まだ、その、なんだ、していないんだな。結婚」
「――全て断っている!」
「はっ……?」
まあ俺もしていないが、という二の句を継ぐ前に美鶴のぴしゃりとした言葉が割り込んで有無を言わせぬ気迫が突如として辺りを漂い出す。見ると美鶴は先程までの面持ちを一変させて烈火の如く、怒っていた。先を母性を含むものとするならばこれは苛烈極まりない、少女の――
「それともなんだ。明彦は私に欲の皮ばかり張った、脂ぎった、金の亡者の中年男を適当に見繕って結婚しろとでも言うのか? 御免被るな。私の身にもなってみろ。舞い込んでくるのは全て縁談或いは求婚というお題目を掲げた遺産目当てのハイエナ共だ。私は奴らに資産やグループをくれてやるぐらいならば持てる全てを慈善事業に注ぎ込むか南条に返還するだろう。南条宗主には迷惑がられるかもしれないが、彼のような高潔な人物に託すのがやはりそこは分家筋の者としては――」
「美鶴、おい、美鶴、落ち着け誰もそんなことは言っていない」
「違わないさ。私にとっては……」
「あの。取り込み中悪いんですけど」
聞き知った少年の声が背後からして、さしもの美鶴も押し黙った。二人して口をぐっとつぐみバツの悪い顔になる。彼の方にはそれを推しはかってくれそうな気配はない。
振り返った先の少年は二人が口を閉ざしたことを確かめてから小さく頷いた。どこからか猫が現れて彼の腕の中に滑り込んでいく。
「有里」
「お疲れ様、ナオ。それから真田さんも」
「わざとか。知っていてはめたな、有里」
「さあ。なんのことですか」
柔かな黒猫の肢体を小さな腕いっぱいに抱き込んで湊が整った微笑をかたち作る。この顔をする時は大抵有里湊は嘘を吐くか、はぐらかすか、ごく稀に誰かをからかうやら女子を丸め込むやらなどの下心をその胸の内に隠していた。詐欺師のする顔だ。
美鶴の妙な興奮を中断してくれたのはありがたいが、それとこれとは話が別だ。二人の友の幻までもが湊の仕組んだものだとは思いたくなかったが、少なくともカエサル覚醒までは彼がある程度思い描いていたシナリオの通りなのだろうと真田は考えていた。有里湊は生前からそういうやつだったのだ。彼はボードゲームの類の思考パズルや戦略ゲームが得意だ。
真田の言わんとしたことを表情から読み取ったのか綾時がこらえきれないといったふうに小さく笑う。ツーマンセルのこの特異な主人とペルソナは感情の配分を違えて生まれてきたんじゃないだろうかと時々思わずにはいられないぐらい、偏った感情の表現をする。
それは神郷が有里で、死神の体現者が宣告者であることを忘却していたその時からそうだった。双生児にも似た二人はだけど湊曰く親子の方が近しい関係であるらしい。
ニュクスが実の母だとするのなら自らは生みと育ての母であり、そこに関してはあまねく死をもたらす月が相手だろうと一歩も譲るところではないとそう豪語したのは、彼が一体どんな眼差しをしていた時だったっけか?
『僕が男でも女でも関係ない。綾時はすごく腑甲斐無くて、ちょっと抜けてて、女の子に目がないけれど。僕のたった一人の息子。たった一人の、きっと一番大事な、何に代えても守らなきゃいけなかったもの』
『だから僕は手の内から滑り落ちてしまったあの十一月の満月の日が好きじゃない。……大切なものはこの手で掴み取る。奪い返す。渡してなんかやらない』
『登ろう、タルタロスの頂へ』
生コンクリートで塗り潰したみたいな灰色の曇りまなこがあの時どこを見ていたのか。或いは何も見てなどいなかったのか。それを真田は知らなかった。彼以外には知る術を持ちあわせていない。
答えは目の前にあるはずだが、永久に遠いものとして定められている。
「僕は可能性に賭けただけです。戦力は多いに越したことないですし。とはいえ事情を説明するのも手間だから……十年前のことを知っている人の方が良かったのは確かかな。でも保険はかけてましたよ。ナオ」
湊が首を撫でるとごろごろと喉を鳴らして黒猫がじゃれつく。「ナオ」と呼ばれた猫はセピアの瞳をきょろきょろと彷徨わせて主人の言葉をじっと待つように(或いは促すように)湊を見上げた。視線を受けた方の湊はすました顔で、「これからびっくり箱を開けるんですよ」と淡々と告げるような顔をしている。
ナオがあくびをした。
すると、猫はするりと湊の内から抜け出て真田と美鶴の元へ駆け寄り、値ぶみをするような目付きでじろじろと眺めてくる。次いでニヤリ……と口端を歪めた。毛並が真黒のくせにビビッドピンクとパープルの縞模様を体毛に持つチェシャキャットみたいに生々しい人間の表情だ。
そうしてまた緊張感もなく、あくびをして、
『そういうわけで、俺が保険だったんだよ。お前のカエサルが出て来るのがあとコンマ一秒遅かったら久々に大暴れ出来たんだけどな』
黒猫が喋り出した。
「……は?」
「今の、この猫の声?」
「まさか、そんな馬鹿な。コロマルとてペルソナを出しはしたが喋るのは犬語だったぞ」
『あ、本物の犬でペルソナを出せるのがいるっての、湊の適当じゃなかったんだな』
「慎兄ちゃん、やっぱりこの子喋ってると思う」
真田と美鶴は当然、湊についてこの浜辺までなんとなくやって来たらしい慎と洵の表情も驚愕に染まっている。おかしそうに笑う綾時の横で湊だけ平然としていて、逆に浮いていた。星明かりの元で闇に色彩が多少溶けている猫はしてやったりというふうに頷いて尚も人語を話し続ける。お構いなしに反応を楽しんでいるふうでもある。
『一応、元は普通の人間。大学生なんてのをやってた。アルカナは俺が皇帝で和也が月。あ、和也って言うのは俺の双子の兄で……まあ、二重人格みたいなものだと思ってくれればいいよ』
「今まで隠してたんだけど、そろそろ教えておこうと思ったんだ。次の満月シャドウからチームを割り振ろうと思ってたから。ナオはね、ちょっと気まぐれで面倒で最低最悪のやつに目を付けられて攫われてたんだ。無理矢理助け出したんだけど上手く人間の姿に戻れなくて、だからとりあえず今は猫」
『それで、元の姿に戻って元々の時空に帰るっていう俺の目的と湊のこの街での目的が一致したから俺は湊に協力してる。利害関係の一致ってやつかな。俺や和也個人でも湊のことは気に入ってるんだけど』
「元の時空?」
『ああ。どうもここ、俺の時代から見て未来にあたるみたいなんだよね。今が二〇一八年だっけ? 俺が覚えてる最後の日付は二〇〇〇年だったはずだ』
猫の尾はしょんぼりと垂れ下がって砂を毛の中に巻き込んでいる。十八年先の未来に頼れるものも殆どなく、単身で、それも猫の姿に身をやつしていることを思えばそれでも随分と気丈な態度だった。二重人格のような双子、という言葉がそれに連想されて蘇る。
多少の余裕は恐らく修羅場をかいくぐった経験から来ているのだろう。高レベルのペルソナ使いというステータスがなければ、状況に押し潰されていたとしても何もおかしくはない。
『約束してたんだ。高校の連中と、今日同窓会をしようって。それが気付いたら猫。笑えるだろ』
「……笑えるものか」
『元に戻る希望があるから笑える。俺は湊を信頼しているし、敵のことも多少は知ってるつもりだ。だから湊が信頼している君らとは上手くやっていきたい。共同戦線は得意な方だ』
「という感じです。ナオ、とりあえず戻ろう。夜が明けるとまずいし、真田さんも美鶴先輩も疲労してると思うし。疲労状態で無理すると風邪ひいちゃうんだ。十年前も真田さんは何回かひきかけてた」
「聞き捨てならんな。実際に風邪までいったのは有里だけだっただろう」
『ああ、やっぱり湊は無理するタイプなんだ』
含み笑いを向けられて珍しく湊がう……と押し黙る。二人の間にはそれなりに対等な関係が構築されているらしい。
それを眺めながらふと思いたって慎は湊に「ところでさ」と向き直った。
「湊、どうでもいいといえばどうでもいいことなんだけど」
「慎兄、なに?」
「なんで湊は尚也さんのことナオって呼んでたんだ? カモフラージュか何かの目的?」
そう尋ねるときょとんとしたどこかあどけない表情になって小首を傾げる。思いもよらない問いだったようでぱちぱちとまぶたをしばたかせて少し考え込む動作を取った。小学生だった頃の洵が、夏休みの自由研究の題材を何にしようかと首を捻っていた時もこんなふうな仕草をしていたような気がする。
しばらくしてやっぱり首をやや傾げたまま、湊が答えた。
「……だって、その方が猫っぽくてかわいい」
灰ねずみの瞳は相変わらず嘘を吐いているのかの判断材料としては抑揚に乏しすぎたが、なんとなくこれは本当のことなんだなとその場の一同が納得した。この少年は時々本気で、何も考えずに行動を起こしていることがあるのだ。
◇◆◇◆◇
ノックの音がする。気怠い体をのっそりと動かして真田は起き上がった。ガラス窓から差し込んでくる日差しが眩しく、よく晴れていることを伝えてくる。
昨晩眠りに落ちたのは結局深夜二時を回った時刻のことで、とはいえ別にそれは大して遅い時間でもないのだけれども、どうやら気が付いたら熟睡してしまっていたらしい。時計の針は十一時半を回った頃を差していた。非番でなければ減点対象だ。
「入れ。誰だ、有里か」
「はい。話がしたくて」
「珍しいな」
「美鶴さんを見て、ちょっと。……皆、今、どうしてるのかなって。元気そうですか」
おずおずと伺うように歯切れが悪い。彼の背後に綾時はおらず、また件の黒猫も連れていなかった。真田はとりあえず座れ、と促して息を吐く。
「男どもはともかく、女性陣のことは美鶴の方が詳しいだろうな。それでも良ければ話すが」
「構いません。お願いします」
珍しいこともあるものだ、と素直にそう感じた。有里湊が戦闘指示やその他の必要不可欠なこと以外で頼みごとをするということはまず殆どなかったのだ。しょっちゅう質問を持ってきていた伊織と違って、彼は優秀を絵に描いたような完璧超人でどちらかと言えば頼みごとを受ける役回りの方が多かった。
「まず、そうだな。お前と一番仲が良かったのは伊織か。あいつは、あいつなりに上手くやってる。なんとか大学に行って就職して、嫁さんも貰った。今確か、子供がいるな。嫁が誰かは……」
「吉野千鳥。彼女、助かったんですね。よかった」
「ああ。天田は今大学だ。元々一丁前に言うやつだったが、今は輪を掛けてそうだ。年に二度、誘い合わせて墓参りに行く。一番よくお前の名前を出していたのも天田だな。他のやつらは、少し……お前の名前を口にすることを憚っているのかもしれない。実際俺もそうだった。天田程まっすぐに見詰められては……いなかった」
何を見詰められなかったのか、それを問うことを湊はしなかった。問わずとも彼の顔を見れば明白であり、間違いなく「有里湊」の死、ひいては有里湊の存在そのもののことであろう。自ずと口を噤み、目を逸らし、顔を両手で覆ってしまうような。
繰り返す三月三十一日の時から、根本的に抜本的には変われないでいるのだろう。仕方がない。
爪痕は大きく、それゆえに巨大な腫れもののようになり、いつしか彼らを縛り上げた。
「コロマルは、もう死んだよ。そのことは知っているんじゃないか? ……寿命だった。だが、あいつは十分に長く生きたはずだ。美鶴の手で荒垣と同じ墓に埋められた。飼い主の元に……一足先にお前と望月のところへ行ったんだなと、天田はそんなことを言った。死の元へ」
死そのものと近しくなった少年が「死の元へ」、そう反芻する。「僕の元へ」、とそう言ったようにも聞こえた。生と死とを隔てる扉の番人は小さく俯いて、窓の向こうの空を見る。
「そういえば来てたかな、コロマル。首に羽型のアームを誇らしげに付けてて、神主さんと一緒だった。アイギスじゃないから正確なことはわからなかったけど、満ち足りて悔いはないって。S.E.E.Sの皆と過ごせた日々を神主さんに楽しそうに聞かせてた。それから僕に、一回鳴いてくれて。きっと『ありがとう』って言ったんだろうね。コロマルは義理堅い犬だし。……彼らももう輪の流れに乗った。いつかまた、会えるかもしれない。どこかで」
「そうか。俺は見ての通りだ。警察組織の中の異端として今日も今日とて肩身の狭い思いをしている。まあそれなりには上手くやっているつもりだがな……美鶴も見ての通りだな。桐条のトップに立って十年も経つし、苦労はしているが充実もしているようだ。アイギスが補佐や実動を担っている。今現在ペルソナが普通に出せるのはアイギスと天田ぐらいのものだ」
「真田さんも、多分もう使えますよ。望めば美鶴さんも出来ると思う。今の綾凪は意志の力が何にも勝る場所だから。……他の人達は?」
「山岸は結婚した。式にも出た。数年前のことだな。岳羽は、少なくとも俺も美鶴も式に呼ばれてないから未婚だろう。美鶴の話では、一人で気丈に生きていると」
その言葉に湊の顔色が変わるのがわかった。予想はしていたがどうしても、というそういう表情だ。小さく見開かれ、そして伏せられたまなじりが雄弁に物語っている。
湊が振り絞るように彼女の名を口にした。
「……ゆかりは」
「ああ」
「結婚、しなかったんですね」
まだしてない、ではなくしなかった、と。
湊はあのどこを見ているのかわからない瞳に珍しく読み取れそうな意志を浮かべて呟いた。懺悔とそれに入り混じった僅かな喜色。はっとする。
そうだ。「有里湊」は、殆どの人間を他人行儀に、もっと言えばそっけなく遠巻きに呼んだ。美鶴は「桐条さん」だとよそよそしくて寂しいと本人に言われたから「美鶴先輩」と呼ぶ。アイギスは苗字が存在しないから「アイギス」。あとは近しい部類に入る課外部のメンバーですら「山岸さん」「天田くん」「荒垣さん」「真田さん」、そう呼んでいた。
真田の知る限りで名前を呼び捨てにされていたのは伊織と岳羽、そして望月の三人だけだ。それが真実彼が心を許した証拠なのかと訝しむように聞かれることもあったが、それでも時折、そうなのだろうと肯定したくなる気持ちが生まれるのは事実だった。
彼が「順平」と呼ぶ声は心を許した朋友へのそれであり(例えば真田と荒垣のような)、「綾時」と呼ぶ声は一線を隠した慈愛を持つもので(最後になって、それは親、きょうだい、そういった無二に向ける無償の愛であったのだと知った)。
そして「ゆかり」と呼ぶ声は柔らかく、けれど整っていて、あらゆる物事をそつなくこなして見せる彼が珍しく言い包められたりしている時は大抵彼女の前でのことだった。
「有里、お前は……」
「ゆかりは。……真田さんだから話しますけど、自分の母親が夫を失った後男から男を渡り歩いて逃げていた事をすごく嫌悪していた。そんな母親が許せなくて、男に溺れることを酷く恐れていて、だから彼女は恋をすることも怖がって躊躇って……僕もゆかりにとっての恋愛は軽いものじゃないなって思ってた。司るアルカナが恋愛だったのはきっとそういうことで、彼女に決して軽くない意味をもってまとわりついていた要素なんだと思う。……でも、ゆかりは」
また、振り絞るように。そして誤解を恐れずに言うのなら泣きたいのに涙が出てこないみたいな声でその言葉を口にする。神に懺悔して今後一生を悔い改めると誓う修道女のような声音で震える唇を動かしていた。あの有里湊がこんな表情をするのかというような顔で、祈り、膝をつくかのように。
「自惚れでなければ、僕のことを好きになってくれたから。『有里湊』が彼女のその後の人生を縛りつけてしまったのならそれはとても悲しいことだと思って」
瞳はそらのように透き通っていた。岳羽ゆかりをとても大事なものだと、彼は心から信じているようだった。
「彼女の好意に出来れば応えてあげたかったし、そうでなくても次の気持ちへの後押しをしてあげられればよかったのに。死んで縛るなんて最低。真田さん、知ってます? 死者は、思い出の中でどんどん美化されて美しいところだけ残していくから、一番綺麗な姿で残された生者を苦しめるんです。丁度僕みたいに。三月三十一日みたいに、……ゆかりみたいに」
「だが、もしそうだとしても岳羽はお前を愛したことを誇りに思っているだろう。忘れられないんじゃない。忘れたくないんだ」
「綺麗ごとじゃないですか、そんなの。僕はゆかりを苦しめたかったわけじゃないし、ましてや彼女の永遠になんてなりたくなかった。なっちゃいけなかった。死人の亡霊に束縛されてていいことなんてあるはずないのに」
「突然どうしたんだ。有里らしくもない」
「真田さんと美鶴先輩を見ていて思い出して、それで、少し。なんでもないです。……なんでも」
言い聞かせるように繰り返して湊がおもむろに立ち上がる。瞳はもう不透明の意志の読めないものに戻っていて、あの半ば硝子玉のような脆く壊れてしまいそうなまなことどちらが望ましいものなのか真田には判ずることが出来ない。
肩から下げられた銀のヘッドホンが陽光を反射して、逆光に晒されて暗く陰った湊の横向きの顔を隠した。青いLEDの光をポータブルプレイヤーが発している。青。空と、海と、湊の髪の色。それは灰色と対を成して彼の印象をかたどる。
ヘッドホンの銀灰と、召喚銃の銀灰。灰ねずみの目。彼を作る半分の灰色。
消えてなくなることのないくすんだ色。
「それから真田さん。美鶴先輩のことですけど、僕は多分二人はお互いにはっきりしないとどうにもいかないと思います。それだけ伝えておこうと思って」
言い残して湊は踵を返し、扉をぱたんと締めて真田の視界から消えていなくなった。きっちりと締められた扉はだらしなくまた口を開くこともない。
それから幾らか後になって、今更のように真田は思い知らされることになる。それこそが有里湊が棄て去ったつもりだった未練の一端であり、彼がまだ、生々しい人間の在り方を失えずにいたことの証明のようなものであったのだと。
途方もない壁となって立ちはだかるのは、もう少しだけ先の話。
「……終わり、か?」
「一応、今回は。やっぱり凄いね、慎兄のそれ……」
「ん? ああ、これ、ね」
アベルの持つ剣には「一切の副作用を伴わずにペルソナを保有者から引き剥がす」特異能力が宿っている。言うならば人間の精神、意識と無意識の狭間に強引に干渉し得る「理論的に本来存在してはならないもの」だ。
この能力は始めからアベルが持っていたものじゃない。後天的に付与されたものだ。神郷夫妻の忘れ形見だった。
祝福であり、また一つの戒めでもあった。
湊が補助に出していたペルソナを引っ込めると、間を置かず綾時が現れて『湊君』と主に声を掛ける。湊はいつもの特に高低差のない声で「慎兄の、どうだった」と問い掛けたが彼は首を振って、『それは後でね』と珍しく湊を遮った。
『湊君、感じてる? ここから北東に離れた位置で強力なペルソナ反応を検出した。同時に、ボスタイプシャドウも二体。はっきりと確定は出来ないんだけど恐らく『エンプレス』と『エンぺラー』だと思う』
「そのペルソナ反応っていうのは誰の。ナオやカズじゃなくて、僕達の知らない誰かのもの?」
『それも、断定は出来ない。でも、これはきっと真田さんの『カエサル』だ。僕が知ってる、懐かしい感じがするもの』
「……そっか。真田さん、上手く行ったんだ」
『善戦してるみたいだよ。尚也達はペルソナ、出してないみたいだね。尚也はともかく和也は我慢しきれなくなって突撃していきそうなものだけど』
「ギリギリ間に合ったのかも。荒垣さんとかひやひやして口出してきそうだし」
冗談めかして言うと、綾時がそうかもね、と頷く。『優しくて強い光を感じたような気がするんだ』と後ろ手にはにかんで、湊の肌に触れているように手のひらを添えた。
『僕にとっての君みたいなものだよ。ねえ湊君、僕は君と出逢えたことにすごく感謝してるんだ。君がいたから僕がいる。真田さんと荒垣さんもそうなんだろうね。それってとても幸せで、素晴らしいことだって僕はそう思うよ』
「そうだね。僕も……同意する。真田さんも美鶴さんも、順平、ゆかり、山岸さん、天田君、荒垣先輩、僕に関わってくれた人達……それから、綾時。ひととひとに囲まれて変わっていくのは、人間の特権なんだ。だから多分、あの時は僕も人間だったんだろうな」
『……なんで君は、この流れでそういうことを言うかな……』
「でもそれもまた一つの事実だ。綾時、思うに僕はね、愚者のコミュニティをマスターして審判のコミュニティを開いた辺りで、恐らく一線を超えてしまっていたんだよ。もう二度と後戻り出来ないっていう最終セーフティラインを乗り越えた。ポイント・オブ・ノーリターン、世の中にはそういうものが確かに存在するって今ならそう断言出来るね」
『相変わらずだ、君は』
「だってそうだろう? 僕が人間のままだったら、今ここにはいないよ」
だからこれでいいんだ。少年の姿をした何かは言った。躊躇いもせずに。
「これでいい。だから僕は、慎兄と洵兄に会えた。結祈に名前を貰った。ここに降り立つことになったのも、一つ一つ意味のあること」
綾時にはそれが少し切ない。
◇◆◇◆◇
影時間が明けかけて、空にはうっすらと緑色の残滓が残っている。だがそれもすぐに消えて、月がいつもの黄金色を取り戻した。冷めた海風がゆるゆると吹きつけて、海辺の砂浜に座り込んでいる真田の肌をほのかな磯の匂いでかすめていく。
カエサルはもう真田のそばに出てはいなかった。召喚銃の中の形のない銃弾――真田の心の中、に還っていったのだと思う。
隣でぴんと背を伸ばして立っている美鶴はどこか不満気な色を覗かせて海の向こうを見ていた。地平線より遠いどこかに、荒垣と諒の亡霊が消えていったとでも考えているのかもしれない。
それとは別に、彼女が不満そうな理由は考えるまでもなく二つあった。一つは美鶴の知らない男が荒垣と共に現れたこと。もう一つは、真田だけがペルソナを呼び出せたことだ。年齢制限は、二人揃って数年前に迎えていた。
「明彦、彼は」
「俺の同僚で……警察組織内部での信頼出来る人間で……『共犯者』だった。『神郷諒』。神郷兄弟の長兄だ。昨年亡くなった」
「……そうか」
「美鶴には言っていなかったな、そういえば。伏せていたと言えば、そうだ。お前に余計な心配を掛けたくなかったし、プライドめいたものもあった」
異例の出世を遂げている真田には何かとやっかんでくる者も多い。くだらない妬みや痛ましい羨望、ありとあらゆる妨害、そういったものを一人で対処していくのにも限度がある。はじめはそういったきっかけで知り合い、やがて二人は互いの秘密を知ることになった。ペルソナ能力だ。
神郷諒は図抜けた能力を持つ、弟の慎と同じ特A潜在者としてリストに名を連ねられていた。基本的に特別課外活動部に所属していたメンバーも自然覚醒者であるためそこに並べられるのだが、やはり普通はそうそうひとところには集まらないものらしい。諒が真田に興味を持ったのはそういった理由もあっただろう。ただ、最後には、心と心で確かに繋がり合えたとそう信じている。
「諒は、望んで逝った。あいつは兄弟を、残された家族を守るためにその彼らさえも謀って、誤解から謗られて、それでも家族を守り通したんだ。シンジに少し似ているな。……寡黙で、必要以上にはものを言わない男だった」
「そうか」
「いい奴だった」
「ああ。私も、その言葉を聞いて安心した」
身を屈めて美鶴が真田の顔を覗き込んでくる。「なんだ。泣いてないのか」と茶化すような声音で言ってから頬に手のひらを当ててくる。細い指。この少し力を込めただけで折れてしまいそうな体で彼女は世界の桐条を支えている。
その感触にふと、湊の「そろそろまずいんじゃないですか」という不躾極まりない台詞を思い出して真田は急に渋い顔になった。二十八という年齢はなんというべきか、相当にぎりぎりだ。
「……美鶴は」
「どうした、明彦」
「まだ、その、なんだ、していないんだな。結婚」
「――全て断っている!」
「はっ……?」
まあ俺もしていないが、という二の句を継ぐ前に美鶴のぴしゃりとした言葉が割り込んで有無を言わせぬ気迫が突如として辺りを漂い出す。見ると美鶴は先程までの面持ちを一変させて烈火の如く、怒っていた。先を母性を含むものとするならばこれは苛烈極まりない、少女の――
「それともなんだ。明彦は私に欲の皮ばかり張った、脂ぎった、金の亡者の中年男を適当に見繕って結婚しろとでも言うのか? 御免被るな。私の身にもなってみろ。舞い込んでくるのは全て縁談或いは求婚というお題目を掲げた遺産目当てのハイエナ共だ。私は奴らに資産やグループをくれてやるぐらいならば持てる全てを慈善事業に注ぎ込むか南条に返還するだろう。南条宗主には迷惑がられるかもしれないが、彼のような高潔な人物に託すのがやはりそこは分家筋の者としては――」
「美鶴、おい、美鶴、落ち着け誰もそんなことは言っていない」
「違わないさ。私にとっては……」
「あの。取り込み中悪いんですけど」
聞き知った少年の声が背後からして、さしもの美鶴も押し黙った。二人して口をぐっとつぐみバツの悪い顔になる。彼の方にはそれを推しはかってくれそうな気配はない。
振り返った先の少年は二人が口を閉ざしたことを確かめてから小さく頷いた。どこからか猫が現れて彼の腕の中に滑り込んでいく。
「有里」
「お疲れ様、ナオ。それから真田さんも」
「わざとか。知っていてはめたな、有里」
「さあ。なんのことですか」
柔かな黒猫の肢体を小さな腕いっぱいに抱き込んで湊が整った微笑をかたち作る。この顔をする時は大抵有里湊は嘘を吐くか、はぐらかすか、ごく稀に誰かをからかうやら女子を丸め込むやらなどの下心をその胸の内に隠していた。詐欺師のする顔だ。
美鶴の妙な興奮を中断してくれたのはありがたいが、それとこれとは話が別だ。二人の友の幻までもが湊の仕組んだものだとは思いたくなかったが、少なくともカエサル覚醒までは彼がある程度思い描いていたシナリオの通りなのだろうと真田は考えていた。有里湊は生前からそういうやつだったのだ。彼はボードゲームの類の思考パズルや戦略ゲームが得意だ。
真田の言わんとしたことを表情から読み取ったのか綾時がこらえきれないといったふうに小さく笑う。ツーマンセルのこの特異な主人とペルソナは感情の配分を違えて生まれてきたんじゃないだろうかと時々思わずにはいられないぐらい、偏った感情の表現をする。
それは神郷が有里で、死神の体現者が宣告者であることを忘却していたその時からそうだった。双生児にも似た二人はだけど湊曰く親子の方が近しい関係であるらしい。
ニュクスが実の母だとするのなら自らは生みと育ての母であり、そこに関してはあまねく死をもたらす月が相手だろうと一歩も譲るところではないとそう豪語したのは、彼が一体どんな眼差しをしていた時だったっけか?
『僕が男でも女でも関係ない。綾時はすごく腑甲斐無くて、ちょっと抜けてて、女の子に目がないけれど。僕のたった一人の息子。たった一人の、きっと一番大事な、何に代えても守らなきゃいけなかったもの』
『だから僕は手の内から滑り落ちてしまったあの十一月の満月の日が好きじゃない。……大切なものはこの手で掴み取る。奪い返す。渡してなんかやらない』
『登ろう、タルタロスの頂へ』
生コンクリートで塗り潰したみたいな灰色の曇りまなこがあの時どこを見ていたのか。或いは何も見てなどいなかったのか。それを真田は知らなかった。彼以外には知る術を持ちあわせていない。
答えは目の前にあるはずだが、永久に遠いものとして定められている。
「僕は可能性に賭けただけです。戦力は多いに越したことないですし。とはいえ事情を説明するのも手間だから……十年前のことを知っている人の方が良かったのは確かかな。でも保険はかけてましたよ。ナオ」
湊が首を撫でるとごろごろと喉を鳴らして黒猫がじゃれつく。「ナオ」と呼ばれた猫はセピアの瞳をきょろきょろと彷徨わせて主人の言葉をじっと待つように(或いは促すように)湊を見上げた。視線を受けた方の湊はすました顔で、「これからびっくり箱を開けるんですよ」と淡々と告げるような顔をしている。
ナオがあくびをした。
すると、猫はするりと湊の内から抜け出て真田と美鶴の元へ駆け寄り、値ぶみをするような目付きでじろじろと眺めてくる。次いでニヤリ……と口端を歪めた。毛並が真黒のくせにビビッドピンクとパープルの縞模様を体毛に持つチェシャキャットみたいに生々しい人間の表情だ。
そうしてまた緊張感もなく、あくびをして、
『そういうわけで、俺が保険だったんだよ。お前のカエサルが出て来るのがあとコンマ一秒遅かったら久々に大暴れ出来たんだけどな』
黒猫が喋り出した。
「……は?」
「今の、この猫の声?」
「まさか、そんな馬鹿な。コロマルとてペルソナを出しはしたが喋るのは犬語だったぞ」
『あ、本物の犬でペルソナを出せるのがいるっての、湊の適当じゃなかったんだな』
「慎兄ちゃん、やっぱりこの子喋ってると思う」
真田と美鶴は当然、湊についてこの浜辺までなんとなくやって来たらしい慎と洵の表情も驚愕に染まっている。おかしそうに笑う綾時の横で湊だけ平然としていて、逆に浮いていた。星明かりの元で闇に色彩が多少溶けている猫はしてやったりというふうに頷いて尚も人語を話し続ける。お構いなしに反応を楽しんでいるふうでもある。
『一応、元は普通の人間。大学生なんてのをやってた。アルカナは俺が皇帝で和也が月。あ、和也って言うのは俺の双子の兄で……まあ、二重人格みたいなものだと思ってくれればいいよ』
「今まで隠してたんだけど、そろそろ教えておこうと思ったんだ。次の満月シャドウからチームを割り振ろうと思ってたから。ナオはね、ちょっと気まぐれで面倒で最低最悪のやつに目を付けられて攫われてたんだ。無理矢理助け出したんだけど上手く人間の姿に戻れなくて、だからとりあえず今は猫」
『それで、元の姿に戻って元々の時空に帰るっていう俺の目的と湊のこの街での目的が一致したから俺は湊に協力してる。利害関係の一致ってやつかな。俺や和也個人でも湊のことは気に入ってるんだけど』
「元の時空?」
『ああ。どうもここ、俺の時代から見て未来にあたるみたいなんだよね。今が二〇一八年だっけ? 俺が覚えてる最後の日付は二〇〇〇年だったはずだ』
猫の尾はしょんぼりと垂れ下がって砂を毛の中に巻き込んでいる。十八年先の未来に頼れるものも殆どなく、単身で、それも猫の姿に身をやつしていることを思えばそれでも随分と気丈な態度だった。二重人格のような双子、という言葉がそれに連想されて蘇る。
多少の余裕は恐らく修羅場をかいくぐった経験から来ているのだろう。高レベルのペルソナ使いというステータスがなければ、状況に押し潰されていたとしても何もおかしくはない。
『約束してたんだ。高校の連中と、今日同窓会をしようって。それが気付いたら猫。笑えるだろ』
「……笑えるものか」
『元に戻る希望があるから笑える。俺は湊を信頼しているし、敵のことも多少は知ってるつもりだ。だから湊が信頼している君らとは上手くやっていきたい。共同戦線は得意な方だ』
「という感じです。ナオ、とりあえず戻ろう。夜が明けるとまずいし、真田さんも美鶴先輩も疲労してると思うし。疲労状態で無理すると風邪ひいちゃうんだ。十年前も真田さんは何回かひきかけてた」
「聞き捨てならんな。実際に風邪までいったのは有里だけだっただろう」
『ああ、やっぱり湊は無理するタイプなんだ』
含み笑いを向けられて珍しく湊がう……と押し黙る。二人の間にはそれなりに対等な関係が構築されているらしい。
それを眺めながらふと思いたって慎は湊に「ところでさ」と向き直った。
「湊、どうでもいいといえばどうでもいいことなんだけど」
「慎兄、なに?」
「なんで湊は尚也さんのことナオって呼んでたんだ? カモフラージュか何かの目的?」
そう尋ねるときょとんとしたどこかあどけない表情になって小首を傾げる。思いもよらない問いだったようでぱちぱちとまぶたをしばたかせて少し考え込む動作を取った。小学生だった頃の洵が、夏休みの自由研究の題材を何にしようかと首を捻っていた時もこんなふうな仕草をしていたような気がする。
しばらくしてやっぱり首をやや傾げたまま、湊が答えた。
「……だって、その方が猫っぽくてかわいい」
灰ねずみの瞳は相変わらず嘘を吐いているのかの判断材料としては抑揚に乏しすぎたが、なんとなくこれは本当のことなんだなとその場の一同が納得した。この少年は時々本気で、何も考えずに行動を起こしていることがあるのだ。
◇◆◇◆◇
ノックの音がする。気怠い体をのっそりと動かして真田は起き上がった。ガラス窓から差し込んでくる日差しが眩しく、よく晴れていることを伝えてくる。
昨晩眠りに落ちたのは結局深夜二時を回った時刻のことで、とはいえ別にそれは大して遅い時間でもないのだけれども、どうやら気が付いたら熟睡してしまっていたらしい。時計の針は十一時半を回った頃を差していた。非番でなければ減点対象だ。
「入れ。誰だ、有里か」
「はい。話がしたくて」
「珍しいな」
「美鶴さんを見て、ちょっと。……皆、今、どうしてるのかなって。元気そうですか」
おずおずと伺うように歯切れが悪い。彼の背後に綾時はおらず、また件の黒猫も連れていなかった。真田はとりあえず座れ、と促して息を吐く。
「男どもはともかく、女性陣のことは美鶴の方が詳しいだろうな。それでも良ければ話すが」
「構いません。お願いします」
珍しいこともあるものだ、と素直にそう感じた。有里湊が戦闘指示やその他の必要不可欠なこと以外で頼みごとをするということはまず殆どなかったのだ。しょっちゅう質問を持ってきていた伊織と違って、彼は優秀を絵に描いたような完璧超人でどちらかと言えば頼みごとを受ける役回りの方が多かった。
「まず、そうだな。お前と一番仲が良かったのは伊織か。あいつは、あいつなりに上手くやってる。なんとか大学に行って就職して、嫁さんも貰った。今確か、子供がいるな。嫁が誰かは……」
「吉野千鳥。彼女、助かったんですね。よかった」
「ああ。天田は今大学だ。元々一丁前に言うやつだったが、今は輪を掛けてそうだ。年に二度、誘い合わせて墓参りに行く。一番よくお前の名前を出していたのも天田だな。他のやつらは、少し……お前の名前を口にすることを憚っているのかもしれない。実際俺もそうだった。天田程まっすぐに見詰められては……いなかった」
何を見詰められなかったのか、それを問うことを湊はしなかった。問わずとも彼の顔を見れば明白であり、間違いなく「有里湊」の死、ひいては有里湊の存在そのもののことであろう。自ずと口を噤み、目を逸らし、顔を両手で覆ってしまうような。
繰り返す三月三十一日の時から、根本的に抜本的には変われないでいるのだろう。仕方がない。
爪痕は大きく、それゆえに巨大な腫れもののようになり、いつしか彼らを縛り上げた。
「コロマルは、もう死んだよ。そのことは知っているんじゃないか? ……寿命だった。だが、あいつは十分に長く生きたはずだ。美鶴の手で荒垣と同じ墓に埋められた。飼い主の元に……一足先にお前と望月のところへ行ったんだなと、天田はそんなことを言った。死の元へ」
死そのものと近しくなった少年が「死の元へ」、そう反芻する。「僕の元へ」、とそう言ったようにも聞こえた。生と死とを隔てる扉の番人は小さく俯いて、窓の向こうの空を見る。
「そういえば来てたかな、コロマル。首に羽型のアームを誇らしげに付けてて、神主さんと一緒だった。アイギスじゃないから正確なことはわからなかったけど、満ち足りて悔いはないって。S.E.E.Sの皆と過ごせた日々を神主さんに楽しそうに聞かせてた。それから僕に、一回鳴いてくれて。きっと『ありがとう』って言ったんだろうね。コロマルは義理堅い犬だし。……彼らももう輪の流れに乗った。いつかまた、会えるかもしれない。どこかで」
「そうか。俺は見ての通りだ。警察組織の中の異端として今日も今日とて肩身の狭い思いをしている。まあそれなりには上手くやっているつもりだがな……美鶴も見ての通りだな。桐条のトップに立って十年も経つし、苦労はしているが充実もしているようだ。アイギスが補佐や実動を担っている。今現在ペルソナが普通に出せるのはアイギスと天田ぐらいのものだ」
「真田さんも、多分もう使えますよ。望めば美鶴さんも出来ると思う。今の綾凪は意志の力が何にも勝る場所だから。……他の人達は?」
「山岸は結婚した。式にも出た。数年前のことだな。岳羽は、少なくとも俺も美鶴も式に呼ばれてないから未婚だろう。美鶴の話では、一人で気丈に生きていると」
その言葉に湊の顔色が変わるのがわかった。予想はしていたがどうしても、というそういう表情だ。小さく見開かれ、そして伏せられたまなじりが雄弁に物語っている。
湊が振り絞るように彼女の名を口にした。
「……ゆかりは」
「ああ」
「結婚、しなかったんですね」
まだしてない、ではなくしなかった、と。
湊はあのどこを見ているのかわからない瞳に珍しく読み取れそうな意志を浮かべて呟いた。懺悔とそれに入り混じった僅かな喜色。はっとする。
そうだ。「有里湊」は、殆どの人間を他人行儀に、もっと言えばそっけなく遠巻きに呼んだ。美鶴は「桐条さん」だとよそよそしくて寂しいと本人に言われたから「美鶴先輩」と呼ぶ。アイギスは苗字が存在しないから「アイギス」。あとは近しい部類に入る課外部のメンバーですら「山岸さん」「天田くん」「荒垣さん」「真田さん」、そう呼んでいた。
真田の知る限りで名前を呼び捨てにされていたのは伊織と岳羽、そして望月の三人だけだ。それが真実彼が心を許した証拠なのかと訝しむように聞かれることもあったが、それでも時折、そうなのだろうと肯定したくなる気持ちが生まれるのは事実だった。
彼が「順平」と呼ぶ声は心を許した朋友へのそれであり(例えば真田と荒垣のような)、「綾時」と呼ぶ声は一線を隠した慈愛を持つもので(最後になって、それは親、きょうだい、そういった無二に向ける無償の愛であったのだと知った)。
そして「ゆかり」と呼ぶ声は柔らかく、けれど整っていて、あらゆる物事をそつなくこなして見せる彼が珍しく言い包められたりしている時は大抵彼女の前でのことだった。
「有里、お前は……」
「ゆかりは。……真田さんだから話しますけど、自分の母親が夫を失った後男から男を渡り歩いて逃げていた事をすごく嫌悪していた。そんな母親が許せなくて、男に溺れることを酷く恐れていて、だから彼女は恋をすることも怖がって躊躇って……僕もゆかりにとっての恋愛は軽いものじゃないなって思ってた。司るアルカナが恋愛だったのはきっとそういうことで、彼女に決して軽くない意味をもってまとわりついていた要素なんだと思う。……でも、ゆかりは」
また、振り絞るように。そして誤解を恐れずに言うのなら泣きたいのに涙が出てこないみたいな声でその言葉を口にする。神に懺悔して今後一生を悔い改めると誓う修道女のような声音で震える唇を動かしていた。あの有里湊がこんな表情をするのかというような顔で、祈り、膝をつくかのように。
「自惚れでなければ、僕のことを好きになってくれたから。『有里湊』が彼女のその後の人生を縛りつけてしまったのならそれはとても悲しいことだと思って」
瞳はそらのように透き通っていた。岳羽ゆかりをとても大事なものだと、彼は心から信じているようだった。
「彼女の好意に出来れば応えてあげたかったし、そうでなくても次の気持ちへの後押しをしてあげられればよかったのに。死んで縛るなんて最低。真田さん、知ってます? 死者は、思い出の中でどんどん美化されて美しいところだけ残していくから、一番綺麗な姿で残された生者を苦しめるんです。丁度僕みたいに。三月三十一日みたいに、……ゆかりみたいに」
「だが、もしそうだとしても岳羽はお前を愛したことを誇りに思っているだろう。忘れられないんじゃない。忘れたくないんだ」
「綺麗ごとじゃないですか、そんなの。僕はゆかりを苦しめたかったわけじゃないし、ましてや彼女の永遠になんてなりたくなかった。なっちゃいけなかった。死人の亡霊に束縛されてていいことなんてあるはずないのに」
「突然どうしたんだ。有里らしくもない」
「真田さんと美鶴先輩を見ていて思い出して、それで、少し。なんでもないです。……なんでも」
言い聞かせるように繰り返して湊がおもむろに立ち上がる。瞳はもう不透明の意志の読めないものに戻っていて、あの半ば硝子玉のような脆く壊れてしまいそうなまなことどちらが望ましいものなのか真田には判ずることが出来ない。
肩から下げられた銀のヘッドホンが陽光を反射して、逆光に晒されて暗く陰った湊の横向きの顔を隠した。青いLEDの光をポータブルプレイヤーが発している。青。空と、海と、湊の髪の色。それは灰色と対を成して彼の印象をかたどる。
ヘッドホンの銀灰と、召喚銃の銀灰。灰ねずみの目。彼を作る半分の灰色。
消えてなくなることのないくすんだ色。
「それから真田さん。美鶴先輩のことですけど、僕は多分二人はお互いにはっきりしないとどうにもいかないと思います。それだけ伝えておこうと思って」
言い残して湊は踵を返し、扉をぱたんと締めて真田の視界から消えていなくなった。きっちりと締められた扉はだらしなくまた口を開くこともない。
それから幾らか後になって、今更のように真田は思い知らされることになる。それこそが有里湊が棄て去ったつもりだった未練の一端であり、彼がまだ、生々しい人間の在り方を失えずにいたことの証明のようなものであったのだと。
途方もない壁となって立ちはだかるのは、もう少しだけ先の話。
Copyright(c)倉田翠.