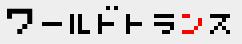Ⅸ HERMIT:兄弟幻想、或いは欠損コンプレックス
「リョージとリーダーって、キョーダイみてえだよなぁ」
「……きょーだい? 鏡の台?」
「違う違う、兄弟。兄と弟って書くやつ。そっちは鏡台、イントネーションが違うだろ」
順平がぶるぶると手を振って綾時の言を訂正した。綾時がぽんと手を打ってぱっと明るい顔をする。どうやら湊と兄弟のようだと言われたことが嬉しくて仕方ないらしい。
「ブラザー! それは、とても素晴らしいことだね! ね、湊くん、湊くんもそう思うでしょ?」
「……ジャックブラザーズは、ジャックフロストとジャックランタンだけじゃなくて、ジャック・リパーも含まれるのに忘れられがち」
「…………何の話?」
綾時が首を傾げた。順平は肩を竦めるとお手上げ侍のポーズをとる。ジャックフロストもジャックランタンも湊の操るペルソナの一つだが、その前提として、ゲームセンターの景品になったりしているようなキャラクターでもある。
「リーダーが好きなゲームのハナシ。今の流れとはなーんも関係ねえよ」
「え、ゲーム! うわあ、僕、ゲームってあんまりやったことないんだ。ねえねえ湊くん、そのゲーム今度僕に教えてよ!」
「めんどくさい」
「ええ、そんなぁ……」
「……ホントなら、お前ら双子ぐらいの感じなのになーんかリョージが甘えん坊の弟ってイメージ強いんだよなぁ。リーダーはリーダーですっげ冷たい兄貴って感じだけど」
まあ、それでいてなかなかうまい具合に仲良しだよな。そう言って肩を叩くと綾時は大仰に喜んで「ほんと? ほんと?!」とぴょこぴょこ跳ね飛んだ。それを見て湊が溜息を吐く。満更でもなさそうな顔で綾時の手を掴み、落ち着けさせると「だってよ弟」、珍しい微笑み顔をした。
「じゃあゲーセン、行こうか。順平も。勝負付き合ってよ」
「おうよ。でも賭けはナシな、リーダー滅茶苦茶食うじゃんかよ~」
「順平が負けるのが悪い」
「うわぁ唯我独尊。リョージ、お前の兄貴なんとかしてやって」
「え、えへへ……弟……湊くんの弟かぁ……」
「……ありゃ。そんなに嬉しかったんかね。こりゃ聞いてねーわ」
俺っちまで嬉しくなってきちまうな~これは! 鼻の下を掻いて仲人のような顔をしている順平を尻目に、湊の手が綾時の手を掴み、握りあって、ゲームセンターのあるポロニアンモールめがけて引きずり出した。
「そうされっと兄弟っつうよか親子みてーなのな。無表情肝っ玉母ちゃん」
「なにそれ。喧嘩でも売ってるの?」
「いやいや滅相もありませんリーダー様。だから賭けはナシ、ナシ、な。俺今日持ち合わせねえんだから!」
「分割払いでいいよ」
「容赦ねえな!」
とうとう苦笑いになって順平が叫ぶ。その間も綾時は湊に引きずられていて、妙に似通った雰囲気を持つ二人がそうしているとやっぱり家族のようだった。
「ああ……でもそっか、やっぱお前らは双子だわ」
順平が首の後ろで腕を組み、笑う。
「一緒なんだよなあ。こんなに正反対の性格してるのに、ホント、なんでなんだろうなぁ?」
◇◆◇◆◇
「ジャスティス――チャリオット――二身一体のシャドウです。どちらか一方を倒すともう一方が蘇生してくるから、同時に倒すしかない。気をつけて」
『要は全体攻撃で仕留めればいいんだろ? 任せろよ』
「……ナオは、独断で突っ走らないでね」
それともカズかな。指揮を執る湊直々に指名を受けて黒猫が露骨にぶすくれる。尚也にとっても和也にとっても実戦投入は久しぶりのことで、気分が高揚しているところにものの見事に水を差されて文句たらたらだ。
人語を介す黒猫の能力は湊以外には未知数のものであり、それを見てみたいという思いはメンバーの中に確かにある。真田の「保険」に彼を付けたという話をされた際に真田は「どの程度の実力なのか」とそれとなく尋ねたが、湊ははぐらかすばかりだった。これで拍子抜けする程弱かったらそれはそれで問題だが、流石にそんな馬鹿なことはないだろう。
恐らくは強力過ぎて測れないのだ。独断を牽制する意味もそこにあると捉えて間違いないはずである。
『そんなに危険かね』
「ナオが一番外しそう。飛ばしすぎちゃうきらいがあるから。片方完全蘇生されると本当煩わしいんだよ……真田さんと美鶴先輩は、覚えがあるでしょう」
「ああ。腹立たしかったな、実に」
「そういうわけ」
作戦会議中のダイニングテーブルに手を置いて小柄な少年はそれで一息を吐いた。四度目となる大型シャドウ討伐の日は今夜零時、満月の影時間だ。真田がペルソナを取り戻したことで前回から作戦の割り振りに余裕が出てきており、大抵は二班に分かれての作戦行動をとるという指針で固まることが多かった。
現在動けるペルソナ使いは四名。神郷湊と神郷慎。そして藤堂尚也と真田明彦。真田のペルソナ「カエサル」の強さは全盛期に比べるとやや劣るらしいが(本人曰わくは)、実戦経験が豊富なため今のところは慎の方が不安要素が多い。
よって基本のフォーメーションとしては、湊を補佐と司令塔に置いて慎を動かし、別働隊で真田達が動く形をとることになる。討伐そのものには規格外の強さを持つ湊一人が全力で当たればそれで確かに十分なのだが、全員一致で湊のペルソナ能力は出来る限り温存する方向で決まっていた。不安要素という点では、慎など問題にならないぐらい遥かに湊の能力は不明瞭なのだ。
「能力の都合上この二体は恐らくまとまって出現すると思います。合体と分離を繰り返すから、出来るだけ合体してる間に叩いた方がいいですね。ナオとカズも、その間なら最大火力で何やってもいいから」
『サポートな。了解』
「回復は僕がやるから、様子見て適当にお願い」
一通りの作戦報告を終えて湊が膝立ちを解いて椅子に座り込む。傍らには相変わらず綾時が付き添って、『湊君お疲れさま』などと花でも飛びそうな笑顔で労いをかけていた。影時間外でのペルソナの顕現が何故出来るのかについては、湊が言うには単純に力量の問題でしかないらしい。
或いは環境の差による先天的な適性の違いか。S.E.E.Sメンバーは皆「影時間のみペルソナ能力は行使出来る」として戦ってきたが、綾凪での異変時には影時間限定等々と言っていたらどうにもならなかった。それ故綾凪が特殊な磁場になり、特質として慎の中に残されているとも考えられる。
湊は本来影時間限定顕現のペルソナ使いのはずなのだが、彼は一度死んでいる。イレギュラーに何を説いても仕方ないというふうに真田と美鶴は現象の解析を半ば諦めていた。
「今考えることはこのぐらいかな……」
湊が机の上を整理して呟く。その時、尚也が真田の前を通り、ちらと目配せをしてから湊の膝に駆け上っていった。
湊が衝撃にか目を細める。頭を撫でると、尚也の方もくすぐったそうに目を細め、話題を切り出した。
『なー湊。こいつはほんの興味本位なんだが』
「何?」
尻尾が意味ありげに揺らめいた。その場の皆の視線をわざと集めでもするかのようにだ。
『物の例えだが。仮定として……湊か綾時が倒れたらそん時はどうなるんだ。――今夜の満月シャドウのようにどちらかがどちらかを再生させるのか?』
尚也の言葉に場の空気が凍りついた。
今この地に再現されている満月シャドウのオリジナルは元々望月綾時……「デス」の破片が形を成したものだ。言い換えれば綾時そのものが彼らのオリジナルシャドウであったと言って過言ではない。そのことを念頭に置いた上でそれを問うのは危険な綱渡りをするような、そういう不安定な行為だ。
少なくとも湊と綾時の間にはまだ開示されていない、彼らが秘匿している要素が片手で数えられるよりは多くあるはずであり、またその問いはそれらの琴線に触れる可能性が高いからである。しかし、
「それはないよ」
湊のそれに対する返答は簡素なものだった。特に動揺している様子もない、が、その表層的な反応は信用に値しないだろう。ポーカーフェイスが彼の常だ。
「綾時は、昔はともかく今はペルソナ。僕が稼働出来なくなったら綾時も動けない。マスターの停止に反応して動き出すペルソナもいるけど、基本的に綾時は僕から供給を受けないと存在出来ないんだ……カズの見立て通りに。これで満足?」
『ああ。そういう意味じゃ、俺達と内情は変わらないってわけか』
「そうだね。ナオとカズは、身体が一つしかないから……意識が二つあるからそれをスイッチすることで対応は変えられるけど、それだけって感じだもんね」
『別にそれだけじゃない』
むくれた声でぷいと顔を背けると黒猫は湊から離れていく。湊も特にそれを止めないので、そのなんとなくはっきりとしない空気の中で作戦会議はお開きになった。別段二人の間で仲違いがあったわけでもないのだが、すっきりしないものが残る。
湊も綾時を伴って退室し、慎と恂もいなくなるとダイニングルームには二人の人間が残るのみとなった。残された真田と美鶴はお互いに示し合わせて、席に着く。二人とも考えていることは同じだった。一件無遠慮に思える先の黒猫の問いは恐らくヒント――誘導なのだ。
「今のうちに考えとけ、という遠回しの示唆であると俺は思うんだが、どうだ。美鶴」
「同意見だ。思考を停滞させるなというところか……彼。なかなかやるな」
「掴みどころがないの間違いじゃないか。まるで……まるで。有里のようだ」
「似ているんだよ、彼らは」
だから有里が口を閉ざしていることに気が付いたのかもしれないな、とひとりごちて美鶴がデバイスを取り出す。特性のモバイルフォンは、秘密の話をするために無線傍受対策のプロテクトがかけられている特注品だ。
「行動は迅速に、が物事の基本だ。今晩はもう満月シャドウ討伐本番だし、私はペルソナを出せない以上現状足手まといでしかないからな。出来るところで対策をとっておかなければ」
「前線に出なきゃいいだけの話だろう」
「馬鹿者。安全地帯で蹲っているだけの指導者を、人は能無しと呼ぶんだ。この先に進むにあたって、『彼』の解析はやはり必要ということなのか……藤堂尚也。誘導にひっかかるのは癪だが一理ある」
アドレスブックを呼び出し、信頼出来る旧知へとコールするために大量の文字列の羅列をスクロールした。彼女は今別の場所でプロジェクトに取り掛かっているが、電話に出るぐらいの時間はあるはずだ。
ディスプレイに「アイギス」の文字が映り込んだところで美鶴の指が止まる。
「なあ明彦、そうは思わないか。――我々の目に映る《望月綾時》とは、一体『何』なのだ?」
◇◆◇◆◇
『何故、そのような大事な話を今まで黙っていたのでありますか』
感情を介するアンドロイド、誰よりも人間らしい機械人形の少女アイギスはことのあらましを聞き終わって一言そう言った。心なしか怒りを持て余しているようにも聞こえる。
『湊さんに関わることとなれば、一大事……わたしたちの皆がずっと気にかけていることです。わたしだけじゃないんです。皆です。それがわからなかったとは、わたしには思えません』
「本人たっての希望だ。だがなりふり構っていられないかもしれない状態になった。アイギス、これは君の口の堅さを見込んでの相談だ」
『……湊さんの? それは……確かにあの人なら……そういうふうに、言いそうではありますが』
「《望月綾時》について、私は知りたいと考えている」
『……!!』
アイギスが息を呑むのがデバイス越しに伝わってくる。彼女は今長期ミッションで確か桐条の海外ラボにいるはずだから、データベースの参照はそれほど難しい仕事ではないはずだ。まるで駆け引きの最中のような沈黙がしばし訪れ、アイギスの動揺を物語った。
当然だろう。望月綾時と彼女の間には浅からぬ因縁がある。
二十年前。作り上げられた《デス》との戦闘で最後まで生き残った個体がアイギスであり、そして処理しあぐねたデスの片鱗を有里湊の体内に押し込んだのもアイギスだった。いわば彼女があの因縁を引き起こした張本人なのだ。そういう縁もあってか、彼女は当初《望月綾時》という存在に対して正体を看破する前から手厳しかった。
自責の念があったのだと、思う。
『あの人が……どうか、したのですか』
「話した通り彼は今『神郷湊』のペルソナと名乗っている。そんなことが、どうして可能なのかと思ってな……尤も、有里の万能性を引き合いに出されると二の句が告げないのも確かだが」
『――そういう問題じゃないです』
「ん? 何だ?」
『あの人は、そういうものじゃ、ないです……』
アイギスの声が震えた。「アイギス?」美鶴が不審がって名を呼ぶと、『申し訳、ありません……』何故だか謝罪が返ってくる。
『わたしは。あの人に触れたことがあります。ムーンライトブリッジで……あの人が『死』としての記憶を取り戻す時のことです。わたしは機械です。その機械に欠損を生じさせるほどたくさんのものを、あの人から読み取りました』
「何をだ?」
『あの人は湊さんによく似ている』
「……それは……私も知っている。顔が瓜二つだ……」
『わたしはその理由を、湊さんから『奪った』からだと、たくさん感じて、結論付けました。だから……尚更……倒さないといけないと思って……だけど違うんです! あの人はただそうしないと生きられなかっただけ。『死』が生きようとするなんておかしいよね、ってあの人はわたしに言いました。『君が死にたくないのと同じだね』と」
電話の先で喋るアイギスの声が、言葉が、まるで目と鼻の先で語られているようだった。「心のあるアンドロイド」としてある程度の融通と落ち着きを持つようになったアイギスが有里湊と触れ合って人間性を得たはじめの頃と同じ剥き出しの感情がそこにある。ロードされた記憶などでは有り得ない。人間と同じ様に、鮮烈な印象を持つ過去を一つずつ引っ張り出して頭の中で追体験をしている。
『あの人は確かに湊さんと同じものを持っています。湊さんから、生きる糧として与えられたんです。……『望月綾時』は。その時わたしを見て、湊さんの名前を呼んで、泣きました。わたしはロジックで理解出来ないものが、その涙によって『わかった』のだと思いました。……あの人は、限りなく、『有里湊』と同じ……』
唇を噛むアイギスの姿が見えた気がした。アンドロイドは唇を噛まない。そういう理屈とは関係なしに、彼女がそういう表情を声に乗せて語っているのだ。
湊に同じように人間性を与えられたアイギスが、その一点でどうしても望月綾時には勝れず、彼にはなれなかったのだということを暗に示しているようだった。決してそれに成り代わりたかったわけではないが、その埋めがたい溝のようなものはアイギスに唇を噛ませるに足るコンプレックスだ。
『同じだけれど……けれど明確に違うものです。それはまるで……双子のよう、でした。或いは母と子のような』
そこまで言うと、アイギスは口を噤んだ。それで彼女は口にするべきことを出し終わったようだった。
美鶴が息を吐く。
「それでは、彼がペルソナであることに不思議はないと?」
『いいえ……おかしいことは、おかしい、です。あの人は死です。シャドウの上位互換。組成としてはペルソナと殆ど変わらないのかもしれないけれど、重たすぎる。制御出来ないペルソナはシャドウと変わりません』
「有里が何らかの方法でそれを制御している可能性は」
『有り得ます。あの人もまた死そのものになったと言うのならば。ですがそれは、いつ破裂するかわからない爆弾を抱えているのと同じ。あの人は、危険です……『ダメ』なんです。それでは』
昔、綾時に向かって「あなたはダメです」と言い張っていた時と同じ言葉をあえて選んで口にする。『ダメです』また繰り返した。『きっとよくないことが起きる。あの日のように……』
『美鶴さん。真田さん。わたしたちは、湊さんがどうしてペルソナを使えるのか本質的にわかっていないのです。ブラックボックスのまま、湊さんは逝ってしまいました。世界と引換にして』
「何故って、それは彼が『適合者』だったからではないのか。影時間に対する適性があった。確かに、紐解いてみれば彼はムーンライトブリッジの事件に関わっていて……ある程度は幾月に仕組まれていたとも考えられるが」
『いいえ。湊さんが各地を転々として最後に、あの時期に辰巳ポートアイランドに帰って来たのはわたしが埋め込んだ《デス》の帰巣本能によるものだと推測されます。あの人は《デス》ありきでペルソナ使いになりました。或いは、ペルソナ使いという形をとることでカモフラージュをしていたとも。ワイルド能力は『いのちのこたえ』に至るための必要最低条件です。もしも、湊さんの能力がそこに至らしめるために《デス》から分け与えられたものであたっとしたら』
舌の乾いたような声音。焦燥がその中にある。美鶴は押し黙った。アイギスの言葉を自らの浅い考えで遮るべきではない。
『ペルソナは心の形。言い換えればコンプレックスの、傷跡の形です。わたしはみなさんを守らなければいけないという、もっと強くなければというコンプレックスから。美鶴さんは父親を守りたいというコンプレックス……そして真田さんは妹さんを守れなかったというコンプレックス……『有里湊』にはそれがない……』
そこでアイギスは一度息を呑み、呼吸を必要としない機械の唇で深呼吸をした。人間が、一際大事なことを口にするように深く深く息を吸い、躊躇いがちに言葉を紡ぐ。
『いつかその事実が、わたしたちに牙をむくかもしれない』
それを言い終わったアイギスの、あの美しい空色の目が歪むのが確かに見えた。苦痛や、憤り、悲しみ、恐れ、不安、そういった感情が彼女の目を歪ませる。
今まで黙っていた真田が美鶴の傍によってアイギスに声をかけた。アイギスは有里湊に惹かれていた。アンドロイドが恋をしたのか、それとも人間性に憧れたのか、もしくはそれを与えた彼に親への慕情に似たものを抱いていたのか、それを彼女は一度も語りはしなかったが、だから何もわからないわけではない。
『あまり力になれず、ごめんなさい』
アイギスが言った。美鶴はそれを否定する。
「いいや、十分さ。望月も疑問の多い存在だが、問題はむしろ有里の方だということにようやく目が行った。アイギス、少なくとも私はな、彼があまりにも優秀で……万能すぎて……死んで蘇ったかのような姿を今また見せつけられて、まるで神様か何かのように地上に降り立ったのかとそうばかげた錯覚をしていたんだ」
『それは、違うであります。湊さんは人間です。紛れもなく、複雑な感情を持った一人の人間でした。わたしはそれを断言出来る』
「そういうことさ。どんな力を持っているにしろ『有里湊』は人間だった。ならば現在の彼の……『神郷湊』を名乗る少年の欠落の正体は何なのだ?」
『……それはわたしにはわかりません。わたしの記憶にあるのは、あの日の……眠るように逝った湊さんの、最後の姿までですから』
「我々が知るべきは恐らくそれだ。這い寄る混沌と彼が称したものも、きっとそこを狙っていると私の勘がそう告げている」
目を瞑った。今でもまだ、あの日の彼の姿を、穏やかな死に顔を鮮明に想起出来る。
「ありがとうアイギス」
◇◆◇◆◇
「おまえのスティグマータはそのヘッドホンだな」と、そう、藤堂の双子が言った。尚也か、或いは和也か。銀のピアスをスティグマータにもつ双生児のその言葉は、どうしてだか、耳にこびりついて湊の中から離れていこうとはしない。スティグマータ。聖痕。痛ましい儀式のように、からだに、こころに、刻み込まれて残り続ける。
「仮に、このヘッドホンが彼らの言う通りに僕の消えない傷跡だったとして」
手の中で銀色の円盤を二つ弄んだ。召還銃と同じ色をしているが、似ているようでまったく違う意味合いを持つヘッドホン。かつて湊が聞かせてくれた言葉を綾時は朧気に思い出す。――「ヘッドホンは、拒絶の象徴なんだよ。だから」。
「だとするのなら……おまえは……綾時は、僕の何……?」
「……。湊君、それはね、僕が定めることではないんだ。きっとね」
「なら、誰が決めること?」
「君だよ。君にしかそれはわからない」
「僕は。ずっと……綾時が……僕から生まれた意思を持つ何かが……僕の心の傷の形だと思ってた。ペルソナの大元だって。だってそうでしょ、僕のペルソナ能力はあの日ムーンライトブリッジで綾時を、デスを受け入れたところに始まっている」
「そうだね。僕――《デス》は、君にペルソナとの関わりを与えた。それに纏わる運命も」
「だけど尚也と和也は綾時じゃなくてこのヘッドホンだって」
「《拒絶の象徴》。昔湊君は、僕にそう言って聞かせてくれたよ。その言葉が気になって僕はもう一度それとなく君に尋ねたんだ。『君は、どうしていつもヘッドホンをしているの』って聞いたら、『一人になりたいから』って。『ヘッドホンは拒絶の象徴。耳にかけたら、話しかけないで欲しいっていう合言葉と同じ』なんだって。僕は、そんなの寂しくって嫌だって、言ったんだけどね……」
二人の少年が向かい合って座るテーブルの中央に、水晶玉のような球が浮かび上がって映像を映し出す。ポロにアンモールのゲームセンターに三人の男子高校生がいて、何がしかのゲームでスコアを競い合っているのだ。在りし日の伊織順平、望月綾時、そして有里湊の姿だった。順平がごく平凡なスコアを出す隣で綾時が初心者丸出しのボロボロのスコアを出して項垂れ、更にその隣では湊が店内ハイスコアを更新して無感動な顔でそれをぼうっと眺めている。
『順平。約束通り、奢ってよ。ワクドナルドのペタワックセット』
『いやいやいやいや勘弁してくださいマジで! 俺っち今月ウルトラ大ピンチ! 明日にも死にそうなの!! っつかそのスコア何よ、店内ハイスコアどころか全国ランキング入りじゃねえか!!』
『結構得意な感じだったから』
『だーっもうすまして言うんじゃねえよ!!』
そのまま順平は絶望的な表情でいかに今の自分の財政状況が悪いのかと、湊のスコアの非常識さについて説き始めた。財布の残りに札はなく、小銭が数枚、友近に借りに土下座に行く寸前。とてもではないがリーダー様の胃袋を養えるとは思えない。そのあたりで綾時が口を出して、『だったら僕が奢ろうか』などと言い出したのでこれ幸いとばかりに順平がそれに縋り付き、湊が彼にしては珍しく露骨に嫌そうな表情をした。
『なんで。綾時は関係ないじゃん』
『でもほら、ぶっちぎりでスコアが低いのは僕だし。その方が皆幸せになれて、いいよ。ね』
『……仕方ない』
『だって! よかったね順平君……え、そんな、泣かなくっても……』
『マジで恩に着るぜリョージ!! この借りはいつか必ず!! 精神的に!!』
『え、いや、そんないいよ。それにしても……湊くん、ゲーム本当に上手だよね。何か秘訣とかあるの? あ、もしかしてだけどそのヘッドホンとか、実はそうだったりして』
『……それはどうかな。僕にもわからない。ただ……ヘッドホンは、拒絶の象徴なんだよ。だから』
『え?』
『なんでもない。忘れて』
「そう。最初に君は、そんなふうに僕に教えてくれた。君はなんでもないって言ったけれど、尚也と和也が気にするのならきっと何かあるんだ」
「それはエリザベスが僕に言った『欠落』と同じもの?」
「――それはいつかわかるよ」
一面濃い青に囲まれた部屋で綾時が言う。それは丁度、主たるイゴールと助手のエリザベスがいないことさえ除けばベルベットルームそのもののような部屋で、酷く高いところにうまく時刻の読み取れない金時計が掛かっていた。それからエレベーターの駆動部品を隠すようなゆったりした巨大なカーテン。ここは湊の精神世界なのだ。彼にとって精神世界というものが、即ちベルベットルームなのだった。
けれど今は契約をはずれ、契約者の鍵もなくしてしまった。だからあの鉤鼻の老人とエレベーター・ガールのいる「正しいベルベットルーム」へは辿り着くことが出来ない。
「ごめんね湊君。僕には、君を守ることしか出来ないんだ。君に教えてあげられる『正しい』答えも、何も僕は持ち合わせていない。君の悩みを解決出来ない。僕って本当、無力だね……」
綾時の小さな手が湊の同じように幼い手のひらを掴み取る。幻の中にある過去よりも一回り縮んでしまった体躯。その理由も、恐らくはエリザベスの言う「欠落」に繋がっていて、未だに解明出来ずにいる。
「僕ってなんて無力なんだろうって何度も思ったよ。だけど、君を守るって決めたから。君を守りたいって、僕は願ったんだ」
「うん」
「だから、僕は君を守護するものになるよ」
きっと。幼い身体が幼い身体を抱きしめる。
いつか二人がもっと大人の姿をしていた頃に。
あの時果たせなかった約束を今度こそ果たすために《望月綾時》は存在している。
「最後になって、全部わかるんだ……」
「湊君?」
「お前を、この手にかけた時もそうだった。大切なことは、いつも、後からやってきて。僕は覚悟をしていたつもりだったし、実際相当覚悟を決めてた。だけど全部わかったのは最期だった」
「……どういうこと?」
「なるようになる。なるようにするしかない。――仮にこのヘッドホンが僕のスティグマータであったとして」
綾時をソファに押し戻し、湊が立ち上がる。右手に召喚銃を握り締め、ヘッドホンを耳にかけた。プレーヤーのスイッチをオンにする。プレーヤーのウィンドウに躍り出るデジタルの文字列。「NOW PLAYING “Burn my Dread”」。
「だとしても、僕は戦う。それだけだ。……答えを知りたいから」
――昔から、湊はこの曲が好きだった。
理由はない。
Copyright(c)倉田翠.