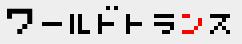Ⅹ FORTUNE:それは残酷なぐらい確かな、
《アルカナ・ユニバース》。誰かのための願いを叶える奇跡。ベルベットルームの契約者がワイルド能力の最後に辿り着けるかもしれないもの。
けれどそれが必ずしもハッピー・エンドを約束してくれるとは限らない。
十年前に有里湊は願った。世界に終焉をもたらしてはいけないと希った。有里湊には絆があり、愛する世界があり、そのために立ち上がらなければならないと心から信じていた。
どうでもよくなんかなかった。
そのためなら、死んでもよかった。
死ぬのは怖くない。初めて満月シャドウが現れた夜に岳羽ゆかりに尋ねたのと同じ言葉を、しかし今はまったく違う意味を込めて反芻する。死ぬのは怖くない。どうでもよくないから、有里湊が愛したうつくしい世界を守りたいから、死ぬのは怖くないのだ。
思えば、「死」というのは最初から彼にとっては近しい、優しいものだった。死は有里湊の隣人でありその身に宿した愛しいものであり、友達だった。
『ね、よければ僕とトモダチになってよ』
死神のあの子の手を取って、契約はそこで交わされた。これから選択することに、責任を持つという当たり前の契約に重ねて、それは二重の契り。
もしも本当に世界から消えてしまうのだとして、だけどそれでも信じたものを守れるのなら有里湊は――《ユニバース》になるだろう。
それでいい。
未練なんか、そこには、ないはずなんだ。
◇◆◇◆◇
「……どこまでシナリオ通りなんだろうな?」
「私のアルテミシアのことか」
「ああ。ここで美鶴が戦力復帰するのは織り込み済みだったんだろうな。山岸のペルソナ程ではないが、美鶴のアルテミシアにも探索スキルは僅かに継承されている。尤も……その気になれば望月が遥かに強力な広域サーチを行えるようだが」
「彼は結局シャドウだからな。同族の探知なら我々より遥かに上手くやるだろう」
美鶴が机上の召喚銃に手で触れて言った。
満月シャドウの討伐は概ね湊の立てたプランの通りに進んだ。その特性からジャスティスとチャリオットが分裂して出現することはない。彼らは必ずひとところに纏めて現れる。そのため、二体の討伐は殆どフルパーティで行われ、バックアップに湊と黒猫がついての総員戦という形になった。
慎がメインアタッカーとなり、アベルの剣を存分にふるう。ジャスティスとチャリオットに関してはそれで何も問題は起こらなかった。しかしその戦闘の途中で美鶴が酷く嫌な予感を覚え、戦線の離脱を湊に提言したのだ。
湊はそれをすんなり受理し、美鶴と真田の抜けた穴に自らと尚也をあてがう。そうして美鶴に連れられるまま向かった先で真田が目にしたのは満月シャドウ《ハーミット》だった。
ハーミットは電撃をすべて吸収し、チャージしてより強力な攻撃に変えて放つという特性を持っている。アルカナの順番通りに今まで満月シャドウは出現していたから、慌てていた美鶴と真田はともかく湊は確実に次に出る可能性があるシャドウがハーミットであることを把握していたはずだ。そしてそれには真田単体では太刀打ちが出来ないだろうということも、予測出来ていたはずなのだ。
「それでも私達を止めなかったのは私が何とか出来るだろうと考えていたからか。確かにそうとしか思えない」
「事実美鶴は引鉄を引けた。お前が正義感の強い人間であることを織り込んでいたわけだ」
「それから負けず嫌いだということもな」
二人して息を吐く。昔からそうだ。有里湊は時折、何かとてつもなく強大な得体の知れないもののような恐怖を他者に与えた。しかしその得体の知れなさと同時に、守ってやらなくてはと思うような危うさもまた同居していて。
「死か……」
――有里湊は。
決してリスキーな賭けを好む性質ではなかったが、自分の負うリスクに対しては無頓着だった。
誰かが死ぬことには過敏だったが、自分が死ぬことには鈍感だった。
悪意や好意には鈍いくせに妙なところばかり敏くて。課外部の誰もがそれに何度も命を救われてきたけれど、その意味で彼の支えにはなれていなかったのかもしれない。
死へと向かう彼を誰も止められなかった。あんなに有里湊に執着していた岳羽ゆかりでさえ。有里湊が、望月綾時の元へ向かうことを誰も阻めなかったのだ。
『契約だよ』
死の声が蘇る。『心配ないよ……この宇宙で、僕は再び、眠りへと還る。今度こそ、本当の日常が戻ってくるよ……君達にも、彼にもね。彼は……“命のこたえ”に辿り着いたんだ。ただそれが、君達より一足早かった……それだけの事さ』。
その言葉が、望月綾時の『ごめんね』というそれに相当するのだということは有里湊が息を引き取った三月になってから、皆が悟った。
「死ぬというのは、一体どういう気持ちなんだろうな……」
桐条美鶴は死を知らない。真田明彦も。瀕死寸前の目には何度も遭ってきたし、それこそ幾月の反乱の時などは本気で死を覚悟したものだが、実際はこうしておめおめと生き延びている。生き延びた。あの滅びの、《せかいがおわるはずだった日》も、結局死ななかった。彼がその存在の全てと引き換えにせかいを救ったから。
遺ったのは彼についての、彼が「生前に」美鶴達に見せたもの、それに纏わる記憶だけ。
有里湊の遺体は眠るように穏やかに目を閉じていた。実際、最期を看取ったアイギスの言葉によると彼は「おやすみ」を言うように、「また明日」と約束をするような優しい声で、「またね」と手を振るように当たり前に、「少しだけ目を閉じて」そのまま事切れたのだという。
『だけど湊さんはその選択で自分が死ぬことをわかっていました』アイギスはまるで悔いるように呟いた。『いいえ、もうずっと前から、湊さんは知っていました。その日自分が死ぬことを。それが人間である自分の最後になることを。そうしてあのひとのところへゆくことを――知っていました。残酷なぐらい確かに……』。
アイギスの手には、有里湊の召喚銃。彼が幾度も幾度も引いてきた引鉄は彼の手垢で僅かに黒ずんでいた。彼が何度、何体のペルソナを召喚したのか? それをもう誰も覚えていないだろう。オルフェウス。ジャックフロスト。サラスヴァティ。フォルトゥナ。タケミカヅチ。キングフロスト。ティターニア。クー・フーリン。スザク。オーディン。ノルン。コウリュウ。キュベレ。ミカエル。サタン。ベルゼブブ。シヴァ。ヴィシュヌ。ルシフェル。ルシファー。メサイア。たくさんのペルソナ達。そして、タナトス。
『死ぬのは怖くないんだって、湊さんは』
もう二度と口を開くことのない有里湊の死体の代わりにアイギスはその機械の唇を震わせ続ける。『湊さんにとって自己の死と生はそう遠いものではなかったんです。彼は十年間死と共にありました。死は湊さんの隣人。だから彼はそこへ行ってしまった。そこに……すぐ隣に行くことで世界を、有里湊の愛したものたちを守れるのなら……』
機械の唇が震えるなんて、おかしいですよね……。アイギスの睫毛が伏せられた。何もおかしなことはないと、課外活動部の誰もがわかっていた。アイギスは心を持つアンドロイド。感情を持つ兵器。それではもう、正しい兵器とは呼べないのかもしれないが、アイギスはそうでいいのだとあの日彼が言ったから。
『だけど私達は湊さんならそうするだろうってことを、わかっていました。彼が。そのためなら。決して死を怖がったりしないって。やさしいひと……あのひとは……有里湊は……』
アイギスは涙を流す。兵器が感情を持つことをダメだとは言わない。機械でありながら人間に近付いてしまった自己を恥じない。
それもまた有里湊が遺していったものの一つだったから。
『確かに生きていた人間だったんです……。』
有里湊は生きていた。きちんと感情を持っていた。大抵は何を考えているのかわかりづらい無表情だったけど、ちゃんと笑うことが出来た。怒りも悲しみもあった。そうしてそれらを呑み込んで、死を受け入れた。
桐条美鶴は死が怖い。もしも自分があの日あの時の有里湊の立ち位置に置かれていたとして、彼のように引鉄を引けるのか、その自信がない。確かに、彼はあの場所で引鉄を引かなければいけないところまで、追い詰められていたというふうにも言えるだろう。彼が大いなる封印をするか、それとも、世界が滅ぶか。とても残酷な二択。約束もあった。彼にとってその選択肢は、最早一つしかないものも同然だったのだ。
だけどそれでも。
「私は自らの中の恐怖を決して無には出来ないだろう。あの場の全員が命を賭ける覚悟を持っていた。だが、だからといって……あんなふうな表情で……私はきっと逝けなかった」
ひとときの休息を取るのと変わらないように眠る死に顔は、自らの死を受け入れて凪いでいた。人生の終焉を惜しむことも、死を迎える恐怖も、およそ人間らしい未練はそこには残されていないように見えた。
「有里は本当に幸せだったのだろうか」
「さあな」
「いや……違うな。そんなことを言いたいんじゃない……本当は……わかっているんだ。あの場の皆が……一度は、彼にあの選択を迫ったことを悔いている。彼を追い詰めてしまったことを責めている。だがそれも元を正せば私達の『彼を失いたくない』というわがままにすぎなくて……」
「望月が言っていた。あいつが何か厄介極まりないものに目をつけられ、今綾凪がこういう状態に陥ったのは、有里が人間だったからだとな。『『有里湊』は決して周囲が思っているような万能の超人じゃなかった。人間だから、ちっとも完璧なんかじゃなかった。有里湊にも本当は人並の感情があって、怒りも憎しみもあって、迷いも悲しみも恐怖もあった。――自らを生贄に世界を救ったことへのほんの僅かな後悔も』。俺は、正直全面的に望月の言葉を信用することは出来ずにいるが……もしかしたら、有里も……」
「死を後悔していたと?」
「その選択を取って、俺達を遺したことを、それによって俺達に混乱を招いてしまったことを後悔していたのかもしれないとは、思う」
そういう奴だろう、あいつは。真田が問うと美鶴も厳かに頷いた。
『おめでとう。奇跡は……果たされた』
宣告者の最後の言葉はそんなふうに締められていた。またいつか会おう。君達が死んだ時に……滑稽な。奇跡は彼の命を供物に贖われたのに。
「どうして……どうしてこんなことを考えてしまうんだろうな? 戦力が増えるのは喜ばしいことだ。その方が作戦も立てやすくなる……理屈としては理解している。私もそうだった。有里が加入し、伊織、山岸……彼らによる戦力増強を指揮官として純粋に有り難く思っていた。だから……あ」
はたと思案気味に動いていた美鶴の指先が止まり、その紅の目が恐ろしい事実に気が付いてしまったというふうに真田に向けられる。真田は震え出した手に自らの手を添わせて、顔を覗き込んだ。美鶴の表情には覚えがある。何度か過去に見た。例えば父親が幾月の凶弾で死んだ時……それから有里湊が自分達を置いて一人でニュクス・コアの元へと逝ってしまった時。
それは桐条美鶴が己の無力さを痛感した時の切望の表情だ。
「ああ……」
「美鶴」
「何故こんなことを考えてしまうのか……わかったんだ、明彦」
「……そうか……」
「そうだ。私は、また彼が自分を犠牲にしてしまうかもしれないことが、怖いんだ……」
ようやく気がついた、というふうに項垂れて美鶴は祈るように両手の平を併せる。最早祈る神など持ち合わせてはいなかったが、それでも、手は自然と祈祷の形を取っていた。
「私一人がペルソナを取り戻したところで、有里一人の持つ戦闘能力に比べたらそれは微々たるものでしかない。『彼が前線に立って戦い続けられる』のなら、私一人にシナリオを割く必要すらないんだ。まるで……まるで、自分が使えなくなる時のための、保険のような……。明彦、私は……私のペルソナ能力の復活がもし彼が思い描いている自己犠牲のシナリオのためなのだとしたら、私はペルソナ能力など使いたくない」
◇◆◇◆◇
ソファの上で、子供が一人寝こけている。遊び疲れてしまった幼児そのものの姿格好だったが彼が遊び疲れたわけではないのだろうということはわかっていたので、洵は首を傾げつつも毛布を取り出して彼に掛けてやった。掛けっぱなしのヘッドホンに繋がっている青いウォークマンは再生中のままで、一定間隔で曲名とアーティスト名のアルファベット表記を繰り返していた。
使用者が寝ているからか、普段はずっとと言っていいぐらい彼のそばに侍っているペルソナの姿もない。こうしていると、彼は無防備な子供そのもので、当たり前の人間みたいで、洵はそれがちょっと嬉しい。
「たまにはお兄さんらしいことさせてくれないと」
『よぉ、洵は今帰りか。……あぁ、そいつさ。寝てる時は存外子供っぽい顔、してるよな。まるでただの子供みたいに』
「そうだね。ただいま、尚也。それから和也も」
『お帰り。って……おい、何してる』
「何って、猫を抱っこしてるんだよ。ほら、あったかいし。僕ね、尚也の毛並み、つやつやふかふかで好きだな」
『ったく……』
洵は物好きだな。そう呟く尚也の声はしかし満更でもなさそうで、喉をくすぐると猫の本能に負けてにゃんごろと鳴く。そうして間近で見ると猫らしからぬ右耳のピアスの装飾がより目立って、光を受けて反射し煌めくように見えた。ふと何の脈絡もなくそれに触れる。すると黒猫の尻尾がたしなめるようにその手を撫でた。
『悪い。あんまそれ、触らないでくれ』
「あ……ごめん」
『や、そんなに駄目ってわけでもないんだけどな。この体になるまでは手持ち無沙汰になるとしょっちゅう癖で自分で弄っちまってたし。ただ、傷痕みたいなものなんだ、それは。湊のヘッドホンと同じだな』
「傷? でもピアスホールのことじゃないでしょ?」
『まあな』
洵の腕の中で実に猫らしく丸まりながら尚也がもっともらしく頷く。湊のヘッドホン。掛けっぱなしの耳に繋がっているそれには、まだ音楽が再生され続けている。曲目は「 Burn my Dread」。『恐怖を燃やし尽くせってのは大分苛烈だよな』黒猫が人事みたいに言った。
『傷痕ってのはさ……目には見えず、だが確実にそこにあり、醜きを晒し続ける……そういうものだ。別に常にじくじく疼いてるとかそういうわけじゃない。それは単なる消えないかさぶたみたいな……それだけだよ。後生大事に抱えて棄てられないトラウマと殆どニアリーイコールだ』
「あ……ちょっと、わかるかな。それ」
『へえ』
「トラウマとは違うんだけどね。僕も結祈の服、棄てられないから」
形見に近いものがある彼女のワンピースのことを思い浮かべた。神郷結祈の生きていた証明の一つのように思えて、また無碍にしてしまうように感じられて、洵はクローゼットの中にそれを綺麗に畳んで仕舞っている。あれを棄てる日というのが、うまく想像出来ない。
神郷結祈は、神郷洵の双子の妹は、つい半年も前まで死後もずっと洵の身体の中に生き続けていた。精神として、洵に寄り添い二人で一つだった。慎もその事を知って受け入れてくれていた。洵のペルソナ能力は繋ぐ力。それは閉鎖された二人で一つの世界に生きていた洵と結祈が、他者と関わるために生み出したものに近しい。だから、定年前だけど洵はもうペルソナを使えない。
「ねえ、尚也って、大学生なんだよね。どんなふうだった? 慎兄も今大学受験中で……あと、単純に藤堂尚也って人に興味があるんだけど。湊、寝てるし良かったら教えて欲しいな」
『俺のこと? 別に面白いことはないと思うけど』
「でも、ペルソナ能力に目覚めた切っ掛けとか。そのピアスのこともね、そういうふうに言われるとなんとなく気になるし」
『んー。まぁ、暇だからいいけど。期待はすんなよ。……俺がペルソナ使えるようになったのは、そん時流行ってたらしい『ペルソナ様』っていう遊びをして……契約をしたからでさ。丁度その頃住んでた街も異界化しちゃって……それでまぁ、否応なくペルソナを使わざるを得ない状況になった。死にたくなかったからな。生きるためには戦わなきゃならなかった。で、気が付いたらペルソナも育ってた』
「ペルソナ様遊び?」
『俺がペルソナ使えるようになったとこだとそれをしないと契約が出来なかったんだ。確か達哉も子供の頃にしてて、それで高校の時にペルソナが発現出来たっつー理屈だったはず……』
「……達哉って誰?」
『あぁ、言ってなかったか。俺と一緒に今回の黒幕に捕まってた奴のことだよ。俺はこんな姿でも一応脱出に成功したけど、あいつはまだ捕らわれたままだ。そういうわけで、達哉の奪還は湊の目的の一つでもある。俺としても一緒に閉じ込められてたってのもあって、達哉はあそこからなんとしても出してやりたいって思ってる。まあ平たく言えば利害の一致ってやつだな』
「そうなんだ。全然知らなかった」
洵は心底驚いたように、それから少し悲しそうにまなじりを下げた。湊に隠し事をされていたということが、存外ショックだったのだろう。だから黒猫は首を振って、それを否定する。湊の行動理念はもっと純粋だ。
『あいつは秘密主義だとか、隠し事をしてるとかじゃなくて、ただ必要ないことは口には出さないんだ。たまに必要なことも口に出して言わないけど。頭はいいけど、意思疎通はちっと苦手っぽいとこあるよな』
「それってなんだか……さみしいね」
『生き方っていうか、それまで生きてきた時間の結果、って感じもする。これは聞いてるだろ? あいつは天涯孤独だったんだ』
「うん。家族は、不思議な感じがするって」
『綾時のやつは家族とかそういう線引きを超えて、半身、みたいな感じなんだろうな。あいつはあれで、慎と洵のことはすごく大事に思ってるよ。あいつが二人のことを兄と呼ぶのには、それなりの意味がある』
絆ってやつ。そう野暮ったい言葉を口にする黒猫の竜胆の瞳は真剣だ。『あいつにとって、絆っていう繋がり方は、本人が自覚しているよりもずっと重い意味を持ってると俺は思う』。
そうしてその絆を引き裂き、姑息な手段を用いて悪辣に利用し、粉々にするのが今現在この綾凪を襲っている敵だ。湊本人が蒔いた種であるということ以上に、それが湊を強く動かしているのかもしれないと黒猫は考えたことがある。世界にまるで無頓着なように見えて、実のところ湊は「世界には」きちんと執着を持っている。でなきゃわざわざ肉体を構成してまで死の扉の前から街一つのために降りようなどと考えないはずだ。
『まあ、そんな感じで達哉のためにも、そしてあいつ自身のためにも黒幕は倒さないといけないわけだ。黒幕のことは、聞いてるか?』
「最初に少しだけね。確か……『この世界の法則を歪めてしまえる』存在だって、綾時が。尚也はそれがどんな姿なのか知ってる?」
『一応戦ったことあるし。むしろ姿形に関しては湊も知らないんじゃないか? 多分、正確に把握してるのは達哉だけだな。それでもどういう存在かってことだけは断言できる。最低最悪の野郎だよ、俺が知る限りでも』
「……すごい言い方だね」
『事実を歪曲しても仕方ないしな』
《這い寄る混沌》ニャルラトホテプ。その行動理念は「人間に異常な負荷をかけることで急速な進化を促す」というものに基づいているらしいが、結果的にそれは人々の破滅への手招きと変わりない。心弱き者を奈落へ引きずり込むとする一方で達哉にあの終わり方を課す。達哉は決して心が弱かったわけではない。ただ、大事な人を失いたくないという、人間のごくありふれた感情を殺すことが出来なかっただけだ。
それをどうして、「心の弱さ」だと責められようか。
その意味で極限まで「心の弱さ」を殺したのが尚也の知る湊という少年の側面の一つだったが、あれはやはり、歪で、アンバランスで、あれが「進化した人類の姿」に成り得るとは思えなかった。ただの特異でしかない。
そしてそんな湊でさえ完璧に心をなくすことは出来なかったから、今綾凪はこうして異常事態に見舞われているのだと理解しているし、だから湊は達哉や尚也を救おうなどという行動に出たのだというふうにも理解している。
神郷湊は確かに人間ではないが、それでも人間らしい残滓は抱え込んでいる。
『ニャルラトホテプっていうそいつは、基本的に精神攻撃というか揺さぶりが得意だ。そこから、不信を煽って自滅なんかの形でもろともダメにしようとする。だから洵、お前は――湊を信じてやってくれ。出来ればこの場にいない慎にも。得体が知れないところもあるだろうけど。俺と和也はそういうのも含めて『神郷湊』のことを信頼しようって決めたんだ。あいつに助けられた時、一つの恩返しの意味も込めて』
「へえ……」
猫を抱いたまま未だに眠りこけている話題の当人に歩み寄り、その寝顔をそっと撫でる。子供らしいふにふにした肌の感触は、とても死そのものから出来ているとは思えないぐらいに優しかった。「優しい死」。いつか湊が綾時をさして言った言葉。
自分も優しいのに、と洵は思う。きっと湊はそのことを自覚してはいないんだろう。
「尚也も和也も本当に湊のことが好きなんだね」
『まあな』
「そっか。それって、すごく素敵だよね」
顔を近づけて、肌を重ねて、そうすると心音が響いてくる。規則的なリズムを刻む鼓動。ああこれは守る音なのだとその時何とはなしに思った。何かを守ろうとして、戦っている誰かの。
――それはまるで宇宙みたいに雄大で。
「湊の優しさは、ひょっとしたら、人間には残酷すぎたのかもしれないね……」
湊は疲弊しきった軍人のように眠り続けていた。これだけ肌を触れあわせても目を覚ますことがないのは、やはり、奇妙な感じがすることだった。
Copyright(c)倉田翠.