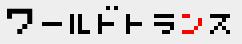ⅩⅠ STRENGTH:コールドストーン・ブルー・ムーン
『……一番怖いのは……死ぬことじゃない。一番怖いこと……それは……執着してしまうこと……』
修学旅行から帰ってきてすぐの日のことだった。ペルソナ《メーディア》を携えた少女が、幽鬼のようにタルタロスの前に立っているのだ。チドリ。《ストレガ》のひとり。開発によって後天的にペルソナを付与され、その代償に「命が終わる日」を予め設定され、生きてきた少女。
伊織順平が愛した少女であり、伊織順平を世界中の誰よりも深く愛し、それによって「人間らしさ」を手に入れた彼女は、それまで使い捨てのカイロみたいに思っていた自分の命を、奪われるばかりですり減っていく石鹸みたいに思っていた自分の能力が、はじめて愛しく思えたのだ。大好きな順平。心が痛いのは彼とずっと一緒にいたいから。怖いのは、彼を失いたくないから。
離れたくない。
『そうすれば失くすのが怖くなる。物だって、命だって、なんだって……。だから私たちはいつだって今という瞬間を楽しむだけ。刹那的な快楽でよかった。なのに……なのに順平は私に要らない苦しみを持ってきて……私は……私は、順平と一緒にいると、今までどうってことなかったものが、どんどん、怖くなるの……。失くすのが怖い……死ぬのだって怖い……一緒の時間が終わっちゃうのが……すごく……怖い』
少女の独白を、遠くから見ていた。死ぬことが怖いと、執着が恐ろしいと言う少女を、曖昧な距離から。ああ、彼女は、「似ている」。少年にはそう思えた。
最初は怖くなかったものが、いつの間にか、怖くなるのだ。
『私たちはあなたと違う。最初にペルソナを得た時からわかってた。『ストレガが命を失う日』』
ストレガは薬物投与で暴走するペルソナを抑えつけている。その副作用は、短命。幼少期から薬物に頼り続けてきた彼らにはもう後がない。いずれ死ぬ。わかっている。だからチドリはそれを選択する。
『自分が死ぬ日のことなんて……今まで一度も想像したことなかった……。ねえ、順平……『死ぬ』って、もう会えないってことなのね……』
この時彼女は初めて「奪われる」のではなく「与える」ためにペルソナを使った。自らの意志でその全てを伊織順平のために捧げた。悲しくなんかない。くだらなくなんかない。彼女が命を捧げるのには意味があり、生命を投げ出すのには理由がある。
自らが次の生命の礎になれるのならば、伊織順平の血と肉となって、彼を守護することが出来るのならば、それは彼女にとって決して愚かな選択ではなかったのだ。
『だからね、これでよかったの』
少女が笑う。花みたいに。満開の時を超え、今から穏やかに終わりを迎える季節の最後の花みたいに、笑う。
それが吉野千鳥の願いで、吉野千鳥のその時持てる全ての感情で、吉野千鳥の一番したいことだったから。少女は笑っている。彼女は幸せだった。
『でも、私は……私はなんでそんなこと選べるのかわかんないです。選んで、欲しくない……』
少女は俯く。まるで納得出来ないメロドラマの悲恋を目にした後のように、沈鬱にそう呟く。彼女も理屈ではわかっている。やがて死ぬことを自覚していた少女が出来る、それが最善の行動だったのだろうということは、わかっている。
だけど岳羽ゆかりはそれに頷くことが出来ない。
『そんなふうに残されたら、私、どうしていいのか、わかんないから……』
顔を上げないままそう言った彼女が、数ヶ月後にコロッセオ・プルガトリオで取った選択は「有里湊を取り戻したい」という、エゴイズムだった。
◇◆◇◆◇
ワイルド能力は空っぽの力。普通のペルソナ能力者のように明確な自己や強い自我を持たないから、空っぽ。
だけどだからこそ何にでもなれるし、無限の可能性を持っている。鼻の長い老人の言葉を借りればそうらしかった。
有里湊という少年は、ゼロでありインフィニティだったのだ。
神様になることも、悪魔になることも、人間になることも、人でなしになることも、父になることも母になることも兄になることも弟になることも死ぬことも生きることも。
彼には無限の可能性が与えられていた。
結末を選び取ったのは彼自身の意志。ユニバースへの足掛かりとして始めに契約を交わしていた有里湊は、自らの選択に責任を持たなくてはならない。
「慎兄のアルカナは、正義かなぁ。うん……それらしいよね」
珍しく洵も連れないで、湊と慎の二人きりで外に出ていた。月の満ち欠けが局地的に狂って、気候なんかにも変化が出てきてしまっているので今綾凪市では急病人が急増している。真田が覚えのある顔で「無気力症か……」と拾い上げていた意識がおぼついていないケースから、果ては体内のサイクルを崩して病を患うケースまで様々だ。最も軽く、かつ頻発しているのだとなんらかの機能不順に陥り、下痢なんかの軽い症状を複数併発するものが挙げられるらしく、それに今のところかかっていない人間はペルソナ使いであるかその素養があるかのどちらかだと美鶴は見解を述べていた。
そういう人たちが稀に影時間に象徴化出来ずに倒れたままでいる場合がたまにあって、それの見回り番が今夜は湊と慎だったのだ。ぎらぎらと異様な明るさを誇る月を背景に歩きながら、湊がぽつりとそんなことを言う。今夜はそれほど、象徴化に失敗した一般人はいないみたいで、気がゆるんでいるのかもしれなかった。
「そうか?」
「そう。僕の知ってる正義アルカナのペルソナ使いの子と少し似てる。正義って多分、ヒーローらしいとか、正義感に満ち溢れてるだとか、それだけのことじゃないんだと思う」
「お前の知り合い、ペルソナ使い多いよな……」
「……そういうところだったからね。ある種作為的に、ペルソナ使いが集められてた、から。引かれていたんだ。或いは惹かれてた……あの場所に。十人と、それから三人」
十年前、辰巳ポートアイランド。私立月光館学園に影時間の間だけ現れる塔タルタロス。十二の大型シャドウ。そして死の体現である宣告者。
そこに集った十三人という、目を疑いたくなるような規格外の数のペルソナ使い達。桐条美鶴に始まり、真田明彦、荒垣真次郎、岳羽ゆかり、伊織順平、山岸風花、天田乾、アイギス、コロマル。白戸陣、吉野千鳥、榊貴隆也。そして有里湊。
運命だったのかもしれない、という考えを否定出来ない。
その全てはムーンライトブリッジで有里湊が「死」を封じられたことから始まり、そして「死」を封じたことにより終わったのだ。
「へぇ……。なぁ、湊はアルカナとか無視してポンポン無節操に使うけど、それでもなんか得意なのとか、あるのか?」
「別に、得手不得手はない。ただ……ええと、僕の一番最初のペルソナ《オルフェウス》は《愚者》で、あの子がくれた……《タナトス》は、《死神》だった。敢えて言うのなら、この、ふたつ」
「零と十三か。湊らしい意味深な感じだなぁ」
「そうだね。《愚者》アルカナが適性の人なんて、そう滅多にいるものではないと思う」
愚者はゼロだから。空っぽのアルカナ。湊はあのいつものがらんどうの灰ねずみの目でそう言う。まるで何も見ていないような冷めた目。これが、時々、はっとしたような青に染まることがあって、慎はそれでやっとこの目は別に湊が特別何かを思っている時のものではないのだと気が付いた。湊を迎えてから、確か三日目ぐらいに。
であるから彼は、自分の適性アルカナが「空っぽ」のアルカナであることを、恐らくどうとも思ってはいないのだろう。彼にとってはふぅん、と慎が聞き流してしまえるぐらいの、「ふつうのこと」なんだろうと思う。
だから、ふぅん、となんでもないことのように、頷いた。湊が本当に空っぽだなんて、思っていないけど。
「《愚者》は。空っぽで、ゼロだけど、始まりのアルカナ。旅人が歩き出す第一歩みたいなもの。人間に無限の可能性があると言われるよりも多岐にわたって、愚者には千万の可能性があった、ってイゴールは言ってた。……結局僕が最後に選んだのは小さな結末だったけど、慎兄、すごく怖い話なんだけどね……」
「うん?」
「《愚者》は、救世主にも破壊者にもなれるんだ。なんにでもなれる。あの子の《死神》をもう一つのパーソナルとして持ってなかったら、僕は一体何になっていたのか、それがまだ……全然、自分でもわからない……」
内緒話をする男の子の顔をした死が嘯いた。
「どうでもよかった、から。下手したら、傍観者になってたかも」
ぞくり、と背を這い上がる感覚を覚えて慎は身震いする。一瞬だけ、湊の目が見たこともないような色に染まっていたような気がしたのだ。影時間の月の色だ。あの気味の悪い満月の色。黄色。濁って、翳りを帯びた奇妙な黄色。酸化したゆで卵の黄身みたいなすっきりしない色。
わかんないけどね、もしもの話なんて、どうでもいいし。二度目の「どうでもいい」を口にする頃には彼の瞳はいつも通りのくすんだ灰色に戻っていて、後ろ手に組んだ手で手持ち無沙汰そうに召還銃を弄っていた。なんでもないよ。ごめん、こんな話して。そう告げるが、「忘れて」とは言わない。慎が忘れるよと返してくれないことをわかっているのか、それとも忘れて欲しくないのか。そのどちらだとしても、強烈な言の葉。
「……だとしても、湊は、傍観者にはならなかったと思う」
絞り出すように口から吐き出されたのはそんな台詞だった。
「何かはしたと思う。湊は傍観者って感じじゃない」
「そう? 自分でもかなり厭世的だと思ってるんだけど」
「人付き合いは確かに下手だけどな。厭世的な傾向があるのと、『執着をもたない』のは、まるで全然違うものだ。俺は、アルカナとかそういうオカルトっぽいことはそんなに詳しくないけど……確か性格付けの占いみたいなのがあるんだっけ? そういうので考えてもさ、何にでもなれるってことは、つまり色んな要素を持ってるってことだろ。違うのかなぁ」
「さあ。結果的に、僕は最後は選び取っちゃったから。どうかはいまいち、断言出来ないけど。それってつまりはあっちつかずこっちつかずのふらふらってことなんだけど……『何にでもなれる』っていうのは、『なる何かを選び取らなきゃならない』ってことでもあるから。そういう意味では確かに傍観者は選べなかったかも。だって見てるだけって、自分で選んでないのと一緒だし」
「ああ。まあ……でもしか論だけどな」
慎が困ったように言うと湊は小さく笑んだ。「そうだね」と平坦な調子で零して慎に背を向ける。
「あの時僕はこれでいいって思ったんだ。これでよかった、って」
それから右手に持った召還銃で前触れなく自らの頭部を擬似的に撃ち抜き、今まで引っ込めていた彼を召還する。望月綾時。神郷湊のペルソナを名乗る何か。
ずっと湊の隣に侍るもの。
そういえば、慎は――慎以外も――どうして綾時が、湊よりもはっきりと感情を表して意思を表明する彼が湊の隣にあることを決めたのか知らない。最初からそうであったため、それが当然だと思っていたけれど。
湊の言葉に今度々出てきた「あの子」という表現が妙に引っかかって、連鎖的にその事を思い出した。湊を守護するため。それは聞いていたけれど、隣にいなければ出来ないわけじゃないかもしれない。人間じゃない人間らしいものが、どうやってペルソナの枠の中に収まったのか? 真田と美鶴の反応では、「望月綾時」は本来ペルソナではなかったはずなのだ。
《死》そのものだったと。
(《死神》……)
綾時が変化するペルソナ《デス》の姿は、棺桶を駆る処刑人のそれだ。湊が言うことには、《タナトス》という、見たことのないペルソナに近い姿をしているらしい。
死を司る神の。
どうして死を宣告する何かが、何かを守ろうだなんて思うのだろう。
『湊君、僕、今ちょっと眠いんだけど……』
「もう夜。十分休んだ」
『そんな……君ってそういうところ、非情だよね……』
二人の間にはどんな繋がりがあって、本当はどういう関係で、どういう存在なんだろう?
『君のためだから頑張るけどね。次のシャドウのこと? サーチしたけど、別に今日出るとかそんなことはないよ?』
「知ってる。でも、せっかく慎兄が暇そうだし、対策しておかないと。もうすぐハングドマン戦。あいつが、どういう強さになってるか推測出来ない。メインは慎兄だし。……慎兄!」
「へっ?! あ、あぁ、なんだ?」
「僕が今どこまで出力出来るかのテストも兼ねて、手合わせしよう」
「ああうん……って?!」
今なら誰も止めに来ない。心なしかうわずって爛々としている眼差しで見上げてくる。湊と慎の間には二十センチ以上の身長差があって、それは上目遣いなんて生やさしいものにはなっていなかった。見上げてくる巨人のような。自然と生唾を呑んでしまう。
そういえば今日はピアスの黒猫を一緒に連れていないから、抑止力は期待出来そうにない。何せ力比べでは圧倒的に湊が有利なのだ。
湊はやる気満々といった風体で早く構えろと催促顔をしている。これは多分、最初から、そのつもりで慎を指名して連れ出したのだ。してやられた。
「じゃなくて! なんで急にそんなこと?!」
「慎兄がもやもやしてる感じの顔だったから」
「え」
「すっきりしない時は、身体を動かすといいと思う。それに、稽古になれば一石二鳥。――もうあんまり時間がないかもしれないし」
「それってどういう……はっ?!」
そのまま二言を許さず、湊は素早く攻撃態勢に入った。どこに隠し持っていたのか、それとも自分で今作ったのか(召還銃も作ったらしいし、有り得る)、いつの間にかレイピアを右手に握り召還銃を左に握り直している。綾時がまだ少年の姿をしていることだけが救いで、慎はそこで我に返ってすんでのところで剣先をかわした。
カツンという鈍い音。刃先が壁にぶつかったのだ。刃こぼれ一つせずに煌めき、逆に壁を削り取っている。これが人の肉体に触れたら、と思うと恐ろしい。レイピア自体の強度や威力もそうだが、使い手の力も尋常ではない。
少なくとも外見に見合った小学生の握力程度で済む話ではない。
否応なしに、戦う意思がなくとも自衛のためにアベルを喚ぶはめになる。せめてペルソナを出しておかないと、生身ではとてもガードすら追いつかない。
「心配しないで。そんなに酷い怪我はしないと思う。あと、治すし。チェンジ、《スルト》」
「そういう問題じゃないんだって……ああもう、アベルの剣の効果範囲、湊だって多分例外じゃないんだぞ!!」
「構わない。僕に傷を付けられるぐらい慎兄が強いんなら、それはそれで」
炎を纏った男神が現れて広域火炎を放つ。アギラオだ。アベルに高速移動させてその場から待避し、一時避難に空中へと逃げ込む。この、ペルソナを用いた浮遊という手法は慎以外はあまり取らない、というか取るのが難しいらしい。湊相手でも数秒は稼げるだろう。
「どうすりゃ……」
が、やはり数秒だったようで、スルトが引っ込んでピクシーが代わりに現れ、ものすごい速度で迫ってくる。機動力に特化した小妖精は、アベルの姿を認めるとにこりと微笑んで裂けてしまいそうなぐらいににんまりと唇を歪めた。そして何かの攻撃フォーメーションを取る。何か考えるよりも先に、反射的に回避行動に身体が動いた。やばい。あれを喰らったら、本当に、まずい。
「メギドラオン」
巨大な光弾が慎の視界の端を掠め、飛び去り、衝突した先で酷く巨大な爆発を起こした。十数メートルは先の臨海方面の上空だったが、慎の身体に届くぐらいのフラッシュと爆風を生み出している。慎は渋々湊の真意を探るのを諦め、アベルで応戦の態勢を取った。きっと、一太刀入れるまでは終わらせてくれないし、逆に言えば一本取れば終わるということでもある。
何を考えているのかと問うのは、それからでも遅くないだろう。諦観に呼応するようにアベルが剣を掲げた。同時に、ピクシーが青い蝶のような粒子になり、そこから《デス》が姿を現した。
◇◆◇◆◇
目を覚ましたのは自室のベッドの上でだった。片付いていない部屋の中央に立っていた少年が、振り向く。神郷湊。神郷姓を結祈に貰ったと自称する不思議な子供。
ぼんやりとそんな言葉を羅列して、この少年について不思議でない事項が一体どれだけあるのかと自問した。殆どない。
受け入れると決めたのに、やっぱりまだ、何も知らない。
「起きたんだ」
「……どのくらい?」
「一晩。たいしたことない。普通に、寝過ごしただけ」
「……どうだった?」
「惜しかった。あと一歩のところで、慎兄がオーバーフロー起こして気絶しちゃった。慎兄は、そこらのシャドウ相手なら引けを取らないとは思ってたけど、あそこまで動けるとは思ってなかった。ハングドマン戦もよろしく」
「その、ハングドマンっていうのは……次のシャドウなのか?」
のそのそと上体を起こして、頭をぐしゃぐしゃに掻きむしりながら問う。湊は簡潔に否定の意を示し、「ちがうよ」と答えた。
「ううん。次はフォーチューンとストレングス。これも、たぶんセットで来る。フォーチューンがストレングスを補佐するっていう戦闘スタイルだから」
「じゃ、ハングドマンに何か強い思い入れでも? ほら、やたら昨日も強調してたし」
「最後の一つだし。これが、一番、桁外れに強かった。それに、倒した後何があるかもわからない。コンプリート直後は存外に危険だよ」
とてとて寄ってきてはい、と服やら何やらを手渡される。受け取って黙々と着替える態勢に移り、その中で少しずつ意識を失う直前の記憶を手繰り寄せた。
まず湊が尚也に「やめておけ」と釘を刺されていた、あの彼の最強ペルソナであるらしき《デス》を容赦なく召還し、しかも一切の制限を設けずにぶちかました。本当にあの綾時と同じ存在なのかと疑いたくなるような迫力を伴って飛来する死神の猛撃をすんでのところで最初はかわしたものの、埒があかず、結局地上に引き戻され、そこで湊が舌打ちと共にペルソナを再召還した。
次のペルソナは《ルシファー》。慎でもロールプレイングゲームなんかで聞きなじみのあるような上位悪魔だ。そのルシファーも一発二発攻撃をさせただけで引っ込め、湊はそこから次々と召還するペルソナの「ランクダウン」を試み始める。
湊が最後に《アリス》で再召還を止めるまで、彼が喚びだしたペルソナはざっと三十体ほどにも上った。三十体というのは概算で、実際は、十八体を過ぎたあたりでカウントは止めた。そんな体力が残っていなかったのだ。
強力なペルソナをラッシュのように召還することで湊の方も結構体力を削っていたらしく、それもあって、慎は何とか即死はせずに済んだ。だが、アリスが出てきて「このへんが限界かな」と湊が呟いたのを最後に記憶が曖昧になっていて、結局一太刀入れられたのかどうかは思い出せなかった。
「推測に過ぎないけど、聞いてるニャルラトホテプの性格からして、十二の満月シャドウだけ倒したらはいおしまい、っていう仕掛けになってるとは思えない。少なくともオリジナルのシナリオをなぞるか、改変ぐらいはしてくるはず。……十年前、十二の満月シャドウを倒した後に起こったのは、すごく緩やかな変化だった。僕の前に綾時が現れた。それだけ。でも、それは、仮初めの平穏で」
幾月の反乱の後、やってきた「転校生」の望月綾時。有里湊によく懐き、明るく、快活で、世界の全てをうつくしいと感じられるような、何もかもが物珍しい新生児のような、不思議な少年だった。
事実として彼は殆ど新生児そのもののような存在だったから、その感想はあながち間違ってはいない。「望月綾時」はこの世界に生まれたばかりだったのだ。
有里湊という卵から養分を集めて孵った雛だった。
「十二の死の破片を僕が集めきって、《宣告者》望月綾時がその存在を現した時点で《世界のおわり》が、決まっていた。僕達が満月シャドウを倒して作っていたものこそが、十三番目のアルカナを持つ《デス》だった。……同じようなことがあった時に何も手を打てていないときっと酷いことになる」
「つまり今回綾凪でハングドマンを倒した後に、直後にしろ間を置くにしろ何かしら一悶着起こる可能性が高いってことか」
「間があればマシな方。対策とか、強化とか、もしかしたら出来るかもしれない。だから多分間はないはず。そういう生やさしい相手じゃない。そう、聞いてる。でもこれで慎兄の力は測れたと思う。付き合ってくれてありがとう」
「あ、ああ……」
「それから僕の限界も。やっぱり、どうしても、この身体はデスみたいな強いペルソナの召還に耐えられないみたい。特にコミュニティ最高ランククラスのやつ……この身体を作るときに何か欠損したって、エリザベスにも言われたから何かそれが関係あるとは思うんだけど。自分じゃ、それが何なのかさっぱりで」
「エリザベスって誰だ」
「バス停を振り回すエレベーター・ガール」
「……物騒だな」
どんな筋骨隆々の女性なのだろう、それは。
「戦ってればわかるかもって放置してるけど。考えても良くならなかったから……フォーチューンとストレングスもすぐに来るだろうしね。考えてる時間がないってのが、本音」
ベッドから離れて着替えを終えた慎の手を取ってぐいと引っ張る。何事かと声をかける前に正面に向かい合わせに態勢をずらされて、湊が無言で何かを差し出してきた。青を基調としたデザインのカードだ。二枚あるそれのトランプのような装飾面を裏返すと、中まできっちり描き込まれたものと枠だけが描かれたものが顔を覗かせる。
片方は《Ⅷ JUSTICE》と書かれた天秤と剣の図柄だった。タロット・カードの大アルカナだ。つまりもう片方は白紙のアルカナ・カードか。
「これ、持ってて。お守りみたいなものだから」
「持っておけばいいんだな?」
「保険になるかもわかんないけどね。手段は一つでも多く必要」
「わかった」
「じゃあ、よろしく」
それで用事は粗方済んだのか、じゃあね、と手を振って湊が背を向ける。その後ろ姿をぐい、と強引に引き留めた。まだ聞きたいことが残っていて、すっきりしない。
「ちょっと待ってくれ……なあ、湊。良ければこれだけ聞かせてくれないか。昨日の夜からずっと気になってた。綾時は――なんなんだ? ペルソナ、ってのは聞いた。死の宣告者だった、ってのも聞いた。元々人間じゃないっていうのも。ただ、引っかかるんだ……どうして『死』が、生を守ろうとする湊の守護なんか、やってるんだ? そのズレって、何か意味があることじゃないのか……?」
引き留められたことに一瞬だけ顔を顰めたが、話に真面目に取り合うつもりはあるらしく、思案するような素振りを見せる。少し俯いて考えてから、湊はすぅ、と慎の心臓を指さした。
「慎兄の『アベルの剣』みたいなものだと思う、僕は」
首を傾げてあまり自信がなさそうに言う。アベルの剣。つまりはイレギュラー。
「一つ言うのなら、僕と綾時にはすごく特殊な絆があるってこと。それはコミュニティでもあるし、それでは括れないもっと大きなものも含まれてる。最初に、確か綾時のことは人間じゃないって教えたと思うけど、実のところ『望月綾時』は半分だけ人間だった。僕から手に入れた人間性。綾時は死という概念だったけど、あの時、僕だけは綾時を殺すことが出来たんだって……」
殺す、という言葉を口にした瞬間湊の眠たげな瞳がまるく見開かれた。カッ、と一際強く、まるく。まるで影時間に見る満月みたいに。その中に交錯するぐちゃぐちゃの感情の切れ端が透けて見えて、それはどうしようもなく「人間臭かった」。
「殺さなかったけど。殺せなかった。そんなことをしてもなんにもならなかった」
本当に、綾時を殺したところで《世界のおわり》が回避出来るわけでもなかったし。
それを彼はらしからぬ感情的な声で告げる。
「湊にとって、綾時は」
「こどもだよ」
「……は?」
「それから、友達。僕とあの子のコミュニティは『トモダチになってよ』っていう、契約で始まった。僕は……」
また、湊が慎を見上げた。だが昨夜突然手合わせを仕掛けてきた時のような挑発はない。もっと切迫している。余裕がなくて、ただ、切々と事実を並べるので手一杯みたいで。
こどもとおとなが混在して、冷静さを欠いてすらいるようで。
「僕は綾時を、あいしてた」
灰ねずみの死の色の瞳は、今ははっとするようなあおいろで、冷たい大理石のようにつるつるして、鋼鉄のように硬く、少年の眼窩に嵌っていた。
Copyright(c)倉田翠.