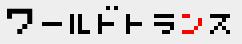ⅩⅣ TEMPERANCE:自発的ハリネズミ
「――ようこそ、ベルベットルームへ。我々はあなたを、ずっと、お待ちしておりました」
軌道エレベータのように無限に上層へと登り続けるその青い部屋の中央に主たる鼻の長い老人と、付き添う形で老人の補佐をする住人が存在している。老人・イゴールはにたりと微笑みテーブルの上のタロット・カードを繰った。
あまり、驚きはなかった。彼らの部屋に、自らの意思で青い扉をくぐる以外の方法で訪れるのはいつも突然で、唐突で、そして時と場を選ばなかったからだ。彼らはあのニュクス・アバターと戦った最後の決戦の最中でさえ有里湊をこの不可思議な青い部屋へ召喚した。
「あなたは、今再び選択をなされました。左様、それは難しい選択です……十年前の契約書へのサインが有効であること、覚えておりましたかな。あなたはかの《愚者》と契約をされました。『自分の選択したことに責任を持つ』という単純明快な取り決めのことですよ。……ご覧なさい」
タロット・カードのうち数枚が老人の手に導かれて空中に浮かび上がる。《女帝》《皇帝》《正義》《節制》《月》。それらが丸く円を作り、中央にヴィジョンを映し出す。
そこには影時間の満月の下に直立する少年の姿が映り込んでいた。月光館学園の男子制服を着て、顔の半分を覆う前髪の上からでもはっきりとわかるほどに爛々と両眼をあのおぞましい黄色に輝かせている。それは握り締めた召喚銃でペルソナを喚び出し、堂々とその名を口にする。ペルソナ《オルフェウス》。はじまりの愚者アルカナを持つ有里湊の原初のペルソナにして、その能力そのものの具現化した姿だ。
「十二の擬似シャドウを倒すという選択に重ねて、あなたは自らのシャドウを拒絶するという選択を取りましたな。自らのペルソナ、仮面の根源と向き合うのは大変に難しいことです。しかしそれこそが、大きな力を得る代償として本来払うべき対価でもあります。件の藤堂尚也、周防達哉……彼らも、そうしてその先へと進んでゆかれました」
「二人を知ってるの」
「勿論ですとも。お二方とも私の大切なお客人。そう……あなたはご存じのはずですよ。藤堂尚也が受け入れた自らのシャドウを……」
「……和也」
「正に然り。その通りです」
あれは極めて珍しいレアケースですがね……タロット・カードの《皇帝》と《月》を指差してイゴールは言う。シャドウとの長期的な対立と現状の副次人格としての共存は他に類を見ない関係性だ。和也、という主人格の死に別れた兄の名前を与えられることで彼の存在は一種の独立を見ている。
「彼らの言葉を借りれば、それは必要なイニシエーションなのですよ。あなたのお仲間もそうだ。彼らは皆、自らの弱さを受け入れそのペルソナを進化させて参りました。あなただけが特別だった。特例だったのです。あなたは一切の通過儀礼を通らず、しかし契約に則ってそれを果たすために大きな力を手に入れられました」
「それがユニバース。何も持たない愚者から、全てを包括する宇宙まで貴方は歩んで行かれましたわ。絆の力を借り……通過儀礼を相克されました。しかし、既に貴方はお気付きになられましたね。置き忘れていった……ご自身の欠落についてです」
「僕の未練……」
「ええ。そしてそれは、貴方の『人間らしさ』でもある」
神郷湊の欠落である「有里湊の未練」。未練は捨てたつもりだった。後悔もないつもりだった。だけど、人間だったから。ましてや、自らの能力の根源と密接に結びついたそれを、失うことは出来なかったのだ。
あの一年間で、何度もフラッシュバックした断片的な、記憶とも言えないトラウマがある。ホワイトアウトしていく視界の中に遠ざかっていく誰か。車。事故。衝突、衝撃、破片。悲鳴。血飛沫、断末魔。悪夢。死。二十年前のムーンライト・ブリッジにおける事故による有里夫婦の絶命と一人残された湊少年、それからその中に強引に宿された死神。
有里湊の第一の未練、愚者の素養はあの瞬間に確たるものとして発生した。
「わたくし、貴方について、あれから随分と調べました。力を管理する者の権限で全書に記録された貴方のタナトスの姿をお借りして、あちこちにちょっかいを出したりもしましたわ。けれど、やはり、我々ベルベットルームの住人はお客人の因果に干渉するべきではないし、また、干渉出来ない、そう、理解しました。誠に残念ですが、わたくしでは力不足……役不足だったのです。けれども」
そのことを思い出して、硝子玉を濁らせる湊に彼女はにこりと微笑んだ。ちょっとした悪戯や、アイディアを思いついた彼女が興味津々といった様子で度々見せた表情だ。ポロニアンモールから始まり、巌戸台、長嶋神社、月光館学園、そして自室、それらに案内してやった時のようにきらきらした笑顔で、まるでせいいっぱいの優しい顔みたいに微笑んで、彼女は指し示してくれる。
「物語の主役を張ることは不得手でも、舞台を整えることでしたら、このエリザベス、得意分野でございます。あちらをご覧くださいませ」
すっ、と示された手の向く方を見ると見慣れない扉が鎮座していた。深層モナドへ続く扉のように豪奢に飾り立てられているが、そのせいで余計に曰くありげな雰囲気を醸し出している。
黒壇のような滑らかさの中に、夜闇の深淵を彷彿とさせる鈍重さが入り込んでいるのもその原因なのかもしれなかった。酷く重たい。その扉の向こうに待っているものに対する警戒心を否応なく喚起させる。
「……あれは」
「主の役目は、決して物事を破壊させる助長ではありませんし決断を迫ることではありませぬゆえ。選ぶのは常に、お客人自身。願うことも祈ることも、剣を手に取ることも、先を望むことも、全て貴方の意思なのです。しかし此度のベルベットルームへの来訪は、貴方自身は望んでいない……そう、お思いでしょう。ふふ……特別ですよ。《彼》が、どうしてもと依頼されたものですから。我々はこの精神と物質の狭間にある部屋の住人として役割を果たしましょう。それが、あの扉」
彼。彼女の所へ、と言って湊を助けその腕の中に抱いたデスのことだろう。あの子は、元々人間じゃないし正確には湊のペルソナではない。だからそういう、反則みたいな橋渡しが出来たのだ。
或いは保険として湊と共に綾凪へ向かう前からこの取り決めを交わしていたのかも知れない。望月綾時はともするとぽやんとした印象も与える、天然という言葉がよく似合う男だったけれど本質のデスやファルロスはそうではない。
そういえば。ここに来て、綾時がそばにいないことに思い至った。現実に一人で残ったというのか? では湊のペルソナは?
「あの扉はその先の世界へと繋がっております。貴方がきっと、会って話がしたいと思っていた方のところへ導くことでしょう。我々にお手伝い出来るのはそこまででございます。それ以降は、保証出来かねます。行きはよいよい、帰りは怖い……童歌にもございますね」
「……あの。綾時がここにいないってことは」
「ああ、貴方のペルソナ能力のことでございますね。通常、自らのシャドウと向き合う際は……《シャドウ》を喪失した状態となりますから、その投影であるペルソナは満足に喚び出せない場合が殆どです。けれども、貴方は元々類い稀なるペルソナ能力者。《死神》と《愚者》以外なら、アニマの投影でお喚びになれるかと」
「それを聞いて少し安心しました。それなら一人でも……なんとか」
「その点についてはご安心くださいませ。わたくしが共に行くことは出来ませんが、貴方はお一人ではなく、絆の力を得て、その先へ進むこととなるでしょう」
「え?」
一人には慣れているし、と言うよりも早くエリザベスがそう突きつけてくる。一体扉の向こうには何があるというのだ。
「さあ、どうなさいますかな、お客人」
一通りの説明をエリザベスが終えたことを確かめて今まで彼女が喋るに任せていたイゴールがその重たそうな口を開く。扉を開くか、閉じたままにしておくか。そのいずれかを選択せよ、という示し。
湊は首を振る。小さな体躯で、右手に銀色の銃を手にとって、彼らと相対している椅子から立ち上がった。
「決まってる。行くよ。それが僕の選択」
「左様でございますか」
「はい」
「フフ……宜しい。では、お進みなさい。あなたのゆく道に幸運があらんことを……」
イゴールは一切の表情を変えなかった。それが長鼻のこの部屋の主のスタンスであることは十年前から知っている。彼の言葉の端々に含まれる喜色からちょっとした推察ぐらいは出来るようになって久しい。
ある種の安堵をそこに覚えて、酷く安らかな顔で住人達に背を向ける。またきっと、会うことがあるだろう。エリザベスの意味ありげな言葉に、そんな気がした。
「じゃあ、また」
扉に手をかけ、少しだけ振り向く。
「行ってらっしゃいませ――有里様」
エリザベスは微笑んで手を振り、湊を送り出した。
◇◆◇◆◇
ペルソナ《オルフェウス》。手に抱えた竪琴で音色を奏でるのかと思いきやそのまま振りかぶって殴りつけてくるような、随分とワイルドな《幽玄の奏者》だなと感じたのを美鶴はつい昨日のことのように覚えている。忘れもしない、あの二〇〇九年四月九日の影時間のことだ。有里湊がはじめてペルソナを喚び出した、満月シャドウ《マジシャン》の襲来の日のことだった。
岳羽ゆかりが取りこぼした召喚銃を手に取り、逡巡の後彼は引鉄を引いた。狂ったような笑顔と喚び出された《オルフェウス》の暴走のような暴れ方。その後に、湊の苦しげな呻き声と共にオルフェウスの身体を突き破って内から現れ出たのは、後に彼が愛用することになるペルソナ《タナトス》の姿をした何かだった。
今、目の前で顕現している死神を眺めながら茫洋とそんなことを思い起こす。きっとあの何かは、《タナトス》ではなく宿主の生命の危機にそれを守らんと這い出てきた《デス》そのものだった。
「やれやれ……まったく手のかかる後輩達だな……」
身体を確かめて立ち上がる。寸前に湊がかけたリカームドラの効力で体力は取り戻している。戦える。戦わなければ。
桐条美鶴は気丈に振る舞い、眼前に展開されている光景に立ち向かう決意をする。あの、在りし日に失ったまぶしい彼の似姿を捉えて俯くことを拒否した。美鶴の覚えている彼の姿そのままに、立ち、喋り、ペルソナを喚ぶ彼のシャドウ。
混乱はあったが、意志の力でねじ伏せられる程度のものだ。この現象に関しては類例を幾つか見たことがある、というのもあった。六年前の八十稲羽市で起こった《マヨナカアリーナ》事件で一人につき一体、このような《シャドウ》が現れ、事態を翻弄した。
「あの時とは、どうも性質が異なるようだがな。問題ない。おい、望月、あれを倒せばいいのだろう?」
『えっ? あ、はい……取り敢えず、倒して弱体化しないといけないから……』
「ならそれでいい。単純明快だ。明彦」
「ああ。とはいえ俺達には未だ飲み込めていない事実が多い。指揮はお前に任せる」
『俺も指揮は綾時で賛成。ついでに説明も適宜してくれると助かるかな』
レイピアを鋭く振り、問うと真田と尚也もそれに乗る。その様に影は肩を竦め、は、と息を吐いた。
「わお。尚也はともかく、美鶴先輩も真田さんも全然容赦ないね。言っておきますけど、僕は、強いですよ?」
「知っているさ。その方がやりがいがある」
「ああ。お前は常に『強かった』よ。悲しくなるぐらいにな……私はそんな有里を見ているのが、時折酷く辛かった。だからその彼の人間性がお前だと言うのなら、私は戦うことを畏れない」
「ああ……美鶴先輩らしいですね。冷静で冷徹なふりして、その本音は偽善に似た、ただの身内への甘さ。そのうち足元を掬われますよ……こんな風に!」
オルフェウスが大口を開けて吼え、そこから波状に衝撃波が発生する。その場の誰も彼もが、吹き飛ばされないように身を屈めた。湊の影が卑屈に嗤う。
デス――望月綾時は棺桶が鎖状に繋がれた背の装飾を広げると彼らを守るように前面に躍り出た。アベルを出したまま呆然としている慎を背後に捉え、吼える。慎の隣には、湊を追って追いついて来ていた洵がいて、現状ペルソナを出せない洵が、今立っている人間の中で最優先の庇護対象であることは疑いようがなかった。
慎が問う。
「……綾時……だよな? あれは、なんなんだ。湊じゃないのか? どうなんだ……?」
『あれは、湊君だよ。湊君の一部。湊君の未練そのもの。それを湊君自身が否定してしまったから、影は自由を得て暴走する。……今、湊君は仮初めの肉体を置いて精神だけで大切なことのために向かっているから、彼を黙らせるのが僕の役目』
「倒したら――どうなる」
『それで湊君が死ぬとか、そういうことはない。むしろ、倒せないと、死ぬ。湊君のみならずここにいる全員が……いいや、この世界の全てすらも、かもしれない。湊君の現在の本質は《ニュクス》。時間経過と共に《ニュクス解放化》が進行し、それそのものになったらもう手が付けられない。僕は夜の子。悲しいかな、子のさだめってやつで、親には逆らえないんだよね……』
それが出来たのなら、十年前に彼の望みで僕は母を止めていたもの。おどろおどろしさすらある死神の姿で、そんな人間らしい綾時らしいことを言う。慎は出来るだけ手早く状況を整理しようともたつく思考を動かした。
あれは湊。慎が出会った「神郷湊」の、十年前の姿と殆ど同じ外見をしているのだろうということは真田と美鶴の反応でわかった。つまりあれが「有里湊」なのだ。特別課外活動部のリーダー、一人で何でも出来る無類の強さを誇る「ワイルド能力」の持ち主。あんまり笑わないし、怒らないし、泣かない。目に見える感情が希薄で――これは神郷湊も同じだが、決定的な差異として、神郷湊にはかつての有里湊に見られた表立っていないだけで人並みに持ち合わせていたらしい感情すら一部すっぱりと欠損しているかのようだった――そして自己犠牲を選択することが出来る、そういう人間だった。
人間だ。
話に聞いていたり、幻覚で何度か見た有里湊よりも目の前の何者かが感情変化の起伏に富んでいるように見えるのは、恐らくそれが《シャドウ》の本質だからなのだろう。まるで抑圧された鬱憤を晴らし、解放し、自由になろうとしているみたいに湊らしからぬ高揚した、暗い瞳の輝きをその中に孕んでいる。
『来るよ、戦う意思がないのなら、伏せて後退して』
警告の後、また強烈な全体攻撃。その後、湊の影はあの鈍く光る銃口を自らの頭に突きつけて、一切の躊躇いなく引き抜いた。ぱきん、というペルソナ召喚のエフェクト。口端をにたりと歪め、どこかハイですらある表情で次のペルソナを召喚する。
顔つきは、まるで、気狂いのようだった。
だけどそれが間違っているとは、思えなかった。
「ああ……くそ……」
神郷湊が「人間らしくなかった」のは、感情を削がれていたから。何者かに感情を抜き取られ、十二のシャドウの形に変えてばらまかれた。感情があった頃の記憶があるから、それに基づいて感情らしきものの真似事も出来るし推察も出来たので、完璧に欠けているようには見えなかったけれど違和感は拭えない。それを初めて強く慎が感じたのが、《ラヴァーズ》討伐の際のことだ。
幻覚攻撃の中で見えた湊は理不尽に理不尽と言うことが出来る少年だった。だけど神郷湊は理不尽をそうあるものと享受した。
シャドウを一つ倒す度、人間らしさ、感情、が彼の中に戻っていったのかはわからない。ただ確かなのは、目の前の有里湊の影だというものはその抜け落ちた感情そのものの集合体で、剥き出しの《有里湊の本音》で、だから……
「《アベル》!!」
「《アリス》!!」
湊の影がアリスを呼び出すのと同時にアベルが高く飛び上がる。かわいらしく会釈する少女の姿をしたペルソナに容赦なく斬り掛かり、アリスがたじろいだ。湊の影がはっきりとわかりやすく、舌打ちをする。
舌打ちをする神郷湊なんてものを、出会ってからこれまでに慎は目にしたことがない。
「わかった。俺も、戦う。綾時の説明は理にかなってるし、俺もあれは湊の中に返してやらないといけないと思うから。……頼む。一番あいつのことをよく知ってるのは、きっと綾時なんだろ?」
『そうだね……わかった。慎は、前に。真田さんも前衛。美鶴さん、バックアップ。尚也、和也でもいいけど、サポートペルソナに替えて。女教皇は……』
『あんまよくないけど使えないこともない……かな……《スクルド》!』
『そうしたら、使えるまでスクルドを降ろしてて。洵は、僕の後ろにいて欲しい。僕が何としても守る。洵が傷付くことを湊君はきっと悲しむから。お願い、そうさせて』
「………………うん」
『ありがとう』
話をしている間も、湊の影は攻撃の手を休めてくれはしない。アベルに斬り掛かられてよろめいたアリスを間髪入れず戻し、次のペルソナに入れ替えた。愚者《オルフェウス・改》。それが両手を広げると上空から光が差し、そのすぐ後に強烈な閃光が慎達の視界を覆い尽くした。あまりにもまばゆいシャインスパーク。「まずい、食いしばれ!」美鶴が叫ぶ。
「《明けの明星》だ! ――耐えねば死ぬぞ!!」
眩しさに灼けてしまうようで、痛みのような熱さすら感じる。これを喰らうとこうなるのか、と痛みが通り過ぎた後になってじわじわと衝撃が這い上がってきて、美鶴は食いしばりながら心臓のある位置を手で押さえた。
《明けの明星》。かつて有里湊が操っていた最高クラスのペルソナ《ルシフェル》が得意としていたその技を、美鶴は何度も目にしたことがる。真田もだ。深層モナドに出入りして「望月綾時の元へ向かうために」剣を振るうようになっていった頃の彼が、なりふり構わず敵を殲滅していた頃の彼がしばしば用いた強烈な一撃。まず人間が受けてまともに立っていられる代物ではない。最前列に出ていた慎を包むように庇い立てしていた死神の姿を見てそれを強く感じる。
あの死ねない死に傷を付ける、それほどの、《有里湊の悪意》。
「たいしたものだな。そうか……これが……彼から私達への報いか」
同じく耐えきった黒猫のメディアラハンを受けながら汗ばむ額を拭った。それを見て、「まあ、これぐらいはふつうですよね?」と湊の影はにこにこ笑って言う。
それからまたアベルが飛びあがった。カエサルのサポートを受けてまっすぐにオルフェウス・改に挑み、しかしすんでの所でペルソナを引っ込め再出現させることでそれは交わされてしまう。
「ううん……違う……あれは、悪意じゃないんだ……」
その光景を見ながら、洵は静かに首を振った。湊の影は確かに暴走して、牙をむき、本体に成り代わろうとしたけれど、あれが攻撃的なのは悪意があるからじゃない。敵意の鎧を身に纏っているからなんかじゃない。もっと根源的な何かだ。まるで殺されそうだから先に殺そうとしているみたいな、切羽詰まった余裕のなさ。
「もっと寂しくて悲しいもの。『わかる』よ、湊。それが僕と結祈の持つ力だった。なのに……」
有里湊は決して仲間達を恨まなかった。それは嘘偽りのない本音なのだろう。湊の後悔や未練が形を成したものが今立ちはだかっている影だけれど、その組成は誰かへの悪意で出来ているわけじゃないはずだ。
悪意が、敵意があるとしたら、結局は湊自身になのだ。
(そうやって追い詰めちゃ駄目だ)
ちらりと見遣ったが、やはり綾時は何も言わない。わかっているのかもしれないけれど、その余裕がないんだろう。洵を守っているからだ。ただでさえ戦力差が厳しいところに、お荷物がいたら当然かもしれない。首を振る。それじゃ駄目だ。
(守られているだけなんて嫌だよ)
湊の影が次なる攻撃モーションに入る。洵は反射的に身構えて、一歩二歩と後ずさった。その時何か、硬いものにかかとがぶつかって眉を顰める。屈んで確かめると、それは見覚えのあるものの形をしていた。
銀色に鈍く光る、死を強く想起させるもの。空っぽのマガジンラック。「S.E.E.S」の刻印、そのそばに「M.A」という所有者を示すマーク。蒼い蝶がセミオートマチックの本体から浮かび上がり、羽ばたいて洵の前を横切った。
――世界がすごく遠いもののようだった。
誰の声も、ペルソナの音も、何も聞こえなくなった。白い。(ここは)見渡しても誰もいない。さっきまでの戦いは? そう思うと、現実(だろう、恐らくは)の光景が白亜に被さるようにちらつく。明滅して、かぶる。
「さあ」
金属の塊に手を伸ばした。持ち上げると、これが結構重い。プラスチックには再現出来ない重みが――いいや、もっと強く怨念のように纏わり付く、そういう積年の想いがそこにあって、知らず喉がひくついた。いつか、アヤネと共にいた時のようなふわふわと浮ついた感触は今度は微塵もなくて、その分重力がとみに厳しいものに感じられる。
右手を拳銃のかたちにして、人差し指を突きつけるジェスチャーを誰かがする。大丈夫だ。出来る。一人じゃない。洵のペルソナ《セト》はそういうもの。二つで一つ、一人で二人、繋ぐちから。
そうして神郷洵は、神郷湊の召喚銃を、あのねずみ色の死がいつもそうしていたように、引鉄にしかと指をかけかしりと銃口を頭に押しつけた。
◇◆◇◆◇
ひとりぼっちで、てくてくと歩み続ける。宇宙を模した空間に、すごろくのような迷路が張り巡らされていて、ここはどこなのかと思考する以前に出口があるのかということを湊は真っ先に心配した。出口のない迷路ほど悪質なものもない。そんなものの中に出てしまったのだとしたら、完全に手詰まりだ。
太陽のない世界で、LEDの人工灯のような奇妙な灯りに照らされながら歩いて行く。確かこういう図面を、曼荼羅というのだか、と朧気な記憶を手繰り寄せた。
「……結局一人なんだけど。エリザベスが嘘を吐くとも思えないし……」
見覚えはまったくない空間だし、人どころか襲ってくるシャドウすら見あたらなくかったが誰かが存在していた感触をそこかしこに感じて、不可思議な気持ちになる。ここで昔何かあったのだ。誰かが、一人じゃない、複数だ――ここに目的を持って訪れた。
(何かを救いたかった気持ち……?)
懸命に戦ったのだと思う。強く、心が痛むほど強い感情の残滓達。自分の手で幸せに出来なかった人のことを思う誰かの後悔。そういったものが、ふわふわとあちこちに浮かんで、行き場を無くしてたゆたっている。
(……違うかな。ただ、必死だっただけだ。自分の目に見える世界だけでも、守りたかった……)
その一つに触れ、両腕の中に抱いてそう結論づける。無数に漂うそれらに目を遣り、湊は歩く足を止めた。無限曼荼羅の中の、恐らく中央に立って辺りを見回す。そしてはっとしたように口を開き、浅く息を漏らした後首を振った。
やってくれる。あのエレベーター・ガールの彼女は、本当に、舞台を整えることに関しても超一流の手腕を兼ね備えているらしい。
一体どういう理屈を用いたのか、彼女が有里湊が死んでからの十年間で何をしていたのかはわからないけれど、今ここに湊が送り込まれたという事実が千載一遇のチャンスであるということは嫌という程理解出来た。
「ここ……達哉の世界だな……?」
首から下げた携帯音楽プレーヤーを心臓を握りしめる代わりに握る。この痛ましい感情は周防達哉のいつかの残滓。もしくはそれに類する感情。かつてここで誰かが迷い、進み、戦ったのだ。
そうして世界は救われる。ペルソナ使い周防達哉の、いない世界が。
「それが僕の生きてきた世界ってこと、かな? つまりここは……歴史の分岐点」
「そう。ニャルラトホテプが、天野舞耶達と交戦して、そして敗れた場所。《モナドマンダラ》って、言うんだって」
「――?!」
「私は聞いただけだけどね。青い服を着たお姉さんが、そう言ってた」
さっきまで誰もいなかったはずなのに、振り向いたモナドマンダラの中央地点に人が立っている。湊はその人物に覚えがあった。知っている。彼女のことを忘れてはいけないと思っていた。「もしもは、絶対に叶わない平行線のこと」だと彼女は湊に言って聞かせてくれた。
「私の名前、覚えてる?」
少女が言った。はじめに、「名前をあげる」と言った時と同じように。
恐る恐る口を開く。彼女ががっかりしたりしないように慎重にだ。
「結祈」
「そう。よく出来ました」
答えると彼女は笑った。白い何かの生き物の羽が、神郷結祈と湊の間を横切って、消えた。
Copyright(c)倉田翠.