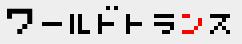ⅩⅤ DEVIL:星と花束、イデアの海と
『キミ、最近結構笑うようになったよね』
ある日少女がそう言ったので、僕はそうかな、と首を捻った。確かそう、冬頃のことだ。あの滅びの塔タルタロスを登りシャドウを薙ぎ払い進む中でのこと。《宣告者》から一つの決断を迫られ、その期日がもうぞろすぐそこまで迫ってきていた。大晦日、二〇〇九年の終わりの日、その最後の時間にもう一度だけ返事を聞きにくると彼は言った。
選択肢は、シンプル。
望月綾時を殺すか殺さないか。
忘却と共に滅びを受け入れるかそれでもなお抗い続けるのか。
答えはもう決まりきっている。一つしかない。一つきりしか。それ以外の答えを塞いだのはきみのくせに、おかしなことを言うんだね。そう最後に呟いたらあの子はただ一言「ごめん」と言った。
儚い顔で、無理矢理笑おうとして、そうしてぐしゃぐしゃに泣きながら。
『……そうなの?』
『うん。最初の頃なんか、ずーっと能面で、無表情でさ。フランスのビスク・ドールみたいですごく整った顔なのに激怖だったよ。まるで死んでるみたいだった。生きてる気がしなかった。でも、今の有里君は大丈夫だね。ちゃんとここで、生きてる』
『まるで死んでるみたい……』
『あ、ごめん、悪い意味じゃなくて。いや、悪い意味か……悪気はないの。ただ、本当に、人形みたいだな、って……』
『……仕方ない。《死》が僕の中にいた。僕はずっと《死》と一緒だった。……あの子はいい子だよ。最後に僕に、色々、返してくれたからね』
『……綾時君?』
『その時初めて僕は、自分に欠けてるものがあったことを知った。……ゆかりとか、順平とか、先輩達とかが僕に抱いてた違和感のこと、僕自身は知らなかったんだよ。わかんなかった。あの子が産まれて……世界ってきれいだねって言うから。僕は、そのことを、思い出したんだ……』
だから。強く思う。剣を握る手に力を込めて強く強く。だから望月綾時には言ってやらなきゃいけない。大晦日の日に、決断を、固い決意を、告げる。断固として。こればかりは譲ってやるわけにはいかないのだ。
『だから、せめてあの子のために笑ってあげなきゃ』
あなたが教えてくれた世界、僕が君と見たもの、青い空、紅葉、季節、星空、小さな街、学校、金閣寺、京都駅、あの日見つけた名もない星、その全てが、そうだね、やっぱり、きれいだねって。
泣きぼくろの上に流れていく涙を拭って、抱き締めて、それから話して聞かせてあげたい。
『綾時は僕の笑顔が、好きだって、言ったから』
僕のする、面白いんだかつまんないんだかわからない話が好きだって言った君に、やっぱり面白いんだかつまんないんだか僕にはわからないけれど、それでもたくさん聞かせてあげる。ゼロから百まで、もっと先まで。始まりから終わりまで。君と僕が一緒にいる限りに。
君に話してあげたいことがたくさんある。
『誰かのため……』
『そういうことになるの、かも』
『……そうだね。有里君は、……』
たとえば海が青いこと。夏の陽射しが眩しいこと。かもめの鳴き声。桜の花、満開になると一面桃色になる。秋しか知らない君に、冬を見せて、これが雪だよって撫でてあげる。春の花々、夏の野草、みんなみんな、あれも、これも、それも。
きれいなものが好きなうつくしい君達。機械人形の少女とあの子は、本当はすごくよく似ていて、あんな形で出会わなければきっといい友達になっただろうに。死ぬのが怖い機械と死にたくない死。内包する矛盾が、二人を引き合わせ、そうして現在を招いたのかもしれない。
僕が生きている理由も、そこにある。
『そうやって、いつも最後まで自分のためには……』
ゆかりが言い淀んだ。言われなくとも、薄ら彼女の言わんとしていることはわかる。きっぱりしていて、そうして厳しい彼女は一度僕に怒ったことがあった。自分の意思がないのなら、来ないで、イライラするから、って。
けれど僕は自分がしたいから、今度こそ、そうするだろう。その決断を選ぶ。綾時に突き付けてやる。例え彼女が、誰が止めてもだ。そういう僕だったからこそ、自分で決めたことはすごく大切だった。
「自分の選択に責任を持つ」。それがまず初めにあの子と交わした約束なのだ。
『……ううん、いいの。わかってる。そういう君だから、私はきっと有里君のことが好きなのよ』
『――え?』
『なんでもない。行きましょ、まだ私、体力あるから上に行けるわよ』
ゆかりが笑った。月光館に転入して来てから何人もの色々な笑顔を見てきたけれど、ゆかりの笑顔だけはいつも奇妙に鮮烈に僕の目に焼き付く。例えば順平なんかはスカッと笑うし、綾時は本当に心から楽しそうに笑う。ゆかりは、その時々で様々だ。泣き笑いをしていたこともあった。今は、ちょっとだけ苦しそうだ。
僕のせいなのだろうか。
けれど僕は綾時にこの言葉を伝えてあげなければいけない。あいしてるよ。そう、言って聞かせてやらないといけない。
それでゆかりがまた、奇妙な笑顔を僕に見せても。
胸の辺りがちくちくして変な感じだった。この気持ちを何と言うのか、あの子なら、僕に教えてくれたのだろうか。
◇◆◇◆◇
かつて世界が二つの可能性に真っ二つに分岐したことがあって、その中心に五人のペルソナ使いがいた。《這い寄る混沌》との戦いの後、しかし天野舞耶は命を落とす。四人の少年少女はその末路を、あまりにも無慈悲な結末を受け入れることが出来ない。彼らには何故天野舞耶が死ななければならなかったのが理解出来なかった。勿論、そんな理由は誰にもわからない。そこには理不尽しかない。そこでフィレモンの言葉を信じ、四人は新たな世界の可能性を創造した。代償に、新しい世界では彼らがペルソナ使いになるという事実を含め、諸々の事柄を全て忘却するという条件付きでそれは行われた。
しかし、ただ一人周防達哉だけは、余りにも抱いていた想いが強すぎて。
――元の世界を棄てることが出来なかった。
「それが《特異点》の意味……周防達哉の罪……」
モナドマンダラに記録された過去の幻影をまとめると、おおよそそのような経緯があって彼はニャルラトホテプの玩具として囚われるに至ったらしい。大切な人の死を受け入れられず、新しい世界を創造するという手段への逃避それそのものがニャルラトホテプの付け入る隙となったのだ。
彼は後に「やり直した世界」の自分の自我に「やり直せなかったの世界」の自分の自我を上書きし……と言うよりはうまく同調出来ずにそれが現出してしまったために、やり直した世界が崩壊しかねない爆弾となってしまう。よって彼は一旦はニャルラトホテプを退けたものの、自らの意志で「やり直せなかった世界」へと戻ることを余儀なくされてしまったのだ。
顔を上げ、それを仰ぎ見た。眼前に球体が浮かび上がり不気味に胎動している。それはともすると漆黒の繭のようでもあり、底なしの沼のようであった。触れると、生温かくぶにょりと震える。それでいて少し手を突き刺すと簡単にその中に呑み込まれてしまいそうになる。
「そして、これが周防達哉の罰。ただ一人新しい世界に適応出来ず、古い世界に取り残されて……永久の時間を過ごす……」
内部にどのぐらい空間が広がっているのかは外からでは推し量れそうにもない。モナドマンダラの一角で湊は立ち尽くし、隣に立つ少女を見た。神郷結祈、十年前に死んでしまった少女。湊に名前をくれた「姉」は、はしばみの色をした長い髪を二つに結わえてそこにいる。
「だけどこんなの、どうやって助ければいいわけ」
「さあ。それは、私にはわからないな。私に出来るのは湊の命綱と無防備になる精神体の外殻のガードぐらい。いつ何が起こるかわからないしね」
「……というか、結祈って何が出来るの?」
「それは勿論湊を応援することよ」
「……何しに来たわけ?」
見たところ、達哉を解放するのに役立つ何かを結祈が持っているようには見えない。湊は訝しげな目で彼女を仰ぎ見た。そもそも今結祈はペルソナさえ使えるかどうか定かではない。
すると胡乱な眼差しを送っていたことに気付いてなのか、結祈はちょっとだけ困ったように笑った。
「私は座標なのよ。私と洵のペルソナ《セト》は元々そういう力。一人でなんでも出来る湊のペルソナ達や、戦うために強い力を発揮出来るお兄ちゃん達のカインやアベルとも違う。鎮め、癒し、繋ぐもの。だから湊は何処へ行こうと思っても大丈夫。私が絶対に連れ戻してあげる。帰してあげる。この中に入っても、絶対にね」
「……ペルソナ使えるの?」
「洵は引鉄を引いたよ。私も一緒にね。湊の召喚器、落ちてたから借りちゃった。引鉄を引くのは……あれは、死を想うこと、なのね。それで私と洵がまず繋がった。元々くじらにお願いしてたのも少しあるかもしれないけど」
右手で拳銃の形を作り、人差し指を突き当ててトリガーを引くジェスチャー。昔、ファルロスも同じように湊に死の想起を促したことを思い出す。「さあ」、と耳元で囁いて。
「……。結祈はなんで僕を助けるの。ちょっとそれが……わかんないんだけど」
胡散臭いものを見る目つきで湊は結祈に向き直った。
「え、理由、必要?」
「わかんないと……納得出来ない」
「ええと……あのね、『くじらのはね』っていう、絵本があったのよ。私達の両親が描いたんだけど……絵本作家だったの……その絵本で、主人公の男の子は最後に満ち足りた気持ちになって……だけど、大切な人達のこと、全部忘れちゃうの」
「それが、何?」
「諒お兄ちゃんは絵本を塗り潰して、慎お兄ちゃんは自分自身の記憶を塗り潰しちゃった。……湊もね、それによく似てる。ほっとけないの。……わたしは」
食い下がる湊を結祈はとても穏やかな表情で見詰めた。そうして後ろから両腕で抱きすくめる。感情を抜き取られ、悪用されてしまったがために力を欠いて縮んでしまった小さな体躯は結祈の細い腕の中にすっぽりと収まってしまう。
湊の耳元に唇を寄せた。青い髪の毛が鼻にかかって少しだけくすぐったくて、切なかった。
「わたしはくじらのはね」
「――?!」
「そしてくじら。くじらはね、皆の心の溶けるところ。心の海、とも呼ばれてる。私は私という『神郷結祈』であって、またくじらの一つ」
「心の海、って」
「ペルソナ能力の根源、意志の力。私はね、湊にずっと恩返しをしたかったんだ」
トン、ととても軽い音がして、湊の小さな体が傾いた。球体に頭からぶつかり、ぶよんという反動の後ずぶりずぶりとその中に沈み込んでいく。告げられた情報と今降りかかってきている現状とがいっぺんに襲ってきて、ごちゃ混ぜになり、湊の思考を掻き乱す。
間もなく湊は周防達哉が幽閉された世界にすとんと入り込み、結祈の視界から消えた。周防達哉もまた、くじらはねの少年とよく似た選択をとってしまった一人で、そうして最悪の結果を突き付けられた人間だった。世界を丸ごと作って記憶を塗り潰したけれど、耐えきれず、決して幸せに満ち足りた気持ちにはなれなくてそれが剥がれ落ちてしまった。
達哉と湊は、似ていて、そして明確に違う。
「きっと湊なら皆を助けられるよ」
現実世界での戦いは洵が、だから結祈は精神の世界で湊を補佐する。ニャルラトホテプがゆすり起こしたものは、本当は湊が乗り越えなければいけなかった試練が変質したものだ。それを正しい形にして湊に返す。それが結祈の選んだ答えだった。
「死んで、私知ったんだ。君がずっと守ってくれているってこと。私達も、洵、慎お兄ちゃん、諒お兄ちゃん、皆湊に守られてた」
あの死者と生者を隔てる扉に半身を埋め、まるでモニュメントのように、磔の聖者のように、そこにあった少年の姿を思い出す。くじらに溶け、彼の意味を知り、ずっと感謝していた。
「だから今度は私が湊を守ってあげる。……頑張って、湊。そして今度こそ……」
ありがとうと、言ってあげたかった。
「湊の伝えたいことを伝えたい人達に、ちゃんと伝えられますように」
両手を組み、祈るようにまぶたを伏せる。モナドマンダラに住まう悪魔達が異変を嗅ぎ付けて急速にポップし、湊を呑み込んだ球体めがけて襲いかかってきた。ヴァルキリー、ヴァスキ、シュブ・ニグラス、フェンリル、ベルセルク。決して弱い悪魔達ではない。かつて周防達哉や天野舞耶らも手を焼いたニャルラトホテプが用意した最後の難関達。
それを、結祈は祈る手も表情も何一つ変えることなく触れる前に消滅させる。悪魔達が散った後に白いはねが現れ、舞い散った。祈り捧ぐ少女の背後にはピンク色の、少年と少女のふたつの意識から生み出されたペルソナが顕現している。
◇◆◇◆◇
「ペルソナ、《セト》――!!」
引鉄を絞り、ペルソナを喚び出した瞬間に世界に速度が還ってきた。
音、色、匂い、風景、それらの全てが還元されて広がる光景を洵に認識させんとして迫る。中央、標的に《湊の影》。それを取り囲むように三人と一匹と五体。
「まだ……まだ出来るはず……!」
更に意識を集中させた。視界に薄い青がさあっと広がり、洵の世界を覆い尽くして満たしていく。ふたりでひとつのペルソナ《セト》。奇妙な魔術師のような姿をしたそのペルソナが、洵の頭上で諸手を広げた。
その直後、みえた、という強烈な意識と共に猛烈な量の情報が洵の頭に流れ込んでくる。死神正義皇帝女帝女教皇愚者。六つのアルカナがペルソナの上に浮かび上がり、可視化される。
「慎兄ちゃん! 右斜め前!! 次のペルソナに切り替えて出現場所が変わる!!」
がむしゃらに叫んだ。その直後に《オルフェウス・改》が今までアベルと交戦していた場所から掻き消えて慎の右斜めに新たなペルソナが顕現する。二振りの剣を携えた虎の頭部を持つ男の姿をして、それは緑のマントを翻すとアベルの不意を突いた。
『愚者アルカナの《オセ》……いや……それより……』
「彼のそれは……索敵型、なのか? 山岸と同じような」
「いや。洵のペルソナは非常に特殊なタイプで、一概にそう括れるようなものではなかったはずだ」
美鶴の問いには真田が答える。真田が洵のペルソナを見るのはこれが初めてではない。半年前の事件の折、マレビト達の複合ペルソナを癒したり、種々の不可思議な働きをしていたのを知っている。
しかしそれは神郷洵と神郷結祈、二人の精神が支えとなり発現するペルソナであるために、結祈の精神が洵から剥離したあの事件の後はもう二度と現れるはずのないものだと思われていた。
『洵、』
「お願い綾時。僕が……僕と結祈が、サポートする。綾時はすごく強いんだから、湊が向き合うんなら……きっと、綾時が一番前に行かなきゃ駄目だよ」
『彼女が?』
「そう。今、湊は結祈と一緒。僕と結祈が座標になって、湊を帰還させる。だからそのためにまず湊の影を、どうにかしなきゃいけない。湊が受け入れてその先に行くにはまずはそうするしか……」
『……! そうか。わかったよ、洵』
オセが雄叫びをあげ、双剣を掲げた。全体攻撃スキル《疾風斬》。強烈な攻撃に会話は自然中断され、複数の眼が湊の影に注視する。
「待ってあげるの、疲れた。話、終わった?」
「――慎兄ちゃん、皆、全体物理、くるよ!!」
「あのさ、綾時」
オセが再び構えを取り剣舞を舞う。全体攻撃スキル《金剛発破》。洵の警告が一瞬早かったために今度は尚也が《マルドゥーク》を降魔し直して《テトラカーン》を用いたことで衝撃を防ぐ。しかし防がれたことを湊の影はさほど気に留めていないようで、ただじっと綾時の、デスの姿を見ていた。
「一つ、訊きたいことがあるんだ」
『……なんだい?』
「なんでそんなに警戒するの?」
オセの三度の攻撃モーション。それを再びマルドゥークで返し、しかしそれ以上の手を撃つことは出来なかった。急に、金縛りにでも遭ったかのように誰一人身体を動かすことが出来なくなる。それは綾時も例外ではなく、そこに湊の影が悠々と接近してきた。
近付いてきた湊の影は、しかし攻撃は一切せずに人差し指で綾時に触れただけだった。指が触れた場所から波紋が広がり、デスの身体が人間のものに成り代わっていく。美鶴と真田が息を呑んだ。黒いオールバックの髪、泣きぼくろ、黄色いマフラー、そして月光館学園の制服。そこに現れたのはずっと神郷湊に付き従っていた少年の姿ではなく、高校二年生だった有里湊の姿をした湊の影に対になる、高校二年生だった望月綾時の姿だった。
綾時の、人の皮膚のかたち、肌の色をした首に指が掛かり、ゆるく締め上げる。うわずった声が喉から漏れ、警告する。
「懐かしいね。今でも覚えてるよ。綾時が僕に言ったこと。ねえ綾時。選択をやり直したいんだ。ずっとね……あそこで見てきてわかった。どうせ皆死にたがりなんだよ。やっぱり、世界なんて、終わっちゃえばよかったんだ……」
『……今、なんて』
「だから綾時は僕に殺されて、僕の方に来てくれる?」
悪魔の囁きのような声音だった。
湊の影が酷薄に目を細める。狂気すら感じさせる黄色の瞳が、光の失われた昏い眼差しで囁く。ぞっとしない。その場の誰もが背筋を走る怖気を覚えて動きを止めた。湊の影はくすくすと笑い、そして嘲り嗤う。
「だって綾時は僕に殺されたくて、お願い殺してって、泣きまでしたじゃないか」
綾時はそれにすぐに言い返すことが出来なかった。脳裏に、過去の、あの二〇〇九年の大晦日の夜の彼の部屋での出来事が蘇っていく。
『……心は決まった?』
一年の終わりの日だった。夜闇に溶け、人間としての存在を消滅させた僕はそう、切り出した。
彼の部屋を訪れるのは初めてじゃない。望月綾時だった頃、順平を交えてちょくちょく訪れていたし、時にはアイギスさんの目を盗んで一人で遊びに行ったりもした。
彼は僕が訪れると、いつもお茶を淹れて僕を迎えてくれた。お茶の味は日によって様々だった。紅茶だったり、緑茶だったり、ハーブティーだったりした。僕はそのどれもが好きだった。彼の味と匂いがするような、そんな気がしていた。
それより前にも、満月が訪れるとその近辺で出向いた。それはいつも影時間の夜に行われて、僕は彼の寝顔を見るのが好きだった。
眠る彼はとても無防備で、ゆえに狂おしい程に愛おしかった。僕は――ファルロスは、確かに彼有里湊を愛していた。僕をその体内で、お腹の中で育ててくれたお母さん。母親が恋しくないはずがない。僕にとって母とは彼という少年だったのだ。
一度、「影時間は星がないね」と彼がぽつりと漏らしたことがある。「星」。僕はそんなものを知らなかったので、あるとは思っていなくて、しきりに首を傾げるばかりで。
『きれいだよ、星』
『……君がそう言うのなら、そうなんだろうね』
『夜の空じゅうにね、散り散りになって。光るんだ。空の目印。割と好き。ファルロスにも、見せてあげたいね』
『ううん、でも、影時間に出ないのなら、無理かもね……』
『そっか。でも機会があれば一度、ね』
結局ファルロスとして彼の中にいる間にはそれは一度も見られなかった。影時間以外で活動するには力が足りなかったからだ。初めて見た影時間の景色は、日が昇る彼の部屋。星はない。代わりに、すごく眩しい、朝の日差しがあった。
「それで、星はどうだった?」
あの日も彼はいつも僕を迎えるのと同じように、お茶を淹れて僕のことを待っていてくれた。お茶の中身はマリーゴールド。僕が一番いいねって言ったやつだ。
「星。きれいだった?」
『ッ、それは、』
「ずっと見たがってたから」
そうして世界の終わりの使者にお茶を出しながら、僕の質問に答える前に彼も質問をする。これから世界を終わらせる夜の女王の、その息子に世界はきれいだった? なんて訊くんだ。とても残酷な問いだった。そうだね。彼はわかっていたんだ。僕がそうだってことを、誰よりも確かに。
『……きれい、だった。とても……』
僕は世界が好きだった。優しくて温かくて、僕の大切なお母さんがいるこの世界が、空が青く秋になると紅葉して、季節があり、思い出があり、あの日見つけた名もない星が煌めくこの世界がどうしようもなく愛おしかった。壊したくない。終わらせたくない。嫌だ。そんなの、嫌なのに。
ニュクスは、待ってくれない。
「そうか」
僕がそう言うと彼はすごく嬉しそうな顔をする。ねえ、そんな顔、しないでよ。棄ててきたはずの、置いてきたはずの僕の心臓がきりきりと痛んだ。ああ、僕はこうしてお母さんを苦しめるのだ。
『ねえ……お願い……僕を殺してよ……』
「いいや」
『どうして? 僕を殺せばそれで楽になる。もう嫌な思いをしなくていいんだ。普通の高校生になって、気がつかない内に滅びは一瞬で終わる。頑張らなくてもいいんだよ……?』
「それで綾時を忘れるのは嫌だよ」
彼の返答は短く簡潔だった。やはり残酷な答えだ、そう思う。美しく残酷な君。それさえも身を焦がす程に狂おしくて、僕は。
『……僕の本当の姿、これ、だよ?』
耐えきれずにその身を変じさせる。人間の物真似をしていた望月綾時の姿から、死の宣告者デスの姿になる。ヒトの皮膚の柔らかさもすべらかさも、温かみも何もない鉄の体。黒いぼろきれ。とても愛らしいとは言えない死神のその姿が僕は嫌いだった。きっと彼に愛して貰えないと思っていたから。そう、彼に望月綾時の姿で会いに来たのは僕のわがまま。僕はどうしても彼に愛して貰いたいという欲望を殺せなかった。
『僕は飽くまでもこの世界に滅びをもたらすための存在。醜くて……とても……』
「タナトス」
『え?』
「ああ……なんだ……そうだったんだ……」
すると、彼がぽかんと目を見開き、僕の姿をさして「タナトス」、と言う。それからあの細い両腕で僕の身体を懸命に抱き締めた。ごつごつした身体のあちこちが彼の脆い肉体を圧迫したけれどそれを気にも留めない。「そう」目を薄く開いて、僕の宣告者の本性を臆することなく眺めて。
「お前が置いていったもの……ちゃんと、大切にしてる。僕のペルソナ『タナトス』。お前の移し身。綾時……僕に残されたお前の欠片……」
そうして彼は「××××××」と僕に言った。
姿は、彼の腕の中で、穏やかに「望月綾時」に戻っていった。「×××××」僕の声は酷く震えていて、けれど、満ち足りていた。穏やかだった。「×××××」、また彼が言う。
――そう、だから、僕は。
望月綾時は。
『たとえ湊君のお願いでも、こればかりは譲れない。湊君、君が教えてくれた世界は、君が守りたくて、守った世界はやっぱりとてもきれいだ。……終わらせちゃいけないよ。その前に君を無力化させてもらう』
顔を上げてそう告げると湊の影はあからさまに面白くなさそうな顔をして、首を傾げた。酷く不機嫌そうだ。抑圧された感情が集合し、増幅された彼は望月綾時以上に感情がすぐ表に出る。
「……なにそれ?」
これは有里湊のシャドウ。ニャルラトホテプに抜き取られ、有り様を歪められていたとしても、根源的には有里湊の内なる叫びの体現。だから「やっぱり世界なんて終わっちゃえばよかった」というのは完全な虚偽の幻ではなく、心のどこかで有里湊が抱いてしまった感情なのだ。
事実、自殺志願などで死を隔てる門に群がり、エレボスとなった人々の欲求と悪意は、湊に強い負荷を掛け続けていた。悪意を浴び続け、それでも、世界を護り続けるために湊は名字と存在と感情を棄てる。あの優しい心をずっときれいに抱えたままでは、それには耐えられなかったから。
いのちのこたえ、アルカナ・ユニバースという到達した真実の一端は紛れもなくそのような事実を指し示していた。
でも有里湊がやさしいひとだと望月綾時は覚えているから。
『僕の帰る場所は今目の前にいる君の隣じゃない。――ごめんね』
銃声が響いた。
こめかみに向けられた銃口から青い光が迸り、《愚者》オセが《死神》アリスに切り替わる。底知れぬ呪力を持つ金髪の少女は、小刻みに震える湊の影の肩の上に座り、足をばたつかせる。
「じゃあ……皆……諸共に、死ねば?」
『え……そ、そうくる……?』
「ねえ、《死んでくれる?》」
その号令で陰鬱な闇がアリスを中核に広がり、ペルソナ使い達をもれなく呑み込んだ。アリス最強のスキルであるそれは、耐性のないものを無作為に殺し尽くす幼子の呪い。そしてこの場のペルソナ使い達はその誰もがこの攻撃に抵抗出来る備えを持っていない。
生き残ることが出来るのは綾時だけだ。死を司る死そのものの化身である綾時だけはアリスでは殺せない。
勿論向こうもそれは承知だったようで、綾時が何の影響も受けていないことは気に留めていなかった。
「ペルソナ使いさえいなくなってしまえば、もう綾時だけじゃどうにもならない。おまえは死だ。誰かを生かす力は持ってない……」
闇色のスモッグがまだくすぶっている。アリスがけたけたと嗤い、冷たい目で綾時を見下ろす。水色のワンピースの中に幼稚な悪意と絶対の殺意を持つ少女のかたちをしたペルソナは、しかし間違いなく暴走した湊の内なる感情を反映させたもので、それが酷く綾時を苛んだ。
有里湊が、大晦日に下した答えはきっと彼自身のためのものではなかった。仲間達と決め、そうして彼自身の意志は望月綾時のために働いた。
母親に子供を殺せ、なんて願うのはおぞましく残酷なことだとあの時も、今もそう思う。けれど綾時にはそう聞くことしか出来なかった。そう聞くことが、綾時の願いだった。
「だから諦めて僕と一緒に全ての死すべき場所へ、帰っておいで。僕がお前を殺してあげるから……」
『いいや。それは不可能だよ。君にはそんなことは出来ない』
「……なんで?」
『簡単なことだ。僕を殺せるのは、いつだって僕の愛するたったひとりのおかあさんだけで、彼は本当に優しかったから』
だから今度はもっと残酷な願いを込めてシャドウの誘いを拒絶する。否定する。母親に殺してくださいと願うよりもずるくて卑怯だけども、湊にはその葛藤を忘れないで受け入れて、一番最初に信じたものを失わないで欲しい。
望月綾時が愛して焦がれた少年は、無口で、表情の変化に乏しくて、ちょっとずれてて、だけどどうしようもなく優しいひとだったから。
無作為な死なんてあれだけ懇願しても望んでくれなかったし、本当は、誰かを殺せるひとじゃないのだ。
『君だけじゃ、だめなんだ』
望月綾時の知っている有里湊は、柔らかく微笑んで、「星がきれいだよ」と教えてくれるそんな人だった。
Copyright(c)倉田翠.