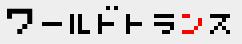ⅩⅥ TOWER:死を想え少年、指先にIを掲げ
のめり込んだ先は暗闇だった。尚也を引きずり出した時にもほんの少し垣間見えたけれど、入ってみるとその空間はもっとずっと陰湿で嫌な感じがした。
前も後ろもなければ右も左もない。方向感覚はもとより聴覚、視覚、五感の全てが奪われていくような虚脱感。
まるでゆるゆると存在を奪われてじっくりといたぶるように絞め殺されていってしまうかのようなそういう苦しさ。
尚也の言うところによれば、周防達哉の司るアルカナは「太陽」であるらしい。なるほどではこれは太陽の逆位置の暗喩でもあるわけか。湊は独りごちた。這い寄る混沌、あの「最低最悪の性悪」と尚也が称したものが好みそうだ、と思う。
「本当にこのどこかに達哉はいるの……?」
エリザベスがお膳立てして、結祈が押し込んだ場所だ。恐らくいるのだろう。しかし尚也の時のように道標になるものが見あたらない。一度、因果の悪戯で訪れた時は尚也自体がぼんやりとした光を放っていて、それを目印にしてすぐに見つけ出すことが出来たのだ。見つけられただけで、引っ張り出すには残念ながら力不足だったのだけれど。
今回はそういうふうなものは一切湊の視界には見つけられなかった。そういえば、あの時も発光していたのは尚也だけで……もう一つのはっきりした光なんか、なかったのではないか?
「達哉はこの虚無空間に呑み込まれかけてる?」
「――それは違う」
急に背後から答える声が届いてきて、湊はぞっとしなくて立ち止まってしまった。慌てて周囲を見渡すがやはり何も見えない。人の気配なとどいうものはなく、しかし届いた音は耳にこびり付いて消えようとはしなかった。
若い男の声だ。少年と青年の途中の、過渡期の声。しかし最も希望に満ちあふれて活発な年頃のはずのその声には抑揚がなく、平坦で、後ろ向きだった。希望などどこにもないと虚ろに語る例の「NYX教」信者達の、末期症状の声に似ているような気がした。
「誰」
警戒を隠さずにぴりぴりした声音で短く尋ねる。するとまたどこからか笑い声がしはじめた。右? 左? 前? 後ろ? 下? 上? ――出所がようとして知れない。
「周防達哉」
声は端的にその言葉を伝えた。
「俺の名前は周防達哉。ペルソナ使い。特異点にして、あの珠閒瑠を中核とした事件の全ての元凶が俺だ。お前こそ誰だ。こちらの世界には珠閒瑠市以外の、その外の世界は存在しないし……」
「まさか……」
「元よりそのただ一つ残された珠閒瑠市、『シバルバー』へと繋がる唯一の回路もこの有様だ。『周防達哉』以外は皆『あちらの世界』へのシンクロを果たしてここから消えてしまった。……俺は」
「違う、そんなの……そんなの、」
「違わない。俺は、ひとりぼっちだ。そうでなければいけない。何故ならそれが『周防達哉』に課された『罰』だから」
シルエットが段々と暗闇の中から浮かび上がってくる。赤地に黒で「X」の形にラインの入ったジャケットを着て、まるで十字架をその身に焼き付けているかのようだった。
尚也を助けに来た時に目にした達哉よりも、「ひどい」ように湊の目には映った。目に見えて症状が悪化している患者の様態を確認させられた医者のような気分だ。ひどい。尚也を助けてからまだ半年も経っていないというのに、時間が止まってしまった身体で千年の月日を課されたかのような変貌をその端々から感じさせられる。
簡潔に言えば、それは「狂って」しまっていたのだ。
「だから誰だか知らないけど、お前はここにいてはいけないんじゃないのか?」
「――ペルソナ!!」
その声に本能的な恐怖を感じて、反射的に後ずさってペルソナを喚んだ。
しかし愚者と死神を喚び出せないという現在の召喚ルールを忘れてデスを喚びそうになったことでワンテンポ反応が遅れてしまう。その隙を見逃すことなく、達哉のペルソナと思しきものが湊の身体を抉り取ろうとする。炎を司る赤きペルソナ。高熱で焼かれだめになった肉を女教皇「パールヴァティ」を喚び出して癒しながら距離を取った。
達哉との距離をじりじりと測りながら思考は回していく。あれは何だろう? あの赤いペルソナは湊の召喚レパートリーにはないものだ。しかしそのごうごうと燃え盛る炎を見れば、それがどんな悪魔を原義に持って達哉の心の海より生まれ出たペルソナなのかは察しが付く。
「太陽神アポロ……!」
「《ノヴァサイザー》」
光球がアポロの天に伸ばされた指先に集い見る見る膨らんでいく。核熱の超高温を孕み、ゆらゆらとした陽炎を周囲に生み出す。その中心に立つ達哉の姿がふらりとぶれて別の物に姿を変えた。何だ。これは一体、何なんだ。
「……だったら勝って正体をはっきりさせる。《コウリュウ》!!」
《法王》最高位のペルソナを喚び出し様子見にマカラカーンを指示する。コウリュウのまばゆい肢体が辺りを僅かに照らし出し、達哉の姿をよりはっきりと浮かび上がらせた。
思わず息を呑んだ。彼は酷くやつれていて、目の下の隈が色濃い。元々細身だったのだろうが、今は度を超して木乃伊の一歩手前だ。全身に生気がなく、天井から垂らされた操り糸によって辛うじて動かされているのだと説明されたら納得してしまいそうだった。
そのくせペルソナだけは、ぎらぎらとした迫力を持って湊を圧倒する。今は山岸風花や綾時がそばにいないから測ることは出来ないが、恐らくとんでもない実力のペルソナ使いなのだろう。数値化は出来なくともそのぐらいは判別がつく。
しかし、であるからこそ。
「むごい」
ただそう思った。これが、こんな姿がこの永遠の暗闇に囚われた末路なのか。彼もまた誰かのために戦って、必死になって、前へ進もうと足掻いただけのはずなのに。無限牢のような地獄に目に見えない鎖で繋ぎ止められて、少しずつ少しずつ、遅効性の毒を盛り続けるように精神をすり減らし、身体中に毒薬が回り、だめになっていく。
達哉についてはナオと何度か話をしたが、彼は達哉がこんな状態になっているとは一言も言わなかった。隠し立てをするようなことではないだろう。つまり、尚也がいなくなってから症状が悪化したのだ。
(一度孤独から回復し……もう一度孤独に引き戻されたから……。マッチポンプだ。僕がナオを連れ出すのを許容したのはこれが読めていたから? だとしたら、想定していたより随分性質が悪いぞ、その邪神ってやつは)
ペルソナは心の形。より強いペルソナに成長させ、或いはベルベッドルームで生み出して乗り換えていくというのは即ちより強固な自我の鎧を身に纏うことを意味している。その意味でアポロは非常に強い自我の鎧にあたるものだ。きっとアポロを心の海の中から喚び出した時は達哉は強い意志を持ち、覚悟と決意とを持ってそれに臨んだのだ。
だけど今はそうじゃない。鎧の中は、常人以上に脆弱で少し力を入れたらそのまま砂になって風に還ってさえしそうな肉体が細々と収まっているにすぎない。虚勢、などという言葉ではそれは表せない。
そしてその衰弱はニャルラトホテプの仕組んだもの。
周防達哉は危険だったのだ。
「つまり……この暗闇は達哉の拒絶、ってこと、かな……?」
結祈から繋がっている糸のような細い絆は感じられるから、ここから離脱することは多分そんなに難しくはないだろう。むしろそれが一番簡易な選択肢であるはずだ。しかし綾時が送り込みエリザベスが道を開き結祈が繋いでくれたこのチャンスを逃すわけにはいかない。
「ナオの身体も元に戻さないといけないしね……」
本当は藤堂尚也をいつまでも黒猫の身体に入れ込んでおくのも危険なのだ。そのまま黒猫に定着して戻ることが出来なくなってしまったりしたら目も当てられない。藤堂尚也という一人の人間として彼には帰るべき場所がある。
「《審判》」
だったら力尽くでも強引でもいい。ニャルラトホテプの支配するこの空間を打ち砕かなければ。銀色の銃口を頭に押しつける。冷たい鉄の塊を感じて目を瞑る。
その時に、身体を残してきた現実のことを少しだけ思った。高校二年生の「有里湊」の姿をした、何か。あれは今どうなっているんだろう?
皆は無事なのだろうか。死ねない綾時は別として、簡単に死ねてしまう他の皆は、大丈夫だろうか。
(だけど信じるしかない)
すぐにそのネガティブな思考を振り払って勢いよく死の想起を引鉄を引く音と共に脳天に突き刺す。《審判》最高位の《メサイア》が現れて救世主が涙を湛えた。リスクを秤にかけている余裕などない。全力だ。目的を果たすためにはそれを厭う必要はない。
◇◆◇◆◇
「じゃあ……皆……諸共に、死ねば?」
湊の影の声は、震えていた。恐怖に震えているようにも取れる声音だった。何を恐れているのか。「有里湊」が恐れるもの。その一つが、自らが絆を勝ち得たと信じていた者達からの拒絶だ。そしてそれは特に、「望月綾時」に対して示される。
綾時は湊と最も濃い結びつきを持ち、密接な関わりを持ち、湊の隣にいた。だから。
「《死んでくれる?》」
その綾時に面と向かって「きみじゃない」と言われることは、恐怖でしかない。
アリスの悉くを殺し尽くす呪いと殺意が等しくそこに居合わせたペルソナ使い達に降りかかる。《死んでくれる?》はその可愛らしい外見とおちょくっているような名前に反して最強クラスの強さを持つ死の呪いだ。大抵のものはこれに耐えることが出来ない。
綾時は低く呻いた。湊の影が言ったように、綾時、デスには誰かを生かす力はない。誰かを傷つけることは得意だけど、癒すことは出来ない。望月綾時は結局死の存在だからだ。死が、生を手助けするなんておかしな話じゃないか。
「ねえ、結局、こうなんだよ。仕方ないんだ。これが帰り着く場所で行き着く場所だ。世界の終わりってきっとそんなものだよ。なるべくしてなる。残念だったね綾時。お前が守りたかったそのちっちゃいのも、もうダメだ」
『どうしてそんなことを言うの……この湊君も、君も、同じだよ。それは影という本質である君自身が一番よくわかっているはず』
「まあ……ね。でも『僕』は僕を拒絶した。綾時ならこの意味も理解してるよね」
『う……それは』
「結局何も見えてない。ばかなやつ」
影が嘯いた。
高校生の有里湊の身体は、改めて見ると信じられないほどに華奢で、だからこそ彼があの時背負った重圧を綾時に思わせる。契約書にサインをしてからの一年間、いや、それよりももっと前にムーンライト・ブリッジでその身に死を宿してからずっと有里湊は大きなものを抱えて生きてきた。
最後の決断をして《大いなる封印》を行使した時、彼は間違いなく世界そのものを、そのほんの一六〇センチと少しの身体に抱いていた。それは望むと望まないとに関わらず、彼の積み上げてきた選択がもたらした「結果」であって、もしかしたら、いやきっと、有里湊は別に世界を救いたかったわけじゃないのだ。
ありふれたロールプレイング・ゲームの主人公の勇者みたいに正義感を振りかざして自分が世界を救わなきゃだなんてことはちっとも考えちゃいなかった。
彼が守りたかったのは目に見える全てで、両腕に包み込める全てでしかなくて、その手の届く範囲のもので、全人類だとか、生命全ての希求だとか、そんなものは考えたかどうかも怪しい。だけど絆を得た人達のことは、失いたくないと思っていた。あの一年間で彼が築き上げたものは、彼にとってどうしようもなく眩しくて尊いものだったから。
そのちょっとしたものこそが「有里湊の世界の全て」で、それを守るためなら、彼はいのちのこたえに辿り着いてそれを行使することを、選ぶことが出来たのだ。
出来てしまった。
「まあ、僕を拒絶しなければとか、そういう単純な問題でもなかったけど。そもそも……無理だ。あいつは感情が剥離してるくせに変なところで人間のままだ。なまぐさい生き物のにおいがする。『有里』であることを棄てて、それでもまだ」
『それこそが湊君の彼らしいところだ。諸刃の剣だと、言うのかも知れないけれど』
「だけど無意識下で自分自身、抑圧を感じていた。完璧な人間がいないのと同じ。中途半端だ。だから僕が代わりにその中途半端さを、甘さを棄ててあげるって言ってるだけ。なのになんで綾時は僕を拒絶するの。僕じゃだめなの。好きだって言ってくれたのに。うそつき……!!」
『僕はずっと湊君を愛してる。だけど君のわがままを唯々諾々と受け入れるのは、本当の愛じゃないよ。決してね』
「……まだ、そういうこと、言う。だけどもう終わりだ。お前だけじゃ僕は倒せないよ。よしんば勝ったとしても……真田先輩も美鶴さんも、藤堂尚也も、神郷慎と洵も死んでる。今は瀕死だけど一刻も早く蘇生しなきゃ普通に命を落とす。その状態で甘ったれの『僕』が現実を受け入れて超克するイニシエーションをきちんと迎えられると思う?」
まあ、そうしたら全部終わって皆僕達のところに来るだけだけどね。湊の影の言葉は冷たかった。皆死ぬ。諸共に死ぬ。望月綾時は死の宣告者であり、有里湊はその門番である。十年前に書き換えられた事実は変わらない。だから全部死ぬというのは、全部二人の元へ来るということで、それはつまり世界そのものが死の膝元にそっくり移りゆくということで。
なんでもないことのように影はそれを言うのだ。
(それじゃ君は一体どんな思いで引鉄を引いてきたの)
結果的に彼の行動は自己犠牲になってしまったけれど、有里湊は「皆のために私が犠牲になりましょう」なんて声高に謳っていたことは一度もなかった。アイギスが自らが機械であることを利用して特攻していくことを諫めるのもままある光景で、誰かが自暴自棄になると必ずそれを実力でもって止めた。
その意味では、自己犠牲というのはなるべくしてなった結論と言うべきか、追い詰められた先の答えでしかなくて、決して望まれたことではなかっただろう。
有里湊のメメント・モリは最初「どうでもいい」「だから、死ぬのは怖くない」という理念と共にあって、やっぱりそれは誰かのための犠牲とは縁遠かった。言い換えれば彼はあらゆる全てが「どうでもよかった」ので、個人で完結してしまって、世界は有象無象の無貌の群像の集合体にすぎなかった。
それが最後には、「どうでもよくない」「だから、死ぬのは怖くない」に変わっていたのだと綾時は理解していて、彼も人間だ、死ぬことに一ミリも恐怖がなかったわけではなかったけれども引鉄を引けたのだ。
『人間だから、死ぬのは怖いよね……』
「……何」
『あの時の君さ。確かに君にとって死は僕という隣人だったんだ。死は常に君の中に存在し、君の死が世界に影響を及ぼしたりなんてことも別にないはずだった。死ぬのも別に怖くないと思ってた。ただ、ふわりと足を運んでちょっと隣に行ってしまうだけだって君はずっと思ってた』
「何が言いたいの」
『だけどそうじゃなかった。死ぬのが怖いんだ。人間だったから、死んだら終わってしまうから、怖かった。でも『こわくない』、って君は祈った。皆を守りたかった。君が愛した人達を失いたくなくて、そのために『本当は怖い』っていう気持ちを押し込めて、世界そのものに大きな意味がもたらされることさえ無視して君は引鉄を引いたね』
「……待て……何を……言おうと、して……」
『その時の感情の矛盾こそが君なんだね。『有里湊のエゴイズム』……湊君がもし、本当は世界なんか救わなければよかったのにとほんの少しでも思っていたのだとすれば、それは『こんな無益な世界のためにどうして命を落とさなきゃいけなかったの?』ではなくて『もっと長く生きて、大切な人達との時間を過ごしたかったし、彼らに自分の死を重く刻ませたくなかった』からなんじゃないかい? 違う? 君って優しいんだ。そしてすごく繊細。死の門番となるために削ぎ落としたそれらの噴出したものこそが『影』。そうじゃない?』
「うるさい……」
気がついた時には湊の影の細い五指は綾時の首元に添えられていた。死の首を締め上げていた。爪をぎちぎち食い込ませて、血管を傷つけようとして、細い指のどこにそんな力があるんだろうってぐらいに強く強く望月綾時を苦しめる。
「うるさい……!!」
『湊君本人の自我が簡単に君を受け入れられなかったのは、そうするととても人間らしい人間のままであの役割に戻らなきゃいけないからだ。人のままで人を裁くのはとても難しい。でも大丈夫だよ。僕は知ってる。君が本当は誰かを殺せるような人じゃないってことをね……』
「それ以上喋るな!!!」
首が完全に絞まった。しかしそれでも尚綾時は喋ることを止めない。死ねない死の演説はその程度で止められたりしない。それを一番よくわかっているのは、湊自身だろうに。それを考えられないぐらい湊の影は、剥き出しの本質は焦燥している。
『君には誰も殺せない。だから、ここにいる慎や洵、尚也、和也、真田さん、美鶴先輩、彼らは決して君のせいで死んだりはしないだろう。僕が断言する』
綾時が微笑む。影は濁った黄色の眼球をはくはくと震えさせて世界の全てを憎悪するように綾時を見た。黄色と青色が対峙する。
その最中で一閃の光が走った。
◇◆◇◆◇
「《メギドラオン》!!」
本当に、どこからあんな力が出ているのだろう。アポロの猛攻をすんでのところで交わしながらそればかりが思考を掠める。太陽神アポロ、オリンポス十二宮の一柱。そりゃあ原義を紐解けば、これほど高位の神の姿を取っているそのペルソナが弱いはずはないのだけれど、そういう理屈だけでは括れない強さがその中には秘められている。
アポロの強さは痛ましい強さだ。悲しいぐらいに。ちょっとだけ近いなと思う。ただがむしゃらに綾時の元を目指していたあの頃の湊に、本当に少しだけど。
刃を交わし、ペルソナで切り結ぶ度に「周防達哉」という獅子のような青年のヴィジョンが流れ込んでくる。小田桐が昔言っていた。「孤独ではなく孤高」。彼は正にその言葉通りの人間だった。
「ああ、もう……!」
だからこそ許せない。周防達哉もやはり大切な人達を守りたかっただけで、でもそのつけをこんな形で払わされることになって、一体誰が悪かったのか湊にはもう判断が付かなかった。これが周防達哉の罰なのだという。けれど達哉はそれほどの罪を犯したのか?
こんなのは、あまりにも凄惨な仕打ちに過ぎる。自我の崩落一歩寸前まで追い詰められて、自責の念に押し潰されて、たった一人永久に孤独の中で。光もなく寄る辺のない世界で出来ることはどうにもならない自問自答と意味のない過去の反芻そればかり。アポロの《ギガンフィスト》を空中で身を翻すことでなんとか避けながら、それが地面らしき場所を強烈に抉り取ってしかし瞬く間にコールタールの闇に呑み込まれて元通りになるのを直視して顔を顰めた。
周防達哉しかいない世界だから、維持には達哉が使われている。それが交戦の間に湊が導き出した答えだった。コアは達哉自身だ。だから達哉がこれでいいと思っている限りこの世界は暗闇に包まれたままで、閉鎖空間のままなのだ。この現状は達哉が招いたもの。達哉自身が望んで受け入れている。
「何で自分が罰されるべきだと思ってるの。そんなに……自分のしてきたことが……悪いことだと……なんで……!」
「自明の理だ。俺がやったことはそれだけの意味があることだった。所詮パラレル・ワールドなんてのは混乱を招くだけだったんだ。だから……こうして俺が取り残されるのは当然のことだ。俺を救おうなんてのは、お綺麗なお題目に過ぎない。後始末は俺がやって然るべきだった」
「欺瞞だね。そうやって自分を納得させることで目を背けようとしてるんだ。罰に甘んじていればいいって、楽な方に逃げてるだけだ」
「部外者にはわからない。今思えばフィレモンの誘いに乗った時点で俺達はニャルラトホテプに根底のところで敗北していた。奴に立ち向かうのなら人間は全てを受け入れ、しかしその上で一つも諦めちゃいけないんだ。だが……」
「ッ……」
「パラレル・ワールドという選択そのものがどうしようもない逃避だった。だから仕方ない」
アポロが一際大きく拳を振りかざす。核熱属性の《ヒートカイザー》だ。それを避け続けることは別段難しいことではないが、避けているだけではどうしようもない。どうすればいい。どうしたら、達哉に外へ出ようという意思を持たせることが出来るのだろう。
(全てを受け入れた上で、諦めない……)
諦め。諦観。覚えのある言葉だった。
「あ」
その言葉をもう一度繰り返して湊ははっとして動きを止めてしまった。その隙を達哉が見逃してくれるはずもなく、アポロの一撃が子供の肉体を貫通して激痛が襲う。しかし意識は肉体の痛みから離れて、幽体離脱のように浮ついているようですらある。諦観。何かを切り捨てて諦めるということ。大事の前の小事のように、全ては選べないから、何かを選択肢から外す。
「僕も同じなんだ」
湊の首を絞めて成り代わろうと言ったあの影はそれそのものだったのではないか。湊が切り捨ててきたものが人の姿を取ったもの。認めたくはなかったけれども未練が確かにあって、湊にそれを突き付けて、だから湊は今こうして達哉と戦っていて。
「達哉!!」
争うつもりはないなんてテンプレートな言葉は流石に言えなかったけれど、それを自覚して伸ばした手は見た目よりも随分と強い力で達哉の襟首を掴み取っていた。流石に動揺したのか、達哉の動きが止まる。懐に入り込んでへばりつくと、アポロは自滅を避けるために攻撃の手を止めた。
「一回諦めたからってそれで全部諦めるな。どうしても心の底から屈服して惨めったらしく諦めたいならいいけど。本当は諦めたくないんだ。僕もそう。僕は人間の感情は諦めたつもりだったけど根底のところで全然棄てられてなくて、だから……だから……仕方なくなんかない……」
「お前……」
「仕方なくなんかない!! 達哉がニャルラトホテプの玩具にされてるのが仕方ないなら、そのために達哉の仲間達は戦ってたって言うわけ。天野舞耶はそのために死んだの。本当にそう思ってるの?!」
「天野舞耶」、の名を出すと達哉の顔色が目に見えて変わった。どうしてその名前を知っているのかと声に出して問うことすら出来ないようだった。ビンゴか。畳み掛けるように灰ねずみの眼を見開く。
「そんなの言い訳だろ。未練がましくても……しがみついたって構わないんだ。人間なんだから」
しがみつく格好から、いつの間にか、抱きつくような格好になっていた。
そのまま振り払われることや、反撃を受けることを覚悟して腕に力を込めたが一向に達哉が湊に手を下すことはなくて、代わりに達哉は湊の少年の身体を兄がそうするように抱きしめた。昔、もっともっと幼かった自分が克也にそうされたように。「……達哉?」きょとんとした声で湊は尋ねる。
「その、僕、見た目ほど子供じゃないから……これちょっと恥ずかしいんだけど……」
「いいだろ。お前の言うことにも一理はあるかなと思ったから」
「じゃ、」
「俺は舞耶姉を殺すために戦ってたなんてつもりは毛頭ない。だが不幸な事故だったと片付けられる気も全くしない。……俺は、『向こうの世界』に行ってあそこは俺の居場所じゃないなって感じて、それでこっちに帰ってきて……その選択自体は後悔してないんだ。それはきっとお前が選択自体は後悔していないことと同じで」
霧が晴れゆくように、暗闇を切り裂いて光が照らし始める。すぐに闇は見えなくなり、辺りはただ白く広く、そして足下、眼下にミニチュアの円形に浮かぶ空中の街が見える。
光の下で見る周防達哉の顔はやはり隈は酷かったけれどきちんと生気があって、目の中に光があった。優しい面立ちをしている。軽い呼吸の後に湊を抱え上げ、達哉はどこかへと歩き出した。
「耐えきれなかったんだろうな。情けない話だ……自分を責めるのは得意だった。ずっとどれほど時が流れたのかもわからなくなってしまうほどあの暗闇の中にいて……閉じ込められてるとばかり思っていたが、閉じこもっていたのは俺の方だったってわけか」
「この空間、時間の流れがおかしかった。人間が一番弱いのは長期にわたる孤独だ。達哉は……ギリギリだった、と思う。あのさ。こんなこというの、調子がいいって思うかもしれないけど」
「わかってる。俺の力が欲しくてわざわざこんなところまで来たって所だろ。あいつは……尚也は元気にしているか。確か身体がこちらに残っていたように思うんだが」
「それも目的の一つだった。今は応急処置で猫の身体に魂入れてるけどあんまりというか全然いい環境じゃないからね。どこにあるかわかる?」
「さあ……このフロアには見あたらないな。下に降りるか。悪魔がそこら中跋扈してるが、ペルソナが使えるなら問題ないだろ」
下、つまりあの模型のような町並みのことか。「あれが俺の住む街だ」達哉は湊の言いかけたことを察してかぽつりとそう呟いた。
「『マイヤの託宣』というトンデモ予言書に則り、古代遺跡『シバルバー』の真上に存在するこの街だけが天空都市として浮上して残り、あとは『グランドクロス』による大粛正で滅亡した、っていうのがこの世界だ。嘘みたいな話だが、噂が現実になるという仕掛けで本当にそうなってしまった。この世界にはシバルバーより外は存在しない。後は無だ。だけどそれでも、この街が俺の育った場所であることには変わりない」
「……『向こう側』は、『向こう側の達哉』の場所ってこと」
「そうだ。この珠閒瑠市こそが、ある意味で俺の世界の全てなんだ」
言葉端は哀愁を帯びている。達哉もまた「棄てられなかった」人種。誰も彼も、自分の目に見えるものを守りたいだけ。
ニャルラトホテプは、そういった純真な心を嘲り弄ぶことをこそ、好んでいる。
◇◆◇◆◇
「――アベル?! なんで……慎に呪殺耐性はなかったはずなのに!!」
ペルソナ《アベル》が、因果を断ち切る剣を振りかぶって湊の影に致命傷を付ける。完全に油断していた。慎が起き上がることなどあり得ないはずだったのだ。
『その油断が運の尽きだな。仮にも死の門番なんだって言うのなら、俺達の生命がこの場にまだ留まっていることにお前はもう少し早く気付くべきだったよ。ま、綾時が思考を誘導してたからそうそう簡単じゃなかったのかもしれないが』
今度はペルソナ《スクルド》だ。それに《カエサル》《アルテミシア》が続き、影を拘束する。綾時が解放されて呼吸を整えている。視線を遣ると、洵もまた《セト》を召喚していた。
影は歯ぎしりをした。一体これはどういうことだ。
「……全員、アリスの呪殺に耐えられるようなペルソナじゃない。……そうか。……もしかしてあの時のアルカナが」
「そういうこと。湊がくれたお守りの『正義のタロット』が身代わりになってくれたみたいでさ。お前は綾時に夢中だったから、反魂香でまず尚也を蘇生して、あとは尚也に任せて体勢を立て直させて貰った。時間は十分にあったし」
からくりは単純だ。アリスの呪いが慎を蝕むその直前に、湊が慎を連れ出した時に渡してきた二枚のタロット・カードのうちの一枚、《JUSTIS》が光り慎を死の呪いから守り通した。タロットが身代わりとして機能すると慎も知っていたわけではないが、その状況が唯一逆転に繋がるチャンスであることはすぐに理解が付いた。
一つだけ渡されていた反魂香で尚也を引き戻し、スクルドで急いで全員にサマリカームを掛けて貰う。幸い湊の影は綾時との会話に集中していてそれに気付く素振りはなく、後は一斉に襲いかかり、首尾良くアベルの剣で一撃お見舞いすることに成功した。
アベルに体力の殆どを持っていかれてしまったのか、湊の影に抵抗する素振りはもうなかった。あからさまに「しくじった」という顔で慎の方を睨んではいるけれど、ペルソナを更に喚び出して攻撃してくる様子はない。
「アベルの剣は、確かにこれだけ力量差はあるけどちゃんと湊にも効いたな。お前って、湊の一番初めのペルソナの根源みたいなもんなんだろ? ……なあ、俺も、洵も……尚也も真田さんも桐条さんも、途中からちゃんと聞いてたよ。湊は……優しいって……」
「神郷慎。お前にしたり顔でそう言われる謂われはない」
「し、したり顔なんかしてないって。……湊はすごいよ。確かに、その強さは人間離れしてるって言えてしまうし、ものすごい強烈で……やばい。でも人間だ。心があって、機械みたいにゼンマイ仕掛けで動いてたりなんか全然しなくて、そんなの俺達みんなわかってるんだ。真田さんとか桐条さんがどれだけ心配してるのか、湊、お前知ってんのかよ。湊は何でも一人で抱え込むから。一人でどっか行こうとするから。一人で何とかしちゃうから。それが、全部が全部悪いことだとは思わないし、……なんかもう、上手く言えないけど」
たどたどしく言葉を紡いで、せめて真摯に湊を見据える。剥き出しの湊の本音に、慎も本音をぶつける。きっと飾る言葉も綺麗な言葉も、要らないんだろうと信じられた。荒削りな言葉で良かった。それが伝えられるように、必死で口を動かす。
「少なくとも俺は湊が好きだ。一緒に色々やって、お節介かもしれないけど心配だなって思うとこもあって、ほんとはすごいいい奴で、大人びて見えるけど実は結構、ナイーブなとこもあってさ……全部じゃないかもしれないけど少しは湊のこと、わかったつもりだ。湊は……湊なら、そういうの全部受け入れてもっと先に進めるよ」
「……やっぱりそういうの、したり顔だと僕は思うけどな。お説教垂れてさ。大体先ってどこ? 僕はもう死んでるんだよ。未来とか別にないし。がむしゃらになって、でもだから何?」
「十年前。きっとやり残したことがあるんだろ。今折角ここにいるんだから、それだけやりに行けばいいじゃん。まずは元凶の奴を倒して」
「綾時にも拒絶されたし」
『やだなぁ。確かに僕は湊君のわがままははね除けたけどね。だって折角君が守った世界なのに、やっぱり滅ぼそうなんて言われて、拒絶する他ないじゃないか。君は確かに湊君の一つの側面だけれども、他人の手が入ってるからね。それでは仰せのままに、とはいかないさ』
「……お前もそういう顔するの」
大きな溜め息が辺りに響き渡った。
溜め息の主は当たり前のように湊の影で、彼はそれから息継ぎに深呼吸をして、ぶるぶるとかぶりを振るとぐるりと周囲を見渡した。アベルの因果律を裁断する特異能力に付けられた傷は深く、回復の見込みはない。不意打ちに完全な敗北を喫していた。だけどどうしてだか、それを憎悪したり恨んだりは出来なかった。
慎はまっすぐだ。まぶしいぐらいに。真っ正面から湊を見ようとした。だからなのかもしれない。
「あーあ……」
トン、と軽く両手で払ってカエサルとアルテミシアを退かす。勢いを削がれて、さっきまで諸共に殺して何もかも道連れにしてやろうと本気で思っていたのが急にしらけてしまって馬鹿みたいにさえ思えた。油断。正にそれだ。舐めてかかっていた。望月綾時を、神郷慎を、神郷洵を、藤堂尚也を、真田明彦を、桐条美鶴を、甘く見ていた。
そして何より有里湊自身を軽んじていた。
「僕の負け」
影時間の月と同じ色の瞳をそっと閉じる。綾時が「少しだけ目を閉じた」湊の身体を抱いて耳元で唇を寄せた。眠りに誘う子守歌を歌うようにそうして囁く。
「おやすみ湊君。目が覚めたら、わがまま、もうちょっと言っていいよ」
影の唇が小さく動いて、声には出すことなく密やかに返答をした。
Copyright(c)倉田翠.