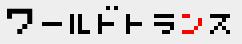ⅩⅦ STAR:スティグマータの洗礼
目覚めた自我は少年の肉体に収まっていた。あの小さな、小学生ぐらいの体躯ではなく月光館学園の制服を着た高校二年生の肉体にだ。右手をゆるゆると握ったり開いたりして、それからぺちぺちと自らの額を叩いてみたが、通り抜けたりはせずきちんと肉の感触がした。
プラネタリウムみたいな世界だった。やっぱり上下左右が曖昧で、天地がどこにあるのかよくわからない。夢の続きみたいで、不可思議な感じだった。
「お目覚めですか」
青い装束に身を包んだショートヘアのエレベーター・ガールがにこりと微笑んで立っている。隣にはツーテールのはしばみ色の少女。二人の女性はただ優しく、見守っていた。
「お疲れ様、湊。よく頑張りました」
「結祈……」
「答えは見つかった?」
「答え?」
「君の捜し物。それから、君が本当は通ってこなければいけなかった道……《有里湊の未練》について、その答えは」
「ああ……」
上半身をぐっと起こし、頭を抱えた。その結祈の問いかけをトリガーに猛烈な勢いで、洪水みたいにレコードが流れ込んでくる。子供の身体で湊が通り過ぎた出来事が圧縮されて降り注いで、その肉体に同調していく。世界に生じた歪みの落とし前を付けるために綾凪へ降り立った瞬間から、周防達哉と交戦して湊自身が目を背けていた事柄まで全て余すことなく。あの十年前の日から少しずつ少しずつ見ないふりをして削っていったものたちが肉体へ回帰する。
「ねえ、結祈、エリザベス」
「うん」
「如何なさいましたか」
「僕、やっぱり、死ぬのは怖かったんだと思うんだ……」
「そうだね」
「左様でございますか」
「人間だから。人間だったから。本能だよね、それってさ……でもチドリが僕より前にそうしたように、強い想いがあると、それを超克出来る、乗り越えてしまえるってことも知っていた。だからそうしたんだ。でも、それをはき違えて……蓋をした」
あの瞬間有里湊の意思は本能を超克して、いのちのこたえを受け入れて、大いなる封印を施すことさえも可能にした。それを支えていたのは湊自身が築き上げた数多のコミュニティがもたらした絆の力だったけれど、裏返すとそれは最も人間らしい感情に直結する事象だ。死の番人を務める上で人間らしさというものは障害にしかならない。あんまりひとつひとつに思い入れを強くしすぎると、次々死んでいく命に、あまつさえ自ら死のうとする意思に耐えきれない。
だからどうでもいいと思わなければいけなかった。意思を歪めて、認識を書き換えても。
「だってそれまでは、本当に死ぬのは怖くないって思ってたから」
有里湊にとってそれは難しいことではなかった。絆を得るまでの少年は、本当に死を恐れていなかったし、死ねと言われないから生きているだけの、空っぽの人形みたいなものだった。
「やり残したことも別にないかなって、思ってたんだ。だけど後から後からぽろぽろ、言いたかったこととか出てきて。今更どうにもならないのに、それはすごい辛かった。なかったことにした方が……楽だったから」
「なくしちゃった?」
「なくしちゃった。その結果がこのざまだ。――でもすっきりしたよ」
一息吐いて立ち上がった。今まで見上げてばかりだった結祈の身体が僅かに自分より低くなっていて、ああ、あの身体に戻って来たんだなと実感する。この姿で洵や慎の隣に立ったら、どのくらいの差があるんだろうか。それを思うとちょっと楽しくなってきて、結構余裕が出てきてるんだなと一人でくすくす笑い出してしまう。
エリザベスが察してくれたのか、「本当にお久しぶりですね、その姿の貴方と対面するのは」とやはり柔らかい笑顔のままで応じる。最後にエリザベスとこの姿で対面したのは確か湊が運命を超克する直前……ニュクス・コアとの戦いの最中に主イゴールにベルベットルームへ呼び出された時だ。実に十年ぶり。冗談めかして「エリザベスは全然変わんないけどね……」と言うと、「あら、それは貴方も同じことです」とあっさり返された。
「やるべきことははっきりした」
意識と無意識の狭間の空間では時が流れない。この空間では意思こそが全ての力の源となり、あらゆる事象を左右する。周防達哉と藤堂尚也が幽閉隔離されていたのもここと連なる狭間の世界だったけれど、彼らには意思の制限が施されていてずっと因果の操作を受けていた。
だけどそれは取り払われた。後は成すべきことを成せば、終わりは、もうすぐそこまで迫ってきている。
青い手袋がスッと道を指し示す。
「では、お帰りはあちらに。あなたを待つ声と、この方の《繋ぐ力》がありますから、きっと大丈夫でしょう。……有里様、一つ、約束をさせてはいただけませんか」
「いいけど、何?」
「全てが終わったら、最後に私のお茶を飲みにいらしてくださいませ。この十年、私も中々貴重な体験をさせていただきました。積もる話をいたしましょう。勿論あの方もご一緒に」
腕によりをかけてお待ちしております。彼女はそんなことを当たり前に言う。それはつまり「貴方の敗北は許しません」という宣言でもあって、湊はつい苦笑した。相変わらずだ。本当に、どこまでいっても。
「あの、あなたの愛された尊いひとと」
「ええ。それじゃ、綾時を連れて帰る前に寄り道します。そういえばエリザベスも何かごちゃごちゃやってたんだっけ。《マヨナカアリーナ》の件とか、介入してたような気もするしね」
結祈の手を取ってエリザベスの示す先へ歩いて行く。腰につり下げられたホルスターには、あの銀色の召喚銃。肩からヘッドホンと携帯音楽プレイヤーをぶら下げて、確かに歩を進めた。不思議と全てが馴染むような、しっくりくる感触がした。喪われたものが身体に還り、そうして最後に、《有里湊のシャドウ》として暴走したものがやってきた。こそばゆいけれど、でも皆これを受け入れてくれた。
「慎兄は強いね」
「当然でしょ。慎お兄ちゃんは、お兄ちゃんだもの」
「そうだね……今更かも。まっすぐで、眩しい。僕は慎兄のそういう所、すごく惹かれて、だから……慎兄を選んだのかもしれないな……」
ぐちゃぐちゃで汚くて、人間の弱さを抱え直してしまったけれど、だから今なら素直にやっぱり世界って綺麗だなと思えるような気がした。大切な人達が笑っていられる世界を守りたいともう一度思った。世界は消えちゃダメだ。終わってはいけない。人間を守らなきゃとかそんな大層なことは言えないけれど、だけど守りたいものぐらいはあってもいい。
「僕のこと、弟だって言ってくれて嬉しかったよ」
「私も弟が出来て嬉しかった」
「ありがとう。――結祈お姉ちゃん」
「え、きゅ、急に、照れるなあ……」
じゃあ行ってらっしゃい、と結祈が立ち止まって僕に手を振る。僕はそれを認めると首を横に振って、結祈の手を掴み直した。体格差がひっくり返ってるから当然僕の方が力は強い。結祈が変な顔をする。
「もう行かなきゃ駄目でしょ?」
「行くよ、そりゃ。でも今度は結祈も一緒に。ねえ知ってる、ユニバースって、奇跡の力なんだよ?」
そのまま結祈を身体ごと抱き上げて、光の渦目掛けて飛び込んだ。奇跡は自分のためには起こせないけれど、だけど、誰かの為になら、自分自身を行使することは可能だ。
「ちょっとだけだけどね……」
結祈が僕の腕の中で頬を膨らませて「男の子って、これだから、もう」とか何とかぶつくさ呟いている。僕の意図が伝わったらしい。男の子というか、洵はともかく慎が結構そういうところがあるから何か被ってしまったんだろう。
だけど本当は湊の方が年とか多分上だし、少しぐらい、これぐらい、許してくれたっていいと思う。
恩返しの一つぐらい。
◇◆◇◆◇
影時間は依然として明ける兆しを見せない。もう随分と長く湊の影と対峙していたような気がしたけれど、時計が動きを止めてしまうこの空間では実際にどの程度の時が流れていたのかは判別が付かないし、もしかしたら影時間は日によって長さが違うんじゃないかっていう話も昔したことがあったし、まあ、要するにそれらは概して曖昧なものだっていうことだ。
有里湊の影が全員に看取られるようにして消滅するのと、意識を失っていた「神郷湊の肉体」が変化を起こすのは殆ど同時だった。横たわる一五〇センチの身体が、淡い光に包まれて緩やかに成長していく。むくむくと水を吸って増えたわかめみたいに一六〇センチと幾らかまで伸びて、光が消える頃には先程まで交戦していた影と全く同じ姿になっていた。月光館学園の冬制服を着込んで耳にイヤホンを付けている。
変化は次々と辺りに訪れた。洵がまず小さく「あ、」と呟いて、それから黒猫が『ん?』と疑問符を示す。洵には目に見えるわかりやすい変貌はなかったけれど、慎は何か感じるところがあったらしく納得したような素振りを見せた。
黒猫も湊と同じような光に包まれたと思ったところで何もないはずの上空からいきなりぼとりと何か巨大なものが落っこちてくる。落下物は粉塵を巻き上げ、そうして煙が晴れた頃には全ての変化は終わっていた。
「うわ……なんだこれ。懐かしいというよりもう変な感じするな……」
黒猫が立っていた場所に、猫の代わりに青年が突っ立っている。黒髪の、少し長めのショートで片耳にピアスをしていた。見たところ大学生ぐらいか。
当然誰にも見覚えのない顔だ。美鶴が恐る恐る口を開く。
「……つかぬことを訊ねるが君は誰だ?」
「えーと、藤堂尚也。一応。大学一年生。さっきまで猫やってた」
「ああ……了解した。ではそちらの彼は?」
まだ横たわっている湊ではなく、尚也のそばに突如落下してきたと思しき方を指さして更に訊ねる。「ええと」尚也が顎に手を当てて唸った。
「こいつが周防達哉。俺の肉体が閉じ込められてた場所にいた、件の『対ニャルラトホテプ最大の犠牲者』だな。ここにいるってことは、湊が連れ出すのに成功したってことだろ。……それで、湊は?」
『……まだ寝てるね』
「起こせ。達哉は寝かしといてもいいから」
赤いジャケットを着た茶髪の謎の青年――周防達哉――を避けて尚也は躊躇なく湊の元へ近付き、そうして一切の躊躇いなくその細身の身体を蹴り上げた。その場の尚也以外全員の顔色が変わる。
『ちょ、ちょっと何してるの?! 湊君はね、ああ見えて意外と繊細っていうか――』
「落ち着け綾時。この程度でへばる男なら世界なんか救ってない」
『いや、それはそうかもしれないけど湊君は僕のおか』
「……《利剣乱舞》」
「《テトラカーン》張ってある。悪いな。元気か?」
大慌てですっ飛んできた綾時を軽くあしらい、そんな応酬の後、むくりと湊が起き上がった。起き抜けに物理反射を喰らったからかあまり機嫌は良くなさそうだ。しかしこれといった外傷は特になく、綺麗なものだった。あの日埋葬された死体がそのまま起き上がってきたかのように、綺麗だった。
「随分なご挨拶だね尚也」
人間の肉体に戻った尚也を湊はもう「ナオ」とは呼ばない。大学生の、湊よりも年が上の肉体に収まっている藤堂尚也はどことなく湊に共通する雰囲気があって、仲がいいような悪いようなよくわからない親族の遣り取りによく似ていた。同じような色の髪の毛で前髪を目にかかるぐらいに流して、だけど全体のイメージ・カラーは僅かに違う。
湊は純然たる青色だが、尚也は癖の強い紫だった。
「そんな不機嫌そうな顔するなって。舞台役者はこれで揃ったってところだろ? 後は俺達、どうしたらいい。湊は確かにイニシエーションを終えたが、言ってしまえばそれだけだ。まだな」
「……もーちょっと、労いの精神ってないの」
「俺が厳しくしなかったら全員お前のこと甘やかしそうだからな」
尚也はまるで悪びれるふうでもない。湊はハァ、と溜め息を吐くとそれで追求を諦めたようだった。そういえば出会ってこの方、藤堂尚也が(それは彼の内にある藤堂和也というもう片方の人格も含めてだ)湊と綾時を甘やかしたことはなかったように思う。
聴き慣れたメロディを流し続けているイヤホンを耳から取り外して、改めて現状を把握するべく周囲を見回した。尚也は元の人間の姿に戻り、連れ戻した達哉はまだ意識を回復していない。引きずり込んだ結祈は洵の中に収まっている。綾時は高校生の姿で、慎と真田、美鶴は無傷ではないものの健常。
《湊の影》がニャルラトホテプが第一に仕掛けた試練なのだとしたら、まずまずの成果でそれを突破出来ていると言えるはずだ。
「向こうで何があった? こっちで起こったことは?」
「……こっちのことは把握してる。ありがとう。慎兄も、うまくやってくれたみたいだし。……それから綾時も」
『あ、う、うん。大したことはしてないよ。それより湊君こそ……』
「僕は大丈夫だから。綾時は心配性すぎ……あ、そうだ。あっちで――意識と無意識の狭間でエリザベスに会ったよ。彼女も手引きしてくれた。後で綾時を連れて来いって」
綾時の言葉を遮って湊は尚也に向き直る。尚也はごく真剣な面持ちをしていて、あまり時間を無駄にすることを許してはくれなさそうだ。単刀直入に結論から入ることにして湊は話を進める。
「結論から言うと、達哉は自我に囚われていた。勿論それはニャルラトホテプの介入による結果だけど、達哉自身が自分を縛り付けてしまっていた。僕が尚也を黒猫、ナオ、として連れ出したのはそんなに昔のことじゃないはずだけど多分時空が歪んでるのかな、あれより気の遠くなるような月日が流れていた感じがした」
「……悪化してたんだな」
「そう」
「そうか。そうなるような気はしてた」
あいつは十分すぎるぐらいに、必要以上に罰を受けた子供の顔をしていたから、と尚也の独り言が続く。「俺は結局達哉を助けられなかったな」と零すと湊は首を振った。
「ううん。尚也が達哉と会話を持ったのは、やっぱり大きかったと思うよ。実を言うと僕達は達哉の世界……達哉が『あちら側』と呼ぶ、滅びを迎えた世界を通って来たんだけど、達哉は随分と尚也に感謝しているみたいだった。疵痕の話とかね」
「スティグマータ」
「そう。僕のイヤホンと、尚也のピアス、達哉の記憶」
「……嫌な所で似たもの同士だな、俺達……」
「そんなもんだよ」
スティグマータ。過去を象徴づけるような、心的外傷の結晶体のような、そういう人格の象徴。尚也のピアスには和也への拭いきれなかった思い出が込められていて、達哉の忘却出来なかった記憶は彼の自覚して抱える罪と罰そのもので。湊のイヤホンは、有里湊の他者への拒絶としかし捨てきれない葛藤の鋳型。
ペルソナは心の形であり疵痕の体現だ。ペルソナ所持者であるということが、既にしてそういうことなのだろう。特に強力なペルソナ能力を持つこの三人はそれが顕著なのだ。
「達哉の記憶……達哉のスティグマータに関しても、ちょっと覗き見したから、少しは話せると思う。ええと……とりあえず、ニャルラトホテプのこと、かな。全貌を理解したわけではないと思うけど……」
「いや、湊はいい。その先は俺が話す」
たどたどしく、糸を手繰るようにそう口にすると湊の説明を遮るように背後から声がした。
「達哉」
「起きて大丈夫なのか? 一先ず今はニャルラトホテプが襲ってくる気配もないし、もう少しゆっくりしてても問題ないとは思うぜ」
「こちらが準備を終えるまで、奴は手出しをしないだろう。そういう奴だ。あいつは、準備万端に整えて俺達が自分からやってくるのを待っている。その間に幾つもの悪趣味なプランを立てながら……だからあまり時間を掛けたいとは俺は感じていない」
起き上がった達哉は少しだけふらついていたが、(ずっとあの暗闇の中にいたから、まだ地上に立っているという感覚に慣れていないのかもしれない)口ぶりは気丈そうだ。湊も尚也もそれを見て余計な口を挟むことを止め、彼の語るに任せることにする。
ジッポーライターをポケットから取り出し、カチカチと炎の出ないそれを弄ぶと達哉は改めて全員に向き直る。達哉は湊と尚也以外の人間を、名前どころか素性も何も知らなかったが全員がペルソナ使いだということは感覚として理解していたのでそれ以上の情報を求めなかった。
ニャルラトホテプという存在はペルソナ使いの全てに密接に関係する。だからそれで十分なのだ。
「ニャルラトホテプの話をしよう。少しの間……すまないが、俺の昔話に付き合ってくれ」
◇◆◇◆◇
――かつて。
フィレモンは周防達哉にこう告げた。『我々は人の心の源、普遍的無意識の化身であり、表裏一体の存在。我々はずっとここから人の営みを見てきた。私は強き心を持つ者を導き、這い寄る混沌は弱き者を奈落へ引き摺り込むために。全ては、矛盾を抱える人の心が、完全なものとして、進化することが出来るのか、その結果を見極めるためだ。諸君は、その可能性を示した。君達のような人間が増えれば、いつしか人は、己の存在意義を知る、完全な存在になれるだろう』。
フィレモンは光であり、ニャルラトホテプは影である。それは人間の表裏一体性と同じもの。人に心の闇がある限りニャルラトホテプは存在し続ける。人間が存在する限り、這い寄る混沌は力を持ち続ける。
ニャルラトホテプは普遍的無意識の暗黒面。人間の持つ負の心それそのもの。あらゆる人間の無意識と繋がり、故に、それを大きく左右し得るのだ。
「俺は……尚也もそうだったと思うんだが、フィレモンに名を告げることでペルソナ使いとして目覚めた。名を告げるという行為それそのものが意識と無意識の狭間で自我を保つという一種の試練なんだな。ペルソナは心の鎧、自我の強さ、それは全員が理解しているところだと思う。必然、フィレモンは光の存在であるから多分いいやつなんだろうという認識が俺の中にはあった。だけどそうじゃない。そういう意味では……ニャルラトホテプが悪だ、と単純に言い切れるわけでもない。性格が最悪なのは取り繕えない部分だが」
「そのフィレモンに名前をなんとかっての、僕、全然覚えないんだよね。それですごい尚也と和也には突っつかれたけどそれって多分僕だけじゃないんだ。真田さんも美鶴先輩も慎兄も洵兄も、結祈も、というか僕が知ってるペルソナ使いは全員突然この能力に目覚めたって感じだったと思う。勿論外敵から身を守るためとか、そういう状況下でのことだったし全員が全員なんらかのトラウマを持ってはいた。だけどそんな奴名前も顔も知らない」
「少なくとも俺の知る世界ではフィレモンはペルソナ使い全員が通過するイニシエーションで常識だった。俺達とそれ以降で差があるのなら俺がパラレル・ワールドの分岐を作ってしまったことが原因なのかもしれないし、俺達が一度完全にニャルラトホテプを退けたことに原因があるのかもしれない。どちらにせよ憶測の域を出ないが……今になって、こうして大きな歪みを起こしてまで奴が動き出した意図は奴自身に語らせる他正確に知る術はないだろう。だが、知りたければすぐに知れることかもしれない。あいつはお喋りが過ぎる」
ニャルラトホテプはその性質上非常に饒舌だ。フィレモンが寡黙さで達哉達を半ば騙したのとは真逆で、消滅間際までいちいち五月蠅かったのを達哉はよく覚えていた。しかし往生際が悪い人間のようだというのは、それだけ人間の負の真理を熟知しているということでもあり、あそこまで粘着的な敵もそうそういるものではないだろう。
出来ればもう二度と関わりたくない相手だ。しかし達哉も発端の一つである以上はそんなことも言っていられない。もう一度相手にするぐらいの気力は何とか補填出来ている。
復讐をしたいわけではないが聞きたいたいこともある。
「それで、どうして湊は奴に目を付けられたんだ? 俺のように因縁があったわけでもなく、そもそも……人としては死んでいる状態なんだろう? 尚也に関しては完全にとばっちりだと思うんだが、湊を狙ってこう回りくどいことを仕掛けてくるからにはそれなりの動機があったはずだ。次の標的に見初められてしまう程度には」
「ううん……? 多分、未練が残ってたからだとは思うんだけどね……」
「未練か」
「そう。僕は、色々あって世界を救ったけれど、命と引き替えだったし……まあ、色々と。イゴールにも言われた。僕は大きな力を得る代償として本来払うべきだった対価をちゃんと払っていなかったって。それが、今になって形を得たのが、さっき僕が受け入れた僕自身の未練だった。一番人間らしい生っぽいやつ」
「それはやはり、ニャルラトホテプの差し金で間違いないわけか」
『間違いないよ。純粋な湊君のシャドウとは言い難かった。混じりものがあったこと、上手く擬態していたけれど僕だけは騙せない』
「……こいつは何なんだ?」
湊に代わって受け答え、息巻く綾時を示してここで初めて達哉が疑問を口にした。
「人間の姿をしている割には、人間じゃないというか、ペルソナに近い気がするんだが」
「流石鋭いな。よくわからないが、『死の根源』、らしいぜ。今は湊のペルソナってポジションに収まっているそうだが」
「危険性はないのか」
『ないよ!!』
「ないよ」
「あ、ああ」
綾時本人と湊に即答されて、達哉が手を引っ込める。「溺愛してんだこいつら」とは尚也の捕捉。「古い馴染みだが、まあ、一応害はないはずだ」と真田も援護する。達哉はすこぶる不思議そうな表情でしばらくじろじろと綾時と湊を見比べ、某かの結論を自分の中で導き出したらしく、手を打った。
「わかった。理屈は知らないが、『半分湊』なのか」
「目敏い。大体そんなもの。綾時の人間性は僕から獲得したものだからそういうことになるんだと思う。一応、ペルソナっぽい姿になれるし。綾時チェンジして」
『うん。了解』
「あ……なるほど。これは、そうだな。ペルソナだな……ならいい」
「これも原因の一つか」と尋ねられ、デスの姿に変化した綾時は静かにそれを肯定する。この綾時と湊の関係性、その異質さは達哉が特異点であることと似通ったものだと解釈されたらしい。「未練と特異点か。選定理由は俺と大方同じだな」と彼は言い、ここでうんざり呆れ返ったように溜め息を吐いた。
予想していなかった反応に湊が目を丸くすると「ああ、悪い。湊のことじゃないんだ」と釈明される。
「人間が進歩しないんだから当たり前のことなんだが、ニャルラトホテプの方も変わりないと思ってな。なんとなく、ニャルラトホテプが何故動き出したのか分かった気がする。……湊」
「え、何」
「お前の抱えているシャドウが大きくなりすぎたんだ。あいつの目に『面白そうな玩具』として留まってしまったんだよ。恐らくだが。俺もそうだった」
蓋をして見ぬ振りをしていた時間が長すぎて、どんどん膨れあがって、あそこまで肥大化してしまった。
「それに加えて、この街の磁場が狂っているのも奴の行動に拍車を掛けたのは間違いない。悪いことが重なったな。そういうの、あいつは得意なんだ。タイミングを最悪の段階で調整することが。人間の因果を全部握ってるような奴だからな」
「詳しいね?」
「付き合いが長い分嫌でも。だが倒せないわけじゃない。俺は倒せるってことも幸いにして知ってる」
――ニャルラトホテプを倒す方法は存在する。
かつてニャルラトホテプを討ち取った時、フィレモンはこうも言った。「彼等は、人の可能性そのものだ。普遍的無意識の暗黒面たる貴様は、確かに全ての人間と繋がっている。だからこそだ……、彼等が人の心を動かしたのだ……」と。
全ての可能性は混沌より生じる。人間の総意そのものをニャルラトホテプとの交戦を通じて揺るがすことが即ち勝利への唯一の道筋だ。
「そのためには希望と、そして揺らがぬ決意があればいい。単純で、だが意外とこれが困難だ。なあ、どうしたいと思ってる」
「僕?」
「ここにいる、これから戦いに望む全員が」
達哉のその言葉に、全員で伺うように顔を見合わせた。
それからすぐに、示し合わせたように頷く。どうしたいか。単純だ。全員、これまで「綾凪を正常化する」ことを目標に動いてきたし、それが各々の目的に直接繋がっている。
慎や洵は住む街を守りたいし、湊と綾時はそもそもニャルラトホテプを倒し、綾凪に異変を引き起こしてしまった元凶として後始末をするためだけに肉体を伴って顕現している。真田や美鶴に関しても綾凪を守って湊を送るのが第一目標。尚也は自分の住む場所へ帰りたいという強い意志がある。
あとは、達哉だ。
「俺は、正直言って、もう帰る場所はあの殆ど滅びかけの世界だけなんだ」
「それで?」
「だけど。囚われていた俺を救ってくれた湊や俺の巻き添えを喰らわせてしまった尚也の力になりたいと思う。それにもう一つ強い望みがあるんだ。あいつをそろそろもう一発殴ってやらないと、気が済まない」
「ニャルラトホテプを」
「それもある。あの懲りない自称神に払わされたつけは随分でかかった。……あとは、フィレモンだな」
「……なんで?」
「単純なことだ。俺はあいつがあまり好きじゃない。それに……影は光があるから生まれるんだ。ニャルラトホテプがいれば必ずそこにはフィレモンもいる。あいつは昔俺に言ったよ。胡散臭い嘘吐きの顔で、『私は全ての人間の、意識と無意識の狭間に住まう者。私は君で、君は私だ……いつまでも、君の中で君を見守ろう。さらばだ』、と」
フィレモン、人間の可能性を見極めるべく手助けをする誰か。それをいつか達哉は思いきりぶん殴ってやったことがある。パラレル・ワールド創造の選択を取って仲間達が次々と向こうの世界へ消えて同調していくのを見送り二人きりになった空間でだ。
礼を言うかほんの少しだけ迷ったが、やはり殴るしかないと思って渾身の力を込めて殴ると、フィレモンがいつもかけていた蝶を象ったマスクが外れてその素顔が明らかになる。フィレモンは達哉の顔をしていた。周防達哉が、やがて年を取り、こうなるのだろうという顔をしていた。
それを見た時、ああこいつはニャルラトホテプと同じだ、と本能でうっすらと感じたのだ。無貌の神、千の顔を持つ邪神、そんなふうに言われるニャルラトホテプと同じように……こいつはきっと見る者によってその顔を変えるのだろうと。
「だからもう一回殴ってやるのさ。――自分自身のために」
達哉が言った。湊は、黙って、その拳を握る力を少しだけ強くした。
Copyright(c)倉田翠.